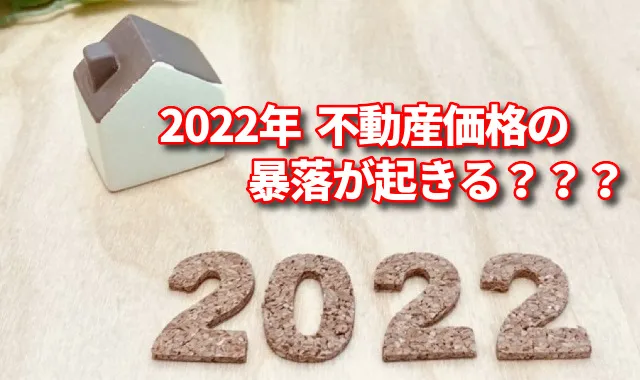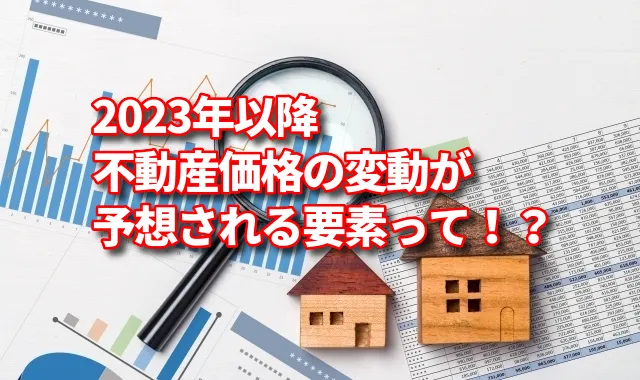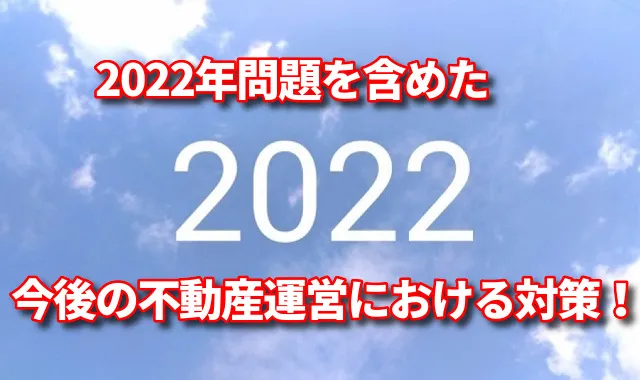- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- 賃貸経営の基礎知識
- 【イエカレ】生産緑地のこれから|土地活用で押さえておくべき注意点と対策
【イエカレ】生産緑地のこれから|土地活用で押さえておくべき注意点と対策
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.2022年問題とは何か
2022年問題とは、「2022年に不動産価格の暴落が起きるのではないか」と懸念されている問題です。
問題の背景には、1991年に制定された生産緑地法改正の影響があります。この改正に伴い多くの土地が「生産緑地」と指定され、売買が禁止されました。2022年にその売買の制限が解除されるため、生産緑地と制定されていた土地が一斉に市場へ出回ります。
通常であれば、土地が一斉に出回ると周辺の不動産価格が暴落し、投資家や不動産運営者に大打撃を与えかねません。
今回の場合は冒頭でお伝えした通り、政府の講じている防止策により暴落はほとんど起きないといわれています。
2.生産緑地とは何か
生産緑地とは、一般農地と同等に固定資産税や相続税が優遇されている市街地にある農地です。1974年に制定された生産緑地法で定められています。制定当時は生産緑地と指定された農地は少数でしたが、1991年の改正によって多くの農地が生産緑地と指定されました。
この項目では、生産緑地について詳しく解説します。
2-1.生産緑地と宅地化農地
1991年に制定された生産緑地法改正で、市街地の農地は「生産緑地」と「宅地化農地」に分類されました。
生産緑地は農地の保全目的に制定された土地です。生産緑地として認定された土地は、30年間税制が優遇されます。ただしその間、土地の売買ができないことになっています。
一方、宅地化農地は宅地(住宅用)として扱われる農地のことで、生産緑地のような税制の優遇はありません。
改正施行は1991年の後期であったため、生産緑地は1992年に認定を受けたものが大半です。2022年はその30年後であるため、改正当時の法令通りであれば、「生産緑地」の数多くは認定を解除されます。
2-2.生産緑地制度が開始された背景
1960年後期から一部地域の都市化が進められていました。それに対して、農地を維持するために制定されたものが生産緑地法です。
その後、住宅地が増えるにあたり土地の自然形態が変化し、公害が懸念され始めました。農地を保護して土地を守るため、1992年に生産緑地法の改正が施行され、数多くの農地が生産緑地として認定されました。
2-3.生産緑地の大半が都心部に集中
生産緑地のほとんどが、三大都市圏(東京、名古屋、大阪の周囲)に集中しています。
そのため、生産緑地の少ない地方は2022年問題の影響は少ないと考えてよいでしょう。
また、生産緑地は駅の近くや利便性の高い区域にはほとんどありません。そのような不動産の需要が高い地域も、地方と同様あまり影響はないと考えられます。
一方で、ファミリー向けの住宅地は駅から離れた郊外にあるため、2022年問題の影響を受けやすいといわれています。
参考:国土交通省「農地面積の現状」
3.2022年問題を見越して政府が事前に行った防止策
2022年問題は政府も懸念しており、対策を既に講じている状況です。
ここでは、政府の行った防止策について詳しく解説します。
3-1.生産緑地に10年の猶予と面積要件の引き下げ|2018年施行・特定生産緑地制度
特定生産緑地制度が2018年に施行され、当初予定していた税制優遇措置の終了から、さらに10年間の税制優遇を受けられるようになりました。この10年間の延長措置を受けた農地を「特定生産緑地」といいます。
また、面積要件も緩和されています。それまでの法令で生産緑地として認められるためには500㎡以上の土地でなければなりませんでした。
改正後には300㎡以上で特定生産緑地として認められ、税制の優遇を受けられるようになりました。
生産緑地は都市郊外に多くあるため、それほど大きくない500㎡〜300㎡の土地が多数あります。
そのため、300㎡に引き下げられたおかげで86%の土地が引き続き、特定生産緑地として認められ、税制優遇が受けられています。
よって、生産緑地を抱えている所有者の負担は引き続き緩和され、土地を一斉に売りに出すようなことは避けられたといえるでしょう。
参考:国土交通省「特定生産緑地指定の手引き」「特定生産緑地 指定見込み86% 国交省調査2022年2月21日」
3-2.建築規制の緩和|2018年施行・都市緑地法等の一部改正
2018年に施行された都市緑地法等の一部改正により、生産緑地内に一部の建築物の建設が許可されました。
改正前は、ビニールハウス・温室や倉庫など、一部の施設を除き建設が規制されていました。
改正後は、農産物の直売所や農産物を使用したレストラン、農産物の加工所(自家販売用)などが新たに建設できるようになっています。
土地活用の幅が増えたことで多くの生産緑地に需要が生まれ、不用意に市場へ出回るようなことが避けられたといえるでしょう。
参考:国土交通省「都市緑地法等の一部を改正する法律の 施行について」
3-3.都市農地の賃貸が円滑化|2018年施行・都市農地法
都市農地賃貸法が2018年に施行されたことにより、都市農地の賃貸がしやすくなりました。
通常であれば、農地の賃貸をした際、知事の許可がない限り賃貸が自動更新され、農地は返ってきません。また、賃貸した時点で税制の優遇措置を受けられなくなります。
一方、この制度を利用すると、契約期間満了時に自動更新されず、農地が返却されます。また、税制の優遇を受けたままで賃貸が可能です。
4.2023年以降に不動産価格が変動する要素
不動産価格の変動要因は、さまざまです。
これまでは2022年問題について触れてきましたが、それ以外でも不動産価格の大きな変動が予想されています。
ここでは、2023年以降に不動産価格の変動が予想される要素について解説します。
4-1.住宅需要のピーク|2023年問題
2023年に日本の世帯数は5,419万世帯でピークを迎え、それ以降は減少すると見立てられています。
世帯数が減少すると、それに比例して需要も減少すると考えられます。需要の減少に伴い、2023年以降に住宅の価格相場が落ちていく可能性があります。
参考:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」
4-2.後期高齢者の増加|2025年問題
2025年には「ベビーブーム世代」と呼ばれる、約800万人の国民が75歳を迎えて、後期高齢者数が約3,500万人になると予想されています。
後期高齢化を迎える方には、元から住んでいた家を出て、介護施設や病院に入る方が多数いると予想されます。一人暮らしの高齢者が移り住んでしまえば、住んでいた家は空き家です。
また、遺産として家や土地を相続する人も増えるでしょう。
それらの土地が売却に出されると、不動産の供給が増えるため不動産価格が落ちる事態になりかねません。
参考:厚生労働省「今後の高齢化の進展 ~2025年の超高齢社会像~」
4-3.関西圏における不動産価格の上昇|2025年大阪万博
2025年に大阪万博が開催されることで、関西圏の不動産価格がさらに上昇すると予想されています。
大阪万博は、国内国外問わず、約2,800万人という多数の来場者が訪れると見込まれています。(※2)
来場者により経済が活性化すると、地価が上がる可能性があります。
また、万博に合わせて、関西圏の商業施設や、宿泊施設の建設が見込まれます。
建設需要が高まるため、周辺地域の不動産価格は上昇すると予想されています。
参考:国土交通省「2025年大阪・関西万博開催に向けて」
(※2)経済産業省「大阪・関西万博」
4-4.不動産バブルの崩壊
コロナ禍でありながら、世界で不動産ブームが訪れています。
これは、在宅勤務の増加に伴って郊外に移り住む人が増え、住宅需要が高まった結果であるといわれています。
さらに、コロナ禍で労働力が不足し木材価格が6倍になった影響で、アメリカの不動産価格は2年間で約30%上昇しました。
一方で、パンデミックが収まり、コロナ禍前の生活に戻れば住宅価格の高騰が終わると指摘されています。
これにより不動産バブルが崩壊すると、価格の暴落が起きかねません。
参考:独立行政法人経済産業研究所「なぜ、コロナ禍でも世界で不動産ブームが起きているのか?住宅価格高騰、予測不能状態に」
5.2022年問題を含めた今後の不動産運営における対策
不動産に影響するさまざまな問題が、近い未来に発生する可能性があります。
では、その問題へどのように向き合っていけばよいのでしょうか。
この項目では、2022年問題を含め、今後の不動産運営における対策を解説します。
5-1.都市部の売却は早めの検討がおすすめ
都市部に不動産を保有し、かつ売却を視野に入れている方は早めに検討することがおすすめです。
とくに、下記の表に記載されている地区は、不動産の価格暴落に気を付けましょう。
価格が落ち始める前に売却すれば、損失を最小限にできます。
|
・東京都(世田谷区、練馬区、多摩地区) ・埼玉県 ・千葉県 ・神奈川県 ・愛知県(名古屋市、岡崎市、一宮市、豊田市) ・大阪府 ・奈良県 ・京都府 |
参考:国土交通省「都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況」
5-2.地方は生産緑地が少ないため売却を急がなくても問題なし
前述したように、生産緑地はそのほとんどが都市部に集中しています。
そのため、2022年問題において地方が受ける影響はあまりありません。売却を急がなくても大きな問題はないでしょう。
ただし、2022年問題は影響がなくても、他の要素によって価格変動が起きる可能性はあります。前述したリスクを見越して、土地活用や売買を考えておきましょう。
5-3.購入は様子見でも問題なし
不動産や土地の購入を検討している方は、急いで購入しなくても問題ありません。
前述のとおり、法改正による政府の対策によって、事前に懸念されているほどの大幅な価格暴落は起きないと予想されています。
また、2023年問題や2025年問題により、購入価格が今より下がる可能性があります。
そのため、不動産価格の経過を見ながら、購入を検討するとよいでしょう。
5-4.景気に左右されない立地条件で購入を検討
さまざまな要因によって不動産価格は変動します。
一方で、景気に左右されない立地条件の不動産を購入すれば、価格変動の影響は少なくて済みます。
たとえば、都市部の駅近くや交通の利便性が高い地域は、安定した相場を維持しているでしょう。
生産緑地の解除を控える土地オーナーへ
生産緑地の「これから」を安心に進めるために —
まずは複数プランを比較して最適策を見つける
生産緑地は資産価値・税負担・収益に大きな影響を与えます。解除後の土地活用は可能性が広がる一方で、想定外のリスクもあるため、複数の活用案(収益想定・補助金適用・税負担の違い)を比較することが何よりの安全策です。
- 解除後の活用案ごとの収支シミュレーションを比較
- 補助金や税制優遇の適用可否をチェック
- リスクとメリットを踏まえた現実的な最適案を発見
※資料請求後は、連絡方法や時間帯の希望を指定可能です。比較だけの利用も歓迎します — 比べて納得してから次に進みましょう。
まとめ
生産緑地の解除や土地活用は、資産価値や税負担、将来の安定収益に直結する重要なテーマです。適切な知識と準備を持つことで、思わぬリスクを回避し、土地を最大限に活かすことが可能になります。
今後の動向をしっかり把握しつつ、自分の土地に合った活用方法を選ぶことが成功への第一歩です。本記事で紹介した注意点と対策を参考に、長期的な視点で土地活用を検討してみてください。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 賃貸経営の基礎知識
賃貸経営の基礎知識の関連記事
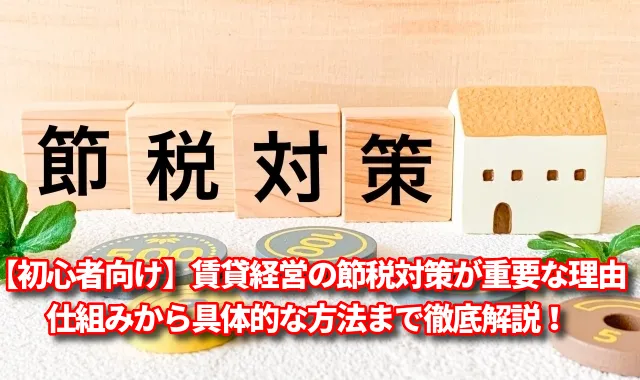
- 【初心者向け】賃貸経営の節税対策が重要な理由を徹底解説!仕組みから具体的な方法まで|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
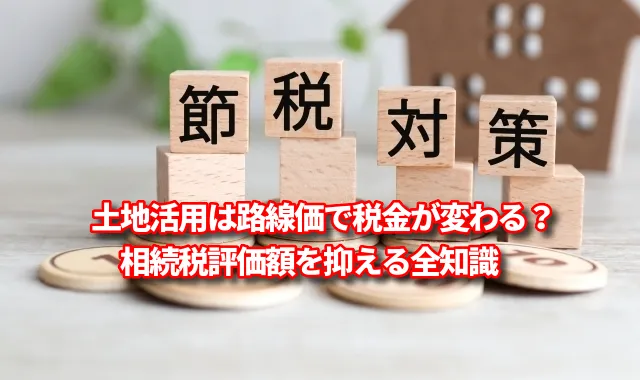
- 土地活用は路線価で税金が変わる?相続税評価額を抑える全知識|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
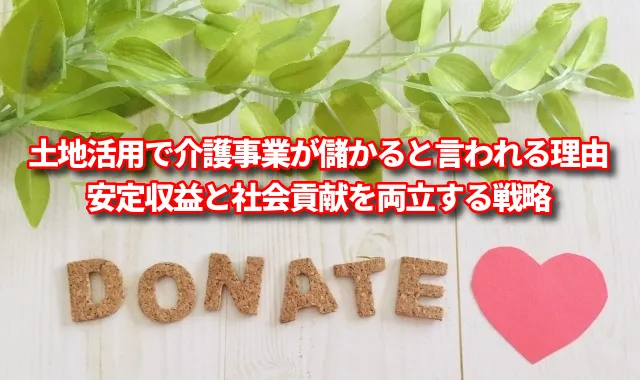
- 土地活用で介護事業が「儲かる」と言われる理由 安定収益と社会貢献を両立する戦略|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開

- 【地域活性化の起爆剤】土地活用と空き家リノベーションで未来を拓く|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開

- 賃貸経営の利回り完全ガイド:計算から平均・シミュレーションまで徹底解説|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
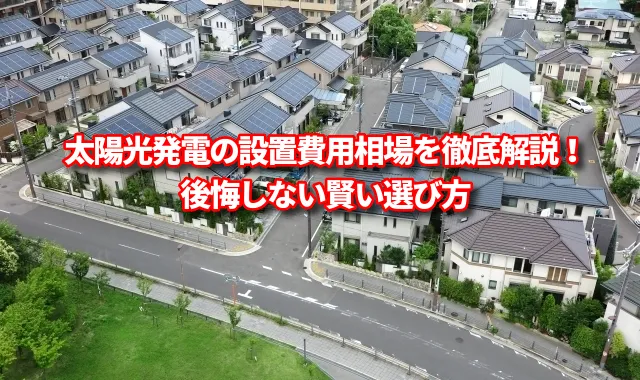
- 太陽光発電の設置費用相場を徹底解説!後悔しない賢い選び方|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開

- 【土地活用】借地権設定で安定収入!リスクを抑えて資産を最大化する方法を徹底解説|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
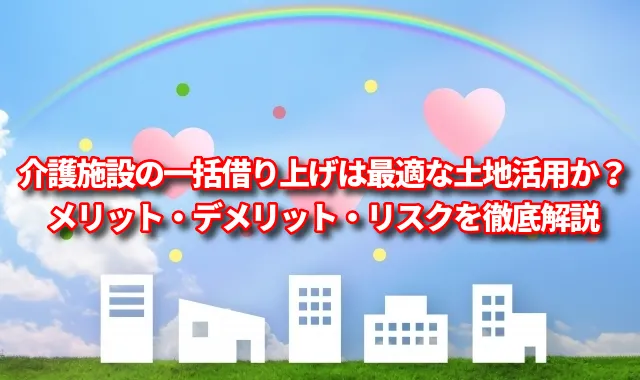
- 介護施設の一括借り上げは最適な土地活用か?メリット・デメリット・リスクを徹底解説|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開

- 太陽光発電の余剰電力売電ガイド:FIT後の最適な選択肢と賢い契約方法|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開

- 太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)とは?FITの仕組みから卒FIT後の賢い選択肢まで徹底解説|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
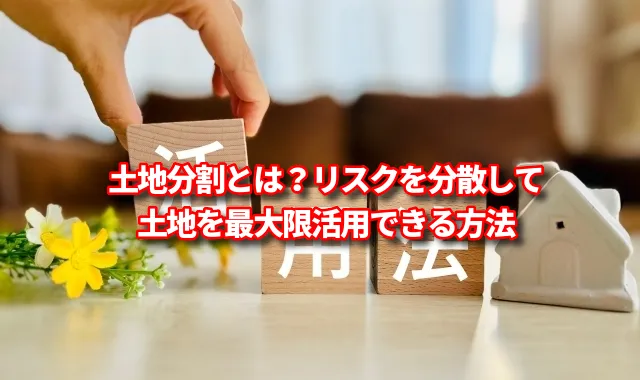
- 土地分割とは?リスクを分散して土地を最大限活用できる方法|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
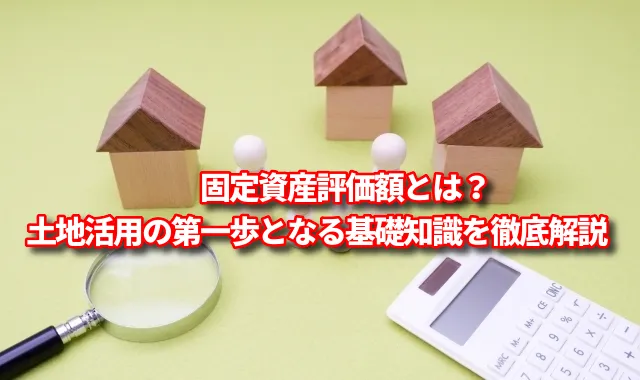
- 固定資産評価額とは?土地活用の第一歩となる基礎知識を徹底解説|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
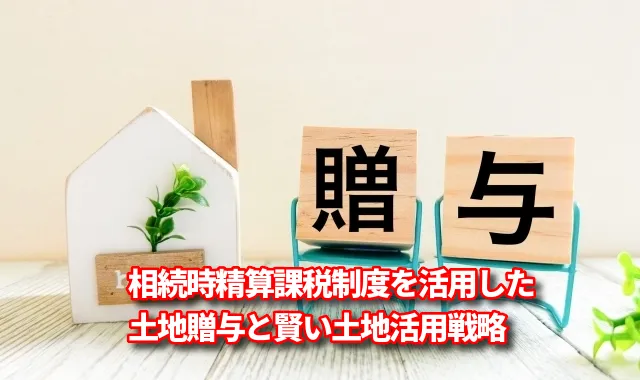
- 相続時精算課税制度を活用した土地贈与と賢い土地活用戦略|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
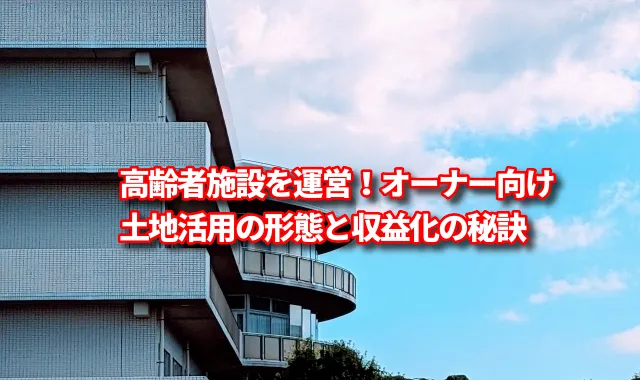
- 高齢者施設を運営!オーナー向け土地活用の形態と収益化の秘訣|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
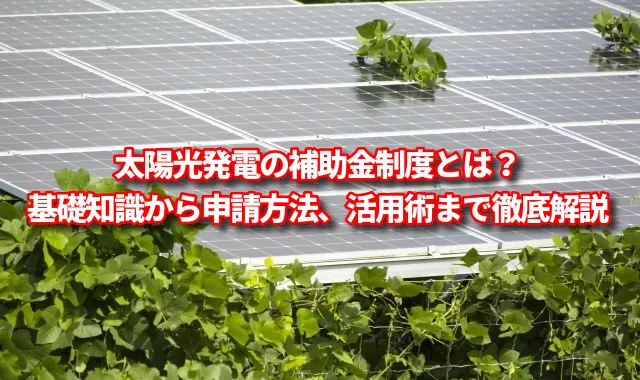
- 太陽光発電の補助金制度とは?基礎知識から申請方法、活用術まで徹底解説|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
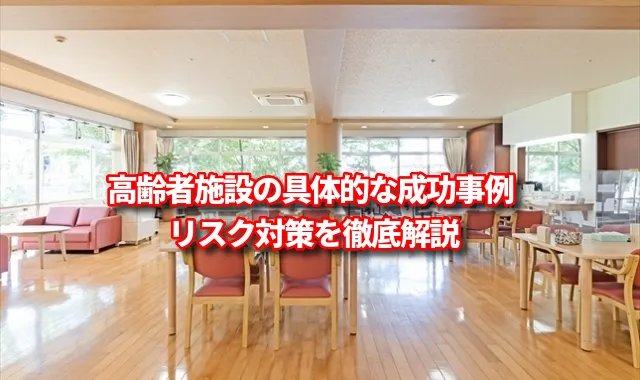
- 高齢者施設の具体的な成功事例とリスク対策を徹底解説|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開

- 土地活用としての太陽光発電投資:投資回収期間と収益最大化の全貌|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開
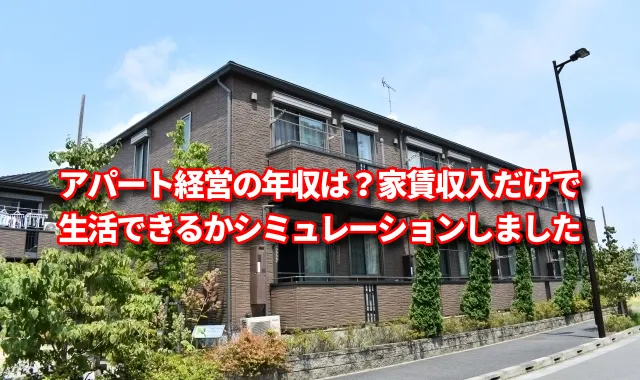
- アパート経営の年収は?家賃収入だけで生活できるかシミュレーションしました|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開

- FIT制度とFIP制度の最も重要な違いとは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開

- 遊休地で太陽光発電、投資回収期間は何年?費用・利回り・失敗しないポイントを徹底解説|土地活用・アパート経営なら一括比較情報サイト【イエカレ】 公開