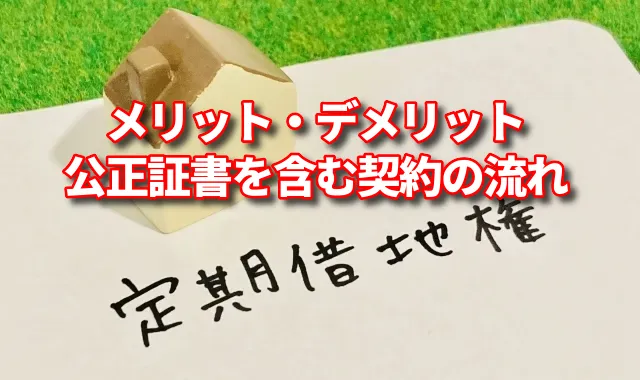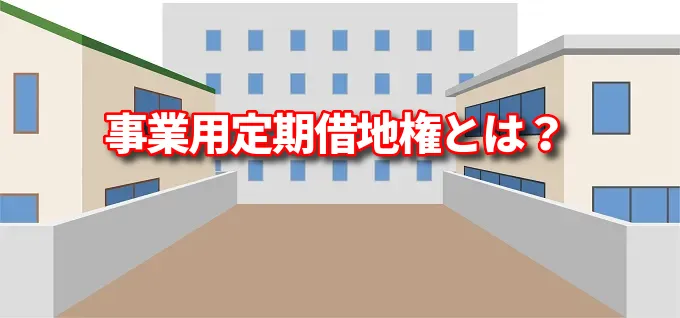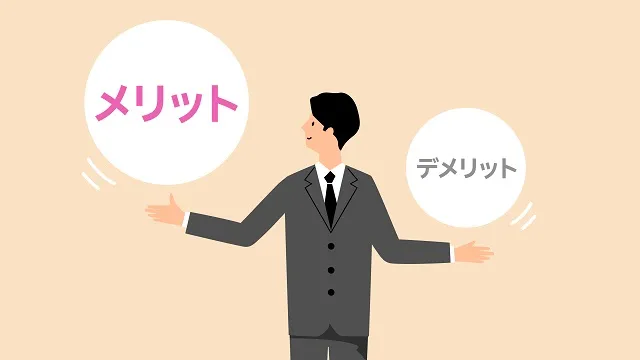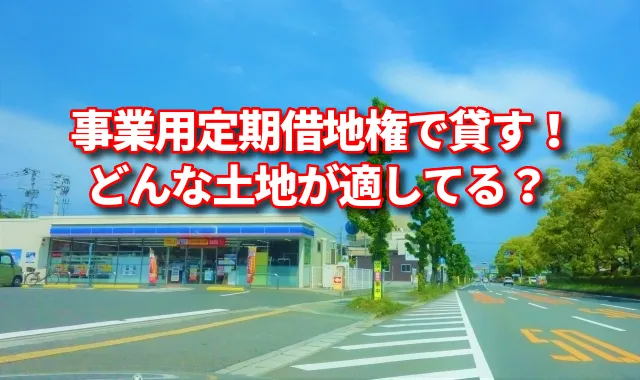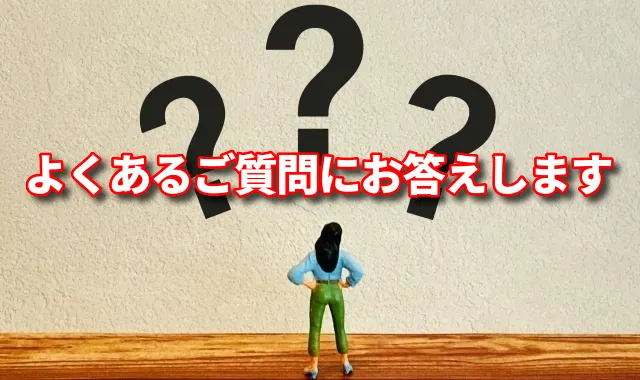- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- FAQーよくあるご質問ー
- 【イエカレ】土地を貸して有効活用をしたい方へ|事業用定期借地権のメリット・デメリットを解説
【イエカレ】土地を貸して有効活用をしたい方へ|事業用定期借地権のメリット・デメリットを解説
目次
1.事業用定期借地権とは用途・期間を限定して土地の貸し出す権利
まず初めに「事業用定期借地権とはなにか?」ということについて解説します。
事業用定期借地権とは、事業の用途に限定して期間を決めて事業に土地を貸し出す権利です。
借地借家法の第23条に定められており、4種類ある定期借地権のうちの1つになります。
事業用定期借地権を使って契約する時には、以下3つのポイントを満たす必要があります。
-
・契約期間は10年以上30年未満(更新不可・更地返還必須)
もしくは30年以上50年未満(更新可能)
・用途は事業用に限定(居住は不可)
・公正証書で契約
出典:e-Gov法令検索「借地借家法 」
この章では「借地の返還時の対応」「公正証書」について詳しく解説します。
1-1.契約満了時の更地返還と買取請求権
1つ目は「契約満了時の更地返還と買取請求権」ということについて解説します。
事業用定期借地権を利用して土地を貸し出した場合、契約満了を向かえると、その時点で、貸し出した土地に建物が残っていても更地にして返還されます。
ただ、30年以上50年未満の契約だった場合は、土地の借主は「買取請求権」の行使が可能です。契約満了時に貸主(土地の所有者)に建物を時価で買い取ってもらうことができます。
これは、契約満了時点でまだ十分使用ができる建物だった場合、それを解体するのは損失とみなされるため、この買取請求権ができました。
参考:国土交通省「建設産業・不動産業:定期借地権の解説」
1-2.事業用定期借地権に必要な公正証書
2つ目は「事業用定期借地権に必要な公正証書」についてです。
事業用定期借地権を使った契約をする場合には、必ず「公正証書」で契約しなければならないと定められています。
公正証書とは,私人(個人または法人)からの嘱託により,公証人がその権限に基づいて作成する文書を言います。街を歩いていると、ビルの一室に公証役場があるのを見掛けた方もいらっしゃると思います。
公正証書が必須になっている理由は、事業用定期借地権の制度が脱法行為として利用されることを防ぐためです。公正証書であれば、公的機関が契約内容を精査することになり、その際、もし、貸し出される土地の利用目的や契約内容に不審な点があれば、契約が認められない可能性もあります。
逆の見方をすれば、公正証書とすることで、土地を貸し出す貸主の権利が守られる一面もあるということです。少し手間はかかるのですが、公正証書で定めないと契約は無効になりますので注意が必要です。
ここは気になる点かとも思いますので、以下でさらに、公正証書作成にかかる費用や、具体的な流れを補足します。
1-2-1.公正証書の費用・負担者
補足の1つ目です。公正証書の費用は「公正証書手数料令」によって定められています。
費用は目的の価額によって決定されます。借地であれば、10年分の賃料の2倍が目的の価額(※)となっています。
以下の表が、価額ごとの手数料です。
目的の価額 手数料 100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 11,000円 500万円を超え1,000万円以下 17,000円 1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円 3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円 5,000万円を超え1億円以下 43,000円 1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
引用: 日本公証人連合会「10 手数料 」
例えば、毎月100万円の賃料で土地を貸し出す場合なら以下の計算になります。
● 価額:100万円×12か月×10年×2=2億4,000万円
● 手数料:4万3,000円+1万3,000円+1万3,000円+1万3,000円=8万2,000円
この様になります。
また、気になる点として「公正証書の費用は誰が支払うのか?」ということがあると思います。実は、これには、負担者(貸主・借主)をどちらにするかについての明確な決まりがないので、貸主と借主が話し合いで決定します。
※出典:日本公証人連合会「Q. 売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明」
1-2-2.公正証書で契約する流れ
補足の2つ目です。公正証書で契約する時の流れは以下となります。
- 公正証書で契約する前に、覚書契約で契約を取り交わす
- 覚書契約を含めた必要書類を集める
- 公証役場で公正証書の作成を申し込む
- 予約日に契約者が出向いて公正証書の作成・支払を済ませる
以上4つです。
一つ目の「覚書契約」についてさらに補足をしておきますと、事業用定期借地権の場合は、公正証書で契約をする前に「覚書契約」の締結を行います。
この覚書を交わす目的は「お互いの契約意思を確認する」ためになります。貸主・借主双方に、契約意思があることを確認することは必要ですから、公正証書で本契約を締結する前の準備段階として覚書契約を取り交わすことには意味があります。
ただ、この覚書は、契約意思確認を目的としたものなので法的な効力はありません。ですから、この覚書を交わしたからと言って「絶対に本契約を結ばないといけない」というものではありません。本契約前に貸主・借主のどちらかが契約することを取りやめることは可能になっています。
2.事業用定期借地権と借地借家法で定められたほかの借地権との違い
次に「事業用定期借地権と借地借家法で定められた他の借地権との違い」について解説します。
借地権には「普通借地権」「定期借地権」の2つがあります。
普通借地権は更新ができることを前提にした契約ですが、定期借地権は更新がされないことを前提とした契約です。
例えば、電車の「定期券」は有効期間が来ると使えなくなりますが、「定期」の意味合いとしてはそれと同じです。
定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「一時使用目的」「事業用定期借地権」の4種類があるのですが、事業用定期借地権は、その中の1つです。
事業用定期借地権と他の借地権との違いをまとめると以下の表の通りとなります。
それらの違いについても解説していきます。
普通借地権 定期借地権 一般定期借地権 建物譲渡特約付借地権 一時使用目的 事業用定期借地権 契約期間 30年以上 50年以上 30年以上 短期間 10年以上50年未満 用途 制限なし 制限なし 制限なし 客観的合理的に短期間と認められるもの(※1) 事業用(居住用途は不可) 契約終了時 更新可能 更地にして返還(※2) 30年経過で地主が建物を買い取り 契約内容に応じる 更地にして返還(※2) 土地活用例 制限なし マンション他 制限なし 制限なし 仮設のプレハブ・選挙事務所・企画展など 店舗・事務所・工場など
参考 国土交通省「建設産業・不動産業:定期借地権の解説」
※1 出典:裁判所「昭和43年3月28日最高裁判例 本文」
※2 建物譲渡特約付借地権と併用することで、契約の更新が可能(事業用定期借地権は30年以上の契約が条件)。
2-1.一般定期借地権は用途が自由な分、期間が最も長い
1つ目の「一般定期借地権」は、事業用定期借地権と比べると用途に制限がありません。
自由に土地を活用できるため、利用目的に関係なく土地の賃貸が可能です。契約満了時は、借主は更地にして貸主へ返還する必要があります。
また、一般的借地権は、最低契約期間が最も長い点も特徴です。最低50年以上の契約となるため、貸主にとって長期的な収入を得るのに向いています。
2-2.建物譲渡特約付借地権は期間の下限が少し長い
2つ目の「建物譲渡特約付借地権」は、契約期間の下限が30年です。
後程詳しく解説する事業用定期借地権の下限が10年ですから、それと比較すると長く設定がされています。そのため、中期での貸し出し・運用に向いていると言えます。
契約満了時には、借主は更地にして貸主へ返還するのではなく、貸主が建物を買い取る必要があります。
ただ、貸主が建物を買い取った後に借主が引き続きその建物を利用したい場合は、「借家契約」として引き続き貸し出すことができる契約になります。
また、建物譲渡特約付借地権は「一般定期借地権」「事業用定期借地権」と併用できることが特徴です。
例えば、最初に事業用定期借地権10年で契約した場合、建物譲渡特約付借地権も契約することで契約期間を延長できるといったイメージです。
2-3.一時使用目的は用途・期間の自由度が比較的高い
3つ目の「一時使用目的」は、用途や期間が明確に制限されてなく、自由度が比較的高い制度といえます。
ただ一方で、これは、客観的かつ合理的に短期間の利用だと認められる必要があるということが前提になります。
例えば、仮設のプレハブ・選挙事務所・企画展などといった「短期間だけ貸したい」場合に向いているものになります。
長期の利用とみなされると、一時使用目的に該当せず、別の借地権が適用される可能性が出るため注意が必要です。
2-4.事業用定期借地権の契約には公正証書が必要
4つ目は「事業用定期借地権」です。
上述しました通り、この契約のみ、「公正証書」が必須とされています。その他の定期借地権に関しては、以下の通り必須とはされていません。
●一般定期借地権:公正証書等の書面
●建物譲渡特約付借地権:口頭でも可
※出典:国土交通省「建設産業・不動産業:定期借地権の解説 」
3.事業用定期借地権を持つことによるメリット
さて、ここから更に事業用定期借地権について掘り下げて解説していきましょう。
まず、この制度を利用するメリットですが、土地の所有者(貸主)と借主の双方にとって、以下のメリットがあると言えます。
・(共通)貸出期間を最短10年・最長50年から選べる
・(貸主側)事業リスクを負わずに安定した収益を得られる
・(貸主側)居住用よりも地代を高めに設定できる
・(貸主側)評価額・相続税の軽減が期待できる
・(借主側)土地の購入費用を抑えて事業を運営できる
・(借主側)建物を自由にデザインできる
以上6つです。
これら6つの「事業用定期借地権を持つことで得られるさまざまなメリット」を以下で詳しく解説します。
3-1.(共通)貸出期間を最短10年・最長50年から選べる
メリット1つ目です。
事業用定期借地権は、貸出期間が10年から50年と自由に選択できるため、運用目的に応じて期間を設定できます。
例えば、「契約の時点で、10年後に別の土地活用を予定していれば短期で契約」、「特に予定がなければ長期で契約」と選択することができます。
以下が、貸主側・借主側、双方にとっての、長期・短期のメリットです。
長期のメリット 短期のメリット 貸主側 長期的に不労所得を得られる 別の土地活用が予定にある際に、それまで収入を得られる 借主側 30年以上であれば買取請求権の行使ができる 短期間の事業運用に向いている返還期間が見えているため計画を立てやすい
3-2.(貸主側)事業リスクを負わずに安定した収益を得られる
メリット2つ目です。
土地の所有者である貸主は、事業リスクを負わずに、安定した収入を得られるというメリットがあります。
例えば、土地を貸し出す際に、貸主が借主のために建物を建築して用意をする必要がないため、建築費が発生しません。建物に対する投資責任は、借主側に一任できます。
また、その土地を使って事業を運営するのは借主側であるため、貸主は事業運営に関与する必要もありません。自分で事業を行うとなると、様々な管理業務や事業を維持する経費や手間が発生したり、事業を遂行する上で様々なリスクを抱えたりしなければなりませんが、貸主にそのような心配は発生しません。
土地を使って事業を行うのは借主側なので、事業の運営に伴う初期費用のほとんどなどを借主に一任しながら、貸主は地代収益を契約期間満了まで一定額もらえる仕組みです。従って、リスクを抑えて土地を有効活用できるわけです。
3-3.(貸主側)居住用よりも地代を高めに設定できる
メリット3つ目です。
地代の相場は、期待できる利回りや固定資産税をはじめとした課税される金額を加味して設定しますが、
一般的に、土地は「居住用」として貸し出すよりも「事業用」として貸し出す方が地代を高めに設定できる傾向があります。
例えば、上述した「一般定期借地権」は、居住用として貸し出されることが多い契約なのですが、それと比較すると、事業用定期借地権の方が高い地代収益を上げられる可能性が高いといえます。
3-4.(貸主側)評価額・相続税の軽減が期待できる
メリット4つ目です。
事業用定期借地権で土地を貸し出すと、契約の残存期間に応じて相続税の評価額が減額されます。
評価額が減額されるということは、相続税の軽減が期待できることを意味します。これは貸主にとって非常にメリットがあると言えます。
評価額の計算式は以下の通りです。
▶計算式
評価額=土地の価額-土地の価額×減額される割合
そしてさらに、以下の通り「減額される割合」は残存期間に応じて変化します。
残存期間 減額される割合 5年以下 5% 5年を超えて10年以下 10% 10年を超えて15年年以下 15% 15年を超える 20%
計算例として、「相続税の評価額が1億円の土地を定期借用地として貸し出した」という状況を想定して計算してみます。
▶契約条件
・契約期間:30年
・目的:事業用
・土地の評価額:1億円
▶10年後に相続した場合の評価額(残存期間20年)
1億円-1億円×0.2=8,000万円
▶20年後に相続した場合の評価額(残存期間10年)
1億円-1億円×0.1=9,000万円
如何でしょうか?以上のように、残存期間が多くなるほど評価額が軽減され、相続税対策になるわけです。
※参考:国税庁「No.4613?貸宅地の評価」
3-5.(借主側)土地の購入費用を抑えて事業を運営できる
メリット5つ目です。
これは借主側のメリットです。借主は土地の購入費用を持っていなくても、事業を開始できることが挙げられます。
事業を始めるには、資金が必要になるわけですが、建物をつくって始める規模の大きな事業となれば、多額の資金が必要になるものです。
事業を始める側にしてみればできるだけ初期投資に掛かる費用は抑えたいと思うでしょう。そこで、事業用定期借地権の制度を利用して土地を借りることができれば、土地を購入する必要はなくなります。
もちろん、土地を借りる訳なので貸主へ支払う賃料は必要ですが、初期投資の段階で、建物の建築費用を用意できさえすれば、事業用の物件を確保できるのは大きな魅力です。
新しい建物を建てて事業を始めるにあたって、初期投資する費用を抑えたい事業者に向いていると言えます。
3-6.(借主側)建物を自由にデザインできる
メリット6つ目です。
借主は、借りた土地に建てる建造物を自由にデザインできます。これも借主にとっては大きなメリットです。
事業用定期借地権の制度において、建物の所有権は借主側にあります。事業用の目的であれば建物の内装・外観に制限は出ないため、自由な建築が可能となります。
まずは無料で資料請求!
土地を貸して安定収入を見込む事業用定期借地権や、アパート・マンション・併用住宅など、複数プランの成功事例と比較できる資料を一括請求できます。
どんな提案が受けられるかを知ることで、自分に合った経営のイメージがぐっと具体的になります。まずは“次の一歩”をご自身の手で踏み出してみませんか。
無料一括資料請求を始める
4.事業用定期借地権を持つことによるデメリット(注意点)と対策
何事もメリットがあればデメリットもあるものですが、次は、この制度を利用する上で考えられる、土地の所有者(貸主)と借主の双方にとってのデメリットも解説します。
以下のデメリットがあると言えます。
・(貸主側)特約を設けても中途解約ができない
・(貸主側)事業者の倒産時、建物の扱いが困難になる
・(貸主側)用途が限定されているため、途中で用途を変更できない
・(貸主側)居住用と異なり、減税措置の特例が適用されない
・(貸主側・相続人)保証金不足でトラブルに発展する恐れがある
・(借主側)撤退リスクが伴う
以上6つです。
前項で解説をしたメリットだけに目を奪われることなく、双方にとって関係してくるリスクを把握したうえで契約の検討をすることが大切になるかと思います。
ここでは、単にデメリットだけを紹介するのではなく、事業用定期借地権の「注意点とその対策」についても詳しく解説したいと思います。
4-1.(貸主側)特約を設けても中途解約ができない
デメリットの1つ目です。
事業用定期借地権の契約では、原則として、貸主と借主ともに契約期間中は途中解約ができません。
これには「借主の利益を守る」というかなり大きな理由があるからです。上述しましたが、土地を借りる借主は事業を行うため、もし仮に1-2年の短期間で貸主から契約を切られてしまうと、事業に投資した資金を回収できないまま撤退を余儀なくされることになります。
ですから「自分の土地であっても、一度事業用定期借地権を使って土地を貸すと、契約期間満了までは自由に使うことができなくなるので注意しましょう!」ということなのです。
補足になりますが、借主は契約書に特約を設けることで中途解約ができる場合がありますが、貸主は特約を設けて中途解約をするといったことは不可能なので知っておいて頂きたい点になります。
▶対策
事業用定期借地権は、貸出期間が10年から50年と自由に選択できるため、運用目的に応じて期間を設定できると上述しましたが、土地の所有者(貸主)は、土地を貸し出す期間を十分に吟味することが、このデメリットに対する対策となります。
短い契約でも10年は地代収入と引き換えに土地を貸すことになりますので、今後のご自身の土地利用の可能性も忘れずに考慮した上で、契約に臨むことが大切になります。
ご子息などへの土地の相続を視野に入れている方々は、特に長期での契約をする際は十分注意することが必要になるでしょう。
4-2.(貸主側)事業者の倒産時、建物の扱いが困難になる
デメリットの2つ目です。
事業用定期借地権で土地を貸し出した場合、もしも契約期間中に、借主の事業所が倒産した場合は、建物が残ったままで土地が貸主へ返還されることになります。
通常、契約満了時に土地が返還される時は、更地にした土地が貸主へ返還されるのですが、借主である事業所が倒産した場合では、更地にしたくてもできない可能性が出てくるわけです。その場合、建物の取り壊し費用を貸主側が負担しなければなりません。
さらに、倒産したとは言え、建物の所有権は借主にあるため、貸主側が勝手に建物を取り壊すことができません。取り壊すためにも法的な手続きが必要になってしまいます。これはかなり手痛いデメリットとなります。
ですから、借主の事業が破綻してしまうと、貸主は収益が得られないだけでなく、貸主側に上記の様な対応の手間や費用負担が発生してしまいかねないので注意をしましょう。
▶対策
どんな取引でも同じことが言えますが、契約前に借主側に対する与信調査が必要不可欠です。
確かに契約時点ではその先の予測をすることなど誰にもできませんが、契約前は、信用調査の内容をもとに、経営基盤がしっかりしており社会的責任も持ち合わせた事業者へ貸すことが重要になります。
4-3.(貸主側)用途が限定されているため、途中で用途を変更できない
デメリットの3つ目です。
事業用定期借地権は、その名の通り、土地の用途が事業用に限定されています。そのため、当然、貸し出している途中で用途を変更することはできません。
例えば、借主側の事業が上手くいかなくなった時に、途中で事業の方向性を変更して、住居用のマンション運営を打診しても、それは認められません。
▶対策
貸主は、土地の利用目的を具体的に定めた上で、やはり長期での見通しを立てる必要があります。
ご自身の土地をどのように運用していくのか考慮して、土地を貸し出しましょう。
4-4.(貸主側)居住用と異なり、減税措置の特例が適用されない
デメリットの4つ目です。
土地に、新しい居住用の建物を建てた場合、3年間(マンションであれば5年間)、固定資産税が2分の1に減税されるという特例が適用されます(適用期限:令和6年3月31日)(※)。
しかし、事業用の建物にはその特例は適用されないため、減税措置は受けられません。居住用で貸し出すよりも事業用で貸し出す方が地代収入が高くなる可能性はあるので、どっちが良いか?ということも判断基準の一つになると思います。
▶対策
土地を事業用だけに決めて運用しない場合は、別の借地権での契約を視野に入れましょう。
特に、居住用で運用したい意向もあるなら、事業用定期借地権を利用しないことも考え方の一つです。
※参考:国土交通省「住宅:新築住宅に係る税額の減額措置」
4-5.(貸主側・相続人)保証金不足でトラブルに発展する恐れがある
デメリットの5つ目です。
事業用定期借地権を利用して借主と契約を交わす際に、保証金を受け取ることがあります。
しかし、契約期間中にその保証金を使う必要がなく契約満了を向かえた場合、この保証金は借主に返還する必要があるのですが、保証金不足でトラブルになるケースが散見されるので注意が必要です。
それにしても、なぜ保証金不足のトラブルなどが発生してしまうのでしょうか?
答えは「相続」です。事業用定期借地権で土地を貸す場合、契約期間の選択幅は、最低でも10年、長期だと50年と長期間に渡ります。保証金不足のトラブルの火種は、長期に渡る契約期間中に相続が発生した際にくすぶることになります。
相続が発生した場合、保証金の返還義務も契約時の貸主から相続人に引き継がれなければなりませんが、その相続人が保証金の返還義務の話しを聞いていなく知らなかった場合、返還しなければならない保証金をすぐに準備できず、借主側とトラブルに発展することになります。
▶対策
貸主は、相続のことを視野に入れて、相続人に保証金を含めて相続をするように手続きすることが重要です。
また、保証金の返還が必要である旨も合わせて伝わるように手配しましょう。
4-6.(借主側)撤退リスクが伴う
デメリットの6つ目です。
借主は、契約満了時に更地で土地を返還する必要があります。そのため、当然、建物の取り壊しが必要になります。
建物を解体するには、規模にもよりますが、数十〜数百万円の費用はかかってきます。これは分かっていた事であっても、借主にとって大きな負担となる場合があります。
事業用定期借地権で土地を借りていた場合は、事業が軌道に乗っていたとしても、契約満了時点で原則的には、その土地から退去する必要があります。別の土地を借りて同じ事業を継続するにしても、移転費がかかります。このように撤退に際して思わぬ費用が発生しかねません。
▶対策
収支計画を考えて契約しましょう。普段の諸費用だけではなく、撤退時や移転時に発生するであろう費用を考慮して計算しておくことも大切です。
また土地の契約形態に関する情報は、担当者が変わっても引き継ぎがされる流れを作っておくことです。
以上、事業用定期借地権を使った契約における、貸主・借主双方のメリットとデメリットを解説しました。
理解を深めて頂いたところで、次の章では「地代相場の計算例」「事業用定期借地権に適した土地」「良くある疑問」に関して順番に解説・回答をしていきます。
5.事業用定期借地権で請求できる地代の相場を計算
地代の相場は、主に「相当地代」を目安にすることが一般的です。
相当地代は原則、更地価格の6%程度とされています(※)。
以下、5億円規模の土地を貸し出す際の計算例を記載しますので、ご参考になさってください。
▶計算式
更地価格:5億円
相当地代:5億円×0.06=3,000万円(年額)
請求できる月額の地代:3,000万円÷12か月=250万円(月額)
「相当地代」はあくまで目安になります。
実際には土地の周辺地域を含めた場所、借主の事業内容、交渉によって詳細な価格が決定されることになります。
事業運用で見込まれる収益も高く見積もられれば、宅地運用よりも高額な地代で契約ができる場合がほとんどです。
安価な地代で契約すると、契約期間満了まで長期間、低い収益しか得られなくなってしまいますので、
積極的に交渉を行って、双方納得する価格で地代を設定しましょう。
※出典:国税庁「No.5732?相当の地代及び相当の地代の改訂」
6.事業用定期借地権の契約はこのような土地におすすめ
事業用定期借地権の契約で貸し出すにあたって、どんな条件の土地が適しているのか?を見ていきましょう。
以下のような条件の土地が適していると言えます。
● まとまった大きさのある土地
● 長期間使用予定がない土地(少なくとも契約期間内)
● 商業地域に近い土地
● 大きな道路や交通量の多い道路に面した土地
以上4つの条件です。
事業用定期借地権では、土地の使用は事業用途に限られますから、スーパーやドラッグストア、コンビニエンスストアを筆頭に、その他商業施設で活用されるのが一般的です。
そのため、店舗が建てられるスペースと来店用の車が駐車できるスペースが確保できる、まとまった広さ、大きさの土地が最適です。
商業地域や、大きな道路や交通量の多い道路に面しているロードサイドの土地は、住宅用としては不向きですが、事業用には最適です。事業所にとっても利益が見込めそうな土地であればあるほど、借り手はつきやすくなります。
「住宅用としては向いていない」と思い込んでいた土地も「事業用途には向いていた!」といった可能性はあるので、そうした観点でもご自身の土地を確認してみてください。
しかし、貸出しの契約期間は、10年から50年のため長期に渡ります。土地の所有者は、借主と契約を交わすと貸主となり、中途解約はできず、後戻りはできなくなりますので、これから先も長期間使用する予定がない土地であることを、念の為確認をしてから検討を開始しましょう。
7.事業用定期借地権に関するよくある疑問
最後の章です。ここでは「事業用定期借地権に関してよくある質問や疑問」を3つまとめてみました。
あなたの疑問と同じものがあるかどうか?確認してみてください。
7-1.事業用定期借地権の登記は必要なのか?
疑問の1つ目は「事業用定期借地権の登記は必要なのか?」という疑問です。
これは、登記が必要という考えと、不要という考えで見解が分かれています。
双方の考えは以下の通りです。
・登記が必要とする考え
貸主と借主以外の第三者とのトラブルを避けるため、通常の借地権との違いが分かるように登記するべき。
・登記が不要とする考え
借地借家法で法的効力があるため、登記は不要。
後者の登記は「不要」と考えている人たちが根拠にした「借地借家法10条」には、以下の条文が記載されています。
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」。
いずれにしても「登記をするか?しないか?」の問題は、貸主と借主の協力が必要になりますから、双方で事前に話し合って決めるべき内容になります。
もし登記をするのであれば、登記方法を下記しておきますのでご確認ください。
▶登記方法
以下必要書類を持って、不動産のある法務局へ申請。
・必要書類
登記済権利証か登記識別情報
登記原因証明情報
印鑑証明書(3か月以内発行・土地の所有者)
土地の所有者の実印と、借りる人の忍印
固定資産評価証明書か固定資産納税通知書
・登記費用
不動産価格の1,000分の10(※)
例:土地価格が1億であれば100万円
※出典:e-Gov法令検索「登録免許税法」
7-2.事業用定期借地権と抵当権、どちらが優先されるのか?
疑問の2つ目は「事業用定期借地権と抵当権、どちらが優先されるのか?」です。
抵当権をご存知でしょうか?「抵当権」とは、金融機関から資金を融資してもらう時などに、土地を担保にした時に、金融機関がその土地に対する権利を持つことを言います。
疑問に対する答えとしては、基本的に、抵当権の設定と賃貸借契約は、登記した順番の早い方が優先されます。
ただ、抵当権の所有に関して金融機関を含めた同意の登記があれば、優先順位の変更が可能となっています。
7-3.駐車場経営は事業用定期借地権の対象か?
疑問の3つ目は「駐車場経営をする場合は事業用定期借地権の対象か?」といった疑問です。
「定期借地権」は、建物の所有を目的とした権利になります。そのため、建物が必要ない駐車場運営は、定期借地権の対象外となります。補足として、マンションに併設する駐車場は居住用と判断されるため、これも事業用定期借地権が適用されません。
事業用定期借地権の対象となる条件は、「建物があり事業用」として運用されていることが必須ということになります。参考にしてみてください。
まずは無料で資料請求!
土地活用は大きな投資ですが、決してひとりで進めるものではありません。借地や賃貸併用住宅など複数プランを横断比較することも重要です。
今こそ、“第一歩”を踏み出しましょう。どんな提案が受けられるかを知ることで、自分に合った経営のイメージがぐっと具体的になります。
無料一括資料請求を始める
この記事のまとめ
以上、今回は、事業用定期借地権について解説をしてきました。
事業用定期借地権とは、事業の用途に限定し土地を貸す権利のことで、土地所有者のメリットとしては、居住用と比較して、高い地代で貸し出せることが期待できる点です。
他にも、契約期間は10年以上50年未満と、短期から長期まで設定できることや、相続税対策になる点、土地所有者自身は、事業リスクを負うことなく、土地の借主から安定した地代収入を得ることができる点もメリットとなります。
デメリットとしては、原則として中途解約ができず、借主と契約を交わすと後戻りが効かない点です。
他にも、万が一、借主の事業が倒産した場合は、地代収入が入って来なくなるのはもちろん、建物が残ったまま土地が返還されることになり、建物の取り壊し費用を貸主側が負担する必要性が出ることです。
また、長期に渡る契約期間中に、貸主側で相続が発生した場合、相続人に保証金の引き継ぎがされていないと、契約満了時に借主へ返還する保証金が不足して返還できない事態になると借主側と金銭トラブルに発展してしまう危険性があることなどが注意が必要な点となります。
このようなメリットとデメリットを踏まえた上でご検討頂ければと思います。
事業用定期借地権を使った土地の賃貸借契約は長期に渡るものになりますので、貸主と借主、双方が、その内容を理解していないとトラブルに発展することもありますので、今回の記事を是非とも参考にして頂き、事業用定期借地権の制度をしっかり理解した上で、計画的に土地を活用して頂きたいと思います。
▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php
賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php
家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php
不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php
記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。
ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
高インパクト・ボトムバーバナー
- カテゴリ:
- FAQーよくあるご質問ー
FAQーよくあるご質問ーの関連記事
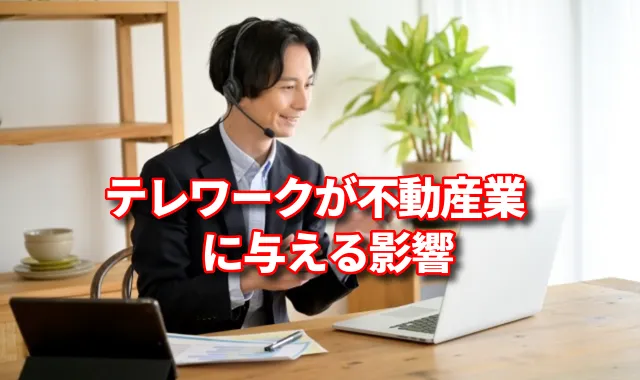
- リモートワークで変わるアパート経営|郊外ニーズが高まる理由と成功のポイント 公開

- 中国不動産バブル崩壊が日本に与える影響とは|投資家が知っておくべきポイント 公開
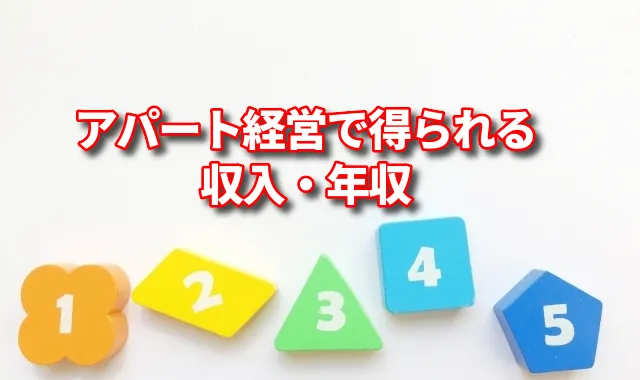
- アパート経営の年収相場と収支内訳|収入の実態と税金まで徹底解説 公開
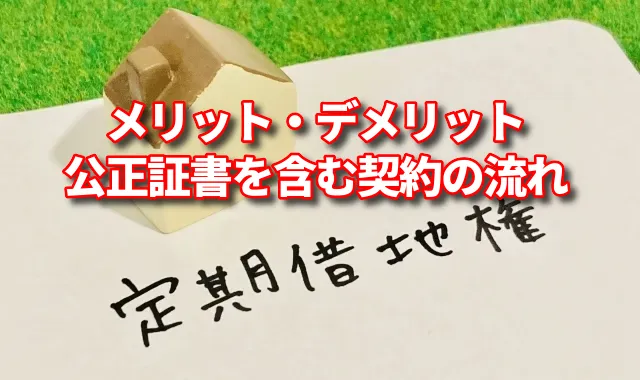
- 土地を貸して有効活用をしたい方へ|事業用定期借地権のメリット・デメリットを解説 公開
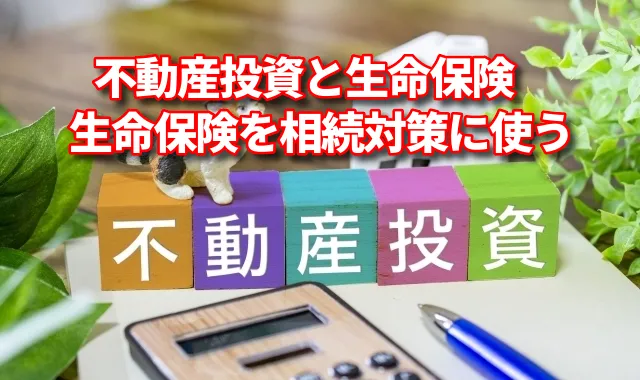
- 不動産投資で使える生命保険|相続対策に効果的な活用法を解説 公開
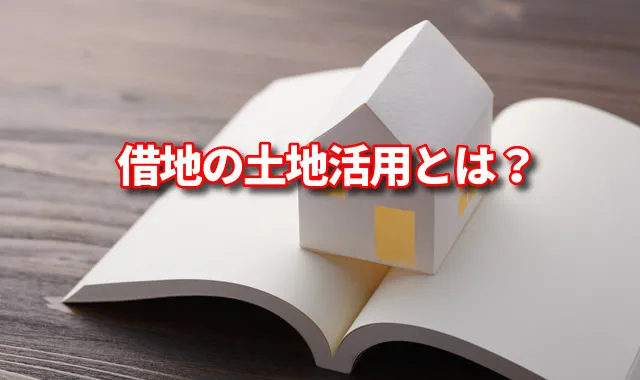
- 借地で賢く土地活用|地代相場と定期借地権メリットを徹底解説 公開
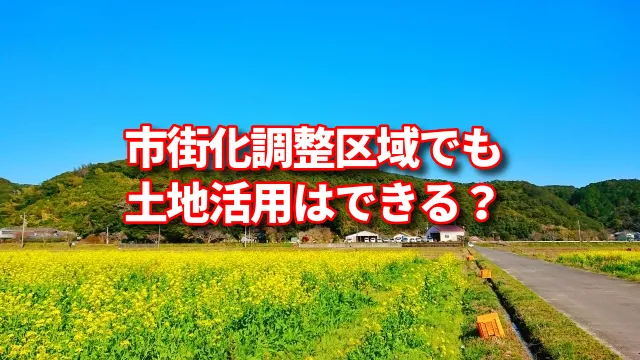
- 市街化調整区域でもあきらめない!土地活用の可否と実現のポイントとは 公開

- アパート建築費用の相場はいくら?|坪単価・自己資金・会社選びをやさしく解説 公開

- 30坪の狭小地はこう活かす!失敗しない土地活用アイデア9選 公開
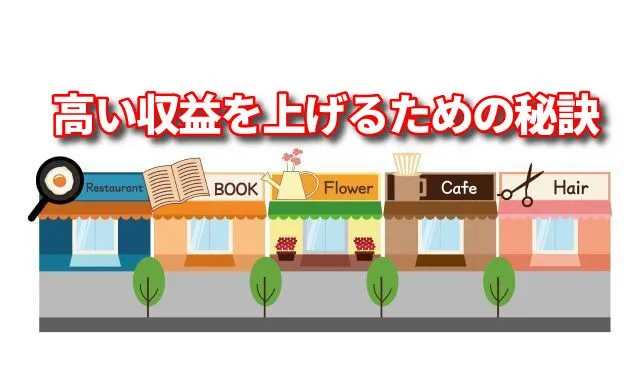
- 商業施設経営をする時の気になる費用を紹介|高収益を上げるコツも解説 公開

- アパート建築会社と管理会社の比較ポイント|選び方を解説 公開
補足の1つ目です。公正証書の費用は「公正証書手数料令」によって定められています。
費用は目的の価額によって決定されます。借地であれば、10年分の賃料の2倍が目的の価額(※)となっています。
以下の表が、価額ごとの手数料です。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
例えば、毎月100万円の賃料で土地を貸し出す場合なら以下の計算になります。
-
● 価額:100万円×12か月×10年×2=2億4,000万円
● 手数料:4万3,000円+1万3,000円+1万3,000円+1万3,000円=8万2,000円
この様になります。
また、気になる点として「公正証書の費用は誰が支払うのか?」ということがあると思います。実は、これには、負担者(貸主・借主)をどちらにするかについての明確な決まりがないので、貸主と借主が話し合いで決定します。
※出典:日本公証人連合会「Q. 売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明」
補足の2つ目です。公正証書で契約する時の流れは以下となります。
- 公正証書で契約する前に、覚書契約で契約を取り交わす
- 覚書契約を含めた必要書類を集める
- 公証役場で公正証書の作成を申し込む
- 予約日に契約者が出向いて公正証書の作成・支払を済ませる
以上4つです。
一つ目の「覚書契約」についてさらに補足をしておきますと、事業用定期借地権の場合は、公正証書で契約をする前に「覚書契約」の締結を行います。
この覚書を交わす目的は「お互いの契約意思を確認する」ためになります。貸主・借主双方に、契約意思があることを確認することは必要ですから、公正証書で本契約を締結する前の準備段階として覚書契約を取り交わすことには意味があります。
ただ、この覚書は、契約意思確認を目的としたものなので法的な効力はありません。ですから、この覚書を交わしたからと言って「絶対に本契約を結ばないといけない」というものではありません。本契約前に貸主・借主のどちらかが契約することを取りやめることは可能になっています。
2.事業用定期借地権と借地借家法で定められたほかの借地権との違い
次に「事業用定期借地権と借地借家法で定められた他の借地権との違い」について解説します。
借地権には「普通借地権」「定期借地権」の2つがあります。
普通借地権は更新ができることを前提にした契約ですが、定期借地権は更新がされないことを前提とした契約です。
例えば、電車の「定期券」は有効期間が来ると使えなくなりますが、「定期」の意味合いとしてはそれと同じです。
定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「一時使用目的」「事業用定期借地権」の4種類があるのですが、事業用定期借地権は、その中の1つです。
事業用定期借地権と他の借地権との違いをまとめると以下の表の通りとなります。
それらの違いについても解説していきます。
| 普通借地権 | 定期借地権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 一時使用目的 | 事業用定期借地権 | ||
| 契約期間 | 30年以上 | 50年以上 | 30年以上 | 短期間 | 10年以上50年未満 |
| 用途 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 客観的合理的に短期間と認められるもの(※1) | 事業用(居住用途は不可) |
| 契約終了時 | 更新可能 | 更地にして返還(※2) | 30年経過で地主が建物を買い取り | 契約内容に応じる | 更地にして返還(※2) |
| 土地活用例 | 制限なし | マンション他 制限なし | 制限なし | 仮設のプレハブ・選挙事務所・企画展など | 店舗・事務所・工場など |
※1 出典:裁判所「昭和43年3月28日最高裁判例 本文」
※2 建物譲渡特約付借地権と併用することで、契約の更新が可能(事業用定期借地権は30年以上の契約が条件)。
2-1.一般定期借地権は用途が自由な分、期間が最も長い
1つ目の「一般定期借地権」は、事業用定期借地権と比べると用途に制限がありません。
自由に土地を活用できるため、利用目的に関係なく土地の賃貸が可能です。契約満了時は、借主は更地にして貸主へ返還する必要があります。
また、一般的借地権は、最低契約期間が最も長い点も特徴です。最低50年以上の契約となるため、貸主にとって長期的な収入を得るのに向いています。
2-2.建物譲渡特約付借地権は期間の下限が少し長い
2つ目の「建物譲渡特約付借地権」は、契約期間の下限が30年です。
後程詳しく解説する事業用定期借地権の下限が10年ですから、それと比較すると長く設定がされています。そのため、中期での貸し出し・運用に向いていると言えます。
契約満了時には、借主は更地にして貸主へ返還するのではなく、貸主が建物を買い取る必要があります。
ただ、貸主が建物を買い取った後に借主が引き続きその建物を利用したい場合は、「借家契約」として引き続き貸し出すことができる契約になります。
また、建物譲渡特約付借地権は「一般定期借地権」「事業用定期借地権」と併用できることが特徴です。
例えば、最初に事業用定期借地権10年で契約した場合、建物譲渡特約付借地権も契約することで契約期間を延長できるといったイメージです。
2-3.一時使用目的は用途・期間の自由度が比較的高い
3つ目の「一時使用目的」は、用途や期間が明確に制限されてなく、自由度が比較的高い制度といえます。
ただ一方で、これは、客観的かつ合理的に短期間の利用だと認められる必要があるということが前提になります。
例えば、仮設のプレハブ・選挙事務所・企画展などといった「短期間だけ貸したい」場合に向いているものになります。
長期の利用とみなされると、一時使用目的に該当せず、別の借地権が適用される可能性が出るため注意が必要です。
2-4.事業用定期借地権の契約には公正証書が必要
4つ目は「事業用定期借地権」です。
上述しました通り、この契約のみ、「公正証書」が必須とされています。その他の定期借地権に関しては、以下の通り必須とはされていません。
-
●一般定期借地権:公正証書等の書面
●建物譲渡特約付借地権:口頭でも可
※出典:国土交通省「建設産業・不動産業:定期借地権の解説 」
3.事業用定期借地権を持つことによるメリット
さて、ここから更に事業用定期借地権について掘り下げて解説していきましょう。
まず、この制度を利用するメリットですが、土地の所有者(貸主)と借主の双方にとって、以下のメリットがあると言えます。
-
・(共通)貸出期間を最短10年・最長50年から選べる
・(貸主側)事業リスクを負わずに安定した収益を得られる
・(貸主側)居住用よりも地代を高めに設定できる
・(貸主側)評価額・相続税の軽減が期待できる
・(借主側)土地の購入費用を抑えて事業を運営できる
・(借主側)建物を自由にデザインできる
以上6つです。
これら6つの「事業用定期借地権を持つことで得られるさまざまなメリット」を以下で詳しく解説します。
3-1.(共通)貸出期間を最短10年・最長50年から選べる
メリット1つ目です。
事業用定期借地権は、貸出期間が10年から50年と自由に選択できるため、運用目的に応じて期間を設定できます。
例えば、「契約の時点で、10年後に別の土地活用を予定していれば短期で契約」、「特に予定がなければ長期で契約」と選択することができます。
以下が、貸主側・借主側、双方にとっての、長期・短期のメリットです。
| 長期のメリット | 短期のメリット | |
|---|---|---|
| 貸主側 | 長期的に不労所得を得られる | 別の土地活用が予定にある際に、それまで収入を得られる |
| 借主側 | 30年以上であれば買取請求権の行使ができる | 短期間の事業運用に向いている返還期間が見えているため計画を立てやすい |
3-2.(貸主側)事業リスクを負わずに安定した収益を得られる
メリット2つ目です。
土地の所有者である貸主は、事業リスクを負わずに、安定した収入を得られるというメリットがあります。
例えば、土地を貸し出す際に、貸主が借主のために建物を建築して用意をする必要がないため、建築費が発生しません。建物に対する投資責任は、借主側に一任できます。
また、その土地を使って事業を運営するのは借主側であるため、貸主は事業運営に関与する必要もありません。自分で事業を行うとなると、様々な管理業務や事業を維持する経費や手間が発生したり、事業を遂行する上で様々なリスクを抱えたりしなければなりませんが、貸主にそのような心配は発生しません。
土地を使って事業を行うのは借主側なので、事業の運営に伴う初期費用のほとんどなどを借主に一任しながら、貸主は地代収益を契約期間満了まで一定額もらえる仕組みです。従って、リスクを抑えて土地を有効活用できるわけです。
3-3.(貸主側)居住用よりも地代を高めに設定できる
メリット3つ目です。
地代の相場は、期待できる利回りや固定資産税をはじめとした課税される金額を加味して設定しますが、
一般的に、土地は「居住用」として貸し出すよりも「事業用」として貸し出す方が地代を高めに設定できる傾向があります。
例えば、上述した「一般定期借地権」は、居住用として貸し出されることが多い契約なのですが、それと比較すると、事業用定期借地権の方が高い地代収益を上げられる可能性が高いといえます。
3-4.(貸主側)評価額・相続税の軽減が期待できる
メリット4つ目です。
事業用定期借地権で土地を貸し出すと、契約の残存期間に応じて相続税の評価額が減額されます。
評価額が減額されるということは、相続税の軽減が期待できることを意味します。これは貸主にとって非常にメリットがあると言えます。
評価額の計算式は以下の通りです。
▶計算式
-
評価額=土地の価額-土地の価額×減額される割合
そしてさらに、以下の通り「減額される割合」は残存期間に応じて変化します。
| 残存期間 | 減額される割合 |
|---|---|
| 5年以下 | 5% |
| 5年を超えて10年以下 | 10% |
| 10年を超えて15年年以下 | 15% |
| 15年を超える | 20% |
計算例として、「相続税の評価額が1億円の土地を定期借用地として貸し出した」という状況を想定して計算してみます。
▶契約条件
-
・契約期間:30年
・目的:事業用
・土地の評価額:1億円
▶10年後に相続した場合の評価額(残存期間20年)
-
1億円-1億円×0.2=8,000万円
▶20年後に相続した場合の評価額(残存期間10年)
-
1億円-1億円×0.1=9,000万円
如何でしょうか?以上のように、残存期間が多くなるほど評価額が軽減され、相続税対策になるわけです。
※参考:国税庁「No.4613?貸宅地の評価」
3-5.(借主側)土地の購入費用を抑えて事業を運営できる
メリット5つ目です。
これは借主側のメリットです。借主は土地の購入費用を持っていなくても、事業を開始できることが挙げられます。
事業を始めるには、資金が必要になるわけですが、建物をつくって始める規模の大きな事業となれば、多額の資金が必要になるものです。
事業を始める側にしてみればできるだけ初期投資に掛かる費用は抑えたいと思うでしょう。そこで、事業用定期借地権の制度を利用して土地を借りることができれば、土地を購入する必要はなくなります。
もちろん、土地を借りる訳なので貸主へ支払う賃料は必要ですが、初期投資の段階で、建物の建築費用を用意できさえすれば、事業用の物件を確保できるのは大きな魅力です。
新しい建物を建てて事業を始めるにあたって、初期投資する費用を抑えたい事業者に向いていると言えます。
3-6.(借主側)建物を自由にデザインできる
メリット6つ目です。
借主は、借りた土地に建てる建造物を自由にデザインできます。これも借主にとっては大きなメリットです。
事業用定期借地権の制度において、建物の所有権は借主側にあります。事業用の目的であれば建物の内装・外観に制限は出ないため、自由な建築が可能となります。
まずは無料で資料請求!
土地を貸して安定収入を見込む事業用定期借地権や、アパート・マンション・併用住宅など、複数プランの成功事例と比較できる資料を一括請求できます。
どんな提案が受けられるかを知ることで、自分に合った経営のイメージがぐっと具体的になります。まずは“次の一歩”をご自身の手で踏み出してみませんか。
4.事業用定期借地権を持つことによるデメリット(注意点)と対策
何事もメリットがあればデメリットもあるものですが、次は、この制度を利用する上で考えられる、土地の所有者(貸主)と借主の双方にとってのデメリットも解説します。
以下のデメリットがあると言えます。
-
・(貸主側)特約を設けても中途解約ができない
・(貸主側)事業者の倒産時、建物の扱いが困難になる
・(貸主側)用途が限定されているため、途中で用途を変更できない
・(貸主側)居住用と異なり、減税措置の特例が適用されない
・(貸主側・相続人)保証金不足でトラブルに発展する恐れがある
・(借主側)撤退リスクが伴う
以上6つです。
前項で解説をしたメリットだけに目を奪われることなく、双方にとって関係してくるリスクを把握したうえで契約の検討をすることが大切になるかと思います。
ここでは、単にデメリットだけを紹介するのではなく、事業用定期借地権の「注意点とその対策」についても詳しく解説したいと思います。
4-1.(貸主側)特約を設けても中途解約ができない
デメリットの1つ目です。
事業用定期借地権の契約では、原則として、貸主と借主ともに契約期間中は途中解約ができません。
これには「借主の利益を守る」というかなり大きな理由があるからです。上述しましたが、土地を借りる借主は事業を行うため、もし仮に1-2年の短期間で貸主から契約を切られてしまうと、事業に投資した資金を回収できないまま撤退を余儀なくされることになります。
ですから「自分の土地であっても、一度事業用定期借地権を使って土地を貸すと、契約期間満了までは自由に使うことができなくなるので注意しましょう!」ということなのです。
補足になりますが、借主は契約書に特約を設けることで中途解約ができる場合がありますが、貸主は特約を設けて中途解約をするといったことは不可能なので知っておいて頂きたい点になります。
▶対策
| 事業用定期借地権は、貸出期間が10年から50年と自由に選択できるため、運用目的に応じて期間を設定できると上述しましたが、土地の所有者(貸主)は、土地を貸し出す期間を十分に吟味することが、このデメリットに対する対策となります。 短い契約でも10年は地代収入と引き換えに土地を貸すことになりますので、今後のご自身の土地利用の可能性も忘れずに考慮した上で、契約に臨むことが大切になります。 ご子息などへの土地の相続を視野に入れている方々は、特に長期での契約をする際は十分注意することが必要になるでしょう。 |
4-2.(貸主側)事業者の倒産時、建物の扱いが困難になる
デメリットの2つ目です。
事業用定期借地権で土地を貸し出した場合、もしも契約期間中に、借主の事業所が倒産した場合は、建物が残ったままで土地が貸主へ返還されることになります。
通常、契約満了時に土地が返還される時は、更地にした土地が貸主へ返還されるのですが、借主である事業所が倒産した場合では、更地にしたくてもできない可能性が出てくるわけです。その場合、建物の取り壊し費用を貸主側が負担しなければなりません。
さらに、倒産したとは言え、建物の所有権は借主にあるため、貸主側が勝手に建物を取り壊すことができません。取り壊すためにも法的な手続きが必要になってしまいます。これはかなり手痛いデメリットとなります。
ですから、借主の事業が破綻してしまうと、貸主は収益が得られないだけでなく、貸主側に上記の様な対応の手間や費用負担が発生してしまいかねないので注意をしましょう。
▶対策
| どんな取引でも同じことが言えますが、契約前に借主側に対する与信調査が必要不可欠です。 確かに契約時点ではその先の予測をすることなど誰にもできませんが、契約前は、信用調査の内容をもとに、経営基盤がしっかりしており社会的責任も持ち合わせた事業者へ貸すことが重要になります。 |
4-3.(貸主側)用途が限定されているため、途中で用途を変更できない
デメリットの3つ目です。
事業用定期借地権は、その名の通り、土地の用途が事業用に限定されています。そのため、当然、貸し出している途中で用途を変更することはできません。
例えば、借主側の事業が上手くいかなくなった時に、途中で事業の方向性を変更して、住居用のマンション運営を打診しても、それは認められません。
▶対策
| 貸主は、土地の利用目的を具体的に定めた上で、やはり長期での見通しを立てる必要があります。 ご自身の土地をどのように運用していくのか考慮して、土地を貸し出しましょう。 |
4-4.(貸主側)居住用と異なり、減税措置の特例が適用されない
デメリットの4つ目です。
土地に、新しい居住用の建物を建てた場合、3年間(マンションであれば5年間)、固定資産税が2分の1に減税されるという特例が適用されます(適用期限:令和6年3月31日)(※)。
しかし、事業用の建物にはその特例は適用されないため、減税措置は受けられません。居住用で貸し出すよりも事業用で貸し出す方が地代収入が高くなる可能性はあるので、どっちが良いか?ということも判断基準の一つになると思います。
▶対策
| 土地を事業用だけに決めて運用しない場合は、別の借地権での契約を視野に入れましょう。 特に、居住用で運用したい意向もあるなら、事業用定期借地権を利用しないことも考え方の一つです。 |
4-5.(貸主側・相続人)保証金不足でトラブルに発展する恐れがある
デメリットの5つ目です。
事業用定期借地権を利用して借主と契約を交わす際に、保証金を受け取ることがあります。
しかし、契約期間中にその保証金を使う必要がなく契約満了を向かえた場合、この保証金は借主に返還する必要があるのですが、保証金不足でトラブルになるケースが散見されるので注意が必要です。
それにしても、なぜ保証金不足のトラブルなどが発生してしまうのでしょうか?
答えは「相続」です。事業用定期借地権で土地を貸す場合、契約期間の選択幅は、最低でも10年、長期だと50年と長期間に渡ります。保証金不足のトラブルの火種は、長期に渡る契約期間中に相続が発生した際にくすぶることになります。
相続が発生した場合、保証金の返還義務も契約時の貸主から相続人に引き継がれなければなりませんが、その相続人が保証金の返還義務の話しを聞いていなく知らなかった場合、返還しなければならない保証金をすぐに準備できず、借主側とトラブルに発展することになります。
▶対策
| 貸主は、相続のことを視野に入れて、相続人に保証金を含めて相続をするように手続きすることが重要です。 また、保証金の返還が必要である旨も合わせて伝わるように手配しましょう。 |
4-6.(借主側)撤退リスクが伴う
デメリットの6つ目です。
借主は、契約満了時に更地で土地を返還する必要があります。そのため、当然、建物の取り壊しが必要になります。
建物を解体するには、規模にもよりますが、数十〜数百万円の費用はかかってきます。これは分かっていた事であっても、借主にとって大きな負担となる場合があります。
事業用定期借地権で土地を借りていた場合は、事業が軌道に乗っていたとしても、契約満了時点で原則的には、その土地から退去する必要があります。別の土地を借りて同じ事業を継続するにしても、移転費がかかります。このように撤退に際して思わぬ費用が発生しかねません。
▶対策
| 収支計画を考えて契約しましょう。普段の諸費用だけではなく、撤退時や移転時に発生するであろう費用を考慮して計算しておくことも大切です。 また土地の契約形態に関する情報は、担当者が変わっても引き継ぎがされる流れを作っておくことです。 |
以上、事業用定期借地権を使った契約における、貸主・借主双方のメリットとデメリットを解説しました。
理解を深めて頂いたところで、次の章では「地代相場の計算例」「事業用定期借地権に適した土地」「良くある疑問」に関して順番に解説・回答をしていきます。
5.事業用定期借地権で請求できる地代の相場を計算
地代の相場は、主に「相当地代」を目安にすることが一般的です。
相当地代は原則、更地価格の6%程度とされています(※)。
以下、5億円規模の土地を貸し出す際の計算例を記載しますので、ご参考になさってください。
▶計算式
-
更地価格:5億円
相当地代:5億円×0.06=3,000万円(年額)
請求できる月額の地代:3,000万円÷12か月=250万円(月額)
「相当地代」はあくまで目安になります。
実際には土地の周辺地域を含めた場所、借主の事業内容、交渉によって詳細な価格が決定されることになります。
事業運用で見込まれる収益も高く見積もられれば、宅地運用よりも高額な地代で契約ができる場合がほとんどです。
安価な地代で契約すると、契約期間満了まで長期間、低い収益しか得られなくなってしまいますので、 積極的に交渉を行って、双方納得する価格で地代を設定しましょう。
※出典:国税庁「No.5732?相当の地代及び相当の地代の改訂」
6.事業用定期借地権の契約はこのような土地におすすめ
事業用定期借地権の契約で貸し出すにあたって、どんな条件の土地が適しているのか?を見ていきましょう。
以下のような条件の土地が適していると言えます。
-
● まとまった大きさのある土地
● 長期間使用予定がない土地(少なくとも契約期間内)
● 商業地域に近い土地
● 大きな道路や交通量の多い道路に面した土地
以上4つの条件です。
事業用定期借地権では、土地の使用は事業用途に限られますから、スーパーやドラッグストア、コンビニエンスストアを筆頭に、その他商業施設で活用されるのが一般的です。
そのため、店舗が建てられるスペースと来店用の車が駐車できるスペースが確保できる、まとまった広さ、大きさの土地が最適です。
商業地域や、大きな道路や交通量の多い道路に面しているロードサイドの土地は、住宅用としては不向きですが、事業用には最適です。事業所にとっても利益が見込めそうな土地であればあるほど、借り手はつきやすくなります。
「住宅用としては向いていない」と思い込んでいた土地も「事業用途には向いていた!」といった可能性はあるので、そうした観点でもご自身の土地を確認してみてください。
しかし、貸出しの契約期間は、10年から50年のため長期に渡ります。土地の所有者は、借主と契約を交わすと貸主となり、中途解約はできず、後戻りはできなくなりますので、これから先も長期間使用する予定がない土地であることを、念の為確認をしてから検討を開始しましょう。
7.事業用定期借地権に関するよくある疑問
最後の章です。ここでは「事業用定期借地権に関してよくある質問や疑問」を3つまとめてみました。 あなたの疑問と同じものがあるかどうか?確認してみてください。
7-1.事業用定期借地権の登記は必要なのか?
疑問の1つ目は「事業用定期借地権の登記は必要なのか?」という疑問です。
これは、登記が必要という考えと、不要という考えで見解が分かれています。
双方の考えは以下の通りです。
-
・登記が必要とする考え
貸主と借主以外の第三者とのトラブルを避けるため、通常の借地権との違いが分かるように登記するべき。
・登記が不要とする考え
借地借家法で法的効力があるため、登記は不要。
後者の登記は「不要」と考えている人たちが根拠にした「借地借家法10条」には、以下の条文が記載されています。
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」。
いずれにしても「登記をするか?しないか?」の問題は、貸主と借主の協力が必要になりますから、双方で事前に話し合って決めるべき内容になります。
もし登記をするのであれば、登記方法を下記しておきますのでご確認ください。
▶登記方法
|
以下必要書類を持って、不動産のある法務局へ申請。 ・必要書類 登記済権利証か登記識別情報 登記原因証明情報 印鑑証明書(3か月以内発行・土地の所有者) 土地の所有者の実印と、借りる人の忍印 固定資産評価証明書か固定資産納税通知書 ・登記費用 不動産価格の1,000分の10(※) 例:土地価格が1億であれば100万円 |
7-2.事業用定期借地権と抵当権、どちらが優先されるのか?
疑問の2つ目は「事業用定期借地権と抵当権、どちらが優先されるのか?」です。
抵当権をご存知でしょうか?「抵当権」とは、金融機関から資金を融資してもらう時などに、土地を担保にした時に、金融機関がその土地に対する権利を持つことを言います。
疑問に対する答えとしては、基本的に、抵当権の設定と賃貸借契約は、登記した順番の早い方が優先されます。
ただ、抵当権の所有に関して金融機関を含めた同意の登記があれば、優先順位の変更が可能となっています。
7-3.駐車場経営は事業用定期借地権の対象か?
疑問の3つ目は「駐車場経営をする場合は事業用定期借地権の対象か?」といった疑問です。
「定期借地権」は、建物の所有を目的とした権利になります。そのため、建物が必要ない駐車場運営は、定期借地権の対象外となります。補足として、マンションに併設する駐車場は居住用と判断されるため、これも事業用定期借地権が適用されません。
事業用定期借地権の対象となる条件は、「建物があり事業用」として運用されていることが必須ということになります。参考にしてみてください。
まずは無料で資料請求!
土地活用は大きな投資ですが、決してひとりで進めるものではありません。借地や賃貸併用住宅など複数プランを横断比較することも重要です。
今こそ、“第一歩”を踏み出しましょう。どんな提案が受けられるかを知ることで、自分に合った経営のイメージがぐっと具体的になります。
この記事のまとめ
以上、今回は、事業用定期借地権について解説をしてきました。
事業用定期借地権とは、事業の用途に限定し土地を貸す権利のことで、土地所有者のメリットとしては、居住用と比較して、高い地代で貸し出せることが期待できる点です。
他にも、契約期間は10年以上50年未満と、短期から長期まで設定できることや、相続税対策になる点、土地所有者自身は、事業リスクを負うことなく、土地の借主から安定した地代収入を得ることができる点もメリットとなります。
デメリットとしては、原則として中途解約ができず、借主と契約を交わすと後戻りが効かない点です。
他にも、万が一、借主の事業が倒産した場合は、地代収入が入って来なくなるのはもちろん、建物が残ったまま土地が返還されることになり、建物の取り壊し費用を貸主側が負担する必要性が出ることです。
また、長期に渡る契約期間中に、貸主側で相続が発生した場合、相続人に保証金の引き継ぎがされていないと、契約満了時に借主へ返還する保証金が不足して返還できない事態になると借主側と金銭トラブルに発展してしまう危険性があることなどが注意が必要な点となります。
このようなメリットとデメリットを踏まえた上でご検討頂ければと思います。
事業用定期借地権を使った土地の賃貸借契約は長期に渡るものになりますので、貸主と借主、双方が、その内容を理解していないとトラブルに発展することもありますので、今回の記事を是非とも参考にして頂き、事業用定期借地権の制度をしっかり理解した上で、計画的に土地を活用して頂きたいと思います。
▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php
賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php
家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php
不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php
記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。
ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- FAQーよくあるご質問ー
FAQーよくあるご質問ーの関連記事
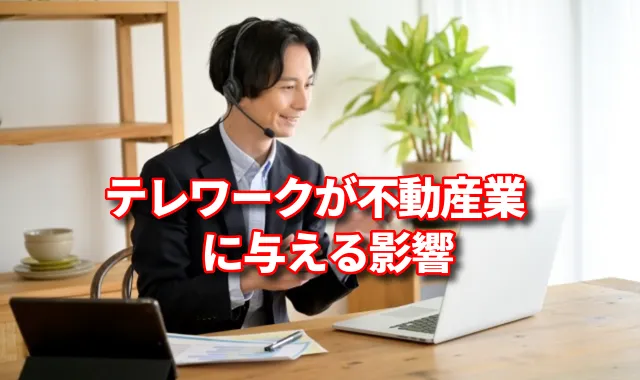
- リモートワークで変わるアパート経営|郊外ニーズが高まる理由と成功のポイント 公開

- 中国不動産バブル崩壊が日本に与える影響とは|投資家が知っておくべきポイント 公開
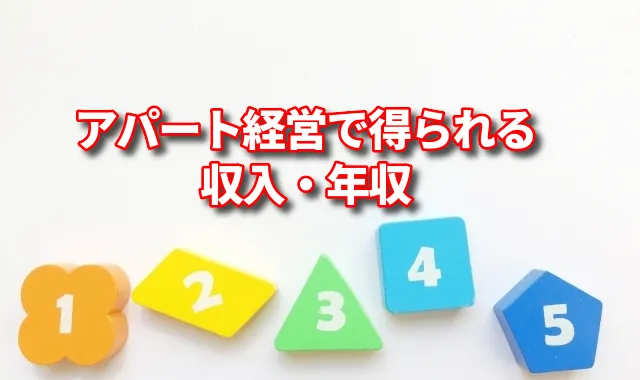
- アパート経営の年収相場と収支内訳|収入の実態と税金まで徹底解説 公開
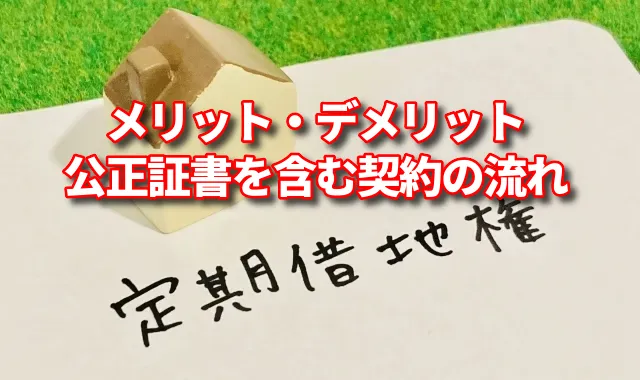
- 土地を貸して有効活用をしたい方へ|事業用定期借地権のメリット・デメリットを解説 公開
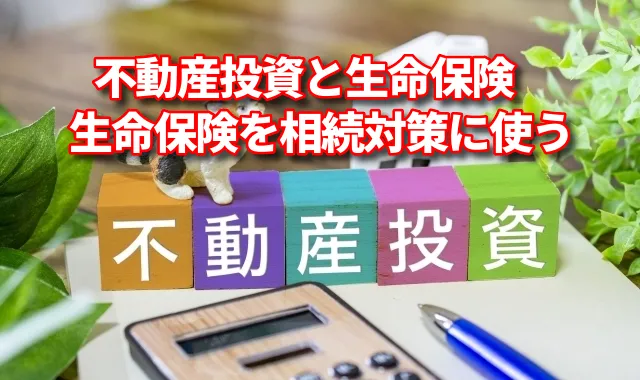
- 不動産投資で使える生命保険|相続対策に効果的な活用法を解説 公開
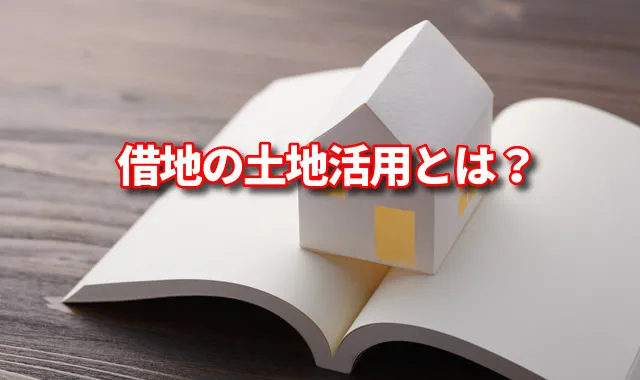
- 借地で賢く土地活用|地代相場と定期借地権メリットを徹底解説 公開
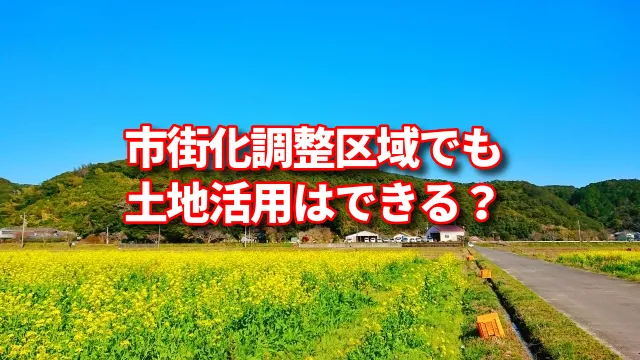
- 市街化調整区域でもあきらめない!土地活用の可否と実現のポイントとは 公開

- アパート建築費用の相場はいくら?|坪単価・自己資金・会社選びをやさしく解説 公開

- 30坪の狭小地はこう活かす!失敗しない土地活用アイデア9選 公開
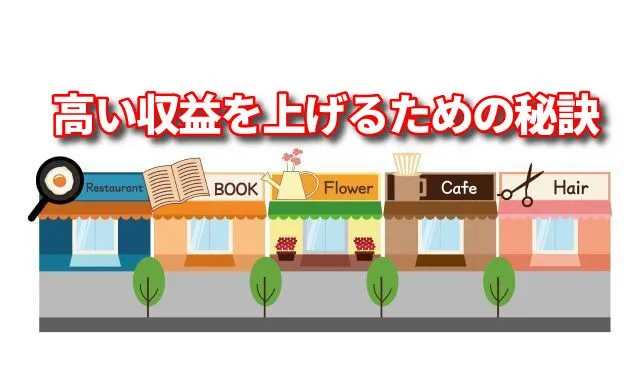
- 商業施設経営をする時の気になる費用を紹介|高収益を上げるコツも解説 公開

- アパート建築会社と管理会社の比較ポイント|選び方を解説 公開