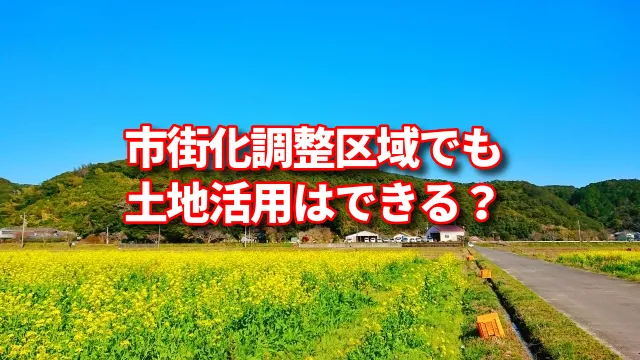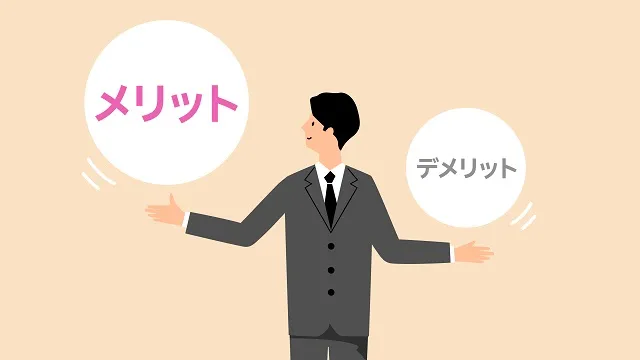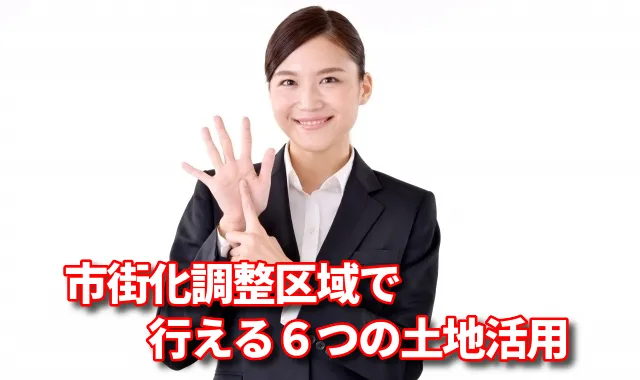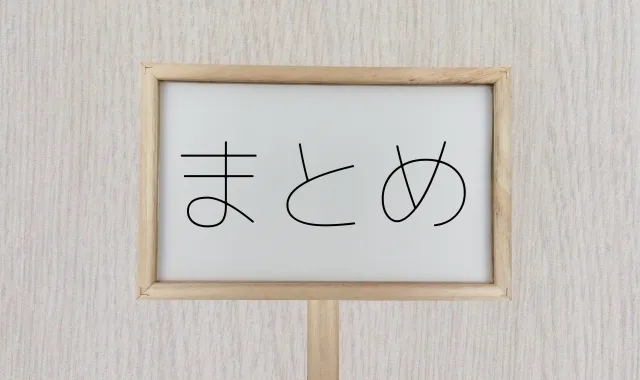- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- FAQーよくあるご質問ー
- 【イエカレ】市街化調整区域でもあきらめない!土地活用の可否と実現のポイントとは
【イエカレ】市街化調整区域でもあきらめない!土地活用の可否と実現のポイントとは
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.市街化調整区域とは
全国各地の土地は、都市計画法に基づいて「都市計画区域」「都市計画区域外」「準都市計画区域」の区域区分のいずれかが適用されています。
さらに、都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引都市計画区域」の3つに分類されています。
市街化区域とは、既に市街化が進んでいる地域、おおむね10年以内に市街化を進めていく地域です。市街地の類型に応じて13種類の用途地域が定められており、建築できる建物の用途や容積率、建蔽率などに規制が設けられています。
市街化調整区域とは、市街化が抑制されている地域です。住宅や施設といった建物の建築が原則禁止されています。
非線引都市計画区域とは、都市計画区域内に位置するものの、市街化区域または市街化調整区域のいずれにも属していない地域です。市街化区域や市街化調整区域と比べると、建物の建築に関する制限が緩いのが特徴です。
市街化区域や非線引都市計画区域は原則建物の建築が可能ですが、市街化調整区域は原則建物の建築が禁止されているため、土地活用を行う場合は手段が限られるので注意が必要です。
まず、ご自身の土地が「どの区域区分」になっているのか?が曖昧な方は、正確なご住所を確認した上で、最寄りの市区町村の都市計画課へお電話やメールでお問い合わせをされると良いでしょう。
インターネットならGoogle検索などから「市町村名」「市街化調整区域」とで検索すれば各市区町村のホームページで都市計画図をみることが可能ですので、それをご活用してみましょう。
まずは無料で資料請求!
市街化調整区域の土地でも、活用の可能性はゼロではありません。実際に、複数の専門業者から“市街化調整区域で可能な活用プラン”を提案してもらえる無料資料請求サービスもあります。
アパート・マンション経営なども視野に入れて、自分の土地でできることを具体的に比較検討してみましょう。
2.市街化調整区域のメリット
建物の建築が原則禁止されている市街化調整区域ですが、他の区域とは異なるメリットを有しています。
市街化調整区域の主なメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- ● ランニングコストを抑えられる
- ● 環境変化が生じにくい
- ● 広大な敷地が手に入りやすい
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
2-1.ランニングコストを抑えられる
建物を原則建てられる市街化区域や非線引都市計画区域と比較すると、残念ながら、市街化調整区域は資産価値が低いと言えます。
しかし、資産価値が低いということは固定資産税評価額も低くなるため、不動産の所有者に対して毎年課される固定資産税や都市計画税を大幅に抑えることが可能とも言えます。
市街化調整区域の土地を取得して活用することになった場合、ランニングコストを大幅に抑えることで利回りが高くなることが大きなメリットと言えるでしょう。
2-2.環境変化が生じにくい
例えば、市街化区域で土地を所有していて、土地活用として太陽光発電を始めたとします。市街化区域では原則建物を建築できるため、近隣に高い建物が建築された場合はパネルに十分な日光が当たらず、収益に大きな支障が生じるので注意が必要です。
しかし、市街化調整区域は市街化が抑制されている地域なので、開発行為が原則禁止されています。数年以内に大きな建物が建築される、商業施設が完成するなど急激に市街化が進むことはほとんどありません。
市街化調整区域内で土地活用を行った場合は環境変化による影響を受けにくいため、収益予想を立てやすいともいえます。
2-3.広大な敷地が手に入りやすい
上述したように、市街化区域と市街化調整区域の土地の資産価値を比べると、市街化区域の資産価値の方が高くなります。そのため、土地の購入に充てられる資金が同じ場合、市街化調整区域の方が広大な敷地を手に入れることが可能です。
例えば、土地活用の手段として、駐車場経営や太陽光発電などを選んだ場合、敷地が狭いと駐車できる車の数や設置できるパネルの数が少なく利回りが低くなります。
しかし、敷地が広ければ駐車できる車の数や設置できるパネルの数が増えて、より多くの利益が得られるため、高利回りでの運用が期待できます。
広大な敷地の方がより多くの利益が期待できる土地活用に取り組もうと考えている人は、市街化区域よりも市街化調整区域の方が良いと言えるでしょう。
3.市街化調整区域のデメリット
市街化調整区域は、ランニングコストを抑えられる、環境変化が生じにくい、広大な敷地が手に入りやすいといったメリットがありました。
メリットだけを見ると、市街化調整区域は土地活用に向いていそうですが、以下の3つのデメリットを伴うので注意が必要です。
- ● 開発が制限されている
- ● インフラ整備が不十分である
- ● 利便性の低さから需要が期待できない
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
3-1.開発が制限されている
市街化調整区域では、原則建物の建築が禁止されています。「市街化調整区域で既に建物が建っている場合はどうなるの?」と気になった人も多いと思います。
既存の建物も建て替えや増築、リノベーションなどについても原則許可が必要になるので注意が必要です。
しかし、市街化調整区域の土地でも、一定の用途に関しては建物を建築できます。
例えば、開発地域に住んでいる人が必要な店舗や学校などの施設、ホテルや遊園地、ゴルフ場などの鉱山や観光資源の設備、市街化区域に建設できない寺や墓、老人ホームなどです。
一定の用途に関しては建物を建築できると言っても、必ず建築できるわけではありません。開発が認められた時しか建築できず、基本的に制限されているので注意しましょう。
3-2.インフラ整備が不十分である
市街化区域は、積極的に市街化を進めているため、電気やガス、水道などのライフラインや道路や鉄道、病院などの生活に必要な施設といったインフラが整備されています。
しかし、市街化調整区域は、市街化を目的としている地域ではなく自然や資源を守るための地域であるため、インフラが整備されていないことがほとんどです。
「将来的に整備されるのでは?」と期待した人もいるかもしれませんが、市街化調整区域に指定されている間は市街化が進まないため、整備される保証はありません。
地震や豪雨といった災害が生じた場合、道路が崩落または土砂崩れで埋まった場合は、生活インフラがストップする可能性もあります。
土地活用を検討する場合は、インフラ整備が不十分な環境でも利益が期待できる手段を選ぶことが重要です。
3-3.利便性の低さから需要が期待できない
電気やガス、水道などのライフライン、道路や鉄道、病院などの生活に必要な施設といったインフラが整備されていないということは、居住に適している環境とは言えない面があります。
ですから、建物の建築が認められて店舗経営を始めても、需要がほとんど期待できないことが多いため、安定した利益を得ることは厳しいと言えます。
また、基本的にはスーパーやコンビニ、娯楽施設などが近くにないと、土地活用のために市街化調整区域の土地を購入しても、後で買い手が見つからない可能性が高いという点に注意が必要です。
まずは無料で資料請求!
なお、「市街化調整区域の土地をどう活用すればいいかわからない」「複数の不動産会社の提案を比較したい」という方は、無料の一括資料請求サービス『イエカレ』をご利用ください。
地域や条件に合った不動産会社を効率よく見つけることができます。土地の活用方法をじっくり比較検討したい方におすすめです。
4.市街化調整区域の6つの土地活用
市街化調整区域では、原則建物の建築が禁止されているため、土地活用を検討している人は、建物を建築せずに取り組める土地活用の手段を選ぶのが無難と言えます。
しかし、建築が認められた場合、建物の建設を伴う土地活用の手段を選ぶことができますが、居住環境が優れているわけではないため、土地活用の手段をしっかり選ぶことが重要です。
市街化調整区域で行える土地活用として、以下の6つが挙げられます。
- ● 駐車場経営
- ● 資材置き場
- ● 太陽光発電
- ● 霊園・墓地
- ● 社会福祉施設
- ● 医療施設
それぞれの土地活用の手段について詳しく見ていきましょう。
4-1.駐車場経営

立体駐車場経営では建物の建設が必要ですが、平面駐車場経営では建物の建設が不要です。そのため、平面駐車場であれば市街化調整区域でも速やかに始められます。
駐車場経営は土地を整備するだけで簡単に開業できるため、他の土地活用と比べて投資を大幅に抑えられるというメリットがあります。また、他の用途への転用を行いやすいため、一時的に運用したいという場合でも選択可能です。
コインパーキングではなく、月極駐車場として利用者と長期契約を締結した場合、継続的に安定した駐車場収入が期待できます。
しかし、駐車場需要の見込めないエリアでは、駐車場経営を始めても安定した駐車場収入が期待できません。
月極駐車場では維持コストや管理コストがほとんどかからないため、駐車場収入をあまり得られなくても影響を受けにくいと言えます。
しかし、コインパーキングでは維持コストや管理コストがかかるため、駐車場経営の継続が困難になるという点に注意が必要です。
駐車場経営では建物の建設を伴わないため、市街化調整区域の土地活用に適していますが、上記のようなデメリットも伴うため、よく考えてから土地活用を始めましょう。
4-2.資材置き場

事業で使う木材や鉄鋼などの置き場に悩む企業に、資材置き場として土地を提供するのも土地活用の選択肢の1つです。
企業の中には、仕入れた木材や鉄鋼などの置き場を確保できずに悩んでいる企業もいます。そのような企業に資材置き場として土地を提供した場合、長期的な収益を確保することが可能です。
土地を借りた企業が土地の運営と管理を行うのが一般的なので、土地の所有者はコストを負担することは基本的にありません。
また、駅から遠く離れている、交通量が少ないなど、土地活用に適していないような土地でも収益が期待できます。
しかし、資材置き場として企業に貸し出すという土地活用は、賃貸住宅や駐車場などの他の土地活用と比べると、得られる収益が少ないというデメリットが挙げられます。
また、周辺に借り手となってくれそうな企業がいくつかあれば問題ありませんが、基本的に一度借り手が付かなくなった場合は、次の借り手が見つかるまでに時間がかかるという点は注意が必要です。
上述した駐車場経営は、ある程度の整地を行う必要がありますが、資材置き場の場合は借りた企業が整地を行ってくれるケースが多いため、ほとんどコストをかけずに始められます。
しかし、借り手がすぐに見つからない可能性もあるため、周辺にどのような企業があるのか事前に調べてみましょう。
4-3.太陽光発電
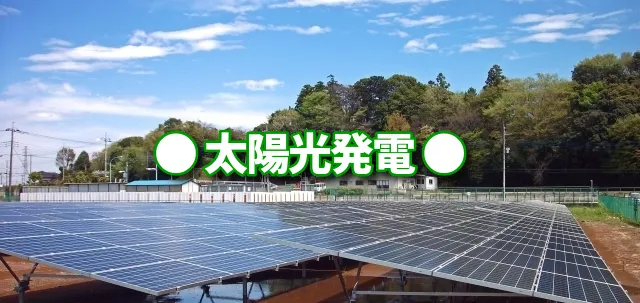
太陽光発電では地面に太陽光パネルを設置することから、「建築物に該当するのでは?」と思った人も多いと思います。
しかし、太陽光パネルは、建築基準法の定めている建築物には該当しません。そのため、市街化調整区域でも太陽光発電を行うことは可能です。
太陽光発電では、発電量の大きさに応じて、10年間または20年間固定価格で電気の買取を行ってくれるため、売電による収益が期待できます。
賃貸経営よりも初期投資が少ない、賃貸経営のように空室のリスクに悩まずに済むというメリットもあるため、太陽光発電は、土地を寝かしておくよりも少しでも収益を得たいという人におすすめです。
しかし、全ての土地で太陽光発電を行えるわけではありません。景観維持や周辺住民の保護、安全面への配慮といった理由で、太陽光発電を禁止するまたは規制する自治体もあるので注意が必要です。
また、太陽光発電では、太陽光パネルに不具合が生じると、安定した収益を確保できなくなります。そのため、保証サービスに加入する、定期的なメンテナンスを行わなくてはなりません。
上述した平面駐車場や資材置き場と比べて、初期投資が大きい、コストが多くかかるという点もよく理解した上で始めましょう。
4-4.霊園・墓地

霊園・墓地の運営者に、土地を貸し出して収益を得ることも土地活用の選択肢の1つです。
土地を貸し出すだけで、霊園・墓地の運営者が土地の運営と管理を行うため、資材置き場のケースと同様、基本的に土地の所有者がコストを負担することはありません。
霊園・墓地に適した条件を満たしている土地の場合、他の土地活用よりも長期的に安定した賃料を得ることが可能です。
しかし、必ずしも霊園・墓地の運営者からの需要が期待できるというわけではありません。
例えば、教育機関や医療機関が周辺にあるような土地は、霊園・墓地に不向きと言えます。地域によって自治体の許可が必要になる場合もあるので確認が必要です。
霊園・墓地の運営者に土地を貸し出す際は、土地の所有者として近隣住民や隣地所有者とのトラブルが生じないように配慮する必要もあります。
また、霊園・墓地の運営者は長期的な使用を前提としているため、土地の所有者の都合だけで簡単に契約を解除できなくなる点は考慮しておくべきでしょう。
もしも、将来的にご自身が使用する可能性がある場合は、土地を自由に使用できなくなりますから注意が必要です
ただ、長期的な土地の使用について問題がなければ、安定且つ継続的な地代収入が期待できるため、土地の所有者にとっては大きなメリットと言えます。
4-5.社会福祉施設

社会福祉施設は建物を建設しますが、自治体ごとに定められている条件を満たした場合は、特別に許可を得て建物を建築することが可能です。社会福祉施設はそのうちの1つです。
社会福祉施設には、介護老人保健施設や有料老人ホームなどが挙げられます。
介護老人保健施設とは、65歳以上で、要介護1以上の高齢者が対象の公的な施設です。医療サービスやリハビリが必要な期間だけ社会福祉施設に入居して、最終的には在宅復帰を目指します。
有料老人ホームとは、60歳以上の高齢者を対象として民間企業が運営している施設です。医療サービスやレクリエーション活動、イベントなど、様々なサービスを提供しています。
テナント方式でご自身が運営をするということではなく、社会福祉施設の運営者に土地を貸し出した場合は、資材置き場や霊園・墓地と同様、土地の所有者は管理と運営を行う必要はありません。
契約期間が比較的長期となるため、安定した賃料を得ることが可能です。
また、建物が建っていない土地を所有している場合、固定資産税が高くなりますが、社会福祉施設が建築された場合は固定資産税の負担が軽減されます。
しかし、社会福祉施設も長期的な土地の使用が前提となるため、土地の所有者の都合だけで簡単に契約解除または転用することはできなくなります。
反対に、上述した霊園・墓地と同様、土地を長期に渡って貸し出す意向があるなら、基本的に長期的な契約が期待できます。
注意点は、土地を貸し出した社会福祉施設選びに失敗した場合は、契約途中での解約となり、想定通りの地代収益が得られない可能性が出るので、貸し出す相手は信用調査をするなどして慎重に選ぶことが必要です。
もし、得たい地代収益を増やしたい場合は、土地の所有者が、施設建設とその運営を任せられるテナント業者を見つけて、建設後は、業者に土地と施設を貸し出すという選択肢もあります。
賃貸アパートや賃貸マンション経営のように収支計算とリスク対策が必要になりますが、ただ土地を貸し出すだけよりも多くの賃料収入が得られる可能性があります。
しかし、この方法の場合は、提携したテナントが事業撤退をしたり、破産してしまった場合は、建物を建築する際にかかった費用の返済だけが残ってしまう危険性があります。
安心して検討するためにも、信頼ができるパートナー選びと、リスク回避のため対策は十分に行いましょう。
4-6.医療施設

医療施設も社会福祉施設と同様、自治体ごとに定められている条件を満たした場合、特別に許可を得て建物を建築することが可能です。
開業予定の医師や医療法人の中には、できる限りコストを抑えながら病院を開業したいと考えている人もいます。ターゲットを絞って募集すれば、市街化調整区域でも十分に需要が期待できます。
医療施設の建設費用は、基本的に土地を借りた開業予定の医師や医療法人が負担するため、土地の所有者は初期費用の負担を抑えることが可能です。また、建物が建築されることで、固定資産税の負担を軽減できます。
しかし、全ての土地が医療施設に適しているというわけではありません。一番注意したいことは、医療施設が多いと需要が期待できなくなるため、医療施設は不向きとなります。
社会福祉施設のケースと同様、得られる収益を少しでも増やしたい場合は、医療施設を土地の所有者が建設して、土地と施設を貸し出すと選択肢も挙げられます。そうすれば、ただ土地を貸し出すだけよりも多くの賃料収入が得られる可能性があります。
しかし、これもまた、提携した開業予定の医師や医療法人が撤退をしたり、破産した場合は、建物の建設にかかった費用を回収できない可能性があるので注意が必要です。
そのため、建物の建築費用を土地の所有者が負担する方法を検討する場合は、安心して検討を進めるためにも、信頼できるパートナーなのか?をしっかり見極めた上で、リスク対策を十分に行いましょう。
まとめ
以上のように、この記事では「市街化調整区域とは何か?」「市街化調整区域のメリットとデメリット」「市街化調整区域でもできる土地活用の手段」をまとめました。
土地を取得したり、またはこれから土地を取得しようと検討している人の中には、市街化調整区域の土地でも問題なく土地活用ができるのか?と気になっている人も多いでしょう。
しかし、市街化調整区域の土地は、建物の建築が原則禁止されているため、土地活用できたとしても活用方法が制限されるので注意が必要です。
市街化調整区域は、100%土地活用に不向きというわけではないことはお分かり頂けたと思いますが、市街化調整区域で土地活用を行う場合は「土地活用の手段が限られる」ことも知っておいて頂ければと思います。
ですから、やみくもに検討をするのではなくどんな土地活用の手段があるのか事前によく理解してから土地活用を始めた方が良いと言えます。
市街化調整区域は制限が多く、独自に判断するのは難しいですが、専門家の提案を比較すれば、思わぬ活用の道が見つかるかもしれません。
「自分の土地で何ができるか」を明確にするために、まずは気軽に、複数社から資料を取り寄せて、条件を整理しながら最適な方法を探してみましょう。
短時間で、地域実績のある企業から提案資料が届きます。制約がある土地だからこそ、早めの情報収集が将来の価値を左右します。
▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php
賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php
家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php
不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php
記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。
ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- FAQーよくあるご質問ー
FAQーよくあるご質問ーの関連記事
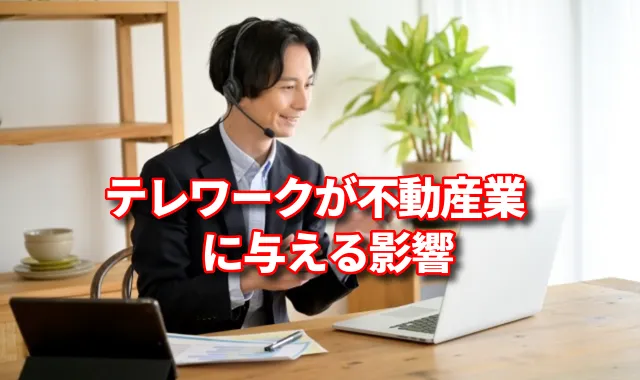
- リモートワークで変わるアパート経営|郊外ニーズが高まる理由と成功のポイント 公開

- 中国不動産バブル崩壊が日本に与える影響とは|投資家が知っておくべきポイント 公開
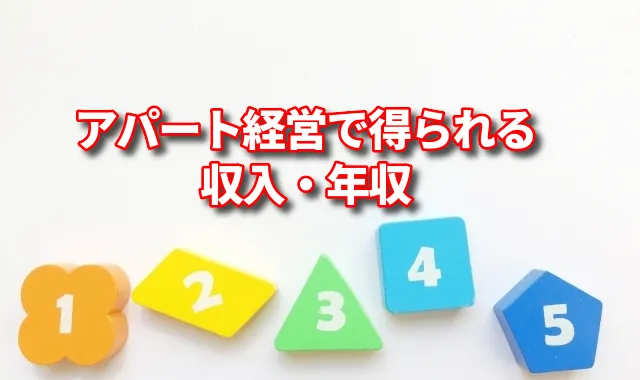
- アパート経営の年収相場と収支内訳|収入の実態と税金まで徹底解説 公開
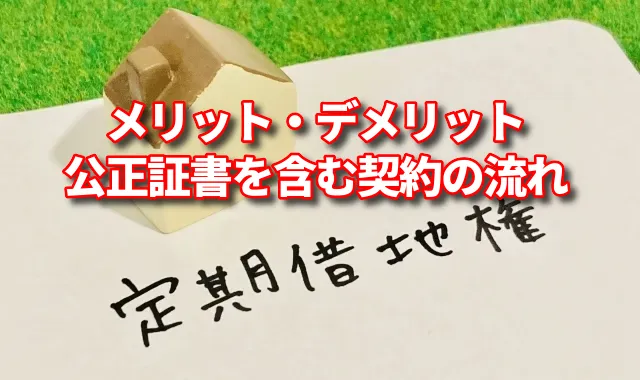
- 土地を貸して有効活用をしたい方へ|事業用定期借地権のメリット・デメリットを解説 公開
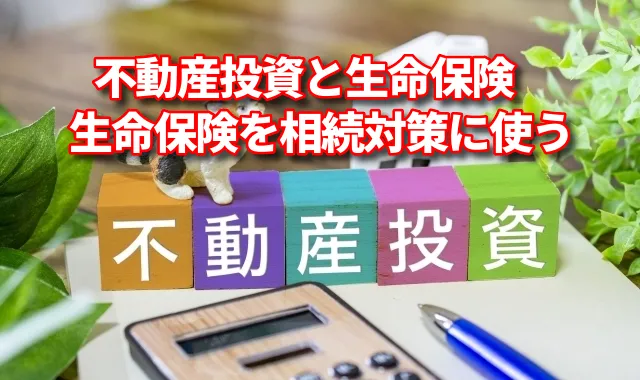
- 不動産投資で使える生命保険|相続対策に効果的な活用法を解説 公開
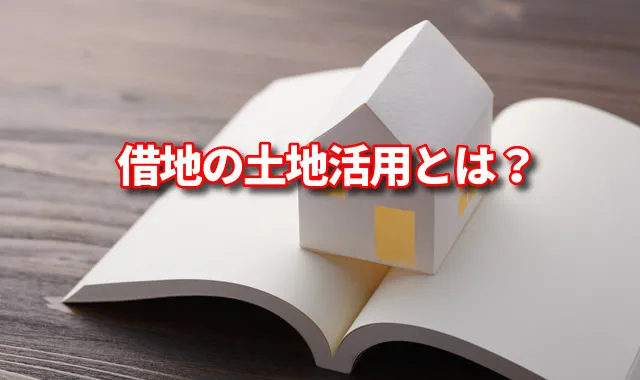
- 借地で賢く土地活用|地代相場と定期借地権メリットを徹底解説 公開
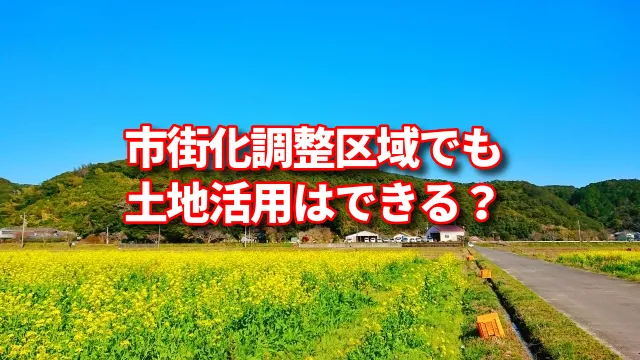
- 市街化調整区域でもあきらめない!土地活用の可否と実現のポイントとは 公開

- アパート建築費用の相場はいくら?|坪単価・自己資金・会社選びをやさしく解説 公開

- 30坪の狭小地はこう活かす!失敗しない土地活用アイデア9選 公開
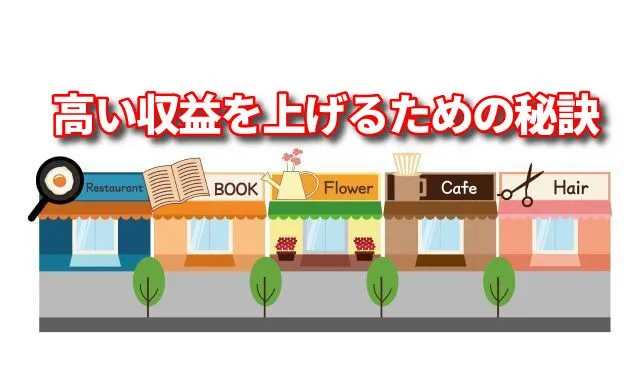
- 商業施設経営をする時の気になる費用を紹介|高収益を上げるコツも解説 公開

- アパート建築会社と管理会社の比較ポイント|選び方を解説 公開