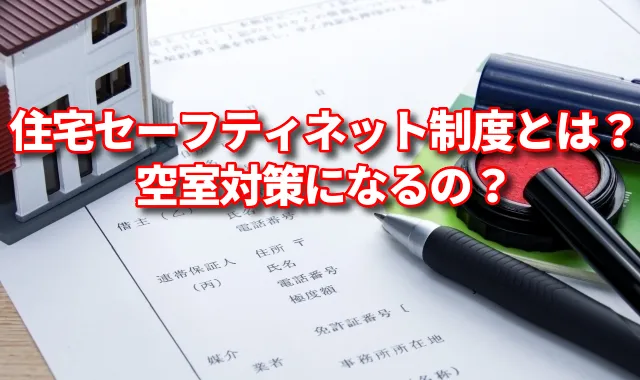- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 不動産管理会社
- アパート・マンションの空室対策
- 【イエカレ】住宅セーフティネット制度の活用法|賃貸オーナーの空室対策になるのか?
【イエカレ】住宅セーフティネット制度の活用法|賃貸オーナーの空室対策になるのか?
この記事を読むのにかかる時間:5分
住宅セーフティネット制度とは?空室対策となるか?その仕組みを解説します!
1.住宅セーフティネット制度とは
近年、日本では高齢者や障害者等の住宅の確保に配慮が必要な人々(住宅確保要配慮者)が増加傾向にあります。
社会福祉の観点からしますと、本来であれば住宅確保要配慮者への住宅供給は、国や地方自治体が行うべきものです。
しかしながら、人口減少社会の中で公営住宅を税金によって増やすことはもはや難しいといえる時代になってきています。
一方で、民間の賃貸住宅の空家は増加傾向にあることから、民間住宅の空家と住宅確保要配慮者をマッチングすれば、この課題を解決できる可能性があります。
このような時代背景の中から、2017年に住宅セーフティネット制度が登場しました。つまり、住宅セーフティネット制度とは、住宅確保要配慮者と民間の賃貸住宅をつなぐ制度といえます。
住宅セーフティネット制度で想定している住宅確保要配慮者とは、以下の様な方々が対象になります。
【住宅確保要配慮者】
|
・低額所得者 ・被災者(発生後3年以内) ・高齢者 ・障害者 ・高校生相当までの子どもを養育している者 ・外国人 ・東日本大震災等の大規模災害の被災者 ・都道府県や市区町村が供給促進計画において定める者(例えばLGBT等) |
もし、空室対策でお悩みの賃貸オーナー様が住宅セーフティネットの利用を始める場合は、自治体の窓口へ行き、ご自身の賃貸住宅を「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅」として登録する必要があります。
そして登録をすると、その賃貸住宅は「登録住宅」と「専用住宅」の2種類に分類されます。
専用住宅とは:住宅確保要配慮者の専用の住宅として登録した住宅のこと。
となります。
また、この登録の要件ですが、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅として登録するには、
●各戸25平米以上
●耐震性を有すること
●台所やトイレ、収納設備、浴室・シャワー室等の一定の設備を設置していること
●家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
等の要件を満たす必要があります。
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅は「居住支援協議会」によって住宅確保要配慮者に対して積極的に情報発信がされ、入居希望者と物件とのマッチングが図られる仕組みとなっています。
居住支援協議会とは、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して設立した協議会になります。
まずは無料で資料請求!
セーフティネット制度のように、空室対策には複数の選択肢があります。
まずは複数の管理会社の提案を比較することで、自分の物件に最適な活用方法が見えてきます。無料の一括資料請求を活用して、第一歩を踏み出してみましょう。
2. 住宅セーフティネットの利用/賃貸オーナー様のメリット
住宅セーフティネットに登録した場合の賃貸オーナー様のメリットは「登録住宅」と「専用住宅」で若干異なってきます。
まず「登録住宅」では、セーフティネット住宅情報提供システムに掲載されることになり、広く周知されることがメリットです。
住宅確保要配慮者に対して寛容な住宅は少ないため、セーフティネット住宅情報提供システムに物件情報が掲載されれば、それは十分な空室対策にもなります。
また、登録住宅は、居住支援法人や居住支援協議会により、円滑な入居のサポートや入居中の見守りサービス等を受けることができる点もメリットです。
居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、都道府県が指定した居住支援を行う法人を指します。単に民間の賃貸住宅として高齢者を受け入れるよりも、手厚いサポートを受けることができます。
一方で「専用住宅」では、改修費の補助がある点がメリットになります。耐震改修やバリアフリー改修、居住支援協議会等が必要と認める改修工事等の幅広い工事に対して、国費限度額として最大50万円/戸の補助金を受けることができます。
また、専用住宅では入居者に対して家賃補助があるため、入居者を確保しやすくなる点もメリットです。住宅確保要配慮者に対する訴求力は登録住宅よりも高くなると考えられます。
3. 住宅セーフティネットの利用/賃貸オーナーのデメリット
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅のデメリットは「入居者トラブルの発生の可能性が高い」という点です。
高齢者であれば孤独死、低額所得者であれば家賃の不払い等のトラブルが考えられます。
逆にいえば住宅確保要配慮者はトラブルの可能性が高いから、一般の賃貸住宅では残念ながら入居を断られるケースが多いのも確かです。
そのため、上述したようなデメリットを考えたくない賃貸オーナー様や、今この段階で普通に入居者が決まる賃貸物件を経営できているのであれば、無理に住宅セーフティネット制度を利用する必要性は低いといえるでしょう。
ただ、それでも、住宅セーフティネットの利用を検討されている賃貸オーナー様の場合、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅として登録する場合は「居住支援法人」とも連携を取りながら賃貸経営を行っていくことが望ましいです。
居住支援法人では、「登録住宅の入居者への家賃債務保証」、「住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談」、「見守りなど要配慮者への生活支援」等のサービスを行ってくれます。
一般的な管理会社では行わないサービスを提供していますので、居住支援法人と協力しながらリスクを最小化していくことをおすすめします。
まずは無料で資料請求!
制度の特徴や制約を理解した上で、他の空室対策と比較することも重要です。
複数社からの土地活用・管理提案を一括で取り寄せることで、納得のいく判断ができます。検討を深める第一歩にしてみてください。
4.住宅セーフティネット制度の利用を始めるにあたっての注意点
住宅セーフティネット制度を始めるにあたっての注意点としては「リスクを抑えながら始めること」。これが注意点です。
つまり、いきなり専用住宅として全戸を住宅確保要配慮者向け賃貸住宅として登録するという考えもあるのですが、まずは登録住宅として登録して「様子を見ながら戸数を増やしていく」やり方が安全といえます。
登録は、集合住宅の1住戸からでも可能です。
例えば、アパートの一室だけ、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅として登録してみるという進め方もあります。一室だけやってみて、効果があれば他の部屋にも拡大していく方が手堅いです。
また、登録住宅では入居を拒まない属性を選択でき、さらに条件も付けることができます。
例えば、入居を拒まない属性として「低額所得者のみ」とすることもできますし、さらに「生活保護受給者については、住宅扶助費の代理納付(自治体が直接家賃を支払うこと)がされる場合に限る」といった条件を付けることも可能です。
まとめ
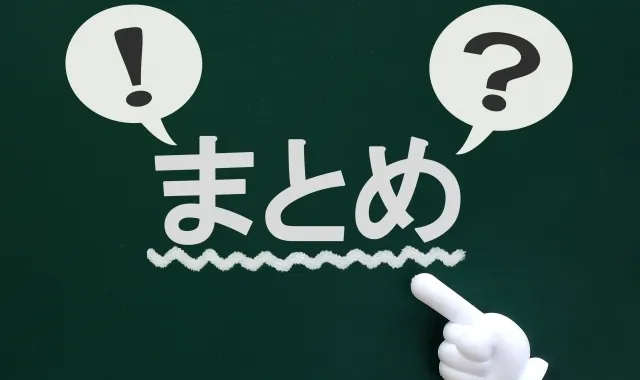
住宅セーフティネット制度のメリット・デメリットについて解説しました。
比較的新しい制度であるため、登録することで他の物件との差別化が可能になり、空室対策の一助となる可能性があります。
ただし、セーフティネット制度は有効な手段の一つに過ぎません。物件の特性や地域によって適性が異なるため、管理会社や土地活用会社を比較して、最適な活用方法を見極めることが重要です。
賃貸オーナーの方は、ぜひ無料一括資料請求を活用して、複数社の情報を比較検討し、空室対策に向けた第一歩を踏み出しましょう。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- アパート・マンションの空室対策
アパート・マンションの空室対策の関連記事

- 空室対策に効くIoT賃貸|メリットと事例を徹底解説 公開
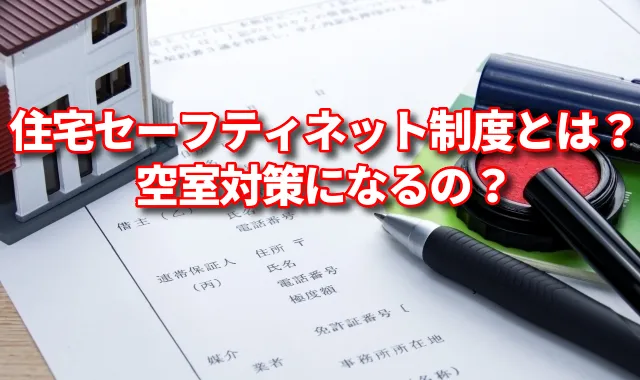
- 住宅セーフティネット制度の活用法|賃貸オーナーの空室対策になるのか? 公開