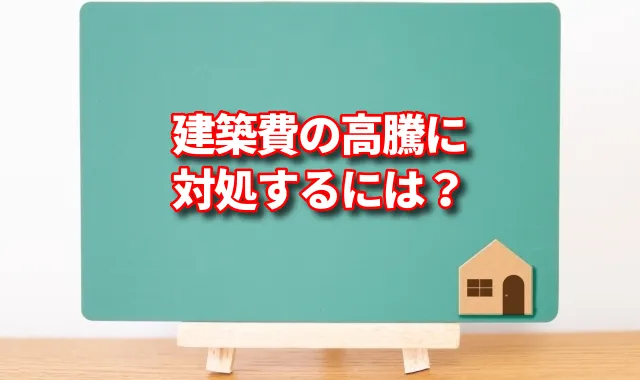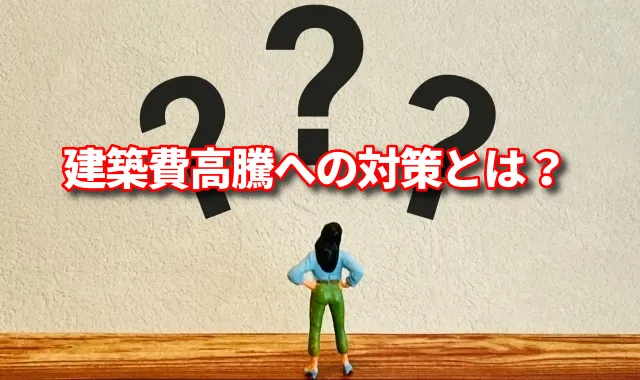- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- 賃貸経営の基礎知識
- 【イエカレ】アパート建築費が高騰しても安心!建築構造を活用した費用削減のポイント
【イエカレ】アパート建築費が高騰しても安心!建築構造を活用した費用削減のポイント
この記事を読むのにかかる時間:5分
現在の建築費高騰の理由と背景!
長期に渡るこの建築費高騰の原因ですが、実は複合的な要因が絡んでおり、もはや原因を一つ二つに限定ができない状況です。
この章では、現在の建築費高騰が続いている主な3つ理由と背景についてお伝えします。
まず1つ目の理由としては、建築業界の慢性的な人手不足が挙げられています。
覚えていらっしゃる方もいると思いますが、建築業界の人手不足は東日本大震災の復興事業を行っていたときにはすでに露呈しており社会問題にもなりました。
これは2011年頃の話ですが、先ほどお伝えした本格的に建築費が上昇し始めた2013年よりも前から問題が継続していると言えます。
2つ目の理由としては、日銀の低金利政策が挙げられます。
日銀は2013年頃から異次元金融緩和政策と呼ばれる超低金利政策を継続してきました。
住宅ローン等が組みやすくなったことから土地や建築費の価格が上がり始め、加えて2015年に相続税強化策が打ち出されたため、この時期は駆け込みでアパート建築をする人が急増しました。その結果、建築費の上昇に拍車がかかったことも一つの原因と考えられています。
3つ目の理由としては、円安です。
現在、日本が総じて円安傾向にあるのは、諸外国と比べて金利が低く、諸外国の方が金利が高い状態が続いているため、外国為替市場では高い金利の通貨で貨幣を運用した方が有利であるという状況があり、円が売られ円安圧力が継続している状況なのです。
もっとも円安状況下では多くの輸入品が割高になるため、建築関連では鉄鋼等の輸入品建築資材の値段も上がっているわけです。
そして2021年には輸入木材が高騰するウッドショックと呼ばれる現象が生じました。今はそのウッドショックは沈静化し始めたと言われますが、ただ、ウッドショックが沈静化しても円安傾向は続いていることで輸入資材の価格は高止まりの状況が続いているというわけです。
構造別の住宅価格相場
ここで、現在の建築材料別の住宅価格の相場を示すと、下表のようになります。
| 構造 | 建築費の坪単価相場 |
|---|---|
| 木造 | 坪70〜100万円 |
| 軽量鉄骨造 | 坪80〜110万円 |
| 重量鉄骨造 | 坪90〜120万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 坪100〜130万円 |
近年はこのような水準の坪単価相場は見慣れてしまいましたが、正直にいえばかなり高い水準です。
例えば、20年ほど前は「木造造り」なら「坪40万円程度」が相場でした。しかし、昨今では木造造りでも「坪80万円を超える」ことも珍しくなくなったので、昔の感覚と比べると2倍以上の金額になった印象です。
ただ、10年近くに渡って高騰し続ける建築費においても「材料別にみる建築費の価格の序列」は基本的に変わっていません。
建築費は安い順から「木造<軽量鉄骨造<重量鉄骨造<鉄筋コンクリート造」の順番でありこの序列は以前から変わらず同じ状況です。
建築資材の高騰はいつまで続く?
この建築資材の高騰、皆さまはいつまで続くと思われますか?
建築費の高騰は様々な要因が絡んでいて、一つの問題が解決されたからといってすぐに建築費が下がる状況にはなっていません。
上述した通り、その大きな要因として日銀の低金利政策を挙げましたが「日銀はもはや金利を上げられないのでは?」という見方もされています。
日銀は国債を大量保有しています。国債の価格は、金利と密接に連動しているので、金利を上げると国債の価格が下がるという関係になっています。
もし仮に日銀が金利を上げれば、自ら保有している国債価格を下げることに繋がるため、その多くの国債を抱えている日銀は多額の含み損を抱える状況に陥り自らの首を絞めることになります。つまり日銀の経営が悪化するわけです。
金利を上げる政策に舵を切った結果、日銀自身の経営が悪化すれば、今度は税金を投入せざるを得ないことも考えられます。さらには国が返済する借金の金額も増える結果を招きます。増税や社会保障の支出の削減等の国民の大きな痛みを伴います。「もはや金利を上げられないのでは?」と言われる背景にはこうした理由が絡んでいます。
日銀は物価の安定という中央銀行に課された命題を果たせない状態にあることから、残念ながら、多くの建築資材を輸入品に頼ってきた日本では、その高止まり傾向が収束する可能性は今後もかなり低いと予想されます。
建築費高騰への対策とは?
では今後、土地活用でアパート・マンション経営を検討したいと思っている方々は、この問題についてどう考えて行ったらよいのでしょうか?
この章では建築費高騰への対策を紹介します。
1.構造は木造と軽量鉄骨を中心に考える!
建築費を抑える考え方として【木造と軽量鉄骨を中心に考える】ことが大きな対処法です。
先程、建築費は安い順から木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順番で、それは昔も今も変わっていないと述べました。基本的に今も木造や軽量鉄骨造を中心にプランを考えた方が建築費は安く抑えられること繋がります。
近年は、木造造りで3階建てマンションをしっかりとした強度で建てる技術を持ったハウスメーカーが登場しています。
木造の建築物に関する可能性は以前よりも非常に拡がっています。例えば、小規模なマンションを建てたいなら「木造のみで検討してみる」こともおすすめです。
2.建築プランを検討する際は必ず相見積もりを取る!
建築費を抑える考え方として【相見積もりを取る】ことは、古典的手法であるものの、やはり合理的な対処法です。
幸い、日本には木造や軽量鉄骨造での建築技術を得意としているハウスメーカーが数多く存在しています。
それゆえ、木造や軽量鉄骨造のマーケットでは、そうしたハウスメーカー間での技術競争や顧客獲得競争も非常に激しいため、相見積もりを取ることで建築費も下げてもらいやすくなる側面があります。
複数のハウスメーカーから建築プランを取り寄せることは、今後ますます重要です。相見積もりを取ることは確かに面倒な側面があるとは思いますが、比較検討対象を増やすことにもなり、多くの情報を収集できるチャンスにもなります。
アパート・マンション経営は長年に渡る大きな投資になります。しっかりと信頼関係が築ける建築会社を探しましょう。
3.入居者は共働き世帯をターゲットにしよう!
建築費を抑える考え方として【共働き世帯を入居者ターゲットにする】という考え方があります。
つまり、ファミリータイプの建築プランを中心にプラン検討をするということです。
実は、アパート建築を例に取ると、その建築費は、ワンルームタイプよりもファミリータイプの方が安くなる傾向があります。大きな理由としては、全体の戸数が減ることでキッチンやバス、トイレ等の住宅設備の数が減らせるからです。
従来「賃貸物件は賃料単価の高いワンルームを建てることがセオリーで、多少建築費が高くなってもワンルームを建てた方が良い!」という定説がありました。そうした提案を受けたことがある土地オーナー様もいらっしゃるのではないでしょうか?
余もするとその考えは今でも主流かもしれませんが、ここで考えたいことは「近年は人口減少社会へ向かっている最中である一方、共働き世帯は増えている」という現実です。
増加はし続けている共働き世帯を入居者として呼び込めれば、この先も中長期で勝機を見出せる可能性が十分あります。
思い切って周辺アパートとの差別化戦略で「1部屋を50平米前後の間取り」にして「入居者満足度と家賃向上策を図ってみる」のも一つではないでしょうか!
アパート建築費を賢く抑えるなら
建物の構造選びや企画設計段階での費用確認は、収益性の高いアパート経営に直結します。後から変更が難しい仕様も、最初の段階でしっかり検討すれば無駄なコストを避けられます。
この記事を参考に、建築会社と相談しながら無理のない費用計画を立て、後悔のないアパート建築を進めてみませんか?
まとめ
以上、アパート建築費の高騰問題を乗り切るためのポイントについて解説しました。
建築費を抑えるには、建物の構造選びや企画設計段階での費用確認が重要です。後から変更が難しい仕様は、最初の設計段階でしっかり検討しておくことで無駄なコストを避けられます。
効率的な建築費の管理は、収益性の高いアパート経営に直結します。この記事を参考に、建築会社と相談しながら無理のない費用計画を立て、後悔のないアパート建築を進めてください。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部 (記事監修)竹内 英二
(竹内 英二プロフィール)
不動産鑑定事務所及び宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。
大手ディベロッパーで不動産開発に長く従事してきたことから土地活用に関する知見が豊富。
保有資格は不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。大阪大学出身。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 賃貸経営の基礎知識
賃貸経営の基礎知識の関連記事
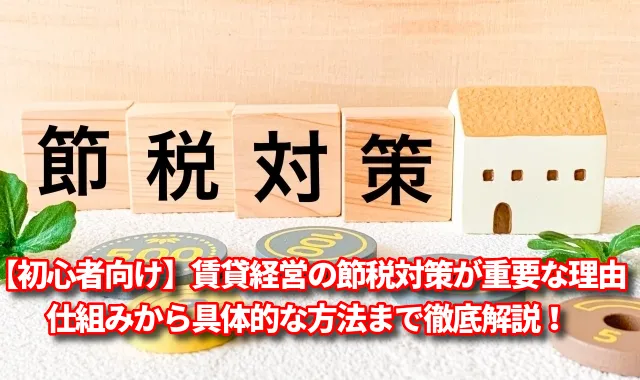
- 【初心者向け】賃貸経営の節税対策が重要な理由を徹底解説!仕組みから具体的な方法まで 公開
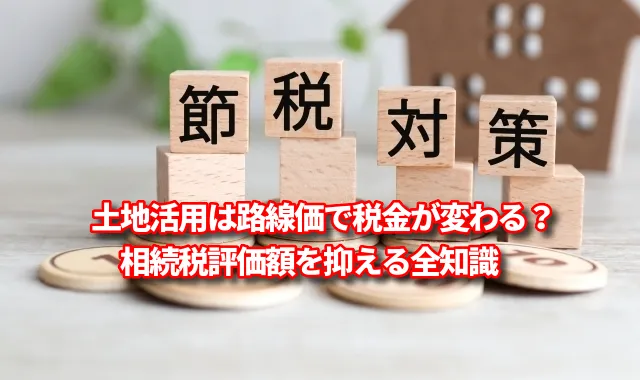
- 土地活用は路線価で税金が変わる?相続税評価額を抑える全知識 公開
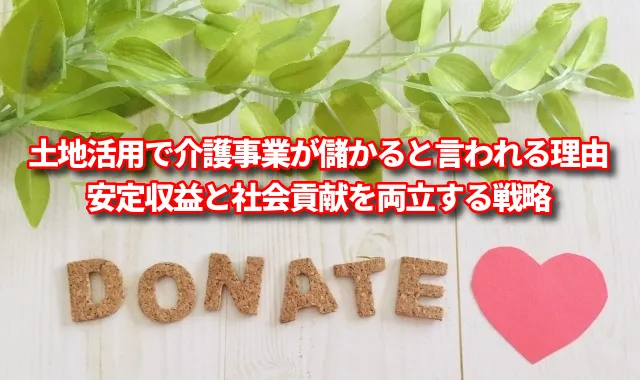
- 土地活用で介護事業が「儲かる」と言われる理由 安定収益と社会貢献を両立する戦略 公開

- 【地域活性化の起爆剤】土地活用と空き家リノベーションで未来を拓く 公開

- 賃貸経営の利回り完全ガイド:計算から平均・シミュレーションまで徹底解説 公開
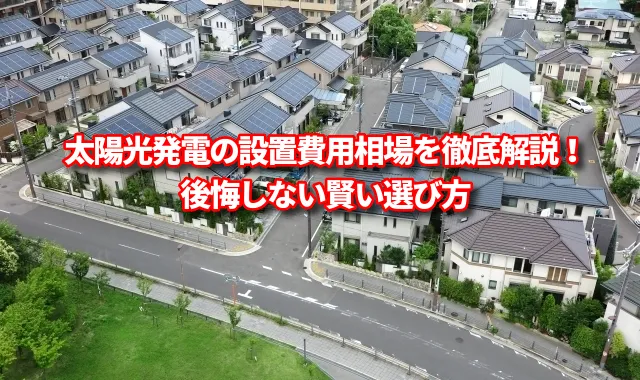
- 太陽光発電の設置費用相場を徹底解説!後悔しない賢い選び方 公開

- 【土地活用】借地権設定で安定収入!リスクを抑えて資産を最大化する方法を徹底解説 公開
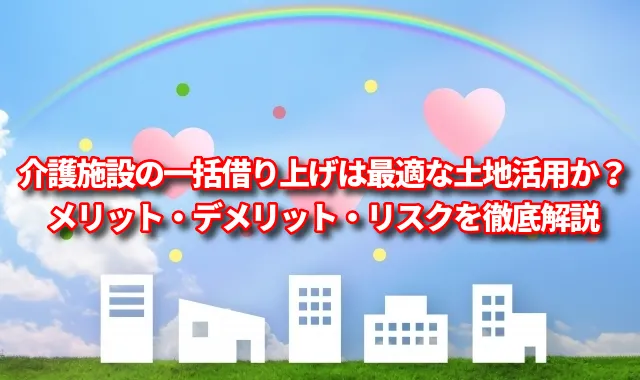
- 介護施設の一括借り上げは最適な土地活用か?メリット・デメリット・リスクを徹底解説 公開

- 太陽光発電の余剰電力売電ガイド:FIT後の最適な選択肢と賢い契約方法 公開

- 太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)とは?FITの仕組みから卒FIT後の賢い選択肢まで徹底解説 公開
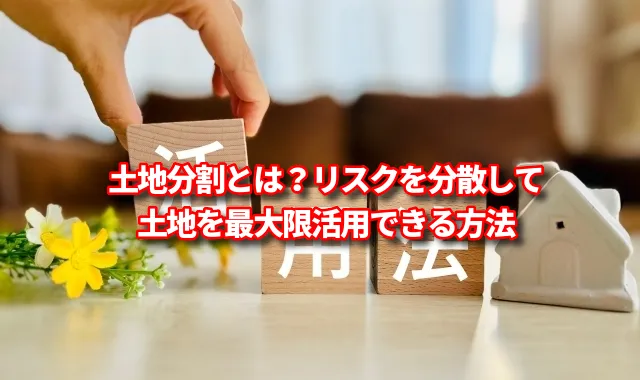
- 土地分割とは?リスクを分散して土地を最大限活用できる方法 公開
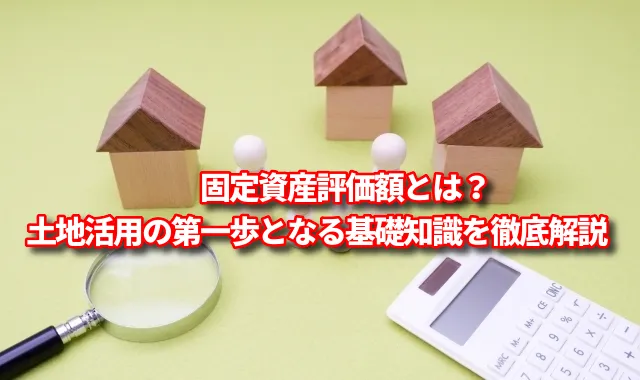
- 固定資産評価額とは?土地活用の第一歩となる基礎知識を徹底解説 公開
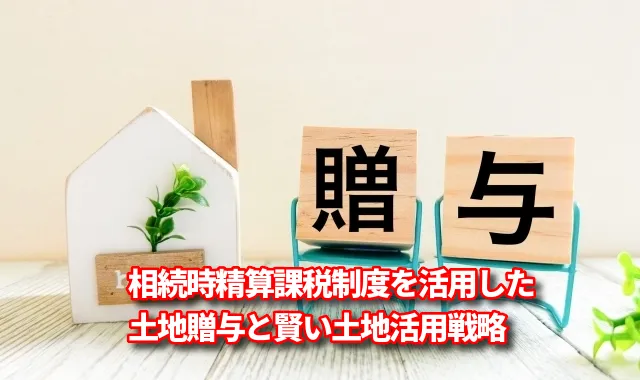
- 相続時精算課税制度を活用した土地贈与と賢い土地活用戦略 公開
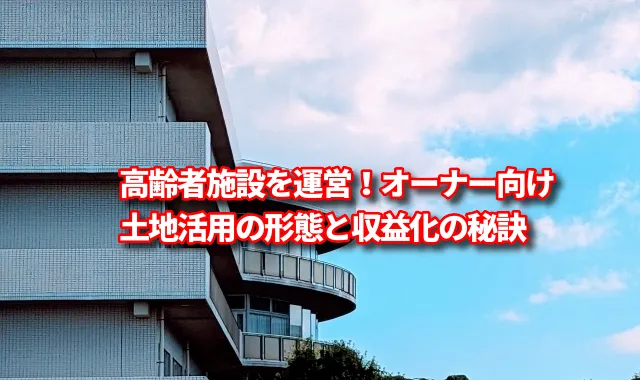
- 高齢者施設を運営!オーナー向け土地活用の形態と収益化の秘訣 公開
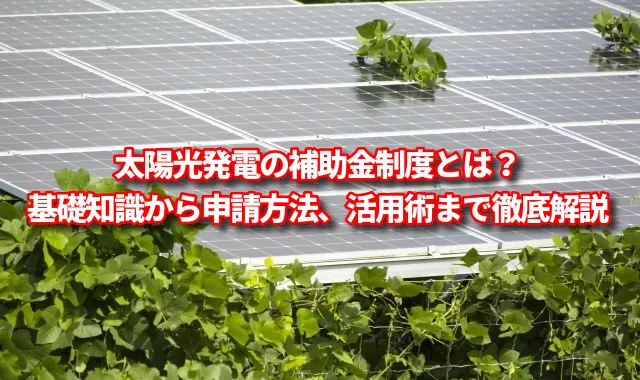
- 太陽光発電の補助金制度とは?基礎知識から申請方法、活用術まで徹底解説 公開
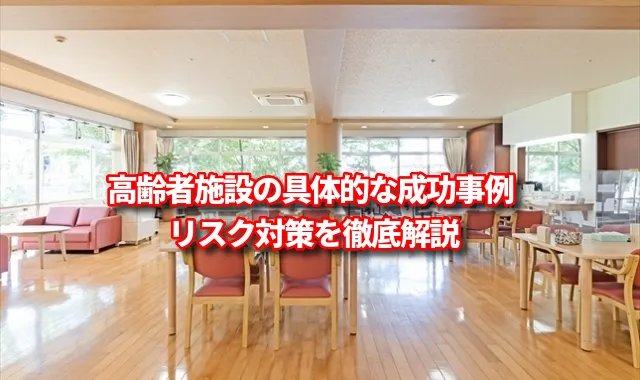
- 高齢者施設の具体的な成功事例とリスク対策を徹底解説 公開

- 土地活用としての太陽光発電投資:投資回収期間と収益最大化の全貌 公開
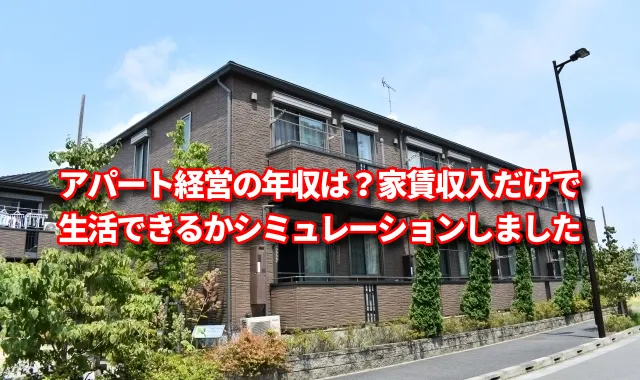
- アパート経営の年収は?家賃収入だけで生活できるかシミュレーションしました 公開

- FIT制度とFIP制度の最も重要な違いとは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説 公開

- 遊休地で太陽光発電、投資回収期間は何年?費用・利回り・失敗しないポイントを徹底解説 公開