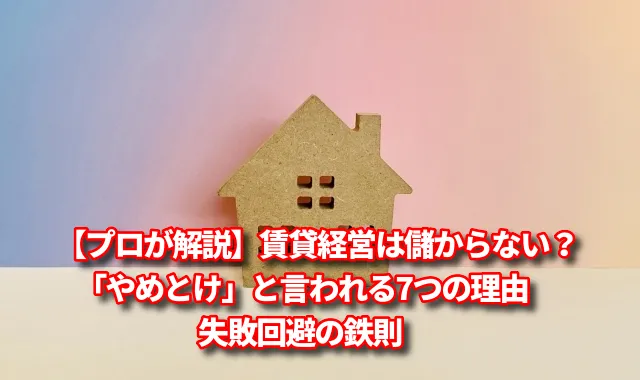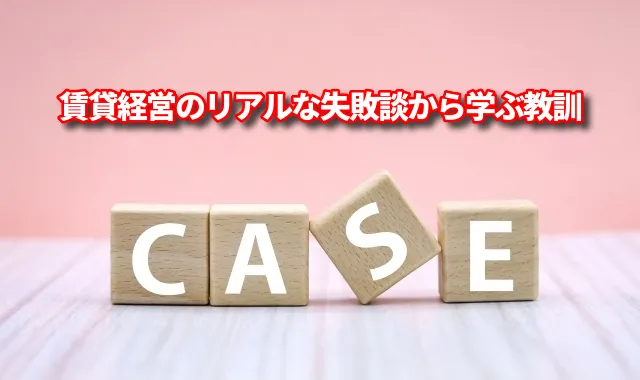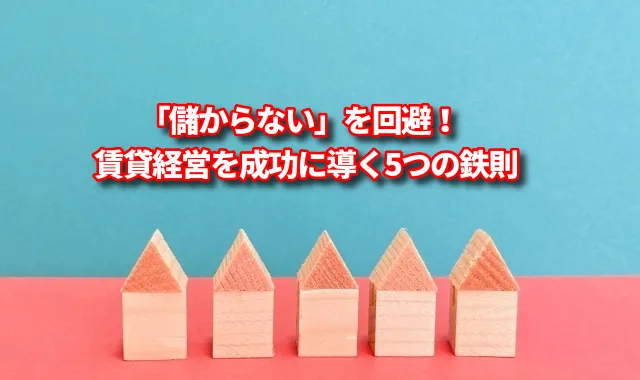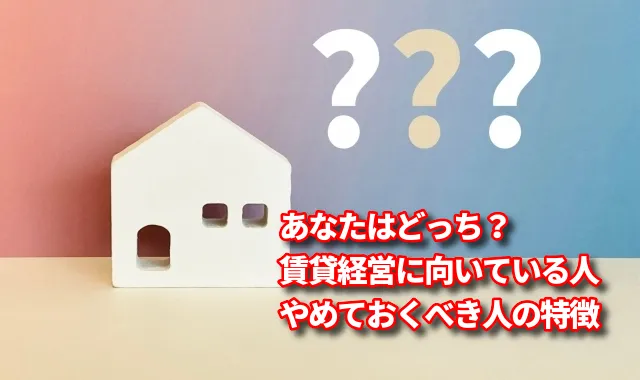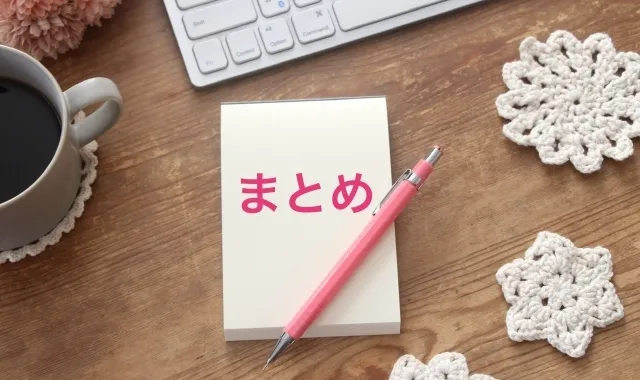- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- 賃貸経営の基礎知識
- 【プロが解説】賃貸経営は儲からない?「やめとけ」と言われる7つの理由と失敗回避の鉄則【イエカレ】
【プロが解説】賃貸経営は儲からない?「やめとけ」と言われる7つの理由と失敗回避の鉄則【イエカレ】
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.「賃貸経営が儲からない」は半分ホント。理由と対策を知れば道は開ける
賃貸経営に対して「儲からない」「やめとけ」といった否定的な意見が多く聞かれる背景には、事前準備の不足による失敗例が数多く存在するためです。確かに、空室リスクや家賃下落、予期せぬ修繕費といったコストの増大が収支を悪化させる要因となります。
しかし、これらのリスクは事前に把握し、適切に備えることで十分に軽減することが可能です。重要なのは、賃貸経営を「不労所得」と甘く見ずに、正確な情報と冷静な判断力を持って臨むこと。
この記事では、賃貸経営における主要なリスクとその対策を具体的に解説します。賢くリスクに備えることが、安定収益への道を切り拓くのです。
2.賃貸経営が儲からないと言われる7つの致命的な理由
賃貸経営において収益性を損なう主な要因は、いずれも見過ごせないリスクです。
この章では、代表的な7つの失敗要因について一つずつ掘り下げ、それぞれのリスクが収益にどう影響するのかを整理します。
2-1.空室リスク|収入ゼロでも経費は発生する
賃貸経営で最も恐れるべきリスクは、空室状態が続くことで家賃収入が途絶える事態です。
借入金の返済や固定資産税、管理費などの支出は入居者の有無にかかわらず発生し続けるため、空室期間が長引くほど赤字が膨らんでいきます。
特に、周辺に競合物件が多いエリアでは、立地や設備に魅力がなければ長期空室に陥る可能性が高まるでしょう。このリスクを軽減するには、入居者ニーズを的確に捉えた物件選定や、信頼できる管理会社との連携が不可欠です。
2-2.家賃下落リスク|築年数と共に資産価値は目減りする
建物の価値は、築年数の経過に伴って徐々に低下し、それに伴い相場家賃も下落する傾向にあります。
新築時に想定していた家賃収入が将来的に維持できなくなることで、収支計画が狂い、利回りが想定を大きく下回る事態も起こり得るのです。
家賃下落に備えるためには、将来的な修繕計画やリノベーションによる付加価値向上策を盛り込んだ、長期的な資金シミュレーションが重要となります。
2-3.修繕・原状回復リスク|想定外の高額出費が利益を蝕む
賃貸物件は経年と共に必ず劣化し、設備や内装の修繕が必要になります。特に、退去時の原状回復費用や給排水設備の故障など、緊急を要する支出は突発的に発生するため、資金計画を逼迫させる大きな原因です。
例えば、エアコンの交換や給湯器の故障といったケースでは、一度に数十万円単位の支出が必要になることも珍しくありません。
こうしたリスクを軽減するためには、あらかじめ長期修繕計画を作成し、計画的に修繕積立金を用意しておくことで資金繰りの安定を図る必要があります。
2-4.金利上昇リスク|ローン返済額が増加し収支が悪化する
変動金利でローンを組んだ場合、金利の上昇が直接的にキャッシュフローを悪化させます。
不動産投資ローンの多くは変動金利で組まれるため、金利の変動が収益に大きな影響を及ぼします。
日本の低金利政策が転換し、市場金利が上昇すれば、毎月のローン返済額も増加し、手元に残る現金(キャッシュフロー)が圧迫されるでしょう。
経済環境の変化によっては、返済そのものが困難になるリスクも存在します。このリスクに備えるには、返済比率を抑えた無理のない借入計画を立てるか、金利上昇の影響を受けない固定金利ローンの活用を検討することが重要です。
2-5.税金リスク|無視できない固定資産税や所得税の負担
利益が出ても、税金の支払いで手残りが想定より少なくなる可能性があります。
賃貸物件を所有すると、毎年必ず固定資産税や都市計画税といった税負担が発生します。さらに、家賃収入から経費を差し引いた利益(不動産所得)に対しては所得税・住民税も課税されるため、思った以上に手元に残る金額が少なくなるケースも少なくありません。
減価償却費の計上などによる節税対策はありますが、確定申告の手間や知識不足によって不利益を被る可能性も考えられます。適切な税務知識を持つ専門家との連携が求められます。
2-6.入居者トラブルリスク|家賃滞納や迷惑行為への対応コスト
賃貸経営では、入居者との間に発生するトラブルも無視できません。家賃滞納、騒音問題、ゴミ出しルールの違反といった問題への対応には、多大な精神的・時間的コストが伴います。
特に家賃滞の長期化は深刻で、収入が途絶えるだけでなく、最終的に訴訟や強制退去の手続きが必要になれば、弁護士費用などの追加コストも発生します。
こうしたリスクに備えるには、入居審査を厳格に行い、家賃保証会社を利用すること、そしてトラブル対応に長けた管理会社と連携することが有効です。
2-7.管理会社リスク|パートナー選びの失敗が経営を左右する
管理会社は、入居者募集からクレーム対応、物件の維持管理までを担う、賃貸経営における最も重要なパートナーです。
しかし、管理会社の対応の質が低いと、入居者の不満が高まって退去率が上昇するだけでなく、物件の劣化やトラブルが放置され、結果として大きな損失につながります。
管理会社を選定する際は、実績や評判、サービス内容を複数の会社で十分に比較し、継続的なコミュニケーションを通じて信頼関係を築くことが不可欠です。
賃貸経営にはリスクもありますが、物件の立地や提案内容によって結果は大きく変わります。
複数の管理会社から提案を受けて比較することで、自分の土地や資金状況に合った収支プランを見極めやすくなります。
どなたでもかんたん!資料請求(無料)3.【実録】賃貸経営のリアルな失敗談から学ぶ教訓
賃貸経営における失敗は、単なる不運ではなく、その多くが準備不足や判断ミスから生じます。
この章では、実際に賃貸経営で苦い経験をした3つのケースをご紹介します。現実に起こり得る失敗から学び、同じ轍を踏まないための教訓としてください。
3-1.ケース1:サブリース契約を鵜呑みにした新築ワンルーム投資の罠
「家賃保証」という言葉の裏に潜むリスクを見抜けなかったケースです。
Aさんは、業者から「30年間の家賃保証」を謳うサブリース契約付きの新築ワンルームマンションを勧められ、安心して契約しました。
しかし、わずか数年で「経済情勢の変動」を理由に保証賃料が一方的に減額。
さらに、契約書には業者に有利な条件が並んでおり、中途解約には高額な違約金が必要でした。
後になって物件が相場より割高な価格で販売されていたことも発覚し、売却しようにも残債割れ(ローン残高が売却価格を上回る状態)となり、身動きが取れない状況に陥りました。
サブリースの甘い言葉に惑わされず、契約内容や収支計画を自ら厳しく精査する姿勢が求められます。
3-2.ケース2:利回りだけを重視した地方・築古物件の末路
「高利回り」の数字の裏にある、隠れたコストとリスクを無視した結果です。
Bさんは、都心に比べて圧倒的に高い「表面利回り」に惹かれ、地方の築30年超えの中古アパートを購入しました。
しかし、実際に募集を始めると入居者が全く決まらず、ようやく決まっても想定より大幅に低い家賃での契約となりました。
さらに、購入後すぐに給湯器の故障や雨漏りなど予期せぬ修繕が多発。修繕費がかさみ、結果的に持ち出しが続く赤字経営に転落しました。
地方物件や築古物件は、利回りの数字だけでなく、実質的な入居ニーズや将来の修繕コストまで含めた「実質利回り」で判断することが不可欠です。
3-3.ケース3:甘い収支シミュレーションでローン破綻したサラリーマン大家
業者の楽観的な見通しを信じ、自らリスクを検証しなかったための失敗です。
Cさんは、不動産会社の提示する楽観的な収支シミュレーションを鵜呑みにし、賃貸経営を開始しました。そのシミュレーションは、空室率が低く設定され、将来の家賃下落や大規模修繕費がほとんど考慮されていないものでした。
数年後、近隣に新築物件が建ったことで空室が発生し、さらに金利が上昇したことでキャッシュフローが急激に悪化。ローン返済が困難となり、最終的には購入価格を大きく下回る金額で物件を売却し、多額の損失を抱えることになりました。
投資の最終判断は、必ず自分自身で、現実的なシナリオに基づいたシミュレーションを行うことが絶対条件です。
4.「儲からない」を回避!賃貸経営を成功に導く5つの鉄則
これまで紹介したリスクや失敗談は、賃貸経営が「儲からない」と言われる原因の本質を表しています。
しかし、これらは決して回避不可能なものではありません。的確な情報収集と慎重な判断、そして具体的な戦略を持てば、安定した収益を実現することは十分可能です。
この章では、賃貸経営で成功を目指すために不可欠な5つの鉄則を解説します。
4-1.鉄則1:物件選び|「立地」こそが全て。人口動態と賃貸需要を見極める
成功の8割は立地で決まると言っても過言ではありません。 物件選びで最も重要な要素は「立地」です。
駅からの距離、商業施設の充実度、治安、学区、そして将来的な都市開発計画など、様々な要素が入居率に直結します。また、その地域の人口動態や世帯構成の変化を読み解くことも重要です。
例えば、単身者が増加しているエリアでファミリータイプの物件を選んでしまうと、深刻なミスマッチが生じます。
公的な統計データなど、客観的な情報に基づいて賃貸需要を分析することが、空室リスクを最小化する絶対的な第一歩です。
4-2.鉄則2:資金計画|出口戦略まで見据えた「現実的な」収支シミュレーション
楽観的な計画は破綻の元。悲観的なシナリオで利益が出るかを検証します。
賃貸経営を始める際は、購入時の諸費用や毎月のローン返済額だけでなく、将来的な売却や建て替えといった「出口戦略」までを見据えた長期的な資金計画が不可欠です。
収支シミュレーションを行う際には、不動産業者が提示するものを鵜呑みにせず、空室率、家賃下落率、修繕費、税金、管理費といったあらゆる支出を、自分自身で厳しめに見積もって行うことが求められます。
特に、収支が悪化した際に備えた予備資金(バッファ)の設定は必須です。金融機関や専門家とも相談し、悲観・中立・楽観の各パターンで損益分岐点を把握することが、長期安定経営の鍵を握ります。
4-3.鉄則3:管理会社選び|経営の成否を分ける優良パートナーの見つけ方
優秀な管理会社は、あなたの資産価値を維持・向上させてくれるパートナーです。
賃貸経営の現場運営は管理会社に委託するケースが多いため、その選定は極めて重要です。管理会社の客付け力(入居者を見つける力)や入居者対応の品質は、入居率や退去率に直接影響します。
複数の会社から話を聞き、管理戸数や入居率といった実績データ、担当者の知識や対応力を比較検討し、信頼できる業者を選ぶことが不可欠です。
また、契約後も定期的に報告内容を精査し、改善点を指摘・共有する姿勢が、健全なパートナーシップを築く上で重要となります。
4-4.鉄則4:リスク対策|保険の活用と計画的な修繕積立
避けられないリスクには、金銭的な備えでダメージを最小化します。
火災や自然災害、入居者の過失による事故といった突発的なリスクには、火災保険や地震保険、施設賠償責任保険などへの適切な加入が必須です。保険商品は補償範囲や免責金額がそれぞれ異なるため、物件のリスクに応じて内容をよく比較検討すべきでしょう。
また、経年劣化による突発的な修繕費に備え、毎月の家賃収入から一定額を「修繕積立金」として確保しておくことが、キャッシュフロー悪化を防ぐために直結します。
リスクは避けられませんが、備えることでそのダメージは最小限に抑えられます。
4-5.鉄則5:知識武装|税金や法律を学び、専門家と対等に話せるようになる
最終的な経営判断を下すのは、専門家ではなくあなた自身です。
賃貸経営においては、所得税や固定資産税といった税金の知識、そして賃貸借契約に関する法律の知識が求められます。
これらの知識を持たずに業者任せにしてしまうと、気づかぬうちに不利な条件で契約を結んでしまう可能性があります。
書籍やセミナー、信頼できるウェブサイトなどを活用して自ら学び、税理士や弁護士といった専門家と対等に話せるだけの知識を備えることで、健全な経営とリスクの抑制が図れます。
賃貸経営の成功には、パートナー選びがとても重要です。実績ある管理会社や建築会社の提案を比較検討することで、収益性や管理面の不安もぐっと軽減されます。
資料請求から、成功に向けた第一歩を踏み出してみませんか?
どなたでもかんたん!資料請求(無料)5.あなたはどっち?賃貸経営に向いている人・やめておくべき人の特徴
賃貸経営には、その特性上、向いている人とそうでない人がいます。
この章では、成功しやすい人とリスクを抱えやすい人の特徴を具体的に解説します。ご自身がどちらに該当するかを客観的に判断するための材料としてください。
5-1.賃貸経営に向いている人の特徴3選
- 数字とシミュレーションに強い人:感情論ではなく、データに基づいて冷静に収支計画や利回りの計算を自ら検証できるため、投資判断の精度が高まります。
- 継続的な学習意欲がある人:市況の変化や税制改正、法改正といった外部環境の変化にアンテナを張り、常に知識をアップデートして経営を柔軟に見直すことができます。
- 人に任せる力を持つ人:全てを自分で抱え込まず、信頼できる専門家(管理会社、税理士など)に適切な業務を委任し、自分は経営判断という最も重要な業務に集中できます。
5-2.賃貸経営をやめておくべき人の特徴3選
- リスクを極端に避ける人:賃貸経営に不確実性はつきものです。空室や家賃滞納といった些細なトラブルにも過剰に反応し、精神的に疲弊してしまう可能性があります。
- 他人任せで判断力がない人:業者の提案を鵜呑みにしてしまい、自ら情報を集めて検証することなく、安易に意思決定してしまう傾向がある人は危険です。
- 短期的な利益を期待する人:賃貸経営は、長期的な視点でコツコツと資産を築いていく投資です。すぐに大きな利益が出ないことに焦りや不満を感じやすいタイプは不向きでしょう。
6.賃貸経営に関するよくある質問(FAQ)
この章では、賃貸経営を検討する方からよく寄せられる質問について、Q&A形式で簡潔に解説します。
6-1.Q1. 自己資金はいくら必要ですか?
A. 一概には言えませんが、一般的に物件価格の1〜3割程度が目安とされています。
物件価格の全額をローンで賄う「フルローン」もありますが、審査が厳しくなる傾向にあります。頭金に加えて、登記費用、不動産取得税、仲介手数料といった諸費用(物件価格の7〜10%程度)も現金で必要です。
また、突発的な修繕費や当面の空室期間の支出に備えるための予備資金も用意しておくことが、安定経営の鍵となります。
6-2.Q2. 不動産所得の確定申告はサラリーマンでも必要ですか?
A. はい、給与所得以外に年間20万円を超える不動産所得がある場合は、確定申告が必須です。
たとえ赤字であっても、確定申告をすることで給与所得と損益通算ができ、所得税や住民税の還付を受けられるメリットがあります。
必要経費(ローン金利、管理費、修繕費、減価償却費など)を適切に計上することで、課税所得を圧縮し、税負担を軽減することが可能になります。
税務署や税理士に相談しながら、正確な申告を行うことが重要です。
6-3.Q3. 法人化するメリットは何ですか?
A. 主に、税負担の軽減と資産管理の柔軟性向上というメリットがあります。
具体的には、以下のような点が挙げられます。
- ・個人の所得税率より法人税率の方が低くなる場合、節税効果が期待できる。
- ・役員報酬の支払いや退職金の活用など、所得を分散できる。
- ・経費として認められる範囲が個人事業主よりも広がる。
- ・相続対策や資産保全がしやすくなる。
ただし、法人の設立・維持にはコストや手間もかかるため、事業規模や将来の展望に応じて、税理士などの専門家と相談しながら慎重に検討することが望ましいです。
まとめ:リスクを制する者が賃貸経営を制す。まずは専門家に相談を。
本記事では、賃貸経営が「儲からない」と言われる本当の理由と、その対策について詳しく解説しました。
賃貸経営は、決して「楽して儲かる」投資ではありません。空室や家賃下落、予期せぬ出費といった数々のリスクと、常に向き合う覚悟が求められます。
しかし、これらのリスクは、事前に学び、一つひとつに対して具体的な対策を講じることで、失敗の確率を大幅に下げ、安定した資産形成を目指すことは十分に可能です。
最も重要なのは、営業トークや他人の意見に振り回されることなく、ご自身の判断軸を持つことです。
もしあなたが本気で賃貸経営を検討するのなら、最初の一歩として、信頼できる複数の不動産会社の専門家に相談し、具体的な収支シミュレーションや物件の提案を受けてみることをお勧めします。その上で、本記事で得た知識を武器に、ご自身の目でその提案が現実的かどうかを厳しく判断してください。
その冷静な一歩が、あなたの将来の経済的安定を築く、確かな礎となるはずです。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 賃貸経営の基礎知識
賃貸経営の基礎知識の関連記事
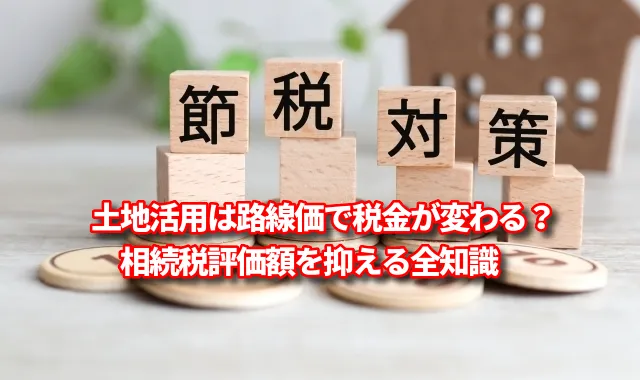
- 土地活用は路線価で税金が変わる?相続税評価額を抑える全知識 公開
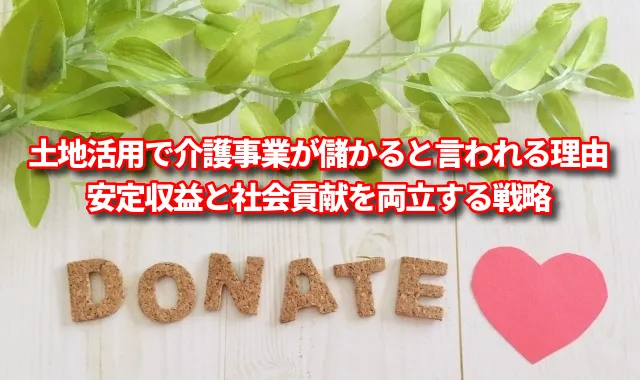
- 土地活用で介護事業が「儲かる」と言われる理由 安定収益と社会貢献を両立する戦略 公開

- 【地域活性化の起爆剤】土地活用と空き家リノベーションで未来を拓く 公開

- 賃貸経営の利回り完全ガイド:計算から平均・シミュレーションまで徹底解説 公開
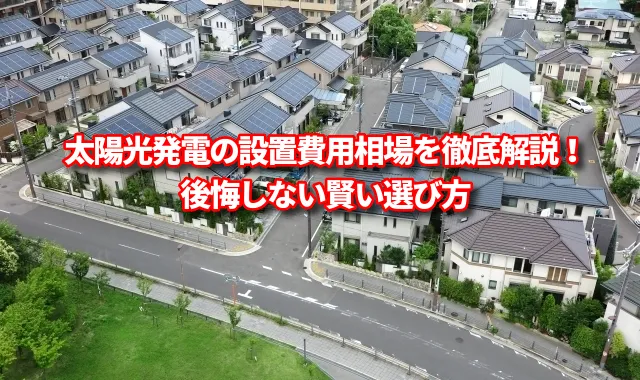
- 太陽光発電の設置費用相場を徹底解説!後悔しない賢い選び方 公開

- 【土地活用】借地権設定で安定収入!リスクを抑えて資産を最大化する方法を徹底解説 公開
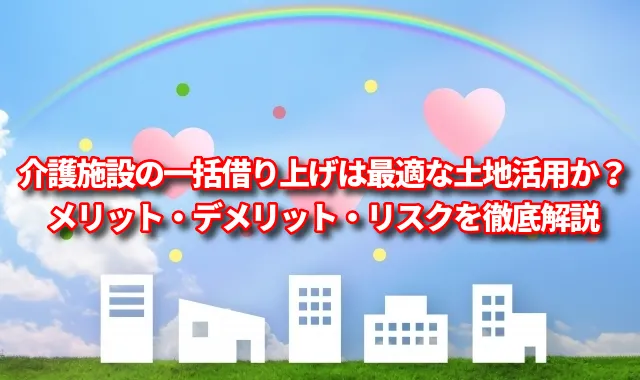
- 介護施設の一括借り上げは最適な土地活用か?メリット・デメリット・リスクを徹底解説 公開

- 太陽光発電の余剰電力売電ガイド:FIT後の最適な選択肢と賢い契約方法 公開

- 太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)とは?FITの仕組みから卒FIT後の賢い選択肢まで徹底解説 公開
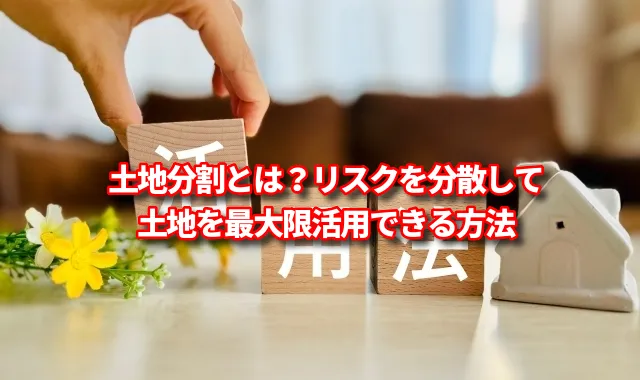
- 土地分割とは?リスクを分散して土地を最大限活用できる方法 公開
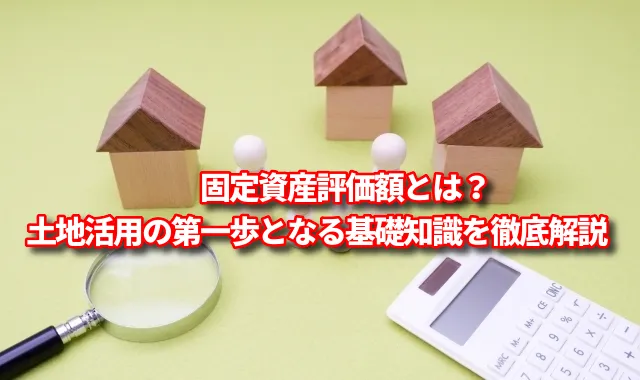
- 固定資産評価額とは?土地活用の第一歩となる基礎知識を徹底解説 公開
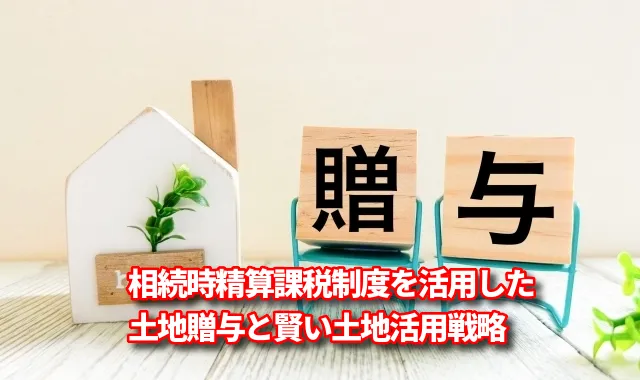
- 相続時精算課税制度を活用した土地贈与と賢い土地活用戦略 公開
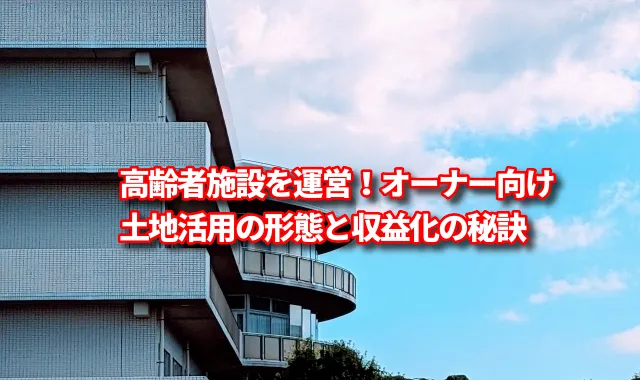
- 高齢者施設を運営!オーナー向け土地活用の形態と収益化の秘訣 公開
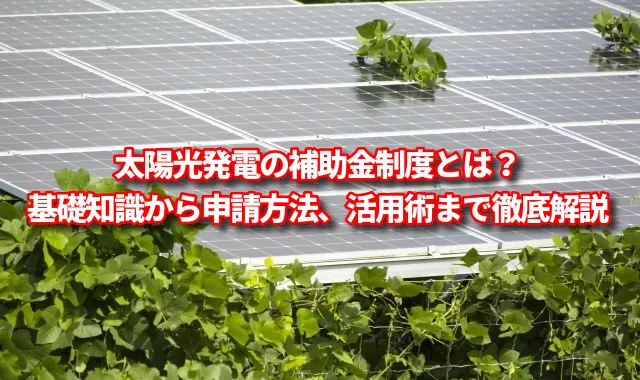
- 太陽光発電の補助金制度とは?基礎知識から申請方法、活用術まで徹底解説 公開
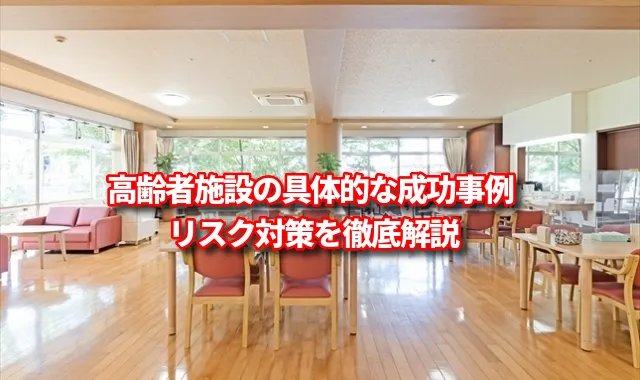
- 高齢者施設の具体的な成功事例とリスク対策を徹底解説 公開

- 土地活用としての太陽光発電投資:投資回収期間と収益最大化の全貌 公開
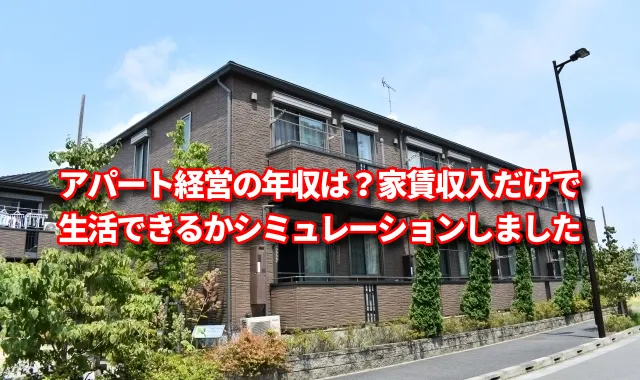
- アパート経営の年収は?家賃収入だけで生活できるかシミュレーションしました 公開

- FIT制度とFIP制度の最も重要な違いとは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説 公開

- 遊休地で太陽光発電、投資回収期間は何年?費用・利回り・失敗しないポイントを徹底解説 公開
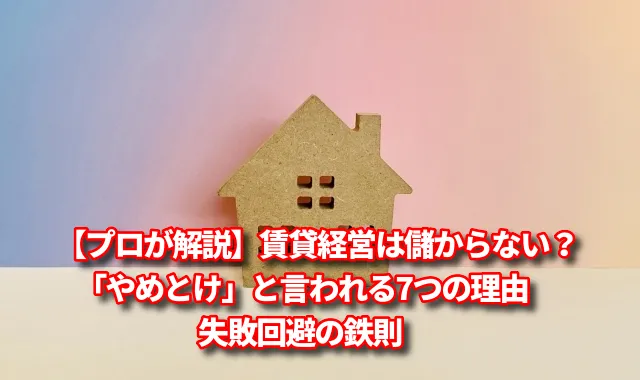
- 【プロが解説】賃貸経営は儲からない?「やめとけ」と言われる7つの理由と失敗回避の鉄則 公開