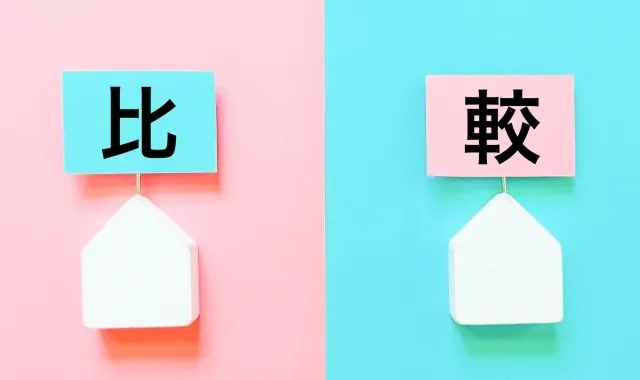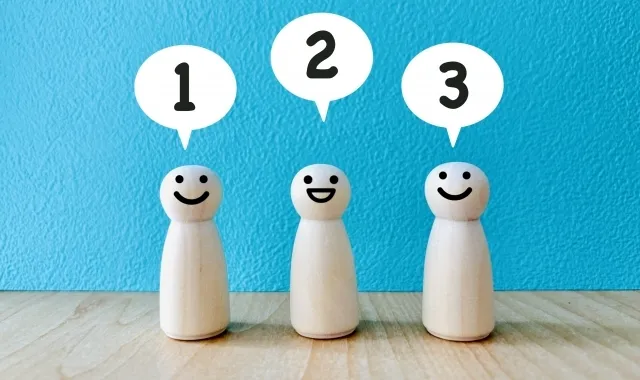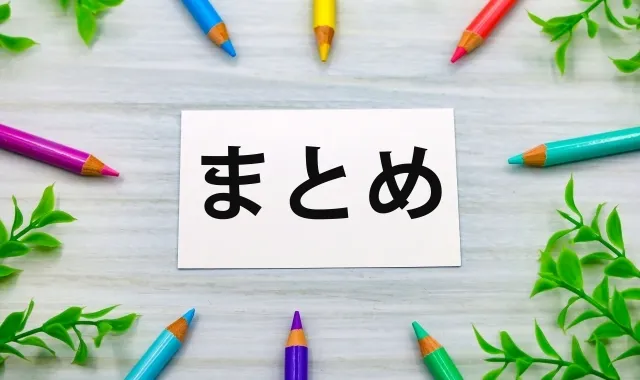- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- 賃貸経営の基礎知識
- 【イエカレ】FIT制度とFIP制度の最も重要な違いとは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説
【イエカレ】FIT制度とFIP制度の最も重要な違いとは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
実は、FITやFIP制度を調べている方の中には、
アパートやマンション経営と比較検討している方も少なくありません。
⇒ 土地活用の選択肢を無料で一括比較してみる
1.そもそもFIT制度とは?基本をおさらい
FIT制度(Feed-in Tariff:固定価格買取制度)は、再エネの普及を目的として2012年に導入された国の支援制度です。
発電事業者にとって、長期間にわたり一定価格で電力が買い取られることで収益の安定が見込めるため、事業参入のハードルを大幅に下げました。
ここでは、FIT制度の仕組みや目的、そして現在直面する「卒FIT」問題について解説します。
1-1.FIT制度(固定価格買取制度)の概要
FIT制度とは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスといった再エネで発電された電力を、電力会社が国で定めた固定価格で一定期間買い取ることを義務付ける制度です。
発電事業者は、売電価格の変動を気にすることなく長期的な収益計画を立てられ、再エネ事業の初期投資を回収しやすくなります。
この制度は、発電事業者が「電力をつくる」、電力会社が「決まった価格で買う」、そして国が国民から広く集めた「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」を原資に、電力会社へ差額を補填するという三者の関係で成り立っています。
この仕組みにより、日本全国で太陽光発電を中心とする再エネの導入が飛躍的に進みました。
1-2.FIT制度の目的とメリット
FIT制度が掲げる主な目的は、再エネの導入促進です。特に太陽光発電のような初期投資が高額になりがちな設備を導入する事業者にとって、長期にわたり安定した売電収入が見込める点は大きなメリットでした。
固定価格が保証されているため、事業計画の策定が容易になり、金融機関からの融資審査にも有利に働くことが多くあります。収益の見通しが立てやすいことから、リスクを最小限に抑えながら設備の導入を進めることが可能だったのです。
1-3.FIT制度の課題と「卒FIT」問題
一方で、FIT制度はいくつかの課題も抱えています。最も大きな問題が、制度の財源を「再エネ賦課金」として全国の電気利用者からの徴収に頼っている点です。再エネ導入量の増加に伴って賦課金も上昇し、国民全体の負担が増加しています。
また、制度開始から10年以上が経過し、多くの発電設備が買取期間の満了、いわゆる「卒FIT」を迎え始めました。卒FIT後は固定価格での売電が終了するため、市場価格に基づく不安定な価格での売電、あるいは自家消費への切り替えといった選択を迫られます。この転換期に、次の一手としてどの運用方法を選ぶかが重要な課題となっています。
2.FIP制度とは?再エネ自立化の切り札
FIP制度は、再エネを電力市場に統合し、より自立的で持続可能な発電ビジネスを促すために導入された新しい制度です。FIT制度と異なり、売電価格が市場価格に連動するため、より戦略的な運用が求められます。
ここでは、FIP制度の仕組みと目的、収益構造、そして発電事業者に求められる新たな役割を詳しく解説します。
2-1.FIP制度の概要と目的
FIP制度(Feed-in Premium)は、発電した再エネを市場価格で売電し、その売上金に国が定める補助額(プレミアム)を上乗せする仕組みです。発電事業者は、自ら電力市場で電気を販売し、国が定める基準価格と市場価格の差を補うプレミアムを受け取ります。
この制度が目指すのは、再エネを電力市場へ本格的に統合し、国の手厚い保護から脱却した「自立型」の発電事業者を育成することです。事業者は電力市場の価格動向を常に把握し、より高度な経営判断を下すことが求められます。
2-2.FIP制度における2つの収入源(市場売電+プレミアム)
FIP制度の収益構造は、以下の2つの要素で成り立ちます。
- ・市場価格に基づく売電収入
発電した電力は、JEPX(日本卸電力取引所)などの電力市場で売却され、その時々の市場価格(30分ごとに変動)に応じた収入を得ます。 - ・プレミアム収入
国が定めた「基準価格(FIP価格)」と、市場価格の平均値である「参照価格」との差額が、プレミアムとして交付されます。市場価格が高いとプレミアムは減少し、低いと増加するこの仕組みにより、価格変動のリスクが一定程度緩和されます。
2-3.FIP制度で求められる事業者の役割(バランシング)
FIP制度では、発電事業者に「バランシング(需給調整責任)」が課せられます。これは、事前に提出する発電量の予測と、実際の発電量を一致させる責任のことです。計画値と実績値にズレが生じた場合、「インバランス料金」というペナルティが発生します。
具体的には、前日までに翌日の発電計画を策定・提出し、その計画通りに電気を供給しなければなりません。天候によって発電量が大きく変動する太陽光発電では、この予測精度が収益を直接左右します。
計画と実績のズレは電力系統全体の需給バランスに影響を与えるため、その補填コストとしてインバランス料金が課されるのです。
このように、FIP制度は単に発電するだけでなく、需給管理や市場分析といった高度な運営能力が問われるため、事業者にはより積極的かつ戦略的な取り組みが求められます。
3.【一覧表で比較】FIT制度とFIP制度の7つの違い
FIT制度とFIP制度は、再エネ電力の導入を支援する点では共通していますが、運用の根幹に関わる多くの点で異なります。特に価格決定方法や収益構造、事業者の責務は制度選択の重要な判断材料です。
ここでは、両制度の違いを7つの観点から比較し、それぞれの特徴を分かりやすく解説します。
| 比較項目 | FIT制度(安定・安心型) | FIP制度(自立・競争型) |
|---|---|---|
| ① 価格の決定方法 | 国が定めた固定価格(20年間不変) | 市場価格に連動(30分毎に変動) |
| ② 収益の安定性 | 高安定(収益予測が容易) | 変動リスクあり(市場次第で高収益も可能) |
| ③ プレミアムの仕組み | なし(全額が固定価格買取) | あり(市場価格を補完し、変動を緩和) |
| ④ 事業者の責務 | バランシング責務は免除 | バランシング責務が発生(インバランス料金のリスク) |
| ⑤ 非化石価値の扱い | 国に帰属 | 発電事業者に帰属(市場で売却可能) |
| ⑥ 対象となる電源 | 低圧(10kW以上)から高圧まで幅広く対象 | 原則、高圧(50kW以上)が対象 ※アグリゲーションで低圧も可 |
| ⑦ 事務負担 | 比較的少ない | 発電計画策定、市場取引など業務が増加 |
4.FIP制度のメリット・デメリットを徹底分析
FIP制度への移行を検討する上で最も重要なのは、その制度がもたらす具体的なメリットとデメリットを正確に把握することです。
ここでは、事業者がFIP制度を選択した際に得られる利点と、注意すべき課題について解説します。
4-1.FIP制度に移行する3つのメリット
- ・収益最大化の可能性
市場価格が高騰した際に、固定価格では得られなかった高単価での売電が可能になります。特に電力需要が集中する時間帯に効率よく売電できれば、FIT制度時代を上回る収益を得られる可能性があるのです。 - ・市場への意識向上と経営自立
FIP制度では、市場価格や需要動向に応じた戦略的な運用が不可欠です。これにより、発電事業が「単なる設備投資」から「経営判断が収益を左右する事業活動」へと進化し、企業の成長性と柔軟性が高まるでしょう。 - ・非化石価値の活用による新たな収益源
FIP制度では、CO2を排出しない再エネの環境価値である「非化石価値」が発電事業者に帰属します。この価値は「非化石価値取引市場」で売却できるほか、環境意識の高い企業との取引にも活用でき、環境経営への取り組みとしてPR効果も期待できます。
4-2.注意すべきFIP制度の3つのデメリット
- ・市場価格の変動リスク
市場価格が下落した場合、売電収益がFIT制度の買取価格を大きく下回る可能性があります。プレミアムによる一定の緩和措置はありますが、極端な価格下落時には事業の収益性が著しく悪化するリスクを伴います。 - ・インバランス料金の発生
発電量の予測と実績に差が出ると「インバランス料金」というペナルティが課されます。この料金は予測精度に依存するため、天候など外的要因に大きく左右される太陽光発電では特に顕著なリスクとなります。 - ・新たな業務負担の増加
発電計画の策定、市場取引への対応、アグリゲーターとの連携など、FIP制度では従来は不要だった業務が発生します。これらに対応するには、専門知識を持つ人材の確保や、業務体制の見直しが不可欠です。
太陽光発電のデメリットに不安を感じたら、
アパート経営などの土地活用と比較してみるのも一つの方法です。
⇒ 今の土地にどんな活用方法が向いているか専門資料を探す
5.【卒FIT後の最適解】FIP制度と他の選択肢を比較
FIT制度による固定価格での買取期間が満了する「卒FIT」は、発電事業者にとって大きな転換点です。FIP制度は有力な移行先ですが、ほかにも自家消費の拡大や相対契約(PPA)といった選択肢があります。
ここでは、卒FIT後に取り得る3つの主要な選択肢を比較し、事業者の目的別に最適な判断基準を提示します。
5-1.選択肢①:FIP制度への移行
収益の最大化を積極的に狙いたい事業者にとって、FIP制度への移行は有力な選択肢です。市場価格が高水準で推移すれば、FIT時代以上の利益を得る可能性があります。また、非化石価値を活用した追加収益の道も開かれます。
一方で、市場価格の下落リスクやインバランスリスク、新たな業務負担といったデメリットも存在するため、リスク管理体制の構築が成功の鍵を握ります。
5-2.選択肢②:蓄電池導入による自家消費の最大化
蓄電池を新たに導入し、発電した電力を自社内で最大限活用する自家消費モデルは、電気料金の削減に直結します。昼間に発電した電気を蓄え、夜間や電力料金が高い時間帯に利用することで、電力会社からの購入量を大幅に削減できます。
また、非常時のバックアップ電源として事業継続計画(BCP)の強化に繋がる点も大きなメリットです。ただし、蓄電池の導入には高額な初期投資が必要なため、費用対効果を慎重に見極める必要があります。
5-3.選択肢③:相対・PPA契約
特定の企業と長期の売電契約を結ぶ「相対契約」や「コーポレートPPA(Power Purchase Agreement)」も注目される選択肢です。
売電価格と期間を当事者間で決定するため、市場価格の変動に左右されず、安定した収益を長期間にわたって確保できます。
この方法では、信頼できるパートナー企業を見つけることが大前提となり、契約条件の交渉力や信用調査といった専門的な対応が求められます。
5-4.どの選択肢を選ぶべきかの判断基準
どの選択肢が最適かは、事業者の目的とリスク許容度によって決まります。自社の状況に合わせて、以下の基準で検討することをおすすめします。
- ・収益の最大化を最優先するなら → FIP制度
市場リスクを取ってでも高いリターンを狙いたい、非化石価値も活用したい場合に適しています。 - ・電気料金の削減と事業の安定性を重視するなら → 自家消費+蓄電池
売電収入よりも、コスト削減や災害時の備え(BCP)を優先したい場合に最適です。 - ・長期的な安定収入とリスク回避を重視するなら → 相対契約/PPA
市場の不確実性を避け、堅実な収益を確保したい場合に有効な選択肢です。
6.FIP制度で収益を最大化するための3つの戦略
FIP制度は、市場価格とプレミアムの変動によって収益が左右されるため、ただ参加するだけでは十分な利益を確保できません。市場変動リスクをコントロールし、収益を最大化するには、計画的かつ戦略的な運用が不可欠です。
ここでは、FIP制度における収益最大化のための3つの具体的な戦略を解説します。
6-1.① アグリゲーターとの連携
FIP制度の運用には、発電計画の策定、市場取引、バランシング対応といった専門業務が伴います。これらの複雑な業務を代行してくれるのが「アグリゲーター」と呼ばれる事業者です。
アグリゲーターは複数の発電設備を束ねて一括管理し、市場への入札やインバランスリスクの緩和などを代行します。
手数料は発生しますが、リスク管理と収益安定化に大きく貢献するため、特に専門部署を持たない事業者にとっては極めて有効な手段です。
6-2.② 蓄電池の戦略的活用
蓄電池を併設し、電力の充放電を戦略的に制御することで、収益の最適化を図れます。
具体的には、電力の市場価格が安い時間帯に蓄電し、価格が高い時間帯に放電・売電するといった運用です。これにより、価格差を利益に変えることができます。
また、天候急変による発電量の変動を蓄電池で吸収し、インバランス料金のリスクを低減する効果も期待できます。
6-3.③ 発電量予測精度の向上
インバランス料金を回避するには、発電計画と実績を可能な限り一致させることが重要です。
近年では、AIや機械学習を活用した高度な発電量予測サービスが登場しており、気象情報と連携して非常に高い精度で予測が可能になっています。
こうしたツールを導入することで予測誤差を最小限に抑え、収益の安定化を図れます。天候の影響を強く受ける太陽光発電にとって、予測精度は収益性を左右する生命線です。
7.FIT・FIP制度に関するよくある質問(FAQ)
FIT制度やFIP制度に関して、事業者の方から多く寄せられる代表的な質問にお答えします。
7-1.Q. FIP制度のプレミアムはいつまで続きますか?
FIP制度におけるプレミアムの交付期間は、FIT制度の買取期間と同様に原則20年間です。
この期間中は、基準価格と市場価格に応じたプレミアムが交付されます。
ただし、プレミアムの算出根拠となる基準価格は社会情勢を反映して見直される可能性があり、補助額が常に一定ではない点に注意が必要です。
7-2.Q. 50kW未満の低圧太陽光でもFIPに移行できますか?
原則として、FIP制度は50kW以上の高圧設備が対象です。
しかし、50kW未満の低圧設備であっても、アグリゲーターが複数の設備を束ねる「アグリゲーション」という形で参加することが可能です。この場合、アグリゲーターが代表して発電計画の策定や市場取引を行います。
7-3.Q. インバランス料金はどのくらいかかりますか?
インバランス料金は、固定額ではなく、市場価格や需給の逼迫状況に応じて変動します。
発電計画と実績のズレ(インバランス量)が大きく、かつ電力需給が厳しい時間帯に発生した場合、ペナルティである精算単価が高騰し、高額になる可能性があります。
リスクを避けるためには、予測精度の向上やアグリゲーターとの連携が非常に有効です。
7-4.Q. おすすめのアグリゲーターはありますか?
特定の企業名を推奨することはできませんが、アグリゲーターを選定する際は、以下の点を比較検討することが重要です。
- ・手数料体系(固定費型か、利益に応じた成功報酬型か)
- ・サービス内容(予測精度、バランシング代行、取引サポートの範囲)
- ・契約条件(契約期間や中途解約の条件)
- ・実績と信頼性(取扱容量や顧客からの評価)
自社の設備規模や方針に合致したサービスを提供しているかを慎重に見極めましょう。
実際の活用方法や収益性は、土地の広さや立地、希望によっても異なります。
FIT・FIP制度に限らず、アパート経営など複数の活用プランを比較した上で、自分に合った選択をするのが成功の近道です。
まずは資料請求から、情報を集めてみませんか?
FIT・FIP制度を調べた今だからこそ、
アパート・マンション経営など他の土地活用も視野に入れてみませんか?
⇒ 複数プランを無料で比較して、納得の活用方法を見つける
まとめ:自社の目的に合った制度を選び、再エネ事業を成功させよう
本記事では、FIT制度とFIP制度の違いを軸に、卒FITを迎える発電事業者が選ぶべき最適な戦略について解説しました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。
- ・FITとFIPの根本的な違いを理解する
FITは国が価格を保証する「安定型」、FIPは市場価格で収益を追求する「自立型」の制度です。FIPではリスクとリターンの両方を事業者が担うため、より戦略的な運営が求められます。 - ・FIP制度の導入にはリスク管理が必須
FIP制度のメリットを享受するには、インバランスリスクや市場価格の変動リスクに備える体制が不可欠です。アグリゲーターの活用や発電量予測精度の向上が成功の鍵となります。 - ・FIP以外の選択肢も視野に入れる
卒FIT後の選択肢はFIP制度だけではありません。自家消費+蓄電池によるコスト削減や、相対契約(PPA)による安定収益の確保も有力です。自社の収益目標、安定性への考え方、投資余力に応じて総合的に判断しましょう。 - ・卒FITは事業モデルを見直す好機と捉える
卒FITは、単なる制度の終了ではなく、自社のエネルギー戦略や事業モデルを再構築する絶好の機会です。非化石価値の売却や環境経営のアピールなど、新たな価値創造に繋がる可能性も広がっています。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
- カテゴリ:
- 賃貸経営の基礎知識
賃貸経営の基礎知識の関連記事
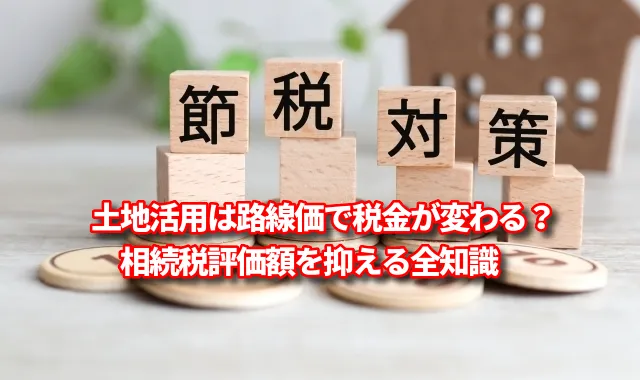
- 土地活用は路線価で税金が変わる?相続税評価額を抑える全知識 公開
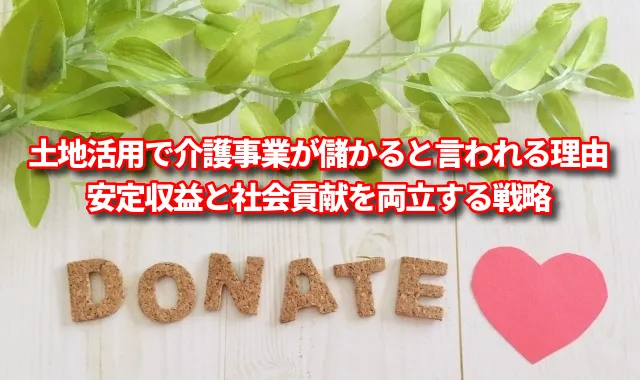
- 土地活用で介護事業が「儲かる」と言われる理由 安定収益と社会貢献を両立する戦略 公開

- 【地域活性化の起爆剤】土地活用と空き家リノベーションで未来を拓く 公開

- 賃貸経営の利回り完全ガイド:計算から平均・シミュレーションまで徹底解説 公開
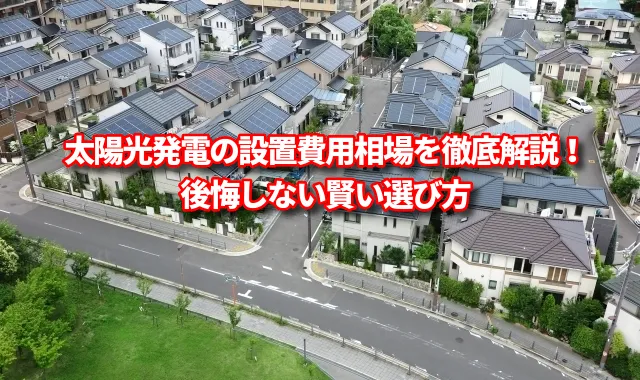
- 太陽光発電の設置費用相場を徹底解説!後悔しない賢い選び方 公開

- 【土地活用】借地権設定で安定収入!リスクを抑えて資産を最大化する方法を徹底解説 公開
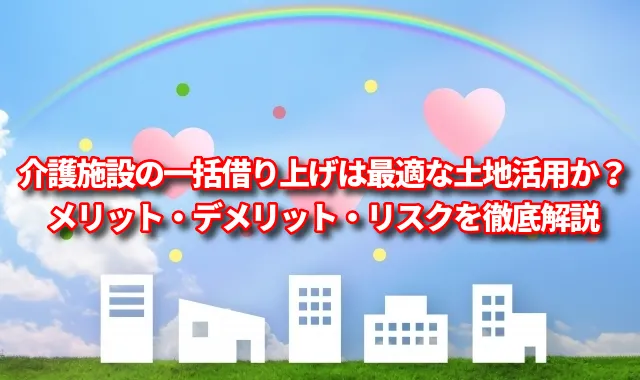
- 介護施設の一括借り上げは最適な土地活用か?メリット・デメリット・リスクを徹底解説 公開

- 太陽光発電の余剰電力売電ガイド:FIT後の最適な選択肢と賢い契約方法 公開

- 太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)とは?FITの仕組みから卒FIT後の賢い選択肢まで徹底解説 公開
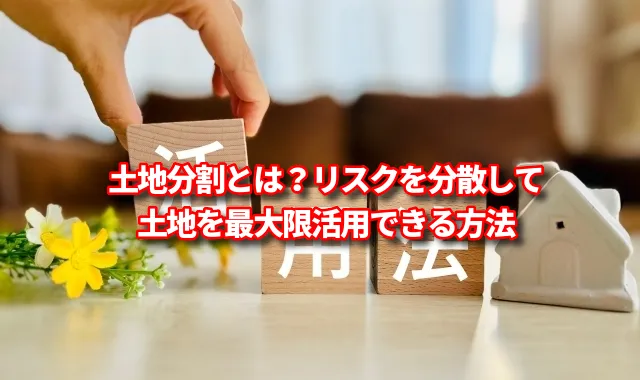
- 土地分割とは?リスクを分散して土地を最大限活用できる方法 公開
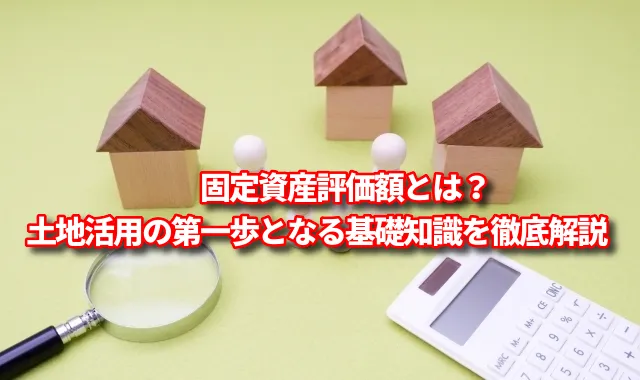
- 固定資産評価額とは?土地活用の第一歩となる基礎知識を徹底解説 公開
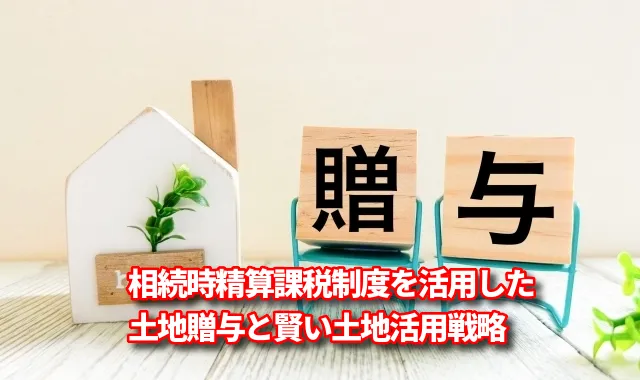
- 相続時精算課税制度を活用した土地贈与と賢い土地活用戦略 公開
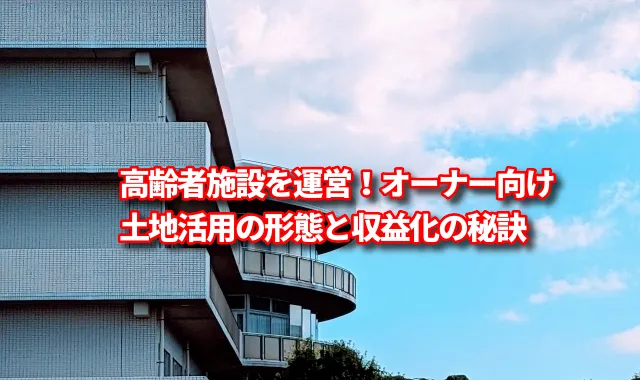
- 高齢者施設を運営!オーナー向け土地活用の形態と収益化の秘訣 公開
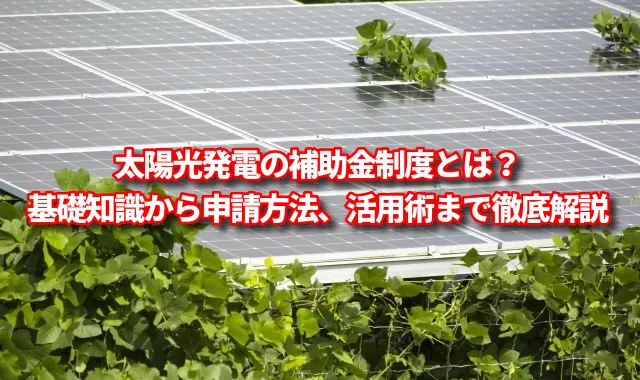
- 太陽光発電の補助金制度とは?基礎知識から申請方法、活用術まで徹底解説 公開
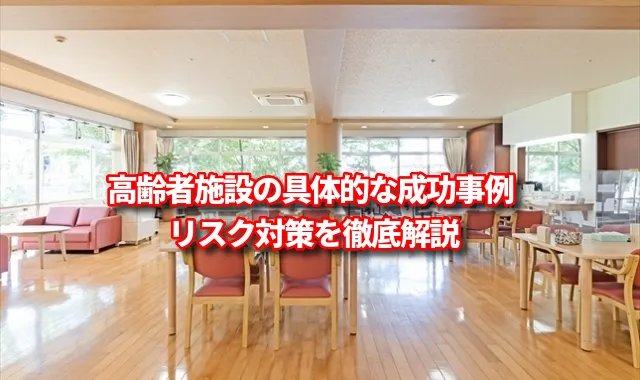
- 高齢者施設の具体的な成功事例とリスク対策を徹底解説 公開

- 土地活用としての太陽光発電投資:投資回収期間と収益最大化の全貌 公開
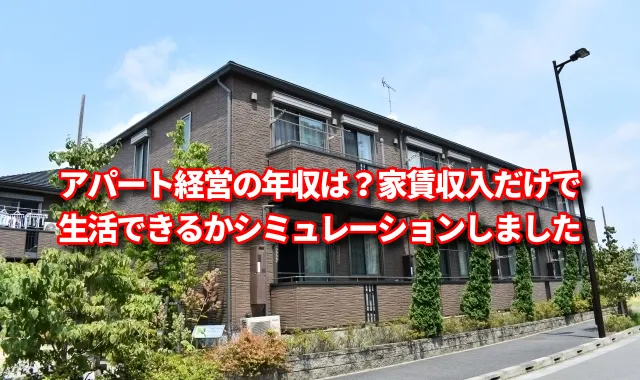
- アパート経営の年収は?家賃収入だけで生活できるかシミュレーションしました 公開

- FIT制度とFIP制度の最も重要な違いとは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説 公開

- 遊休地で太陽光発電、投資回収期間は何年?費用・利回り・失敗しないポイントを徹底解説 公開
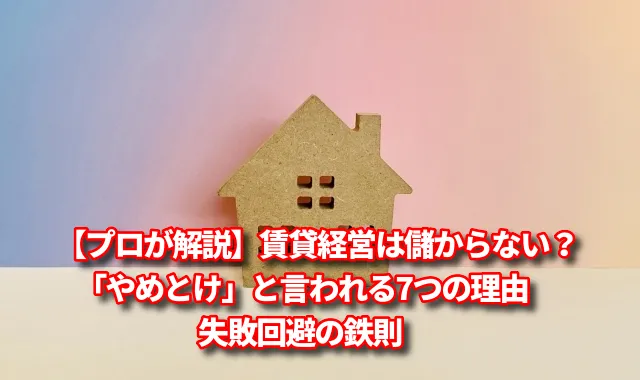
- 【プロが解説】賃貸経営は儲からない?「やめとけ」と言われる7つの理由と失敗回避の鉄則 公開