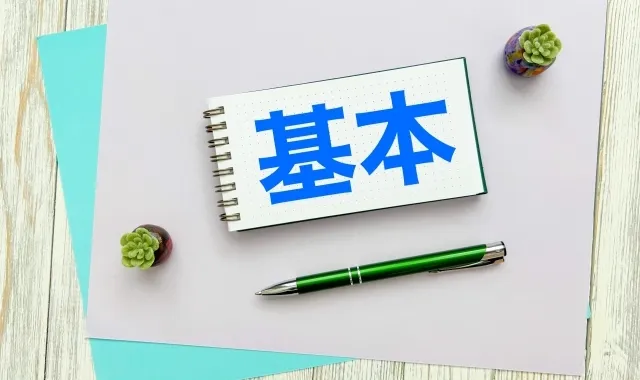- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- リロケーション
- 自宅の賃料の相場を知る
- 【イエカレ】海外赴任で自宅を貸すなら定期借家契約|家賃を下げずに安心運用する方法
【イエカレ】海外赴任で自宅を貸すなら定期借家契約|家賃を下げずに安心運用する方法
この記事を読むのにかかる時間:10分
1.定期借家契約とは?普通借家契約との違い
海外赴任や転勤で自宅を一時的に貸し出す場合、最も懸念されるのは「帰任時に自宅に戻れなくなる」というリスクではないでしょうか。このリスクを回避し、貸主様の期間設定通りに契約を確実に終了させるための賃貸借契約が定期借家契約です。
定期借家契約は、一般的な賃貸契約である普通借家契約と異なり、契約期間の満了をもって自動的に契約が終了し、入居者様は原則として退去する義務を負います。
1-1.更新がない「定期借家契約」の基本仕組み
定期借家契約とは、借地借家法に定められた賃貸借契約の一種で、契約期間の満了により、更新されることなく確定的に終了する賃貸契約のことです。
帰任日が決まっている海外赴任の場合、この「確実な終了」が貸主様の最大の安心材料となります。契約期間は自由に設定可能であり、1年や2年など、貸主様の赴任期間に合わせて柔軟に定めることが可能です。
普通借家契約では、貸主様が「正当な事由」を証明しなければ契約を終了させることが難しいのに対し、定期借家契約では期間の満了をもって終了が確定します。
| 契約の種類 | 契約の更新 | 契約期間 | 契約終了時の退去義務 |
|---|---|---|---|
| 定期借家契約 | なし(再契約は可能) | 1年〜、自由に設定可能 | 原則あり(通知により確定終了) |
| 普通借家契約 | あり(借主が望めば更新可能) | 制限なし | 貸主の「正当事由」が必要で困難 |
2.普通借家契約との3つの違い(更新/期間/退去義務)
定期借家契約と普通借家契約には、貸主にとって運用上のリスクに直結する3つの決定的な違いがあります。
2-1.契約の更新がない
普通借家契約では、入居者様が希望する限り契約が自動的に更新され、貸主様から契約の終了を申し出るには「正当な事由」が必要です。
この「正当な事由」の証明は非常に難しく、裁判になった場合でも貸主様側の主張が通りにくいケースが多いため、結果的に自宅に戻れなくなるリスクが発生します。
一方、定期借家契約には契約の更新自体がないため、期間が満了すれば契約は確実に終了します。
2-2.契約期間を自由に設定できる
普通借家契約では、原則として1年未満の契約期間を定めることはできません。
これに対し、定期借家契約では契約期間の制限がなく、貸主様の海外赴任期間に合わせて1年間や2年間といった短い期間を設定することが可能です。
この柔軟な期間設定は、短期の貸し出しを希望する海外赴任者にとって非常に大きなメリットとなります。
2-3.期間満了で退去義務が発生する
定期借家契約では、入居者様に対し、契約期間満了の6ヶ月前から1年前に通知を行うことで、契約の終了と退去を確実に求めることができます。
この法的根拠があるため、「帰任時に自宅に戻れない」という最大のリスクを回避することが可能となるのです。
3.家賃は安くなる?定期借家の賃料相場と設定ポイント
海外赴任中の自宅を貸す上で、「家賃を下げずに収益を維持したい」という思いは、貸主様にとって重要な関心事です。
定期借家契約は、契約の特性上、家賃が相場よりも低くなる傾向がありますが、戦略的な家賃設定と募集条件の工夫により、その影響を最小限に抑えることが可能です。
3-1.相場より低くなる傾向と理由
結論から述べると、定期借家契約の家賃は、普通借家契約の物件に比べて相場より1割〜2割程度低くなる傾向があります。
この主な理由は、以下の2点です。
- 契約期間が短い・再契約が不確定:入居者様は一定期間での退去を求められるため、長期的な居住を前提とした普通借家契約よりも物件の魅力が低下します。この「不便さ」を補うために、家賃を調整する必要が出てきます。
- 市場の認知度がまだ低い:定期借家契約はまだ一般的な契約形態ではないため、入居者様が契約内容を理解するのに時間がかかったり、敬遠したりする傾向があります。
3-2.家賃を下げずに契約する条件(立地・期間設計・管理形態)
家賃の低下リスクを回避し、相場を維持、または相場同等で契約を成立させるためには、募集における条件を工夫することが不可欠です。
特に以下の3つの条件が重要となります。
- 立地条件の優位性を強調する:駅からの距離、周辺施設の充実度、転勤人口が多い都市圏での稀少性など、物件の立地条件が持つ優位性を最大限に訴求します。
- 契約期間に柔軟性を持たせる:「再契約の可能性あり(貸主都合による)」といった一文を付け加え、期間に柔軟性を持たせて不安を軽減します。
- リロケーション管理体制の信頼性を示す:専門の管理会社が関与することで、トラブル対応や手続きがスムーズである安心感を提供できます。
3-3.【比較表】リロケーション会社経由と自己募集の相場差
家賃設定を検討する際には、自己募集とリロケーション会社経由の募集の差を理解することが、収益の最大化に繋がります。
| 方法 | 平均家賃 | 契約安定性 | 管理負担 |
|---|---|---|---|
| 自己募集 | 相場−1割 | △(法的手続きリスク) | 高い(トラブル対応・通知義務) |
| リロケーション会社経由 | 相場同等 | ◎(専門知識による法遵守) | 低い(代行・丸投げが可能) |
リロケーション管理会社は、法人契約や外国人駐在員向けなど、高単価のニッチな入居者層へのネットワークを持っているため、家賃を下げずに契約できる可能性が高まります。
4.家賃交渉が起こりやすいケースと対応策
定期借家契約で家賃交渉が起こりやすいのは、「短期契約」や「家具なし」の条件で募集する場合です。
4-1.短期契約(1年未満)
契約期間が短いほど、入居者様は退去と引っ越しという手間を繰り返すことになるため、家賃交渉の要求が高まります。
4-2.対応策
「光熱費込み」や「家具家電付き」といった付加価値を提供することで、家賃の根拠を明確にし、交渉の余地を減らすことができます。特に家具家電付きは、入居者様の初期費用負担を大幅に減らすため、家賃を下げずに契約する有効な手段です。
5.収益を維持する募集条件の工夫
収益を維持、または最大化するためには、家賃の絶対額だけでなく、付加価値による高単価維持を狙う工夫が必要です。
5-1.「家具家電付き」で高単価維持
赴任者や単身者など、短期間の入居を希望する層は、家具家電を揃える手間を省きたいニーズが高いため、この条件は高いニーズがあります。
5-2.「光熱費込み」
家賃と光熱費を合算した金額を提示することで、入居者様にとっては毎月の支払い管理が楽になり、貸主様は実質的な家賃収入を高く維持することが可能です。
6.貸主が注意すべき契約手続きとリスク管理
定期借家契約は「帰任時に戻れる」安心感を提供しますが、その手続きには借地借家法による厳格な規定があり、ひとつでも欠けると契約が無効になるリスクを伴います。
リロケーション管理会社と連携し、正確な手続きを踏むことが、契約トラブルを避けるための必須条件です。
6-1.契約書・書面交付・重要事項説明の義務
定期借家契約を有効に締結するためには、以下の3つの義務を履行することが法律で定められています。
- ・契約書の作成
- ・契約書とは別に、「更新がない」ことを記載した書面の交付
- ・不動産会社の宅地建物取引士による重要事項説明の実施
特に「契約書とは別の書面の交付」と「更新がないことの説明」が最も重要です。これが欠けると、契約全体が普通借家契約と見なされ、契約期間満了で退去を求められなくなる致命的なトラブルにつながります。
6-2.トラブルが起きやすい3つのパターン
- 書面不備:「更新がない」旨を記載した書面を交付しなかった、または契約書にその旨を記載しただけで済ませてしまったケースでは、定期借家契約として成立しません。
- 通知漏れ:契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、貸主様から入居者様に対して契約終了の通知を行わなかった場合、契約の終了を対抗できなくなることがあります。
- 再契約誤認:入居者様に対して、更新や再契約について曖昧な説明をしたり、再契約を保証するような発言をしたりすることで、普通借家契約であると誤認させてしまうケースです。
6-3.家賃滞納・再契約拒否リスクの備え方
- 家賃保証会社の活用:滞納時に保証会社が立て替えるため、収益を守ることができます。
- 自動振込設定の推奨:指定口座への自動振込により、支払い遅延を防止します。
- 再契約拒否のリスク回避:支払い履歴や使用状況を確認し、問題のない入居者様のみに再契約を打診します。
7.リロケーション対応のある管理会社を選ぶポイント
海外赴任中に、貸主様自身でこれらのリスク管理や法的手続きを行うのは現実的ではありません。だからこそ、リロケーションサービスに特化し、定期借家契約の取り扱いに慣れた管理会社を選ぶことが重要です。
7-1.チェック項目の評価表
| チェック項目 | 重要度 | 理由 |
|---|---|---|
| 定期借家契約の経験 | 高 | 法的手続きを正確に代行できる専門性があるか |
| 海外赴任中のオーナー実績 | 高 | 時差や言語の壁を理解し、コミュニケーションできるか |
| 入居者募集力 | 中 | 法人契約や外国人向けなど、優良顧客のネットワークがあるか |
| トラブル対応実績 | 高 | 24時間体制など、緊急時の対応力とスピードがあるか |
| 家賃保証の体制 | 高 | 提携している保証会社の信頼性、滞納時の対応スピード |
8.定期借家契約で収益を最大化する方法
定期借家契約を単なる「安心のための契約」で終わらせず、収益を最大化する手段として活用するためには、家賃設定、契約期間の設計、リロケーション管理会社との連携という3つの要素を戦略的に組み合わせることが不可欠です。
空き家にしておく場合と比較して、大きな損失回避と収益獲得に繋がります。
8-1.家賃設定と契約期間の最適バランス
家賃設定と空室リスクはトレードオフの関係にあり、このバランスを見極めることが収益最大化の鍵となります。
相場以上の高家賃は空室長期化のリスク、相場より低い設定は毎月の収益減少につながります。管理会社と相談し、空室期間が3ヶ月以内に収まる水準を目標とするのが現実的です。
8-2.再契約を見越した長期収益モデル
定期借家契約は更新がない契約ですが、双方の合意があれば再契約は可能です。初期契約を赴任期間に合わせて設定し、再契約時の条件(家賃見直し・修繕状況など)を事前に整理しておくことで、単発ではなく長期の安定収益を目指せます。
8-3.リロケーション管理会社との連携で安定運用
優良な入居者様の選定、契約手続きの正確性、トラブル防止と迅速対応など、管理会社への委託は収益の安定化に直結します。海外赴任中の賃料送金や確定申告に必要な書類作成まで代行されるため、本業に集中できます。
9.失敗パターンとその回避策
定期借家契約での運用における主な失敗パターンは、「自己募集による法的手続きの不備」です。
9-1.失敗パターン:自己募集や安易な契約
仲介手数料を惜しんで自己募集を行い、定期借家契約に必要な書面交付や通知義務を怠ることで、契約が普通借家契約と見なされてしまうケースです。結果、帰任時に自宅に戻れなくなるという最悪の事態を招きます。
9-2.回避策
「リロケーションサービス」に特化した管理会社に依頼することで、法的手続きの正確性と優良な入居者様の選定を保証してもらい、収益と安心を両立させることが可能です。
10.まとめ
海外赴任で自宅を貸す場合、定期借家契約は、帰任時に確実に自宅に戻れるという最大の安心を貸主様に提供する、最も適した契約形態です。
この契約は、普通借家契約とは異なり、契約期間の満了とともに更新なく終了する点が最大のメリットです。
契約手続きの際には、書面交付や通知義務といった法的な注意点を遵守することが不可欠ですが、これはリロケーション管理会社に委託することで、リスクをゼロに近づけることが可能です。
家賃を下げずに収益を確保するためには、立地条件の優位性、家具付きなどの付加価値、そして管理会社による優良入居者の選定を組み合わせた戦略が鍵となります。
赴任前に専門家へ無料相談することで、法的な安心と、収益最大化という二重のメリットを手に入れ、安心して自宅を収益化できる未来を実現しましょう。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 自宅の賃料の相場を知る
自宅の賃料の相場を知るの関連記事
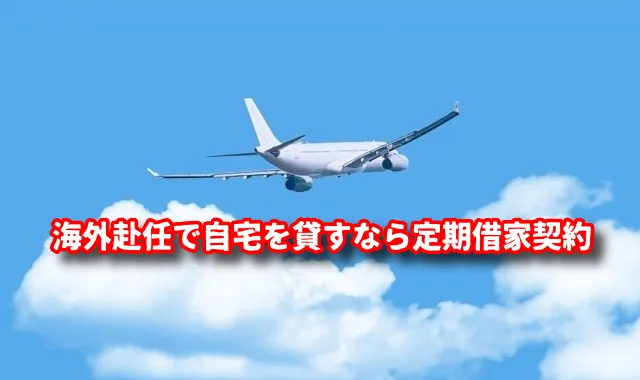
- 海外赴任で自宅を貸すなら定期借家契約|家賃を下げずに安心運用する方法 公開

- 家を貸すなら知っておきたい!適正家賃の決め方と相場チェック術【初心者向け】 公開