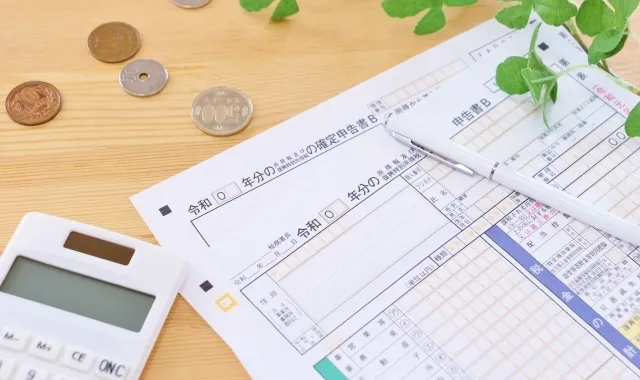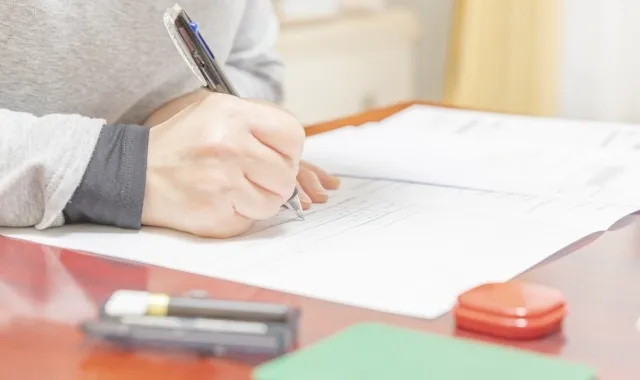- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- リロケーション
- リロケーションと税金
- 【海外赴任者必見】持ち家を賃貸に出すオーナーが「税金で損をしない」ための完全ガイド:住宅ローン控除と確定申告のすべて
【海外赴任者必見】持ち家を賃貸に出すオーナーが「税金で損をしない」ための完全ガイド:住宅ローン控除と確定申告のすべて
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.オーナーがまず知るべき「税金とローン」の全体像
1-1.住宅ローン控除は「中断」と「再開」ができる!その条件と手続き
持ち家を賃貸に出すオーナーにとって、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が継続できなくなる不安は最も大きいといえます。
しかし、住宅ローン控除は海外赴任による賃貸開始後も「中断」の手続きを行い、帰国後に再居住することで「再開」できる仕組みが整備されています。
この中断と再開の手続きを正確に行うことで、控除を失うことなく将来的に恩恵を受けることが可能です。
賃貸開始時の「中断」手続きと必要書類
住宅ローン控除を海外赴任中に中断するためには、賃貸開始日の前日までに、所轄の税務署に「転居の際の手続き」として必要書類を提出する必要があります。
提出する書類は、「転居の日の属する年分の確定申告書」に「特定事由に該当する旨の届出書」を添付することが基本です。この特定事由とは、海外赴任などやむを得ない事情で居住できなくなった場合を指します。
この届出書には、控除の再開を希望する旨を記載する欄があるため、必ず将来的な再開の意思を明示することが重要です。
帰国後の「再開」条件と注意点:帰国後の再居住が必須
帰国後に住宅ローン控除を再開するための最も重要な条件は、オーナー自身がその持ち家に再び居住することです。帰国後、単に所有しているだけでは再開は認められません。
また、再開には「再居住の日の属する年分の確定申告書」に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などを添付する必要があります。
特に注意すべきなのは、控除期間の残存期間内に再居住しなければならないという点です。
賃貸に出していた期間は控除期間に算入されませんが、再開するためには、当初の控除期間が満了するまでに帰国し、居住を開始することが求められます。
この「再居住の義務」を念頭に、定期借家契約の期間を設定することが、将来的な住宅ローン控除の恩恵を受けるための一般的な選択肢となります。
1-2.家賃収入は「不動産所得」として課税される仕組み
海外赴任中に持ち家を賃貸に出して家賃収入を得た場合、この収入は不動産所得として日本の税金(所得税・住民税)の課税対象となります。この仕組みを正しく理解することは、適切な納税と節税対策の基盤になります。
不動産所得の計算式:収入から経費を引けるメリット
不動産所得は、「総収入金額 − 必要経費」という計算式で算出されます。ここでいう総収入金額には、毎月の家賃だけでなく、礼金や更新料、共益費なども含まれます。
大きなメリットは、この収入から必要経費を差し引くことができる点です。例えば、固定資産税、火災保険料、管理会社への手数料、そして最も節税効果が大きいとされる減価償却費などが経費として認められます。
これらの経費を漏れなく計上することで、課税対象となる不動産所得を減らし、結果として手元に残る収益を最大化することが可能です。
1-3.非居住者(海外在住者)としての納税義務と日本の税金(所得税・住民税)
海外に1年以上居住する場合、税法上は非居住者となります。非居住者であっても、日本国内にある不動産の賃貸で得た家賃収入(不動産所得)は、日本の税金(所得税・住民税)の課税対象です。
賃借人が個人の場合、賃貸人であるオーナーが非居住者であっても、所得税の源泉徴収は原則不要です。
しかし、賃借人が法人の場合は、家賃から所得税を源泉徴収し、納税する義務が生じます。非居住者のオーナーは、この不動産所得を日本で確定申告し、納税する義務を負います。
所得税の確定申告が必要な場合、住民税も原則として申告内容に基づいて課税される仕組みです。
1-4.納税管理人とは?選任の義務と選任しない際のリスク
非居住者として日本の不動産所得を適切に管理・納税するためには、納税管理人の選任は極めて重要です。この選任は、オーナーの義務であり、適切な手続きを行うことで税務上のリスクを回避できます。
納税管理人とは、非居住者であるオーナーに代わり、確定申告書の提出、税金の納付、税務署からの書類受領や問い合わせへの対応など、税務に関する一切の事項を代行する者のことです。
納税管理人を選任した場合は、所轄の税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書(兼)居所、事業所等変更届出書」を提出する必要があります。
納税管理人を選任しない場合、税務署からの重要な通知や書類が海外のオーナーに直接送付されます。しかし海外在住では迅速な対応が困難となり、申告期限や納税期限に遅れるリスクが飛躍的に高まります。
期限遅れは延滞税や無申告加算税などの追徴課税リスクを招き、最終的に手元に残る収益を大きく損なう結果に繋がります。
2.手元に残るお金を最大化する「経費と節税」の具体的な知識
2-1.知識が収益に直結!家賃収入から控除できる経費の網羅リスト
不動産所得の計算において、収入から控除できる経費の知識は、オーナーの手元に残る収益に直結します。控除可能な経費を漏れなく計上することが、実質的な手取り額を最大化するための重要なステップです。
2-2.賃貸経営特有の「減価償却費」の計算と節税効果
経費の中でも特に節税効果が大きいのが減価償却費です。
減価償却費とは、建物の取得費用を、法定耐用年数に応じて毎年費用として計上する会計上の概念です。実際には現金の支出がないにもかかわらず経費にできるというメリットがあります。
計算方法は、建物の取得費用に法定耐用年数に応じた償却率を乗じる定額法が一般的です。例えば、取得価格1,000万円(建物部分)の耐用年数25年の物件の場合、定額法の償却率を使用して計算します。
この減価償却費を毎年計上することで、帳簿上の不動産所得を圧縮し、課税対象額を大幅に減らすことが可能になります。
2-3.ローン関連費用(利息など)の経費計上ルール
住宅ローンを継続している場合、ローンの返済元本は経費になりませんが、支払利息の一部は経費として計上できます。
経費に計上できる利息は、「業務に要した部分」に限られ、賃貸に出している建物の床面積の割合や、ローンの使途(賃貸部分の取得に充てられた部分)に応じて按分計算が必要です。
この按分計算が複雑になるため、特に海外赴任期間中は、正確な利息額の計上について、不動産税務に詳しい納税管理人や税理士などの専門家の知見を借りることが、後々の税務調査リスクを回避する上で推奨されます。
2-4.その他、見落としがちな管理費用、修繕費、交通費など
賃貸経営では、毎月の管理会社への管理手数料、火災保険料、固定資産税、都市計画税、賃貸募集広告費用、入居者退去時の原状回復費用や修繕費用などが経費として控除できます。
見落としがちなのは、オーナーが賃貸経営のために行った活動にかかる費用です。
例えば、定期借家契約の更新手続きのための通信費や、必要な書類を税理士に送るための郵送費、オーナーが物件管理のために一時帰国した際の交通費や宿泊費なども、合理的な範囲内で経費として認められる可能性があります。
これらの小さな費用も、年間を通して積み重ねれば大きな金額になるため、領収書や記録を漏れなく保管することが重要です。
2-5.【独自シミュレーション】あなたの「実質収益」をデータで予測
オーナーが最も知りたいのは、家賃収入から税金や経費を引いた後に「手元にいくら残るのか」という実質収益です。
客観的な数字で損をしないことを確認したいという不安を解消するために、簡易的な収支予測は不可欠です。
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 年間家賃収入 | 2,400,000 |
| 減価償却費 | -400,000 |
| 管理費・修繕積立金 | -360,000 |
| 固定資産税等 | -240,000 |
| 管理手数料 | -240,000 |
| ローン利息(按分後) | -100,000 |
| 経費合計 | -1,340,000 |
| 不動産所得 | 1,060,000 |
| 所得税・住民税(概算) | -150,000 |
| 実質収益(手取り) | 910,000 |
3.海外赴任オーナー特有の「確定申告」手続き
3-1.失敗しない!非居住者の「確定申告」ステップバイステップ
非居住者として日本の不動産所得の確定申告を行うプロセスは、居住者の場合と異なり、複数のステップがあり煩雑です。
申告漏れや誤りを防ぎ、追徴課税のリスクを回避するためには、この手順を正確に実行することが不可欠です。
ステップ1: 納税管理人の届出(提出期限と場所)
非居住者となるオーナーは、海外へ出国するまでに、納税管理人を選任し、所轄の税務署へ「所得税・消費税の納税管理人の届出書(兼)居所、事業所等変更届出書」を提出する必要があります。
届出書の提出期限は、オーナーが非居住者となる前、つまり出国前が原則です。
納税管理人を定めておくことで、税務署からの通知や書類が納税管理人に送付され、確定申告や納税を代行してもらうことが可能になります。
特に海外赴任中は、日本の税務情報に即座に対応することが困難なため、このステップは最も重要といえます。
ステップ2: 確定申告に必要な書類と管理方法
確定申告には、家賃収入や経費に関する多くの書類が必要です。
- ・家賃送金明細書、管理会社からの年間収支報告書
- ・固定資産税・都市計画税の納税通知書
- ・火災保険料の領収書、減価償却費の計算資料
- ・住宅ローンの年末残高証明書(利息部分の計算に必要)
これらの書類を海外赴任中も紛失しないよう、納税管理人が責任をもって管理できる体制を構築しておくことが重要です。
デジタルデータでの管理や、クラウドサービスを活用し、オーナーと納税管理人で情報を共有する仕組みを整えることが推奨されます。
ステップ3: 帰国後の確定申告(準確定申告)の注意点
非居住者であったオーナーが帰国し居住者に戻った場合、その年の1月1日から帰国日までの所得について、通常の確定申告とは異なる準確定申告が必要になる場合があります。
特に、海外での給与所得がある場合は、二重課税を防ぐための外国税額控除の適用など、申告内容が複雑化する可能性があります。
帰国後の住宅ローン控除再開手続きも同時に行う必要があるため、納税管理人と緊密に連携を取り、帰国後速やかに申告準備を開始することが大切です。
4.【落とし穴】賃貸契約書で注意すべき税務上の特約
4-1.「敷金・礼金・更新料」の税務上の取り扱いの違いについて
敷金は、原則として退去時に返還される性質を持つため、受け取った時点では不動産所得の収入とはなりません。
これに対し、礼金や更新料は、受け取った時点で不動産所得の総収入金額に算入され、課税対象となります。
賃貸契約を締結する際、この税務上の取り扱いを理解した上で、礼金や更新料の設定を検討することが、手取り収益の計算に直結します。
サブキーワードである定期借家契約においては、契約期間の終期が明確なため、更新料の有無や設定が収支計画に大きな影響を与えます。
4-2.定期借家契約に含めるべき「税金・手続き協力」に関する特約の推奨例
「オーナーが非居住者となった場合の、源泉徴収義務に関する協力」や、「納税管理人との連絡・書類提出への協力」といった特約を賃貸契約書に明記することが推奨されます。
特に、賃借人が法人の場合、源泉徴収義務が生じます。その手続きに関する協力体制を契約書で明確に定めることで、オーナーの納税義務履行をスムーズにし、将来的な税務上のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
この特約は、納税管理人を選任している場合でも、賃借人の理解と協力を得るための重要な予防策となります。
5.オーナーの不安を解消する事例と教訓
5-1.【オーナー実話】税理士に依頼して「安心」を買ったケース
多くの海外赴任オーナーが抱える「税金で損をする不安」や「手続きの煩雑さ」は、納税管理人の選任と確定申告のプロへの委託によって解消されています。
事例:「40代駐在員A氏:ローンの不安から解放され、海外での仕事に集中できた理由」を紹介します。
大手メーカーに勤務するA氏は、初めての海外赴任にあたり、住宅ローン控除の再開手続きや、非居住者としての複雑な確定申告に強い不安を感じていました。
特に、赴任後も続くローンの支払いや、不動産所得に関する日本の税法を海外から把握し続けることに、大きな精神的負荷を感じていました。
A氏は、赴任前に海外不動産税務に強い税理士を納税管理人として選任しました。これにより、A氏は海外滞在中に発生する家賃収入の不動産所得計算、減価償却費の計上、そして定期借家契約の更新手続きに至るまで、全てを専門家に一任することができました。
教訓:「自己解決の限界点」と、「追徴課税リスクを回避した価値」を強調します。
税理士に依頼することで、節税対策が法的に正確に行われ、追徴課税という金銭的なリスクが回避されました。
その結果、A氏は複雑な税務手続きから解放され、現地での駐在業務に集中することができました。この「安心」こそが、専門家への依頼費用を上回る最大の価値となりました。
自己解決を試みて手続きにミスがあった場合の精神的・金銭的損失を考慮すると、プロの力を借りることは、オーナーの海外赴任キャリアを守るための戦略的な選択といえます。
6.FAQ:海外赴任オーナーが抱く「税金のよくある疑問」
海外赴任オーナーが抱く、税金や納税管理人に関する具体的な疑問を解消することは、オーナーの不安を軽減するために不可欠です。
6-1.Q1. 海外にいる間に税務署から問い合わせが来たらどうなるか
A:納税管理人を選任している場合、税務署からの問い合わせや書類は全て納税管理人に送付されます。
納税管理人がオーナーに代わって対応するため、オーナーは海外にいながら日本の税務署とのやり取りを心配する必要はありません。この機能こそが、納税管理人を選任する最大のメリットの一つです。
6-2.Q2. 納税管理人を依頼する際の費用相場と選び方の基準は
A:納税管理人の依頼費用は、依頼する専門家(税理士など)や業務範囲によって大きく異なります。費用相場は年間〇万円〜〇十万円程度の幅があります。
選ぶ基準として、海外赴任者や非居住者の不動産所得に関する税務に精通しているか、定期借家契約などの特殊なケースの取り扱いに慣れているか、オーナーとの連絡体制がスムーズかなどを確認することが重要です。
6-3.Q3. 賃貸期間中に売却を検討した場合の税金はどうなるか
A:賃貸期間中に持ち家を売却した場合、譲渡所得(売却益)に対して税金が課されます。この場合、居住用の特例(住宅ローン控除と並行して使える3,000万円特別控除など)は原則として適用できません。
また、非居住者として売却する場合、買主が譲渡対価から所得税等を源泉徴収し、納税する義務があるため、国内での売却とは異なる手続きが必要になります。
売却を検討し始めた時点で、税理士に相談し、税金シミュレーションを行うことが不可欠です。
7.プロの力を借りて「安心」を資産にする
本記事では、海外赴任に伴い持ち家を賃貸に出すオーナーが、住宅ローン控除の仕組みから確定申告の手順、不動産所得の経費計上のポイントまでを網羅的に解説しました。これらの知識は、オーナーとして「損をしない」ための最低限必要な基盤です。
しかし、税法は毎年変わります。あなたが最も獲得したい「安心」は、最新の制度に精通した専門家に手続きを任せることでしか得られません。
自己判断によるリスクを回避し、大切な海外でのキャリアに集中するためにも、セカンドオピニオンとして専門家の力を借りることを強く推奨します。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- リロケーションと税金
リロケーションと税金の関連記事

- 【海外赴任者必見】持ち家を賃貸に出すオーナーが「税金で損をしない」ための完全ガイド:住宅ローン控除と確定申告のすべて 公開

- 空き家の不動産価値を徹底解剖!評価基準から査定方法、固定資産税まで解説 公開
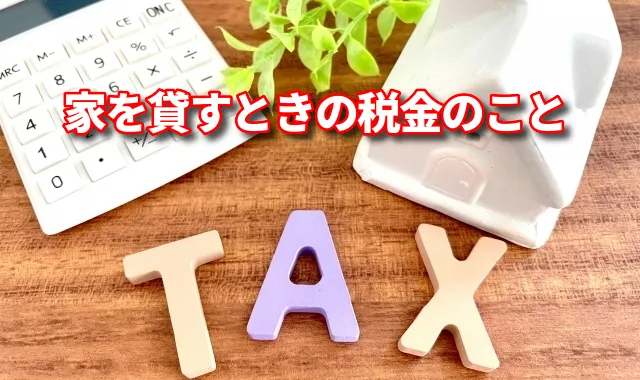
- 家賃収入の“税金と損益通算”を速攻マスター|手取りを増やす節税戦略 公開

- 家賃収入の“税金と費用”徹底ガイド|手元に残すための節税と収益確保のコツ 公開