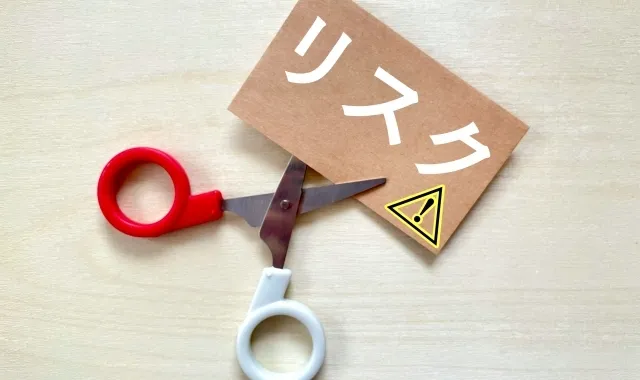- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- マンションを建てるための基礎知識
- 【イエカレ】マンション経営のリスク9選と対策完全ガイド|初心者でも失敗を防ぐチェックリスト付き
【イエカレ】マンション経営のリスク9選と対策完全ガイド|初心者でも失敗を防ぐチェックリスト付き
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.マンション経営の基礎と「リスク」の考え方
マンション経営は、単に物件を購入する不動産投資ではなく、長期にわたって家賃という安定収入を得るための事業活動です。この活動において、リターンを最大化するためには、その裏側にあるリスクの特性を深く理解することが欠かせません。
このセクションでは、マンション経営の基本的な仕組み、利回りとリスクの関係、そして一般的に「怖い」「不安」と言われる要因について解説します。安定収入を得るためには、適切な管理が不可欠であることを理解することが大切です。
1-1.マンション経営とは?仕組みと収益構造
マンション経営とは、購入したマンションの部屋を第三者に賃貸し、毎月発生する家賃収入から経費やローン返済額を差し引いた差額を収益とする不動産投資の手法を言います。
主な収益構造は、家賃収入から管理費、修繕積立金、固定資産税、不動産取得税、そしてローン返済といった経費を差し引いた額が手元に残る「キャッシュフロー」です。このキャッシュフローをプラスにする資金計画が成功の鍵となります。
物件を担保にローンを組むことで、少ない初期費用で始められる点が特徴です。しかし、経費やローン返済額が家賃収入を上回れば、キャッシュフローはマイナスとなり、毎月持ち出しが発生するリスクが生じます。
1-2.不動産投資におけるリスクとリターンの関係
不動産投資におけるリターンとは、主に家賃収入から経費を差し引いたキャッシュフローや、売却益(キャピタルゲイン)を指します。利回りは、投資額に対するリターンの割合を示す重要な指標です。
投資の世界では、「高利回りは高リスク」という原則があります。安定収入を目指すあまり、高利回りに目を奪われると、災害リスクが高いエリアや、将来的な資産価値下落の可能性が高い物件に手を出してしまうリスクを負うことになります。
逆に、リスクを極端に避けすぎるとリターンが小さくなり、時間をかけて安定収入を築くというマンション経営のメリットを活かせません。リスク許容度を明確にし、その範囲内でリターンを追求する資金計画が重要です。
1-3.なぜ「マンション経営はリスクが高い」と言われるのか
マンション経営が「リスクが高い」と言われる主な要因は、空室、金利変動、老朽化に伴う修繕費の増加といった具体的な不確実性にあります。
メディアや口コミでは、これらのリスクが強調され、「失敗すると借金だけが残る」「管理が大変」といったネガティブなイメージが先行しがちです。特に、経済危機を経験した世代には、不動産投資への不安感が根強く残っています。
しかし、これらのリスクは適切な対策と管理によって十分にコントロールできるものです。
リスク理解を深め、冷静な資金計画を立てることで、「怖い」という感情を「備えるべき課題」という認識に変えられます。
1-4.初心者が誤解しがちな3つのリスク認識
マンション経営を始める初心者が失敗しやすい、よくあるリスク認識の誤解を3つご紹介します。これらの誤解を解消し、正しいリスク理解を持つことが安定収入への第一歩です。
①「ローン返済不能=失敗」という誤解
マンション経営のローンには、団体信用生命保険(団信)が付いているケースがほとんどです。
万が一、オーナーが死亡または高度障害になった場合、保険金でローンが完済され、残された家族に無借金の安定収入(家賃収入)が残る仕組みです。
万一の際には資産を残せるため、失敗=全てを失うという認識は誤りです。
②「サブリースなら安心」という誤解
サブリースは、管理会社が物件を一括で借り上げ、オーナーに一定の家賃を保証するシステムです。
空室リスクは軽減されますが、家賃保証額はサブリース会社によって定期的に見直され、減額されるリスクがあります。
減額リスクは契約書に明記されている場合があるため、契約内容の詳細確認が必須です。また、サブリース契約自体の解除が困難になるリスクもあります。
③「都心なら絶対儲かる」という誤解
都心の物件は資産価値が下落しにくい傾向がありますが、高額なため利回りが低くなりがちです。
また、都心であっても供給過多による空室リスクや、家賃競争による家賃下落リスクは存在します。
立地だけで判断せず、周辺の需給バランスや賃料相場を分析する資金計画が欠かせません。
2.マンション経営で特に注意すべき9つのリスク
マンション経営で直面する可能性のある9つの代表的なリスクについて、それぞれの解説と具体的な対策を解説します。
これらのリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることは、安定収入の獲得を目指す不動産投資において非常に重要です。
空室、家賃滞納、金利変動、修繕費といった具体的な不安要素を一つずつ整理し、「備えたい」という読者の潜在ニーズに応えます。
2-1.9リスク項目と対策概要
マンション経営における9つの主要なリスクとその対策を簡潔にまとめます。
①空室リスク
入居者がいない期間、家賃収入が途絶えるリスクです。
対策概要: 単身者需要が高い駅近の立地を選定することや、入居者付けに強い管理会社を選ぶことで、空室率を低減できます。
②家賃滞納リスク
入居者が家賃の支払いを遅延または停止するリスクです。
対策概要: 入居審査時に信用度の高い入居者を選定することや、賃貸保証会社への加入を必須とすることで、家賃滞納による安定収入の途絶を避けられます。
③家賃下落リスク
物件の老朽化や競合物件の増加により、家賃相場が下がり、収益が減少するリスクです。
対策概要: 築年数が経過しても魅力的な立地や、定期的な室内リフォームで付加価値を維持することで、家賃相場の極端な下落を抑制できます。
④金利変動リスク
ローン返済期間中に市場金利が上昇し、毎月の返済額が増加するリスクです。
対策概要: 金利上昇に備えて、固定金利型を選ぶことが重要です。また、変動金利型を選ぶ場合は、金利上昇に備えた十分なバッファ(余裕資金)を持つことが賢明です。毎月の返済額に占める返済比率を低く抑える資金計画も重要です。
⑤老朽化・修繕リスク
建物の老朽化に伴う大規模修繕や設備交換で、想定外の費用が発生するリスクです。
対策概要: 長期修繕計画を事前に確認し、修繕積立金が適切に積み立てられている物件を選ぶこと、また自身で修繕積立金を別途確保する資金計画が欠かせません。
⑥災害リスク
地震、火災、水害などにより建物が損壊し、賃貸不能になるリスクです。
対策概要: ハザードマップで浸水や土砂災害の危険性を確認し、適切な火災保険や地震保険に加入することで、損害をカバーできます。
⑦資産価値下落リスク
不動産投資の出口となる売却時に、物件の資産価値が購入時を下回り、売却損が発生するリスクです。
対策概要: 将来性のある立地を選定し、適切な管理と修繕を行うことで、物件の資産価値を可能な限り維持する出口戦略が重要です。
⑧サブリース契約リスク
サブリース会社による家賃保証額の減額や、契約解除による空室リスクの顕在化など、サブリース契約特有のリスクです。
対策概要: 契約内容を深く理解し、家賃保証の更新条件や解約条件を厳しくチェックすること、保証率に依存しすぎない資金計画が必要です。
⑨管理会社・入居者トラブルリスク
管理会社の管理体制の不備や、入居者間の騒音・ゴミ出しなどのトラブル対応で精神的負担が増加するリスクです。
対策概要: 評判が良く、迅速かつ誠実な対応が期待できる管理会社を厳選し、特に夜間や緊急時の対応体制を確認することが重要です。管理委託契約の内容を詳細に確認することも欠かせません。
3.ワンルームマンション経営ならではのリスクと対策
ワンルームマンション経営は、初期費用が比較的低く、手軽に始められる不動産投資としてサラリーマンに人気があります。
しかし、単身者需要に依存する特性ゆえの注意点や、出口戦略の難しさといった落とし穴も存在します。
このセクションでは、ワンルームならではのリスクとその対策を詳しく解説し、特に初期費用を抑えたいと考える読者の具体的な不安に対応します。
3-1.単身者需要に依存するリスクと安定化策
ワンルームマンションは、基本的に学生や社会人の単身者需要に依存しています。この市場は、景気や雇用状況、大学・企業の移転といった要因に左右されやすく、需要の変動が空室率に直結するリスクがあります。
単身者需要は、ファミリー向けと比較して入れ替わりが激しく、入居者が変わるたびに原状回復費用が発生し、実質利回りが低下する原因にもなります。
安定化策としては、単身者需要が安定している立地(大学や大規模オフィス街の最寄り駅など)を選ぶことが重要です。
また、内装をシンプルかつモダンに保ち、インターネット無料設備を導入するなど、入居者が「住み続けたい」と感じる付加価値を低コストで提供する管理戦略が有効です。
3-2.ファミリー向けとの違いと出口戦略
ワンルームマンションはファミリー向けと比較して、修繕が必要な専有面積が小さいため、修繕コストが低いというメリットがあります。しかし、売却時における出口戦略には注意点があります。
ワンルームは総額が低い分、リターンを求めて購入する投資家層が主要なターゲットとなるため、景気変動や金利変動の影響を受けやすく、流通価格が不安定になりがちです。
一方で、ファミリー向けは、実需層(自身で住む人)も購入候補となるため、資産価値が比較的安定しやすい傾向があります。
ワンルームの出口戦略としては、購入層のターゲットが明確であるため、売却のタイミングを市場の流動性が高い時期に合わせることが重要です。
3-3.サラリーマンが陥りやすい失敗パターン
サラリーマンの初心者オーナーがワンルーム経営で陥りやすい失敗パターンを具体的に知ることで、同様のリスクを回避できます。
失敗パターンの一つは、「節税目的で購入」することに注力しすぎたケースです。不動産投資の初年度は減価償却費などで赤字計上となり、給与所得との損益通算により節税効果を得られます。
しかし、この節税効果を過信し、利回りが低く、資産価値が低い物件を購入してしまうと、節税効果以上にキャッシュフローが悪化し、失敗につながります。
もう一つは、「家賃保証を過信」したケースです。サブリース契約は空室リスクを避けられますが、家賃保証額が減額されたり、サブリース会社が倒産したりするリスクを考慮しない資金計画は危険です。
安定収入を得るには、保証がない状態でも収支が成り立つ資金計画を立てる必要があります。
4.アパート・駐車場など他の土地活用とのリスク比較
不動産投資はマンション経営だけではありません。土地活用には、一棟アパート経営、駐車場経営、戸建賃貸など、多様な方法があり、それぞれ初期費用、安定収益、リスクの特性が異なります。
このセクションでは、他の土地活用と比較することで、マンション経営の特性を多角的に解説し、比較検討層のニーズに応えます。
4-1.マンション経営と一棟アパートのリスクの違い
マンション経営(区分所有)と一棟アパート経営のリスクは、資産分散と修繕費の点で大きく異なります。両者の違いを下記の表で比較します。
区分所有マンションは、初期費用を抑えられる一方で、1室空室になると安定収益が途絶えるリスクがあります。
これに対し、一棟アパートは初期費用が高いものの、複数の部屋で空室リスクを分散できるメリットがあります。
しかし、共用部分の修繕積立金がオーナー負担となるため、突発的な修繕費発生のリスクが高くなります。
4-2.駐車場・戸建賃貸との比較:リターンと安定性
駐車場経営や戸建賃貸も土地活用の一環ですが、初期費用、維持費、収益性といった観点で、マンション経営とは異なる特性を持ちます。
駐車場経営は、初期費用や維持費が最も低く、撤退も容易な土地活用方法です。しかし、安定収益は低い傾向にあり、利回りもマンション経営に劣ることが多いです。
戸建賃貸は、一度入居者が決まると長期入居になりやすく、安定収益が期待できます。しかし、流動性が低く、売却が難航する出口戦略上のリスクがあります。
また、修繕費用はオーナーが全額負担することになり、一回あたりの負担が大きいというリスクもあります。
マンション経営は、初期費用とリターンのバランスが取れており、管理会社に管理を任せることで、安定収益を目指しやすい不動産投資と言えます。
4-3.自分の資金・土地条件に合う投資スタイルの選び方
自身に合った不動産投資スタイルを選ぶには、資金計画、立地、そして管理負担を総合的に判断することが必要です。
資金額: 初期費用を極力抑えたい場合は、ワンルームマンション(区分所有)が適しています。多額の自己資金を用意でき、リスク許容度が高い場合は、一棟アパートや商業ビルへの不動産投資を検討できます。
立地: 既に土地を所有している場合は、その立地に合わせた土地活用(駐車場、戸建賃貸など)を検討します。安定収入を最優先する場合は、単身者需要の高い都心駅近のワンルームが最適です。
管理負担: 管理に時間を割きたくないサラリーマンには、管理会社への委託が容易な区分所有マンションが最も適しています。一棟アパートは、管理する範囲が広がり、負担が増します。
これらの条件に基づき、自身のリスク許容度とライフスタイルに合った投資スタイルを選ぶことで、安定収益への道筋を明確にできます。
5.実際の失敗事例から学ぶ「やってはいけない」投資判断
マンション経営の失敗は、リスクの存在そのものではなく、そのリスクを軽視したり、誤った投資判断を下したりすることによって引き起こされます。
実際の失敗例から学ぶことで、「怖い」と感じていたリスクの実態を理解し、納得のいく資金計画を立てるための教訓を得られます。
このセクションでは、オーナーが失敗しやすい4つのパターンを構造化して解説します。
5-1.利回りだけで物件を選んでしまったケース
物件の利回りは、不動産投資の魅力を示す指標として非常に重要ですが、それだけで投資判断を下すのは危険です。
原因: 利回りが高い物件に飛びついた結果、立地が極端に悪く、単身者需要が低いエリアの物件を購入してしまいました。
結果: 高い利回りを謳っていたものの、実際には慢性的な空室が続き、家賃収入が途絶えたことで、ローンの返済が厳しくなりキャッシュフローが悪化しました。
対策: 利回りの数字だけでなく、空室率、修繕履歴、周辺の家賃相場、将来的な人口動向など、安定収入を得るための実質的なリスク要因を多角的に分析することが重要です。
5-2.サブリース契約に過度に依存したケース
サブリース契約は空室リスクを避けられる管理方法ですが、その管理システムに過度に依存した結果、失敗につながるケースがあります。
原因: サブリース会社が提供する家賃保証を「安定収入が保証された安全な投資」と過信し、資金計画から空室と家賃下落リスクを除外してしまいました。
結果: サブリース会社から家賃保証の減額を通知され、資金計画が破綻しました。また、契約解除の条件が厳しく、物件を売却したくても身動きが取れなくなる事態に陥りました。
対策: サブリース契約の保証率や更新条件は、オーナーにとって不利な条項が含まれていないか、事前に弁護士や専門家に相談して確認することが必要です。また、保証がない状態でも安定収益が得られる資金計画を立て、保証額に依存しない出口戦略を確保することが重要です。
5-3.修繕費・税金を軽視してキャッシュフロー悪化したケース
不動産投資の資金計画において、ランニングコストとなる修繕費や税金を軽視すると、手元に残る収益であるキャッシュフローが急激に悪化するリスクがあります。
原因: 毎月の修繕積立金が適切に積み立てられていない物件を購入した結果、築年数の経過に伴う大規模修繕で、数十万円単位の一時金を要求されました。
また、固定資産税や都市計画税といった税金を過小評価していました。
結果: 想定外の修繕費の支払いにより、キャッシュフローが大幅に悪化し、手持ちの貯蓄を取り崩す事態に陥りました。
対策: 物件購入前に、管理組合の修繕計画と修繕積立金の積立状況を詳細に確認することが必須です。
また、不動産投資で発生する税金の種類と額を事前に正確に試算した資金計画を立てることが、安定収益を維持する上で欠かせません。
5-4.出口戦略を考えずに売却難航したケース
マンション経営は、物件の売却(出口戦略)によってリターンを確定させる側面もあります。出口戦略を考えずに物件を購入すると、売却時に大きな失敗につながります。
原因: 「安定収入を得ること」だけに着目し、将来的な資産価値の下落や売却難易度を考慮せずに物件を購入しました。
結果: 売却しようとした際に、立地が既に賃貸需要を失っており、買い手が見つからず、売却価格を大幅に下げざるを得ませんでした。最終的に、購入価格を下回る金額で売却し、リターンがマイナスになりました。
対策: 物件購入時から、「何年後に、いくらで売却したいか」という明確な出口戦略を設定することが重要です。
そのためには、立地の将来性や、売却ターゲットとなる層のニーズを予測し、資産価値が維持されやすい物件を選ぶことが求められます。
6.リスクを抑えたマンション経営を成功させるチェックリスト
マンション経営を成功させるには、リスクを事前に特定し、適切な対策を講じるためのチェックリストが必要です。
このセクションでは、初心者が失敗を防ぎ、安定収入を目指すためのHow-toを具体的に解説します。
このチェックリストを活用し、安心して投資判断を下せる自信を身につけてください。
6-1.物件・立地選びのチェックポイント
マンション経営の成否は、物件と立地で80%決まると言われます。安定収入を確保するために、下記のチェックリストを活用してください。
立地: 最寄り駅から徒歩10分以内か。単身者需要が高い立地か。
築年数: 新築か中古か。中古の場合は築20年以内を目安にする。
管理状態: 共用部分(エントランス、廊下)の清掃が行き届いているか。
修繕計画: 長期修繕計画が具体的に策定されているか。
修繕積立金: 現在の積立額が適切か、滞納している所有者がいないか。
家賃相場: 周辺の家賃相場と比較して適正な賃料設定が可能か。
ハザードマップ: 水害・土砂災害などの災害リスクが低いエリアか。
6-2.資金計画・ローン審査前に決めておくこと
金利変動や修繕費といったリスクに備えるには、ローン審査を受ける前に、徹底した資金計画を立てておくことが不可欠です。
金利上昇シミュレーション: 現在金利が1%上昇した場合、毎月の返済額がいくらになるかを確認します。これにより、金利変動リスクに対するリスク許容度を把握できます。
返済比率の設定: 家賃収入に占めるローン返済額の割合(返済比率)を、50%以下に抑えることを目指します。これにより、空室や家賃下落リスクが発生しても、キャッシュフローが急激にマイナスになることを防げます。
キャッシュフローシミュレーション: 空室率を10%と仮定し、修繕費として年間10万円を計上するなど、悲観的なシナリオでキャッシュフローを試算します。これにより、最悪の事態でも資金がショートしない資金計画を立てられます。
6-3.管理会社・パートナー選びのチェック項目
マンション経営は管理会社とのパートナーシップが鍵となります。信頼できる管理会社を選ぶことで、家賃滞納や入居者トラブルといった管理上のリスクを大幅に軽減できます。
信頼性: 不動産投資に関する実績が豊富か、評判はどうか。
管理体制: 空室時の入居者募集力、家賃滞納時の督促体制が確立されているか。
レスポンス速度: 問い合わせやトラブル発生時の対応が迅速か。
業務範囲: 家賃集金、修繕手配、入居者対応、空室時の募集など、どこまで委託できるか。
手数料: 管理委託手数料が家賃の5%程度であるか。
6-4.自分のリスク許容度と投資目的の棚卸し
不動産投資は長期的な事業であり、途中で不安になって撤退するリスクを避けるためにも、自身のリスク許容度を把握することが重要です。
| チェック項目 | YES | NO |
|---|---|---|
| 金利が1%上昇しても生活資金に影響はないか | ||
| 3ヶ月空室が続いてもキャッシュフローは耐えられるか | ||
| 修繕積立金が不足した場合、50万円の一時金を支払えるか | ||
| 出口戦略として20年後の売却で損益ゼロでも許容できるか | ||
| 毎月の管理状況報告を欠かさずチェックできるか |
これらの自己診断の結果、YESが4個未満の場合は、リスク許容度が低いと判断し、より安全投資を重視した物件選びや資金計画の見直しが必要です。
7.FAQ(よくある質問)
Q1. マンション経営は本当に儲かりますか?
A.家賃収入から経費とローン返済を引いたキャッシュフローがプラスになれば、安定収入としてリターンを得られます。
しかし、空室や修繕費といったリスクを理解し、適切な管理と資金計画を行うことが前提です。
Q2. 初心者でも始められますか?
A.初心者でも、立地選定の基準、資金計画の基本、そして信頼できる管理会社の選び方を学べば、失敗リスクを抑えて始められます。
まず公式サイトで無料シミュレーションを活用し、リスク許容度と収益性を確認することをおすすめします。
Q3. リスクを抑える一番の方法は?
A.リスクを抑える一番の成功法は、立地の選定と修繕計画の事前設計です。単身者需要が安定している立地を選び、修繕積立金が適切に確保されている物件を選ぶことで、空室と修繕費という2大リスクを大きく軽減できます。
Q4. 相談や診断は無料ですか?
A.はい、当社の専門家相談サービスでは、あなたの資金計画やリスク許容度に基づいたリスク診断を無料で実施しております。安全投資に向けた具体的な一歩として、お気軽にご活用ください。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- マンションを建てるための基礎知識
マンションを建てるための基礎知識の関連記事

- マンション経営のリスク9選と対策完全ガイド|初心者でも失敗を防ぐチェックリスト付き 公開

- マンション経営初心者必見|建築メリット・費用相場・満室にする3つの戦略 公開

- 儲かるマンションを建てるための10ヶ条|建築の流れや費用についても解説 公開