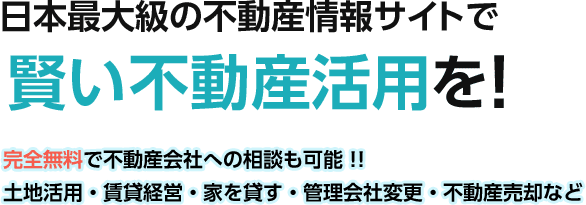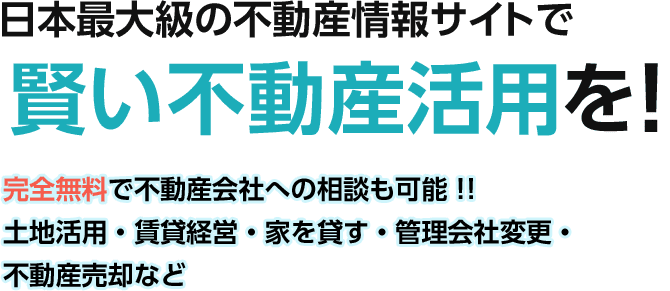「イエカレ」とは
イエカレ(Ie College/イエ・カレッジ)とは、日本最大級の不動産の総合比較サイトです。
2008年に土地活用の相談に特化した『賃貸経営ナビゲーション』を開設し、サービス開始以降、不動産売却や賃貸管理の専門サイトを追加した上でサービスの拡充を行って参りました。2015年にそれらのサイト統合を行い『イエカレ』へ名称を変更し現在に至っています。イエカレでは、皆さまの不動産に関する不安やお悩みを解決できるように、不動産コラムを通じて、日々最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供などに取り組んでいます。
「不動産コラム」の掲載
皆さまが「不動産会社」に対して抱いている印象とはどのようなものでしょうか?
不動産に関する取引は、皆さまの人生において、そうそう何度もあることではないかもしれません。人生の中で、ご自身の大切な不動産資産を使い、大きな取引を行う場合、大抵の方々は大きな不安を持つと思います。でも、なぜ不安になるのでしょうか?その大きな理由の一つは、不動産に対する知識が乏しいと、騙されてしまうのではないか?という思いに駆られるからではないでしょうか。
不動産取引では誰しもが「失敗したくない」と考えます。そのために必要な情報を収集し、専門知識を得ようとすることは自然の成り行きです。イエカレでは、そのような状況をお持ちの方々へ少しでも寄り添えるようなテーマや問題を取り上げて情報を発信しています。是非、イエカレの不動産コラムのなかから、皆さまにとって役立つ不動産情報や知識の習得にお役立て頂けたら幸いです。
「一括無料査定サービス」の提供とそのメニュー
現在、イエカレでは、以下4つ一括査定サービスの提供を行っています。ご利用は完全無料です。イエカレは全国約400社超の優良不動産企業と提携を行っており、これまで約40万人の方々に一括無料査定サービスをご利用頂いています。
https://plus-search.com/order/
●土地活用(イエカレ賃貸経営)
アパート経営、マンション経営など、有効な土地活用をお考えの方へ向けたサービスです。大手一流企業を含めた設計建築会社やハウスメーカーから、個別の土地活用プランを一括でお取り寄せ頂き、比較検討をして頂く事が可能です。
https://plus-search.com/chintai/
●家を貸す(イエカレリロケーション)
転勤・住み替えや相続などで空いたご自宅(一戸建て、分譲マンション)を貸し出して、家賃収入を得たい方へ向けたサービスです。家賃査定見積り、賃貸管理サービスの提供とお客様探しの仲介を一気通貫で行う優良賃貸管理会社から個別管理プランを一括でお取り寄せ頂き、比較検討をして頂く事が可能です。
https://plus-search.com/relocation/
●アパート・マンションの管理会社を探す(イエカレ不動産管理会社)
既にアパートやマンションを経営されている方や、これから行う方で、管理会社の選定や変更をお考えの方へ向けたサービスです。信頼できる管理会社、担当者をパートナーにすることが賃貸経営を安定させる上では重要です。そうした賃貸管理サービスの提供を行っている優良賃貸管理会社から個別管理プランを一括でお取り寄せお取り寄せ頂き、比較検討をして頂く事が可能です。
https://plus-search.com/property_management/
●不動産売却(イエカレ不動産売却)
ご所有の不動産を売却されたい方へ向けたサービスです。不動産売却に関して一から親切かつ丁寧に行う優良企業へ一括で不動産査定を依頼することができ、比較検討することができるサービスです。
https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/
イエカレの一括無料査定サービスを利用するメリットとは?
例えば、ご実家などの不動産を相続した場合、ご自身が住まない場合、売却を検討する方が多いかもしれません。様々なご事情のなかで、売却をすることで問題解決が図れるなら、もちろんそれは問題ありません。しかし、一方で「その他の有効活用方法はないものか?」と考える方がいることも事実です。そのご実家を「賃貸に出して家賃収入を得ることが可能か?」または「アパートやマンションへ建て替えてその経営をすることができないか?」など。後悔をしないように、あらゆるケースを想定しながら相談内容をご選択頂き、個別プランをお取り寄せ頂いた上で、それぞれのケースに応じた比較検討ができる。それがイエカレの一括無料査定サービスをご利用頂く最大のメリットです。
不動産の相談相手として思い浮かぶのは、知人からの紹介やご自宅の近くにある知り合いの不動産会社、または、過去にお付き合いをしたことのある不動産会社かもしれません。既に知っている不動産会社で信頼ができる担当者であれば、依頼するのは気心が知れていて楽かもしれませんが1社だけで決めてしまうと「その情報や査定内容などが本当に適切なものだったか?」が、実は良く分からなかったという場合があるものです。そのため一括査定によって複数社のプランや査定額を比較することでご自身の希望に沿った適正プランや価格を冷静な目で掴むことが出来るのです。不動産の取引は、大きな金額が動くものです。後悔をしないように情報を集めてプランや査定額などの内容を比較検討することが重要になるのです。
最後に。「比べて賢く選ぶ!」
プランや査定額などを比較検討するのは、たしかに労力が掛かって面倒なことかもしれませんが、かといってご自身で優良な不動産会社や担当者を見つけるのも大変な作業です。イエカレは、複数の優良企業と提携をしているため、ご自宅のパソコンやお手持ちのスマートフォンなどを使って、自宅や外出先から、場所を選ばずに複数の優良企業へ個別プランや査定などを依頼することが可能です。複数の優良不動産会社から連絡がもらえた上で、プランや査定額を比較検討でき、また、そうした企業から多くの不動産情報を入手することができる上、更にその情報の比較もできることから、多くの方からご満足を頂いて来ました。
ご利用者の方からは
●土地活用をどうするか?で悩んでいたが、複数社のプランを比較検討する中で信頼できる企業を見つけることができた。
●急いで自宅の賃貸管理を頼みたい状況になってしまい藁をも掴む思いでおもい切って利用してみた。すぐに賃貸管理を受けてもらえる管理会社が見つかった。
●当たり前の仕事を当たり前にやってもらえる管理会社が見つかった。
●複数の会社から査定額を出してもらい比べたことで、相場よりも2割~3割近く高値で自宅を売る事ができた。
などのお声を頂いています。
イエカレの査定サービスを賢く利用して、是非、ご自身の夢や要望を実現してくれる不動産会社を選択してください。
※イエカレではフリーコールやメールによるご利用者様のサポート窓口設けて、ご安心してご利用いただけるよう努めております。
(フリーコール:0120-900-536/土日祝日を除く、平日10:00~18:00)
※イエカレを運営するイクス株式会社は「プライバシーマーク」使用許諾事業者として認定されています。個人情報保護方針