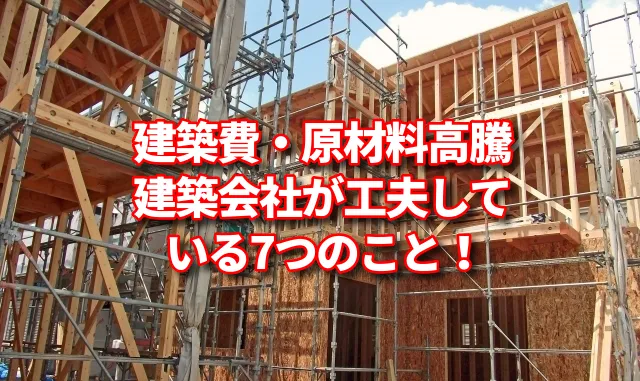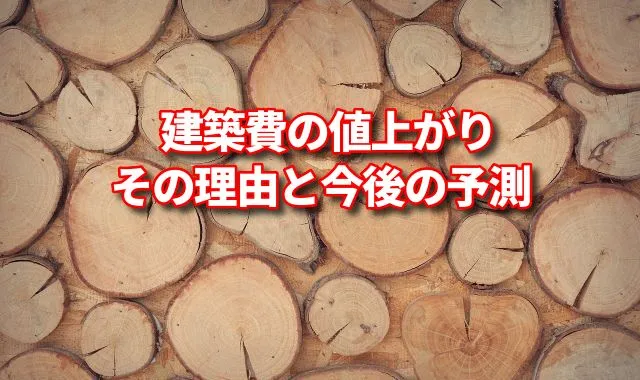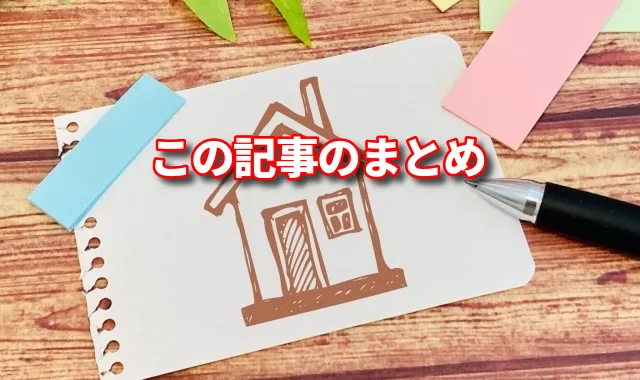- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- 賃貸経営の基礎知識
- アパート建築費はどうすれば安くなる?建築会社が実践する7つのコスト削減策
アパート建築費はどうすれば安くなる?建築会社が実践する7つのコスト削減策
この記事を読むのにかかる時間:5分
建築費値上がりの理由と今後の予測
まず初めに「現在、日本において建築費高騰がなぜ続いてしまっているのか?」
その原因から話を始めます。
それらの主な原因は、
- ウッドショック
- 給湯器等の住宅設備の不足
- ロシアによるウクライナ侵攻
- 円安
以上4つです。以下で、時系列で説明します。
この10年近く続く建築費高騰は、様々な理由が複層的に重なりあって生じているといえます。ですから、1つの問題が解決されたからといって簡単に建築費高騰が治まることにはならない状況に陥っています。
当初、東北を襲った東日本大震災後、建築費の高騰は「人手不足」が主な原因とされていました。
そして、政府・日銀の低金利政策によるインフレが進むなか、新型コロナウイルスの世界的なパンデミックの発生も起きたことでダブルパンチとなり、その後「ウッドショック」や「給湯器等の住宅設備の不足」が問題化していきました。
ウッドショックとはご存知のない方のために補足しますと、輸入木材の価格高騰を言います。2021年3月頃から顕著に見られ始めたもので、主にはアメリカと中国で住宅の建築需要が増加したことで端を発した輸入木材の建築資材不足のことを言います。また、給湯器等の設備不足は、2021年秋頃に新型コロナウイルスによってベトナムや東南アジアがロックダウンを余儀なくされ工場が閉鎖されたために起きた問題でした。いずれも殆どの建築資材を輸入品に頼ってきた日本にとっては打撃となるものでした。
そして「ロシアによるウクライナ侵攻」は、世界的なインフレも引き起こしました。主に西側先進国が中心となりロシアへ政治的経済的圧力を加える意味で今も経済制裁を続けています。状況としては、日本を含む多くの国は、エネルギー資源などを武器にしてきたロシアからの建築資材を含む多くのものを輸入停止している状態です。ガソリン代や天然ガス不足によって電気代等が高騰しているのもロシアによるウクライナ侵攻が原因ですし、建築費高騰の理由の一つにもなっています。
さらには、2022年に入って以降は「円安」が加速し、輸入資材の価格がさらに高騰していきました。上述した通り、日本は建築資材の多くを輸入に頼ってきたため、円安が起きると輸入価格の上昇を招くため建築費高騰に大きな影響を及ぼしています。
このように、この約10年間においては、このように建築費を上げる要因がいくつも発生してしまっていることから、これも上述した通り、何か1つの問題が解決できたからと言って建築費が容易に下がるとは考えられない状況になっています。その証拠に、例えば、ウッドショックは既に沈静化されたと言われていますが、建築費は一向に下がる気配はありません。
現在の建築費の高騰は、複層的に原因が絡み合っているため、今後も続いてしまう見込みが高く、長期化していくものと予想されます。
「建築費が高すぎて、アパート建築に踏み切れない…」そんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実際、建築費高騰が長期化する中でも、多くの建築会社が“価格と品質のバランス”に工夫を凝らし、柔軟な提案で施主の希望に応えています。
まずは、複数社の提案を比較することが、無理のない建築計画の第一歩です。
まずは無料で資料請求!
【無料】建築費用や提案力で比較できる →《一括資料請求はこちら》
どんな提案が受けられるかを知ることで、自分に合った経営のイメージがぐっと具体的になります。
建築会社が工夫している7つのこと
こうした心配な状況が続いている日本の建築業界ではありますが、この章では、建築会社各社が、建築費や原材料の高騰に対して「どのような対策や工夫をしているか?」7つご紹介したいと思います。
1.補助金提案
1つ目は「補助金提案」です。
近年は「省エネ住宅」や「耐久性に優れた住宅」を中心に「建築費の補助金制度」が増えています。省エネ住宅とは、消費するエネルギーを押さえた環境に優しい住宅のことです。長期的なランニングコストを考慮するなら検討するのも良いシステムでしょう。
建築費の補助金は、建築会社が登録企業となって申請を行い、補助金は建築会社に振り込まれて「発注者に還元される形式」のものが多いです。そのため、発注者は補助金申請に掛かる手間はほとんどなく、還元という形で補助金の恩恵を受けることができるため、昨今の建築費高騰の中では発注者にとってもありがたい制度となっています。
発注者がその恩恵を受けるためには、建築発注をする建築会社が補助金制度の登録企業となっている必要があり、手続等の内容をしっかり理解していることが必要です。提案に熱心な建築会社は補助金制度に熟知した上で、発注者への提案内容にしっかりと取り入れて、補助金提案ができる設備等の情報提供をしています。最終的な決定を下すのはもちろん発注者ですが、建築会社から補助金制度が使える設備提案などを受けたら、受け流さずに検討だけでもしてみてはいかがでしょうか?
2つ目は「設計変更提案」です。
設計変更の提案は、建築費高騰に対して従来から行われている建築会社の工夫です。今はさらにそこを加速させて、VE(バリュー・エンジニアリング)またはCD(コスト・ダウン)と呼ばれる設計変更の提案を行い、建築費を発注者の予算に近付けていく手法に重点を置いています。
VE(バリュー・エンジニアリング)とは「機能を落とさずに価格を下げること」です。「これは本当に必要な機能なのか?」と取捨選択を考えたり、「他の代替技術を使ってもっとコストを抑えよう」など、品質や機能を維持・向上しながらコストを削減することを発注者へ提案する手法です。
また、CD(コスト・ダウン)とは、これも「機能を落とすことで価格を下げること」ですが時には「コストを下げるには、高い材料を使うよりも若干品質や機能が低下しても仕方がない」という考えで発注者へ提案する手法なのでVEとは区別されます。
こうしたVEやCDは、どちらも建築会社の設計・建築技術のノウハウの見せ所ともいえるでしょう。
3つ目は「竣工後の売却提案」です。
近年は、建築費が高騰している分「竣工後にその新築物件を売る」と売却価格も高くできるメリットがあります。そこで建築会社各社では、売却価格が高くなるというメリットを生かして、竣工後に新築物件を売却して「発注者(地主や土地オーナー)に売却益を得てもらう」という提案も増えてきました。<
皆さまのなかに「ランドセット」という言葉を聞いたことはないでしょうか?
日本は現在、人口減少が進んでいますが、実はアパートやマンションの建設は増えています。その要因のひとつに「ランドセット」と呼ばれる土地(ランド)と新築された建物が一緒に売り出される手法があり、最近、新築の収益物件として流行りになっています。
ランドセットでどういう人たちがそうした収益物件を購入しているか?と言えば、元々土地は持っていないがアパート経営には興味があった人たちです。そうした人たちは中古の投資物件を探している人たちも多いのですが新築は中古の投資物件よりも賃貸経営が始めやすいメリットがあります。地主は土地そのものを売ろうとするのではなく、新築アパートなどの収益物件を作った上で付加価値を付けて、そうした人たちに高値で買い取ってもらうわけです。
以上のことから、建築費が高くても、土地と収益物件をセットにして付加価値を付けて売却すれば、資産価値が高い場所に土地を持っている地主だった場合は、大きな売却益を得ることができますので比較的受け入れやすい提案となっています。
本記事では、建築会社側の「努力」に焦点をあてて紹介しています。
高騰する資材価格の中でも、提案の工夫や見積の透明性、仕様調整のノウハウなどを駆使し、オーナーの希望に応えている企業は数多くあります。
ただし、それらは“建築会社によって差が大きい”のも事実です。
後悔しないためにも、複数の建築会社の資料を一括で取り寄せて、提案内容やコスト感を比較してみるのがおすすめです。
まずは無料で資料請求!
これから本格的にアパート経営を考えるなら、まず複数の建築会社に相談してみるのも一つの手です。
複数社の施工プラン資料を無料で請求できる“イエカレの一括資料請求サービス”で、あなた専用の仕様比較が可能です。
4つ目は「ファミリータイプの提案」です。
アパート経営等で「ファミリータイプを提案する」というのも建築費高騰に対処する建築会社各社の工夫の一つになっています。これだけでは分かりにくいので理由を説明しましょう。
まず、同じアパートを建築すると言っても、基本的に建築費はワンルームよりもファミリータイプのアパートを作る方が安くなることをご存知でしょうか?理由としては、同じ面積に対してファミリータイプの方が部屋を広くしなければならないため戸数は減り、それに伴いバスやトイレ、キッチン等の住宅設備の数が減るからです。
これまで土地活用の世界では「アパート・マンション経営では、ファミリータイプはワンルームと比べると賃貸需要が少なく賃貸経営上のメリットが少ない」と考えられ「多少建築費は上がったとしてもワンルームタイプを作って賃貸経営をした方が収益を生み出せる」という定説がありました。理由としては、家族で住む場合は持ち家を購入する場合が多く、さらに単身世帯が増加傾向にあったからです。そのため、ファミリータイプの土地活用の提案は、従来であればネガティブな部類の提案でした。
「もし結婚をしたらパートナーや子供と住むための家を購入したい!」と思う方は多いといえますが、昨今では一軒家や分譲マンション等の価格も高騰しているため、住宅を購入したくてもそれができない「共働き世帯」や「子育て世帯」が賃貸物件に住むことを選択せざるを得ないケースが増えています。そうした背景もありファミリータイプの賃貸需要は以前よりも強まってきた状況です。事実、メゾネットタイプの賃貸住宅は人気がありますし、そうした「共働き世帯」や「子育て世帯」で勤めがしっかりとした人達に気に入ってもらえれば定住率も高くなることも考えられるので地主にとっても経営上のメリットが出てきます。
不動産を取得すると「不動産取得税」がかかりますが、アパート等の戸建て以外の貸家であれば1戸あたり40平米以上になると不動産取得税も安くなります。こうしたこともあり、ファミリータイプの賃貸物件は初期費用を抑えられることにも繋がるため、最近ではかなりポジティブな提案になっています。
5つ目は「資材調達の前倒し」です。
建築会社の内部的な工夫のなかに「資材調達の前倒し」があります。
まさに企業努力だと言える部分になりますが、現在のようなインフレ状態にあるときは、先に資材を調達して買うほど価格を安く抑えることができます。
例えば、取引先に1~2カ月先の必要量を示して、先行して資材を確保するようにします。また、取引先から届いた見積書の品目や数量をチェックした後に発注していたのを、取引先に見積もりを依頼した時点で発注する会社もあります。資金力のある建築会社は、まだ発注のない段階でも資材を購入しており、こうした建築費を抑える企業努力を行っています。
6つ目は「受注内定から契約までの短縮化」が挙げられます。
「受注内定から契約までの短縮化」することも、建築会社が収益を悪化させないための企業努力の工夫の一つとなっています。
現在の様なインフレの時期は、時間が経てば経つほど建築費が上がってしまう危険性があるため、見積もり段階から契約までの期間が空いてしまうと工事費に大きな狂いが生じてしまうことにもなりやすくなっています。要するに発注者から受注内定をもらえても「見積書より大幅に値上がりしてしまう可能性がある」ということです。
発注者もなるべく費用を抑えて欲しいと思う方が多いわけですから、受注内定から契約までの短縮化を図るのは発注者と建築会社双方にとっても理がかなった良い方法と言えます。
そして最後、7つ目は「生産性改善」です。
建築費高騰は10年近く続いていることから「生産性改善」を行っている建築会社は多いです。建築会社は人材不足や長時間労働で生産性が低いと言われていましたが、改善させるために様々な取り組みを行っています。
例えば、外国人労働者を受け入れて低コスト化を実現している会社や、ITテクノロジーを取り入れて、これまで以上の工程管理を効率化している会社もあります。昨今、DX(デジタルトランスフォーメーション)を耳にしたことがある方が多いのではないでしょうか?DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を用いることで、ビジネスや人々の生活をより良い状態へ変革することを意味します。
建築業界でも、生産性改善のためDX導入の必要性が叫ばれるようになりました。
生産性改善を行っていない建築会社は「建築費高騰に対応した提案をして欲しい」といった発注者の要望に応えることはできません。多くの建築会社ではそれが徐々に進んでおり、改善方向にあるといえます。
この記事のまとめ
以上、今回は、建築費高騰・原材料高騰の背景と、それに対する「建築会社の工夫」7つについて解説してきました。
昨今の建築費の高騰は、ここ直近10年近くに及ぶ出口の見えない問題となっており、ウッドショックといった問題だけではなく、円安やインフレといった複層的な原因が絡み合っ
た結果起きているため、今後も長期化する見込みが強いと言えます。
再度まとめてみます。建築費や原材料の高騰に対して、建築会社は下記のような工夫を行っています。
・補助金提案
・設計変更提案
・竣工後の売却提案
・ファミリータイプの提案
・資材調達の前倒し
・受注内定から契約までの短縮化
・生産性改善
今後、土地活用でアパート・マンション経営をご検討されている方々が建築費を抑えるにあたり、この記事を参考にして頂き、建築会社を選択頂く際の判断材料の一つにして頂ければ幸いです。
▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php
賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php
家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php
不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php
記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。
ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。
アパート建築は一度きりの大きな投資。不安を減らすためには、「どこに頼むか」だけでなく「どういう提案をしてくれるか」が非常に重要です。
今回のような各社の企業努力を知ると、単純な価格だけで判断するのではなく、総合的に比較したくなるはず。
資料請求は完全無料。まずは**“どんな建築会社があるのか”**を知ることから始めてみてください。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部 (記事監修)竹内 英二
(竹内 英二プロフィール)
不動産鑑定事務所及び宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。
大手ディベロッパーで不動産開発に長く従事してきたことから土地活用に関する知見が豊富。
保有資格は不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。大阪大学出身。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 賃貸経営の基礎知識
賃貸経営の基礎知識の関連記事
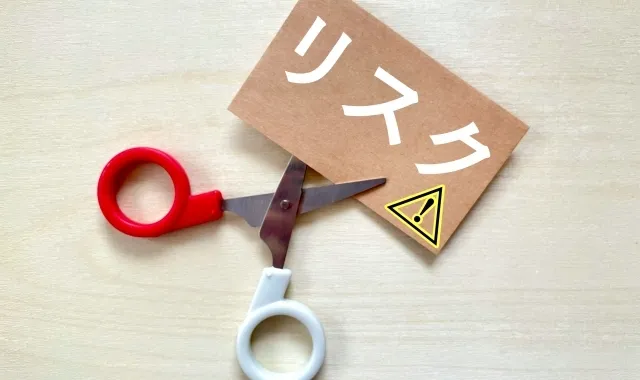
- 賃貸経営のリスクと対処法|初心者が失敗しないための完全ガイド 公開
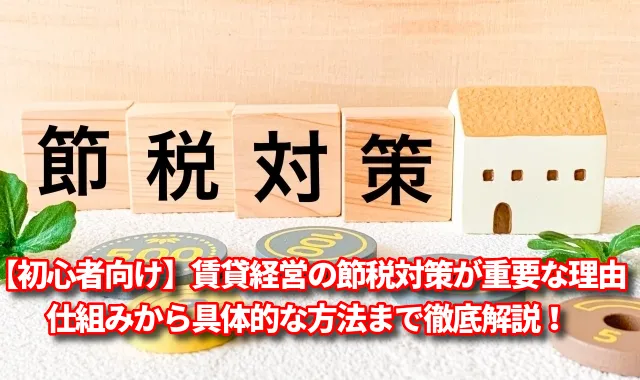
- 【初心者向け】賃貸経営の節税対策が重要な理由を徹底解説!仕組みから具体的な方法まで 公開
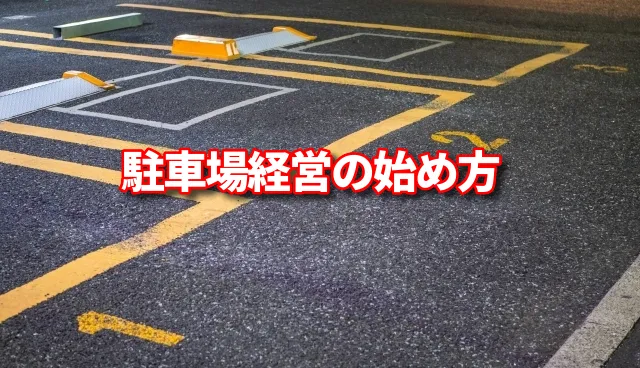
- 駐車場経営は儲かる?始め方とメリット・デメリット|土地活用で失敗しない注意点 公開
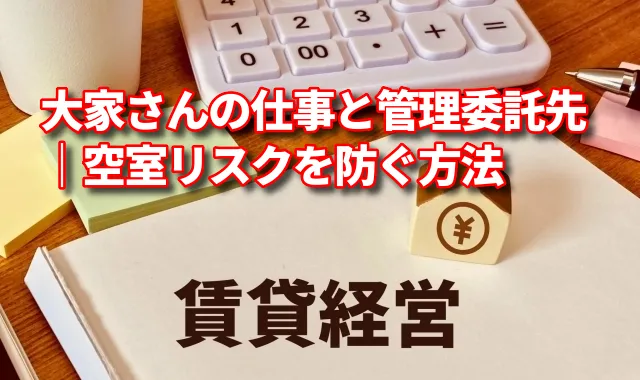
- 大家さん必見|賃貸経営の仕事内容と空室対策・優良管理会社の選び方 公開
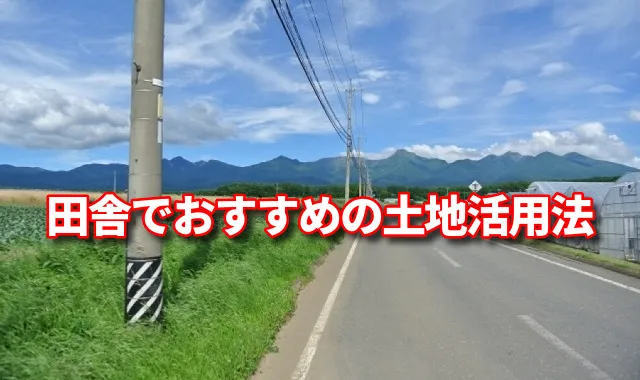
- 田舎の土地活用完全ガイド|空き地や遊休地で収益化するおすすめ方法と注意点 公開
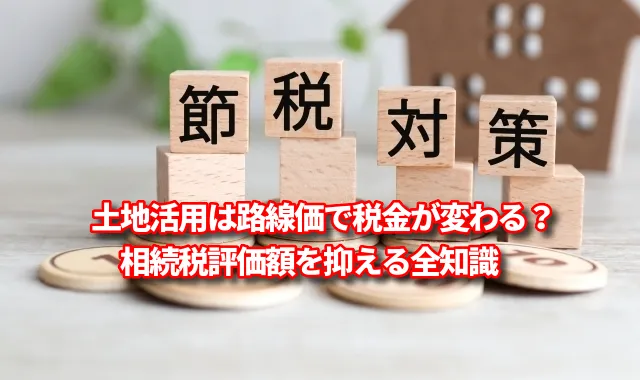
- 土地活用は路線価で税金が変わる?相続税評価額を抑える全知識 公開
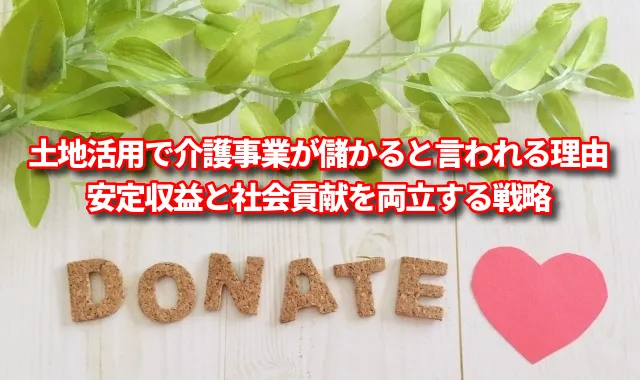
- 土地活用で介護事業が「儲かる」と言われる理由 安定収益と社会貢献を両立する戦略 公開

- 土地活用の最新動向と将来性|ランキングで分かる人気活用法と成功のポイント 公開

- 【地域活性化の起爆剤】土地活用と空き家リノベーションで未来を拓く 公開
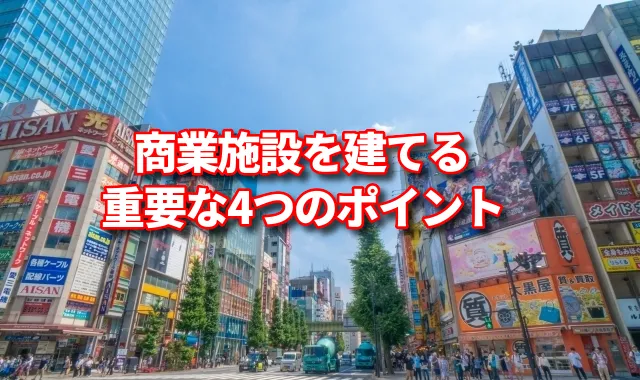
- 土地活用で高収益を狙うなら?商業施設活用の魅力とアパート経営との比較ポイント4選 公開

- 賃貸経営の利回り完全ガイド:計算から平均・シミュレーションまで徹底解説 公開
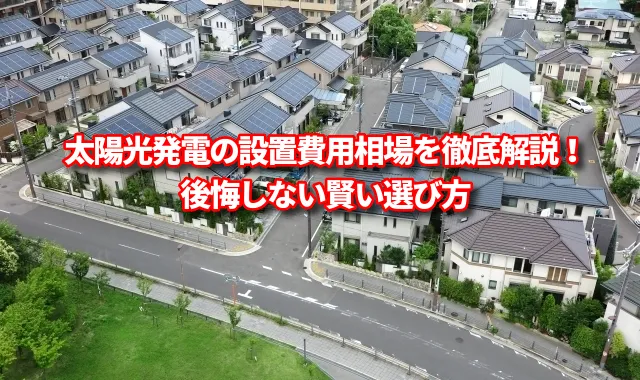
- 太陽光発電の設置費用相場を徹底解説!後悔しない賢い選び方 公開

- 【土地活用】借地権設定で安定収入!リスクを抑えて資産を最大化する方法を徹底解説 公開
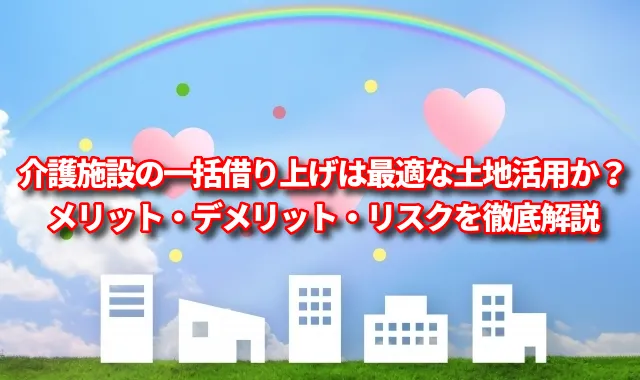
- 介護施設の一括借り上げは最適な土地活用か?メリット・デメリット・リスクを徹底解説 公開

- 太陽光発電の余剰電力売電ガイド:FIT後の最適な選択肢と賢い契約方法 公開

- 太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)とは?FITの仕組みから卒FIT後の賢い選択肢まで徹底解説 公開
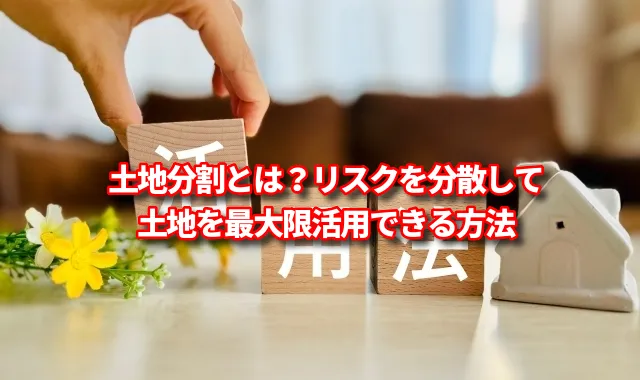
- 土地分割とは?リスクを分散して土地を最大限活用できる方法 公開
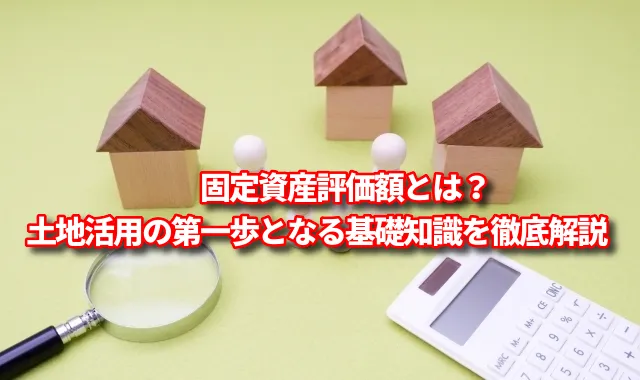
- 固定資産評価額とは?土地活用の第一歩となる基礎知識を徹底解説 公開
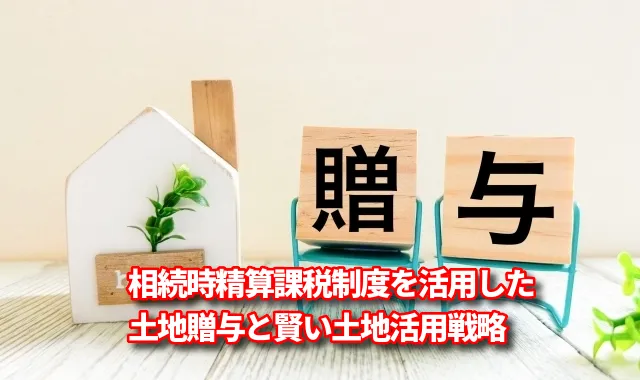
- 相続時精算課税制度を活用した土地贈与と賢い土地活用戦略 公開
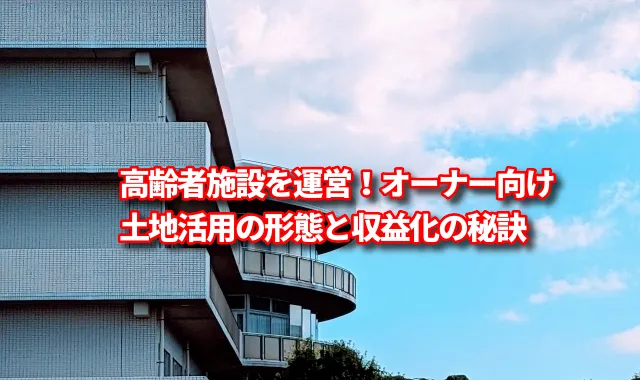
- 高齢者施設を運営!オーナー向け土地活用の形態と収益化の秘訣 公開