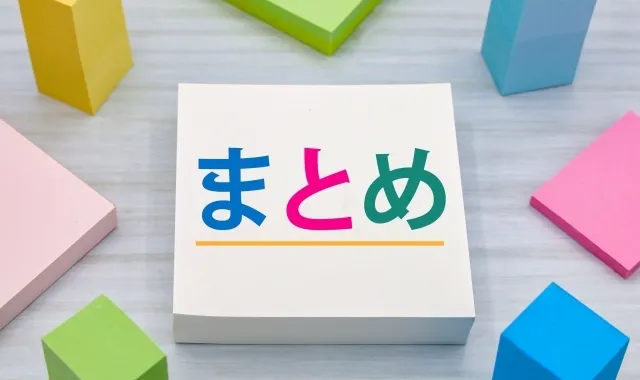- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- 賃貸経営の基礎知識
- 【イエカレ】太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)とは?FITの仕組みから卒FIT後の賢い選択肢まで徹底解説
【イエカレ】太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)とは?FITの仕組みから卒FIT後の賢い選択肢まで徹底解説
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
「土地活用って、そもそも自分にもできるの?」── そんな不安をお持ちの方へ、まずは全体像がわかる一括資料請求から始めませんか?
無料で資料をまとめて請求する1.太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)とは?
1-1.固定価格買取制度(FIT)の定義と目的
固定価格買取制度(FIT:Feed-in Tariff)は、再生可能エネルギーの普及を促進するため、政府が定めた価格で一定期間、電力会社が電気を買い取ることを義務付ける制度です。
これにより、一般家庭や事業者が太陽光発電などの設備を導入しやすくなり、初期投資の回収見通しが立てやすくなります。特に住宅用太陽光発電においては、10年間の固定価格での売電収入が見込めるため、資産形成の一環としても注目されています。
1-2.再生可能エネルギー普及促進の役割
この制度は2012年に本格導入されました。背景には、東日本大震災と福島第一原発事故を契機とした原発依存からの脱却と、再生可能エネルギーの早急な拡大がありました。
FIT制度は、太陽光発電の導入促進を強力に後押しし、結果として日本全国で数多くの住宅・施設に太陽光パネルが設置されるようになりました。
1-3.安定した売電収入の保証
FIT制度の大きな魅力は「価格が固定されること」にあります。通常、電力の市場価格は需給バランスによって変動しますが、FITでは10年(住宅用)から20年(非住宅用)の間、あらかじめ決まった価格で売電できるため、収支計画を立てやすいのが特徴です。
2.FIT制度の仕組み:認定から買取期間まで
2-1.認定手続きの概要
太陽光発電システムで固定価格買取制度を利用するには、再生可能エネルギー発電設備として国から「事業計画の認定」を受ける必要があります。この申請は、原則として設備の設置前に行い、設備の種類や出力規模、設置場所などを詳細に記載します。
申請先は経済産業省所管の「再生可能エネルギー電子申請システム」であり、施工業者が代行するケースが一般的です。認定を受けた後、初めて売電契約が可能となり、買取価格と期間が確定します。
2-2.買取期間と価格決定のプロセス
住宅用太陽光発電(10kW未満)の場合、買取期間は10年間と定められています。買取価格は年度ごとに見直されており、設備の認定を受けた年度の価格が、以降10年間にわたり適用されます。
例えば、2016年度に認定を受けた住宅用太陽光発電は、10年間にわたり国によって定められた当時の買取価格で売電することが保証されます。
価格は年々低下傾向にあり、制度導入当初は40円/kWh台だったのが、2024年度では16円/kWh程度にまで下がっています。
2-3.電力会社による買取義務
FIT制度のもとでは、電力会社(送配電事業者)は、認定された再エネ電力を必ず買い取る義務があります。これは「全量買取」または「余剰電力買取」として実施され、一般家庭では後者が適用されるのが一般的です。
この買取義務は、事業者の自由な契約によるものではなく、法律に基づく強制力を持つものです。したがって、発電量が天候に左右される太陽光でも、一定の収入を得られる仕組みとなっています。
3.太陽光発電導入を検討中の方へ:FIT制度のメリット・デメリット
これから太陽光発電システムの導入を検討している方にとって、FIT制度の活用は大きな判断材料となります。
ここでは、制度の具体的なメリットとデメリットを整理し、導入前に確認すべきポイントを解説します。
3-1.導入のメリット:売電収入と環境貢献
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売電収入による投資回収と経済的メリット |
FIT制度により、導入年度の固定価格で10年間売電が可能。 例:4kWの太陽光発電で年間約6〜8万円の売電収入が期待でき、初期投資の回収が見込める。 |
| 電気代削減効果 |
発電した電力を自家消費することで電気代が削減。 特に昼間の使用電力が多い家庭は「自家消費+売電」のダブルメリットがある。 |
| 環境負荷低減と企業のCSR(法人向け) |
太陽光発電はCO₂を排出しない再生可能エネルギー。 個人はエコ意識向上、企業はCSRやESG投資へのアピールにも活用可能。 |
| 災害時の非常用電源としての活用 |
停電時には非常用コンセントを通じて発電中の電力を使用可能。 冷蔵庫・照明・スマートフォン充電など最低限の生活インフラを維持できる。 |
導入のデメリットと注意点:維持コスト・将来性・リスク
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期投資費用と回収期間 |
住宅用(4〜5kW)太陽光発電システムの導入費用は約100〜150万円。 FIT制度による売電収入で回収可能だが、一般的に7〜10年かかる。短期回収は困難。 |
| 売電価格の下落傾向 |
FIT制度初期は40円/kWh以上だったが、現在は16〜17円/kWh程度に下落。 今後も価格下落が予想されるため、早期導入のメリットもある。 |
| メンテナンス費用と故障リスク |
パワーコンディショナーは10〜15年で交換が必要(費用:20万〜30万円)。 台風・積雪・落ち葉・鳥のふんなど自然による影響も考慮が必要。 |
| 将来的な制度変更のリスク |
FIT制度は法制度に基づいており、改正・条件変更のリスクがある。 導入時には最新の制度動向を確認することが重要。 |
3-2.卒FIT(FIT期間終了)後の太陽光発電:最適な選択肢と経済的影響
FIT制度によって約10年間の安定した売電収入を得ていた住宅用太陽光発電も、ゆくゆくは契約期間満了(卒FIT)を迎えます。卒FIT後には、これまでのような高額での売電はできず、新たな選択と対策が必要になります。
ここでは、卒FIT後に選べる具体的な選択肢と、それぞれのメリット・デメリット、経済的な影響を解説します。
3-3.選択肢1:電力会社との再契約(売電継続)
・各電力会社の買取プラン比較
多くの電力会社は卒FITユーザー向けに独自の買取プランを提供しています。価格は1kWhあたり7〜12円程度が主流で、プランによってはポイント還元や、電気料金とのセット割引がある場合もあります。
・売電価格と契約条件
売電価格は各社異なり、1年契約〜3年契約など条件もさまざまです。買取価格の更新タイミングや、解約・変更のルールも含めて確認が必要です。
・メリットとデメリット
メリット
- ・手続きが簡単で、今までと同様に売電が続けられます。
- ・設備や生活スタイルを変更する必要がありません。
デメリット
- ・売電価格が低く、電力の価値を十分に活かせません。
- ・長期的には「自家消費」に比べて経済効果が劣る可能性があります。
3-4.選択肢2:自家消費への切り替え(経済的メリットを最大化)
・自家消費の仕組みとメリット
自家消費とは、発電した電力を自宅で使い、電気代を節約する方法です。売電価格が10円前後でも、電気を買うコストが25〜30円/kWhであることを考えると、「使ったほうが得」という状況になります。
・蓄電池導入の検討
発電は昼間に集中する一方、電力の使用ピークは夕方〜夜間が多いため、蓄電池を導入することで電力を一時的にためて夜間に使用できます。これにより、さらに自家消費率を高めることができます。
・エコキュートやEVとの連携
太陽光発電の電力をエコキュート(深夜電力型電気給湯器)や電気自動車(EV)と組み合わせることで、電力の有効活用が可能になります。電気料金のピークシフト対策としても効果的です。
3-5.選択肢3:蓄電池導入による電力の最適化
・蓄電池の種類と選び方
蓄電池には「特定負荷型」「全負荷型」「ハイブリッド型」などがあり、それぞれに特徴があります。選ぶ際は、停電時の使用可能容量・充放電サイクル・設置スペースなども考慮する必要があります。
・導入費用と補助金
家庭用蓄電池の価格は70万円〜150万円程度です。自治体によっては、補助金制度を設けている場合もあり、数万円〜数十万円が支給されることがあります。
・停電時の活用方法
停電時には、冷蔵庫・照明・携帯の充電といった最低限のライフラインを維持できます。地域によっては台風・地震の備えとして需要が高まっており、防災資産としての価値も注目されています。
3-6.選択肢4:EV(電気自動車)を活用したV2Hシステム
・V2Hとは何か
V2Hとは、「Vehicle to Home」の略で、電気自動車(EV)に蓄えた電力を家庭で利用するシステムです。日中に太陽光発電で充電したEVから、夜間に家庭へ電力を供給することで、自家消費の効率を最大化できます。
また、EVは蓄電池としても機能するため、移動手段+電力インフラという二重の役割を果たす点が注目されています。
・EVへの充電・給電の仕組み
V2Hを活用するには、専用の充放電器(V2Hスタンド)を自宅に設置する必要があります。これにより、EVは太陽光発電から直接充電でき、必要に応じて家庭に電力を供給します。使用するEVはV2H対応車種である必要があり、国産車では日産リーフ、三菱アウトランダーPHEVなどが対応しています。
・導入メリットと課題
メリット
- ・昼間に発電した電力を効率よく活用できます。
- ・停電時の非常用電源としても利用できます(EVの蓄電容量は家庭用蓄電池の数倍)。
- ・EV購入補助金・V2H補助金の同時活用が可能です。
課題・注意点
- ・初期費用(V2H機器で約50万〜100万円+設置工事費)がかかります。
- ・V2H対応車種が限定されています。
- ・車の利用と電力利用のバランス調整が必要です。
今後の再生可能エネルギー社会においては、「車=動く蓄電池」としての役割がますます重要になると予想されます。
3-7.選択肢5:新たな売電先(市場連動型など)
・PPAモデルや地域電力会社との契約
卒FIT後は、地域の新電力会社やPPA(Power Purchase Agreement)モデルを採用する事業者と契約する選択肢もあります。PPAモデルでは、発電設備を第三者が所有・管理し、家庭や事業者がその電力を購入する形で、自家発電をしながらも売電に近い形で収益化が可能になります。
また、地域電力会社の中には、地域還元型の売電プラン(地産地消電力)を提供しているところもあり、通常の大手電力会社よりも高単価で買い取ってくれる場合もあります。
・市場価格連動型プランの検討
電力取引市場(JEPX)価格に連動した買取プランも広がっています。これは、時間帯によって売電価格が変動するため、電力需要が高いタイミングに売ると高値で売電できるという特徴があります。
ただし、価格の安定性には欠けるため、蓄電池やHEMS(家庭用エネルギー管理システム)との併用が推奨されます。
| 選択肢 | 初期費用 | 経済効果 | 停電対策 | 継続性 | 補助金の有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力会社との再契約 | 低〜なし | △(売電価格が低い) | × | ○ | 一部あり |
| 自家消費 | 中〜高 | ○(電気代削減) | △ | ○ | あり |
| 蓄電池導入 | 高 | ◎(自家消費率向上) | ◎ | ○ | あり |
| V2H+EV活用 | 高 | ◎(防災・移動兼用) | ◎ | ○ | EV+V2H補助あり |
| 新たな売電先(地域電力・市場連動) | 低〜中 | △〜○(価格に左右される) | × | △ | 条件による |
この先どれを選ぶか迷われているなら── あなたに合った土地活用プランを“無料で一括比較”できる資料が、今、すぐに届きます。
資料を一括で請求してみる4.【Q&A】太陽光発電のFIT制度と卒FITに関するよくある質問
太陽光発電の導入や卒FIT後の対応に関しては、専門用語や制度の変更など分かりづらい点も多く、不安や疑問を抱える方も少なくありません。
ここでは、よくある質問にQ&A形式でわかりやすくお答えします。
4-1.Q1. FIT制度の売電価格はなぜ年々下がっているのですか?
A. FIT制度の目的は、再生可能エネルギーの普及と市場の自立化です。
導入当初は高価格で売電を保証することで設置のハードルを下げましたが、太陽光パネルの普及と価格の低下、発電効率の向上などにより、コストが下がってきました。
そのため、国は補助的な役割を段階的に縮小しており、売電価格も年々引き下げられています。
4-2.Q2. 卒FIT後、何も手続きしないとどうなりますか?
A. FIT期間が終了すると、既存の売電契約は自動的に終了します。
もしそのまま放置しておくと、発電した電力は電力会社に無償で供給される状態になることもあり、経済的にもったいない状況です。
必ず再契約・自家消費・蓄電池導入などの次のステップを選択し、早めに手続きを進めることが重要です。
4-3.Q3. 自家消費に切り替えるには、どのくらいの費用がかかりますか?
A. 自家消費そのものは、既存の太陽光発電システムで可能ですが、蓄電池やエネルギー管理システム(HEMS)を導入して効率を高めたい場合、以下のような費用がかかることがあります。
- 家庭用蓄電池:70万〜150万円程度
- HEMS:数万円〜10万円前後
- 設置・工事費:別途10万〜30万円程度
ただし、国や自治体の補助金を活用することで数万〜数十万円の助成が受けられる場合もあります。
4-4.Q4. 蓄電池は必ず導入すべきですか?
A. 必須ではありませんが、経済的な自家消費率の向上と防災対策の両面で非常に効果的です。特に夜間の電力使用量が多い家庭や、災害リスクの高い地域にお住まいの方は導入を検討する価値があります。
ただし、費用が高額なため、導入効果をシミュレーションした上で、家庭のライフスタイルや今後の使用計画に合致するかを確認することが大切です。
4-5.Q5. FIT制度が終了しても、補助金や税制優遇は利用できますか?
A. FIT制度そのものは終了しても、蓄電池やV2H、太陽光発電の新規・増設に対する補助金制度は継続されています。また、以下のような税制優遇も引き続き利用可能です。
- ・蓄電池やエネルギー機器の導入補助金(自治体・国)
- ・固定資産税の軽減(条件付き)
- ・グリーン住宅ポイント制度(過去実施例あり)
導入する機器や時期によって制度の有無・金額が異なるため、最新の補助制度を各自治体・国の公式サイトで確認するのがおすすめです。
4-6.Q6. 卒FIT後の選択肢は、途中で切り替えることもできますか?
A. はい、可能です。
たとえば、最初は電力会社と再契約して売電を継続し、後から蓄電池を導入して自家消費へ切り替えるといった方法も選べます。
ただし、契約内容によっては途中解約に違約金が発生するケースや、再契約時に条件が変わる可能性もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
資料請求は無料・簡単・安心。 実績豊富な専門企業から、土地に合ったプランが届くから、始める“きっかけ”がここにあります。
一括資料請求で未来の一歩へ進むまとめ:太陽光発電FIT制度と卒FIT後の未来
FIT制度の総括と今後の展望
太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)は、2012年の本格導入以降、日本の再生可能エネルギー拡大に大きく貢献してきました。制度によって多くの一般家庭や事業者が太陽光発電に参入し、初期投資の回収と安定した売電収入が可能になったことは、エネルギー政策の一大転換点だったといえるでしょう。
そして、卒FITを迎えるということは、「発電した電気を誰に、どう活用してもらうか」から、「自分でどう使うかを選ぶ時代」への移行でもあります。売電価格に依存せず、自らのライフスタイルに合った電力利用を設計することが、今後ますます重要になります。
信頼できるパートナー企業を選び、これからの10年と次の10年へ。
あなたの目的に合った方法を見極めるには、専門家のアドバイスや複数の見積もりを比較することが不可欠です。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 賃貸経営の基礎知識
賃貸経営の基礎知識の関連記事
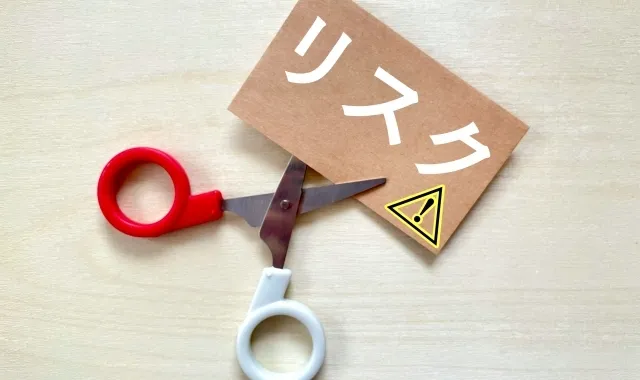
- 賃貸経営のリスクと対処法|初心者が失敗しないための完全ガイド 公開
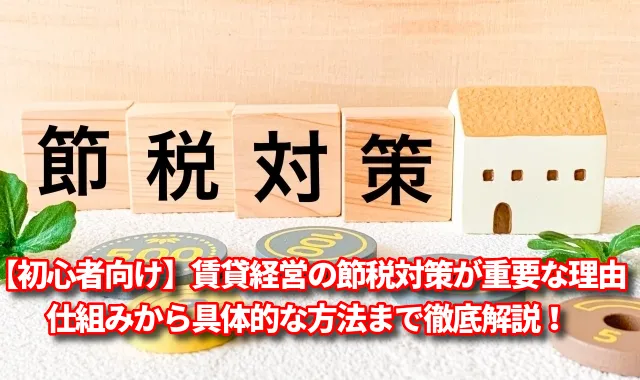
- 【初心者向け】賃貸経営の節税対策が重要な理由を徹底解説!仕組みから具体的な方法まで 公開
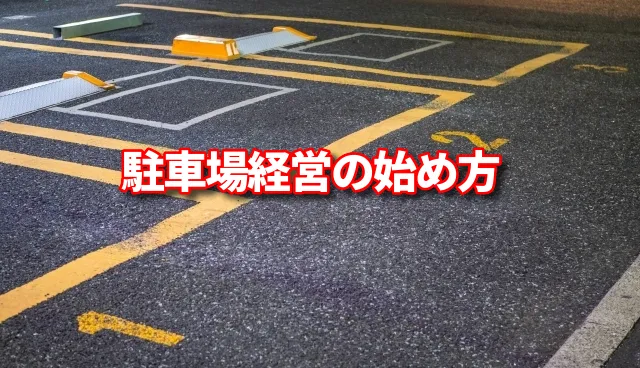
- 駐車場経営は儲かる?始め方とメリット・デメリット|土地活用で失敗しない注意点 公開
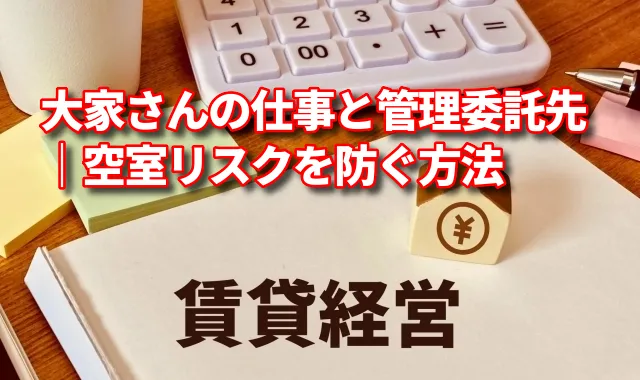
- 大家さん必見|賃貸経営の仕事内容と空室対策・優良管理会社の選び方 公開
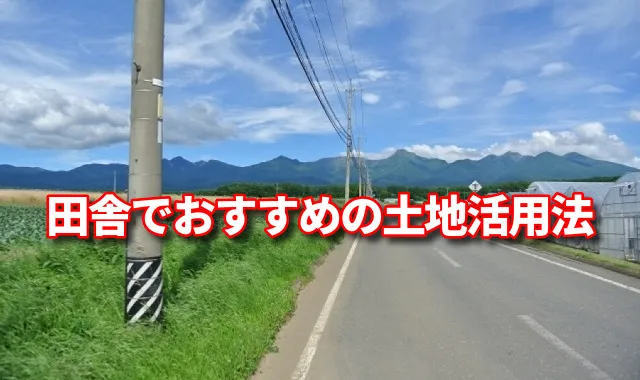
- 田舎の土地活用完全ガイド|空き地や遊休地で収益化するおすすめ方法と注意点 公開
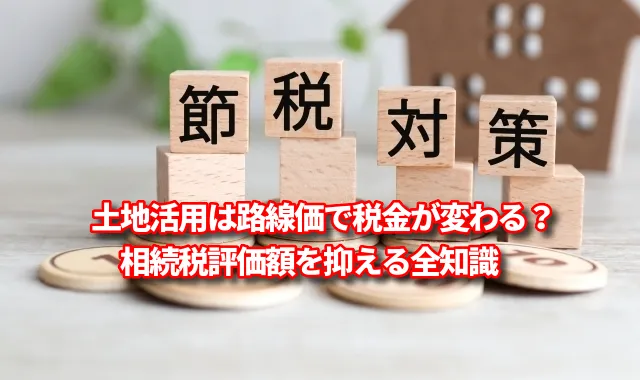
- 土地活用は路線価で税金が変わる?相続税評価額を抑える全知識 公開
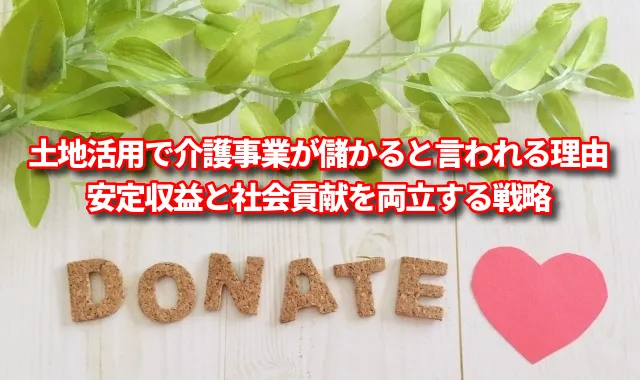
- 土地活用で介護事業が「儲かる」と言われる理由 安定収益と社会貢献を両立する戦略 公開

- 土地活用の最新動向と将来性|ランキングで分かる人気活用法と成功のポイント 公開

- 【地域活性化の起爆剤】土地活用と空き家リノベーションで未来を拓く 公開
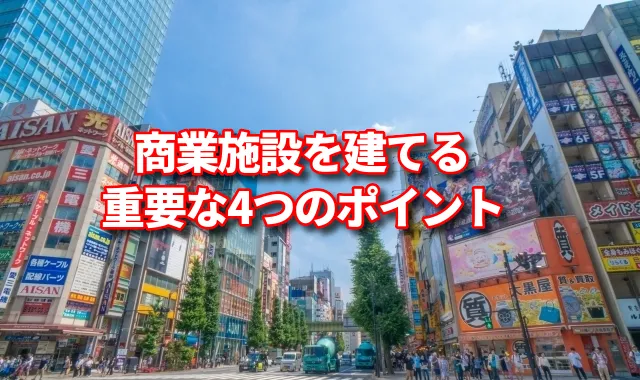
- 土地活用で高収益を狙うなら?商業施設活用の魅力とアパート経営との比較ポイント4選 公開

- 賃貸経営の利回り完全ガイド:計算から平均・シミュレーションまで徹底解説 公開
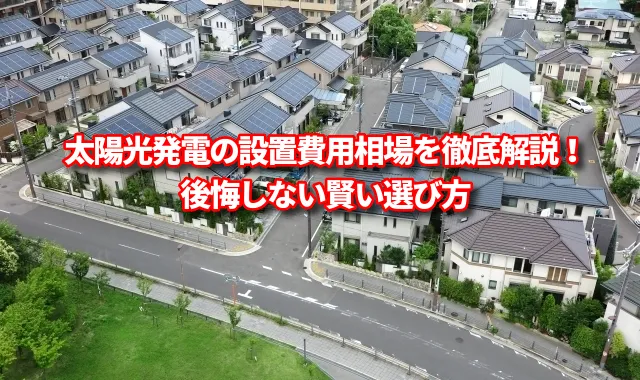
- 太陽光発電の設置費用相場を徹底解説!後悔しない賢い選び方 公開

- 【土地活用】借地権設定で安定収入!リスクを抑えて資産を最大化する方法を徹底解説 公開
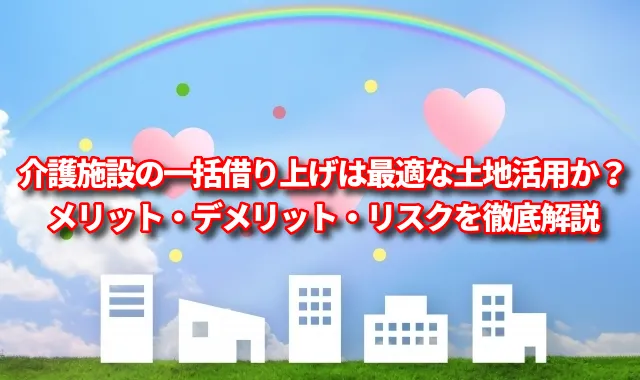
- 介護施設の一括借り上げは最適な土地活用か?メリット・デメリット・リスクを徹底解説 公開

- 太陽光発電の余剰電力売電ガイド:FIT後の最適な選択肢と賢い契約方法 公開

- 太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)とは?FITの仕組みから卒FIT後の賢い選択肢まで徹底解説 公開
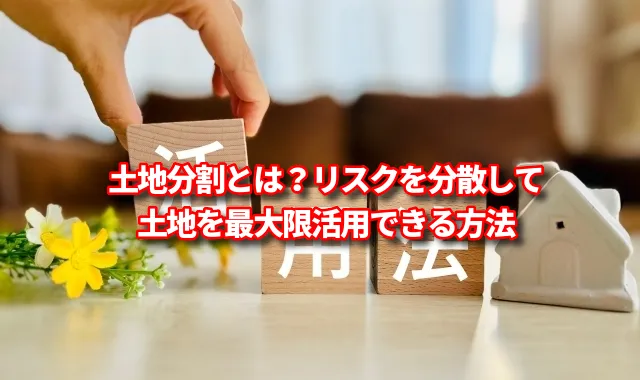
- 土地分割とは?リスクを分散して土地を最大限活用できる方法 公開
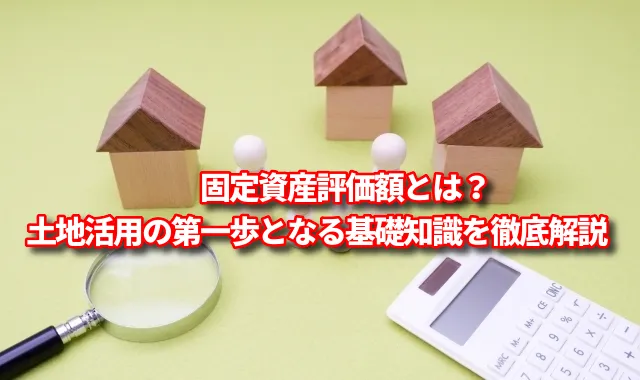
- 固定資産評価額とは?土地活用の第一歩となる基礎知識を徹底解説 公開
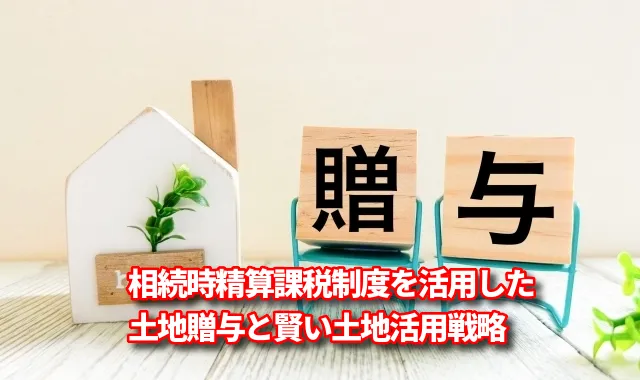
- 相続時精算課税制度を活用した土地贈与と賢い土地活用戦略 公開
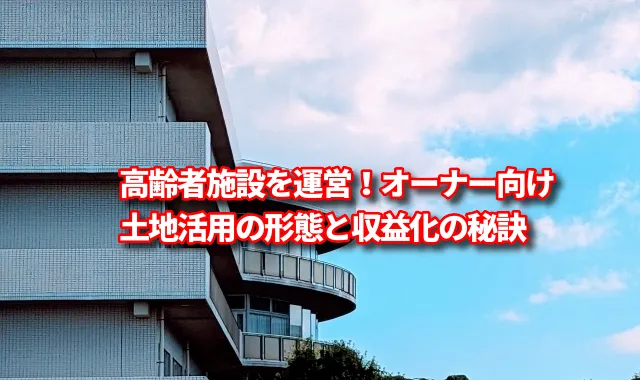
- 高齢者施設を運営!オーナー向け土地活用の形態と収益化の秘訣 公開