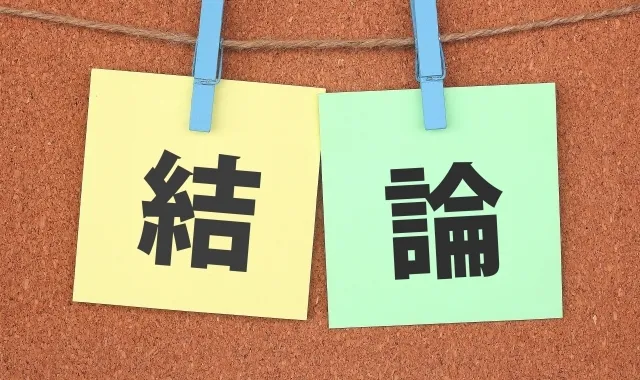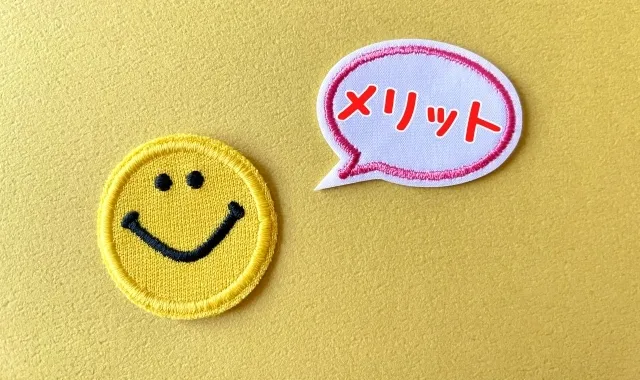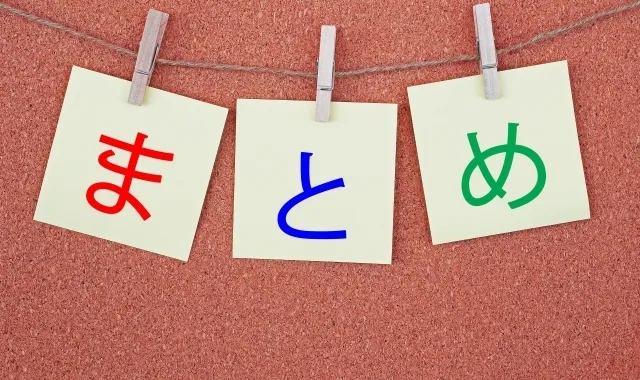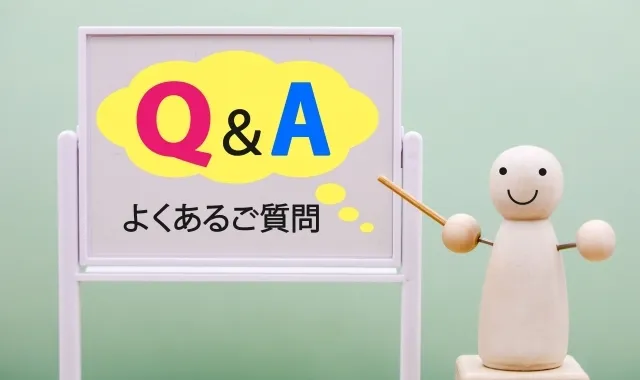- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- リロケーション
- リロケーションのトラブルとリスク
- リロケーションで定期借家を外国人に貸す際の必須知識|トラブルを防ぐ安心運用のポイント
リロケーションで定期借家を外国人に貸す際の必須知識|トラブルを防ぐ安心運用のポイント
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.外国人入居者は増加増加傾向 貸しても大丈夫か?結論と背景
近年、日本に住む外国人の増加に伴い賃貸需要は高まっており、空室対策として外国人入居者を受け入れるケースが増えています。しかし、言語や文化の違いから「トラブルが起きるのではないか」と不安を感じるオーナー様も少なくありません。
本記事では、外国人入居者への「定期借家契約」を活用したリロケーション運用について、トラブルを防ぐための具体的な注意点と対策を体系的に解説します。
適切な準備と管理体制さえ整えれば、外国人への賃貸は決して怖いものではありません。安心して自宅を貸し出すための判断材料としてお役立てください。
日本における外国人入居需要は年々拡大しています。少子高齢化による労働力不足を背景に、政府は特定技能制度の拡充などを進め、2023年末には在留外国人数が過去最高の341万人を記録、その後も増加の一途を辿っています。
彼らの生活基盤となる住居は、半数以上が民間の賃貸物件であり、今後もこの需要は堅調に推移すると予測されます。
1-1.トラブルへの不安と実際
多くのオーナー様が懸念するのは、契約内容への理解不足、生活習慣の違い、そして言語の壁によるトラブルです。
国土交通省の指摘通り、海外には敷金・礼金・更新料といった日本独自の商習慣や、原状回復という概念が存在しない国も多くあります。
また、書面よりも口頭契約が主流の文化圏では、契約書の内容を十分に理解しないまま署名してしまうケースも見受けられます。
1-2.適切な管理体制があれば安心運用は可能
しかし、こうしたトラブルの多くは事前の準備と適切な管理体制で防ぐことが可能です。
国土交通省は多言語対応の契約書やチェックシートを提供しております。契約期間が満了すれば確実に契約が終了する「定期建物賃貸借契約」を活用することで、居座りなどのリスクも回避できます。
生活ルールの周知や適切な保証会社の選定、そして専門知識を持つ管理会社との連携を行うことで、外国人入居者であっても安心して自宅を貸し出すことができます。
2.外国人に定期借家で貸す際の主要な注意点
外国人に自宅を定期借家として貸す際、トラブルの芽を事前に摘むために特に注意すべきポイントは大きく5つあります。それぞれの詳細と対策を見ていきましょう。
2-1.定期借家の「更新なし」を確実に伝える
定期建物賃貸借契約は契約期間の満了をもって終了し、再契約を行わない限り退去が必要です。しかし、海外では契約期間の概念が柔軟な国もあり、「更新して当たり前」と捉えられることがあります。
この認識のズレを防ぐため、契約時には「期間満了で必ず退去が必要であること」を多言語で説明し、理解を得ることが不可欠です。
日本語の契約書だけでなく、英語や中国語などの翻訳版を用意し、事前説明書と終了通知書も合わせて交付する運用が求められます。
また、退去時期が近づいた際の通知も重要です。多言語対応のリマインダーなどを活用し、手続き期限を入居者と共有する仕組み作りが効果的です。
2-2.生活ルールの認識差を埋める視覚的工夫
ゴミの分別、騒音、共用部の使い方といった生活ルールは、日本独自の細かい規定が多く、外国人には理解のハードルが高いものです。
例えば、夜間の騒音に対する許容度や、友人を招いてのパーティー、ペットの飼育など、文化による感覚の違いが近隣トラブルに発展することもあります。
対策として有効なのが、視覚的な情報の提供です。文字だけの説明ではなく、イラスト付きのハウスルールブックや、色分けされたゴミ出しカレンダーを配布することで、直感的にルールを理解してもらえます。
禁止事項については具体的な例を示し、入居前にしっかりと合意形成を図ることが大切です。
2-3.原状回復ルールの明確化と入居時の記録
退去時の原状回復費用をめぐるトラブルは、文化的な背景の違いから生じやすい問題です。
日本では「経年変化や通常損耗は家賃に含まれる」と考えますが、海外では「入居時の状態に戻す」あるいは「そもそも原状回復義務がない」と考える場合もあります。
国土交通省のガイドラインに基づき、入居者の故意・過失による汚損と、通常使用による損耗の線引きを、契約時に明確に説明する必要があります。
入居直後の室内状況を写真に残して双方向で共有し、退去時の費用負担基準を具体的に示しておくことが、後の紛争を防ぐ鍵となります。
2-4.外国人対応に強い保証会社の選定
日本での賃貸契約には連帯保証人が求められることが一般的ですが、外国人にとって日本人の保証人を見つけることは困難です。
そのため、家賃債務保証会社の利用が前提となります。現在は多言語対応可能な保証会社が増えており、2025年9月時点で52社が外国語サポートを提供しています。
審査や滞納時の督促において通訳を介してコミュニケーションが取れる会社を選ぶことで、オーナー様の負担は大幅に軽減されます。
保証料や更新料の仕組みについても、契約時に丁寧に説明し納得してもらうプロセスを忘れてはいけません。
2-5.緊急時の連絡体制の確保
言葉の壁は、火災や水漏れ、急病といった緊急時の対応を遅らせる要因になります。
契約時には、日本語が話せる緊急連絡先の設定や、在留資格・期間の確認を徹底しましょう。
もし入居者本人の日本語能力に不安がある場合は、24時間対応の多言語コールセンターを持つ管理会社や保証会社のサービスを利用するのが賢明です。
いつでも連絡が取れる体制を整えておくことは、物件を守るだけでなく、入居者の安全を守ることにもつながります。
3.トラブルを防ぐための事前準備
前述の注意点をクリアにするためには、入念な事前準備が欠かせません。
3-1.多言語ツールの活用
自治体が発行する多言語のゴミ出しパンフレットや、国交省のガイドラインに沿った外国語版の契約書を用意しましょう。
機械翻訳ではなく、専門家が監修した正確な文書を使用することで、法的な誤解を防げます。
3-2.IT重説と電子契約
海外在住の入居予定者ともスムーズに契約できるよう、IT重説や電子契約の導入も検討に値します。画面上で資料を共有しながら説明できるため、理解度を確認しながら進められます。
3-3.コミュニケーション手段の多重化
翻訳アプリやチャットツールを導入し、気軽に問い合わせができる環境を作ります。一方通行の連絡にならないよう、双方向のコミュニケーションラインを確保しておくことが信頼関係の構築に役立ちます。
4.外国人対応を「自主管理」することのリスク
コスト削減のために自主管理を検討するオーナー様もいますが、外国人入居者の管理には特有の難しさがあります。
まず、言語対応の限界です。日常会話レベルなら翻訳アプリで対応できても、契約更新や設備トラブル、近隣クレーム対応といった複雑な場面では、微妙なニュアンスが伝わらず事態が悪化するリスクがあります。
次に、法的な専門知識の必要性です。特に定期借家契約の期日管理は厳格に行う必要があり、通知期間を誤ると契約が終了できなくなる法的な落とし穴があります。
原状回復の交渉においても、ガイドラインに基づいた論理的な説明ができなければ、不当な請求と受け取られかねません。
これらのリスクを考慮すると、専門家のサポートなしでの自主管理はハードルが高いと言わざるを得ません。
5.リロケーションサービスを利用するメリット
そこで推奨されるのが、留守宅管理のプロであるリロケーションサービスの利用です。
5-1.プロによる外国人対応と契約管理
リロケーション会社は、多言語対応可能なスタッフや通訳サービスを完備しており、募集から契約、入居中の対応までを一貫して代行します。
特に定期借家契約の運用においては、法令に則ったスケジュール管理を徹底するため、帰任時に「家が返ってこない」という事態を確実に防ぎます。
5-2.退去立ち合いと原状回復の適正化
退去時の立ち合いや原状回復工事の手配も、すべてプロが行います。ガイドラインや過去の判例に基づき、入居者に費用負担の根拠を説明するため、納得感のある精算が可能となり、トラブルを最小限に抑えられます。
5-3.空室リスクの低減と収益の安定
外国人入居者は、一度入居すると居住期間が長くなる傾向があり、安定した家賃収入が見込めます。
リロケーション会社は独自のネットワークで外国人入居希望者にアプローチできるため、日本人だけをターゲットにするよりも空室期間を短縮できる可能性が高まります。
6.まとめ
外国人入居需要の取り込みは、リロケーション運用において有効な選択肢です。
文化や言葉の壁によるトラブルは、定期借家契約の正しい運用、視覚的なルール周知、多言語対応の保証会社利用、そして緊急連絡体制の整備によって防ぐことができます。
しかし、これらを個人で完璧に行うには限界があります。外国人対応に実績のあるリロケーションサービスを活用することで、言語や法的なリスクをプロに委ね、安心かつ安定した賃貸経営を実現してください。
7.よくある質問(FAQ)
7-1.Q1. 外国人でも定期借家契約を結べますか?
はい、問題なく結べます。国土交通省も外国人入居者への定期建物賃貸借契約の活用を推奨しています。
重要なのは、契約期間満了で必ず退去が必要であることを多言語で説明し、理解を得ておくことです。
7-2.Q2. 言葉が通じない場合の対応はどうすればよいですか?
翻訳アプリのほか、多言語対応のコールセンターや通訳サービスを利用するのが確実です。
契約時には日本語ができる友人の同伴を求めたり、多言語対応スタッフがいる管理会社に仲介を依頼したりすることをお勧めします。
7-3.Q3. 保証会社の審査は外国人でも通りますか?
はい、通ります。現在は多くの保証会社が外国人の受け入れを行っており、多言語サポート体制も整っています。
審査には在留カードや就労証明書などが必要になりますが、適切な保証会社を選べばスムーズに契約可能です。
7-4.Q4. 近隣トラブルが増える心配はありませんか?
生活ルールの違いによるトラブルの可能性はありますが、悪意があるわけではなく「ルールを知らない」ことが大半です。
入居前にイラスト付きのガイドなどで日本のマナーを丁寧に説明することで、多くのトラブルは未然に防げます。
7-5.Q5. プロ(リロケーション会社)に任せるべき判断基準は?
語学力に不安がある場合、または帰任時期が決まっており確実に家を明け渡してもらいたい場合は、プロに任せるべきです。
自主管理では契約不備や対応の遅れが大きなリスクになりますが、リロケーション会社なら法的な管理を含めて全て代行してくれます。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- リロケーションのトラブルとリスク
リロケーションのトラブルとリスクの関連記事

- リロケーションで定期借家を外国人に貸す際の必須知識|トラブルを防ぐ安心運用のポイント 公開

- リロケーションサービスのトラブルとリスクを徹底回避!持ち家を安全に貸し出すための完全ガイド 公開
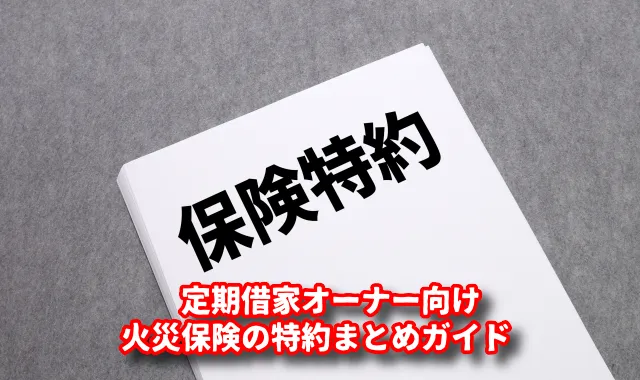
- 定期借家オーナー向け|火災保険の特約まとめガイド(原状回復・設備トラブル・家賃リスクを防ぐ選び方) 公開

- 定期借家「自己使用できない」問題を解決!違約金ゼロで自宅に戻る法的ステップ 公開
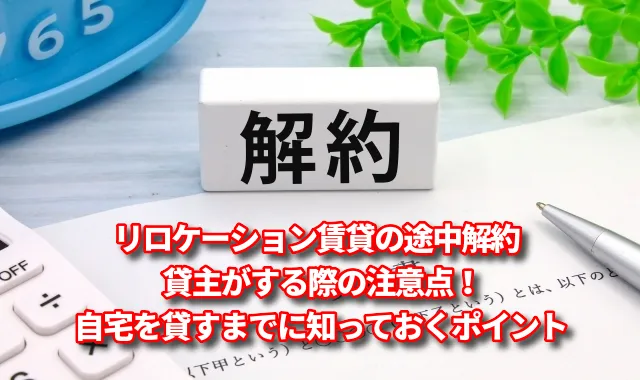
- リロケーション賃貸の途中解約を貸主がする際の注意点!自宅を貸すまでに知っておくポイント 公開
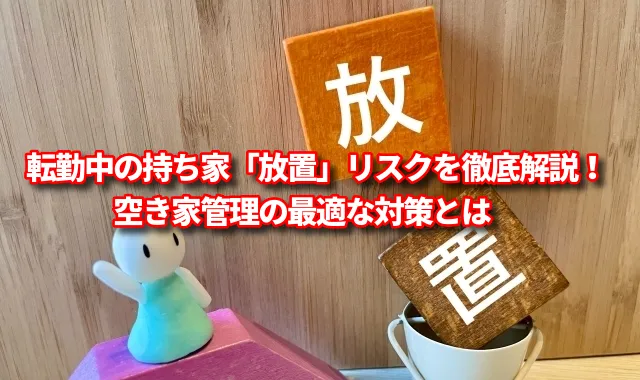
- 転勤中の持ち家「放置」リスクを徹底解説!空き家管理の最適な対策とは 公開
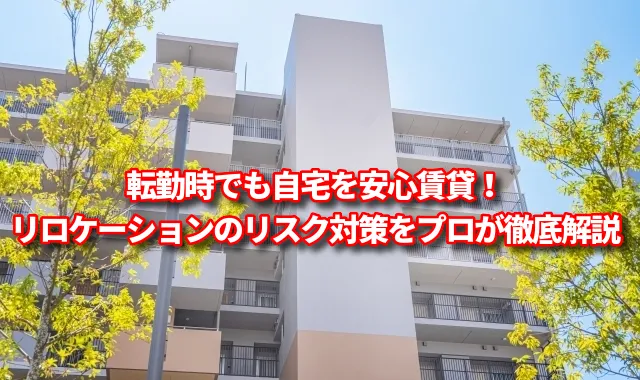
- 転勤時でも自宅を安心賃貸!リロケーションのリスクと対策をプロが徹底解説 公開

- 転勤で心配なリロケーションサービスのトラブルと費用を徹底解説! 公開
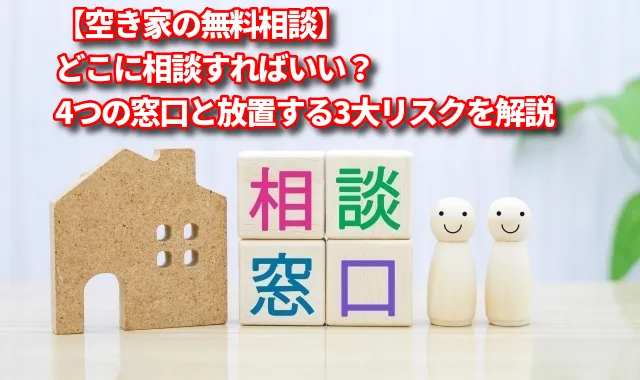
- 【空き家の無料相談】どこに相談すればいい?4つの窓口と放置する3大リスクを専門家が徹底解説 公開
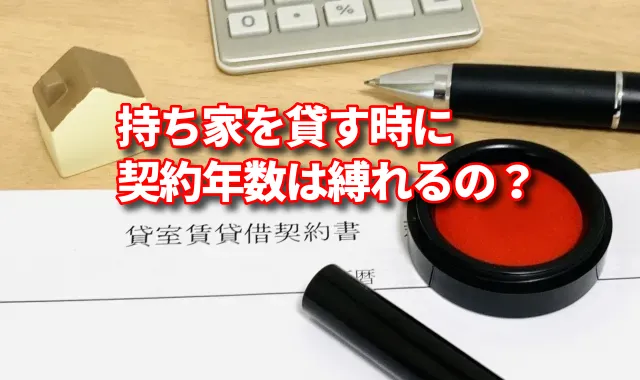
- 家を貸すなら知っておきたい!普通賃貸借契約と定期借家契約の違いと選び方 公開

- 賃貸オーナー必見!家を貸す時によくあるトラブルと今すぐできる回避・対策ガイド 公開