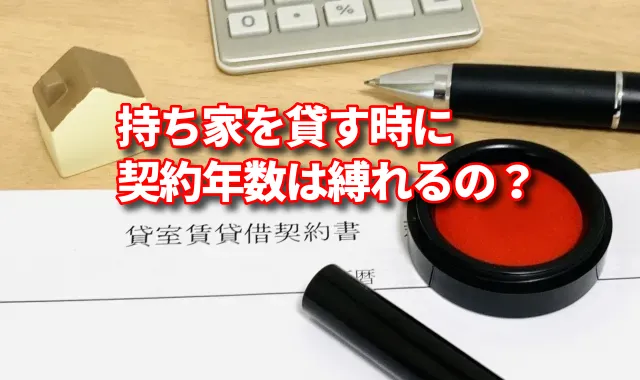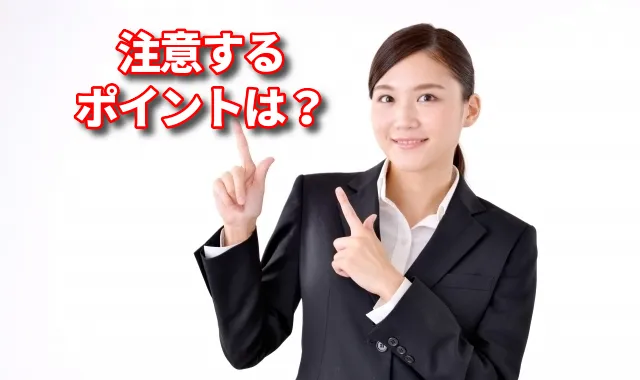- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- リロケーション
- リロケーション基礎講座
- 転勤で持ち家を賃貸化!空き家放置せず高収益を目指す方法と注意点
転勤で持ち家を賃貸化!空き家放置せず高収益を目指す方法と注意点
この記事を読むのにかかる時間:5分
「いずれはその家に戻りたいのですが...」。人に貸してしまったら戻れなくなる!?
どちらがお得?ライフプランに合った契約内容を理解しよう!
一般的に、自宅を賃貸に出す理由として最も多いのは「国内での転勤」や「海外赴任」です。転勤はビジネスパーソンでしたら経験する人も多いでしょう。
最悪かもしれないのは、家を購入した直後に転勤や海外赴任になった場合でしょう。「せっかく家を購入したのにどうしよう?」と正直お悩みになると思います。次に多いのが「実家を相続したが自分は住まない」といった場合です。
ここでは、最も多い「転勤で家を貸したい」と思った場合を例にします。こうした方々が賃貸物件として貸したいと思うのは「自分が住まない間、家を手放すことなく貸すことができれば、その家賃収入からご自身の住宅ローンが補填でき、転勤が終れば再び家に戻ることもできる」というのが一番の理由になるでしょう。
ただ、ここで一つの疑問を感じるかもしれません。「家を人に貸した後、入居者がまだいても確実に家に戻ることはできるの?」という疑問です。転勤期間が終わり「いざ戻りたい」と思ったタイミングで、まだ入居者が住んでいて自分は戻れず住む家に困った、なんてことになった場合は笑い話にもなりません。
そうしたことを防ぐ方法として「定期借家契約」という契約形態があります。これは入居者(借主)と一定期間だけ賃貸契約を結ぶことができる契約形態です。
具体的には「【家の所有者(貸主)が決めた】一定期間、借主は家を貸してもらうことができるが、契約満了日を迎えた時点での契約更新がないため、借主はその家から必ず退去をしないといけない」という契約形態になります。電車の定期券は使用期限が来たら使えなくなりますが「定期借家契約」の「定期」もそれと同じ意味合いになります。
ですので、転勤や海外赴任である程度期間が決まっている場合なら、自宅の賃貸化をするには最適の賃貸借契約になります。契約満了後は、自分の家が確実に手元に戻ってくるので安心できるわけです。
この契約形態では、自分の家(所有する不動産)を完全に手放すことなく、賃貸物件として貸し出せるのが特徴です。
例えば、転勤期間が2年であれば、実際に賃貸化する期間は、自分の家に戻りたい日から逆算した期間で考えると良いことになります。
これは補足になりますが「もう戻ることも自分が住む予定もないので、家をずっと賃貸物件として貸し出したい」という場合は「普通借家契約」を結ぶのが一般的です。
普通借家契約の場合、一般的な契約期間としては2年間が最も多く、借主が退去を申し出ない限りは、都度、自動更新となるのが特徴です。ただ貸主は「正当な事由」がない限り自分の都合だけで借主を途中退去させることはできない契約形態になりますので注意が必要です。
またこの契約では、1年未満で契約を設定した場合は、期間が決まっていない契約として扱われますので、そこも注意が必要です。
このように賃貸に出す理由によって契約内容は変わるため、契約内容をしっかり把握してみて下さい。
以下で、これらの賃貸借契約の特徴を再度整理して記載しておきますので、ご確認ください。
定期借家契約と普通借家契約についてもっと詳しく!
定期借家契約
入居者(借主)との契約更新はありません。貸主が予め設定した契約期間が終了した時点で、その賃貸借契約は打ち切られますので、貸主は借主から確実に家の明け渡しを受けることができます。
一般的には、貸主が賃貸に出したい契約期間を自由に定めることができ、それを「公正証書」といった書面にした上で契約を締結します。
注意点として、この契約形態を使う場合は、契約締結前に「貸主側は、借主に対して、契約満了と共に退去しなくてはならないことについて誤解がされないように、しっかりとその内容を説明しておく必要がある」というものになります。この重要説明を怠った場合は「普通借家契約」となってしまうので必ず注意しましょう。
また、定期借家契約は、原則、貸主借主双方とも中途解約をすることができません。しかし契約期間中、借主側にやむを得ないと認められる事情、例えば「転勤」や「介護が必要になった」などの理由で、どうしても退去せざるをなくなった場合は、中途解約の申し入れができることになっています。
ただ、この解約権の行使については、通常「床面積が200平方メートル未満の住宅」に限られます。さらに、中途解約に関しては個別に特約をつけることは可能です。
また、契約期間が1年以上の場合、貸主は契約期間満了前の6カ月前までの間に、借主に対して契約終了のお知らせをしなければなりません。
普通借家契約
契約期間は原則1年以上となりますが、一般的には2年契約で設定されることが多いです。ただ、1年未満の場合は「期間の定めのない契約」となり、借主の状況により中途解約の特約を設けることがあります。
また、解約の予告期間や直近での解約の場合では、借主が支払う金額がどれぐらいかを定めておきます。
普通借家契約を結ぶ際の注意点は、貸主の状況で契約期間を終了としたい場合「正当な事由」がない限り契約終了ができないことです。借主を強制的に途中退去をさせることはできません。
正当な事由とは、例えば「貸主がその物件にどうしても住む必要が出てきた」などの理由です。
従って、普通借家契約の契約期間は、貸主と借主双方の意向に左右されることがあります。
では、賃貸に出した時のメリット・デメリットはどのようなものがあるのか見てみましょう。
状況によっては貸さない方が良いことも!?自宅の賃貸化はメリット・デメリットどちらも有しています。
家を賃貸に出すメリットは、賃貸に出せれば、その期間は借主からの家賃収入を得ることができ、家を保有し続けることができることです。
また、上述した「定期借家契約」を使えば、借主との賃貸借契約が終了した時点で契約更新はないので、将来、確実にその家に戻ることができることです。
また、賃貸化したい家の物件形態が「分譲マンション」だった場合は、購入したマンションで組織されているマンション組合で決められた「管理費」や「修繕積立金」などを毎月支払っている費用や「固定資産税」「住宅ローン金利」などが「経費として計上できる」ため控除対象にできます。
そして、分譲マンションは、相対的に一軒家よりも設備仕様や管理がしっかりしている物件もあるので、そうした物件だった場合は、家賃を若干高めに設定しても、一軒家よりも入居希望者が見つかりやすい傾向があります。
注意!入居者が入れ替わる時は、その間の家賃収入がなくなる恐れがあります...。
一方、デメリットとして考えられることは、一般のアパートやマンションといった賃貸物件と同じように、借主が見つからず空室期間が生じた場合、家賃収入が途絶えることです。
また、家を賃貸に出すことは、自分の所有する不動産を全くの他人に貸し出すことになるので、万が一、借主の素行が悪かった場合、入居者が引き起こすトラブルが起きる危険性を貸主として考えておく必要があります。
これは「入居者リスク」とも言い換えることができますが、具体的には「家賃滞納」「ゴミの散乱」「借主に起因する物件の損傷」などです。万が一、そうした入居者リスクが発生した場合は、原則的には貸主が問題解決に対応する必要があります。
しかし、現実的に貸主自身がそうした対応を行うのは、時間的にも精神的にも負担が大きく日常生活がままならなくなる恐れもあるため、家を貸し出す場合は自主管理ではなく信頼できる不動産管理会社を探して、家の管理業務の委託を依頼した方が適切なリスク対処法になります。
次に考えられるデメリットは、建物のサッシや壁、天井や廊下などの不具合、電気・ガス・水道設備の故障などが起きた場合は、明らかに借主の取り扱いに問題があった場合を除き、すべて貸主の費用負担で修理をする必要があることです。
そのため家を貸し出す場合は、家賃収入の一部を「修繕費」として積み立てておくなどの経費管理が必要になります。もちろん、 固定資産税・都市計画税などの経費も貸主負担になります。
こうした、家賃収入で得た所得管理、それによって行わなければならない確定申告、物件の維持管理費なども発生しますので、単純に「家を貸し出せれば、家賃収入は全て収入にできる」と勘違いしてしまうと「あれ!違ったの?」ということになりますので注意しましょう。
こうした収支に関係する所得管理や確定申告についても、不動産管理会社によって相談に乗ってくれる会社がありますので、家の管理業務の委託と合わせて相談すると良いでしょう。
また、入居者が退去したり、新たな入居希望者を募ることになった場合(普通借家契約の場合)は、「敷金の返金」「現状復帰のための清掃代」「家や設備の修繕が必要な場合」は、そうした費用が掛かってしまいます。
特に、現状復帰に関する費用負担については、入居者との契約時に細かく取り決めをしておかないと、将来の退去時にトラブルになるケースがありますので注意しましょう。
また、入居者の入れ替え時は、最低でも新しい入居者が見つかるまで1~2カ月ほど掛かることが多いため、その間の家賃収入が途絶えてしまいますので、入居者の退去情報をいち早くキャッチして、次の入居希望者を探すための準備をする必要があることをあらかじめ理解しておく必要があります。
またこれは補足になりますが、家を一度賃貸として貸し出した場合は、賃貸経営という事業を行うことになるため、その家が「収益物件」とみなされます。将来もし売却したくなった場合は、売却候補先として「収益物件を求めている人」が対象となります。
その物件の利回りが低いとみなされた場合は、不動産評価が厳しくなり購入希望者がなかなか見つからない可能性がありますので、知っておいた方が良いでしょう。逆に物件の利回りが高かった場合は有利な条件で売却が可能です。
このように自宅を賃貸化して貸し出すことは、メリットも大きいのですがデメリットも知って頂いた上で、ご自身のライフプランをよく考えて総合的に判断しましょう。
リスクを回避するためには!?
リスクを回避するためには、売却も1つの手段にはなります。
自宅の賃貸化にあたっては、入居者の目線でも考慮して頂きたいことがあります。
確かに「転勤や相続で家を貸して賃料収入を得たい」というご自身の希望は痛いほど良く分かるのですが、入居希望者と賃貸借契約を交わして、実際に家を貸し出したあと、ご自身の勝手な都合だけで「いつでも入居者に途中退去をしてもらうことができる」わけではないのが現実です。そこは入居者に迷惑が掛からない様に慎重に行いましょう。
また、契約したい期間や戻ってくる時期が明確であれば、「定期借家契約」を取り交わした上で、家を賃貸に出すことが有効ですが、もし期間が曖昧でハッキリと決まっていないケースでは賃貸に出すべきではないかもしれません。
例えば、結婚や出産、子供の成長といったライフステージの変化の中で「家を住み変えたい」という場合「その家に再び住むということはない」といったケースなら「売却」。「老後はその家に再び戻って住む予定がある」ということならそのまま所有をして家を賃貸に出すというやり方が考えられますが、それもその期間や時期をしっかりと考えておく必要はあります。
つまり、自宅を賃貸に出すことを検討する際は「今後の自分のライフプランがどうなっていくか?」を予想することが重要だということなのです。
家を賃貸に出すと、単に人に貸すというだけでなく「税金の管理」「点検・清掃」「確定申告」「その他雑多な作業」が発生することは上述しました。
また、仕事をしながら家の建物管理や入居者管理を同時にこなしていくのは、かなりの手間であり肉体的精神的にも大変です。そのため、ご家族と相談して、自分が遠く離れた場所に住むことになっても、誰かの協力を得られる環境を作っておくことが大事です。
家や分譲マンションといった不動産を持っていると、自分のステータスが上がったような気分になり「不動産を所有しておきたい」というお気持ちを持つ方もいるかもしれません。
しかし、家を貸す上で「建物に関するリスク」や「入居者に関するリスク」対策をまったく考えずに家を賃貸に出すというのも安易な考えになってしまう場合があります。
今後のライフプランが今一見えていない場合は断腸の思いかもしれませんが「不動産を売却することで資産を現金化して、維持費もかからない」という選択肢を取る方法もあります。
どうしても「自宅は手元に残したいが、売るか?貸すか?迷う・・・」ということで、判断に決めかねる場合は、知識不足のまま、自己判断でどちらかに決めることはおすすめできませんので、必ず「賃貸に出すか?それとも売却するか?」「賃貸に出すか?それともいっそのこと他の有効活用方法を模索するか?」など、不動産の専門家から情報を集めて比較検討されることをおすすめします。
まずは無料で資料請求!
空き家の賃貸経営は、正しい情報収集と慎重な比較から始まります。
今すぐ無料の一括資料請求を利用して、信頼できる管理会社のプランを手に入れ、安心の賃貸経営をスタートしましょう。
この記事のまとめ
転勤によって持ち家が空き家になるのはもったいない選択肢です。本記事で紹介したように、適切な賃貸化手法を使えば、空き家を活用して家賃収入を得つつ資産を守ることができます。
転勤や住み替えで持ち家が空き家になると、固定資産税の負担や劣化、防犯リスクが増してしまいます。一方で、賃貸として活用すれば不安を解消しつつ、安定した家賃収入を得られる可能性があります。
ただし成功させるためには、市場ニーズをしっかり見極めることが重要です。ファミリー向け需要が強い地域では戸建賃貸、独身者の多い地域ではシェアハウス化やリノベーションなど、土地や建物に合わせた柔軟な活用方法が求められます。
そのためには、やはり個人では限界があるのでプロに頼るのが現実的です。複数の専門会社から提案を比較するのが最も効果的です。まずはイエカレの無料一括資料請求を利用して、家賃査定・入居者募集・管理方法など幅広い情報を集めましょう。様々な貸し出しプラン比較するだけで、あなたの持ち家を「負担」から「収益資産」へと変える最適なプランが見つかります。 今すぐ第一歩を踏み出してみてください。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部
【イエカレ】では、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
(コラム・アドバイザー)檜垣 知宏

株式会社ライフアドバンス代表取締役の檜垣知宏です。 2014年8月に設立し、恵比寿不動産という屋号で賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理を行う不動産業者です。 不動産業界歴15年の経験を生かし、 運営しているサービスサイトである「不動産の相談窓口」の運営者も務めております。
【保有資格】宅地建物取引士
【関連URL】
[恵比寿不動産×賃貸]
[恵比寿不動産×売買]
[恵比寿不動産×リフォーム]
[不動産の相談窓口]
[資産運用の相談窓口]
[転勤東京.com]
[LGBT不動産]
[賃貸管理ナビ]
[ライフアドバンス]
【関連コラム】 空き家を貸さないのは損!?空き家を貸すメリットと貸す方法を解説!
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- リロケーション基礎講座
リロケーション基礎講座の関連記事

- 【30秒診断付き】海外赴任中の自宅の管理はどうする?|賃貸・空き家・売却の最適な選択は? 公開

- 住宅ローンが残っている家を賃貸にするには?許可・税金・控除の正しい手続きを解説 公開

- リロケーションの原状回復トラブルと費用負担を徹底解説!【貸主が損をしないための法的根拠と全知識】 公開
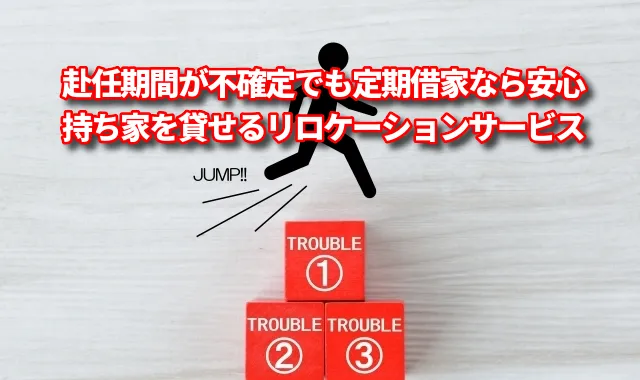
- 赴任期間が不確定でも定期借家なら安心!持ち家を貸せるリロケーションサービス 公開
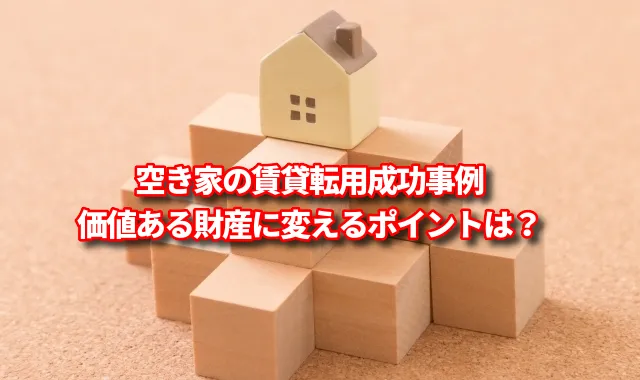
- 空き家の賃貸転用成功事例|価値ある財産に変えるポイントは? 公開

- 土地活用×空き家リノベーション|デザイン力で資産価値を最大化する方法 公開

- 転勤で持ち家を賃貸化!空き家放置せず高収益を目指す方法と注意点 公開

- 賃貸・借家の違いを徹底解説|普通借家契約 vs 定期借家契約 公開
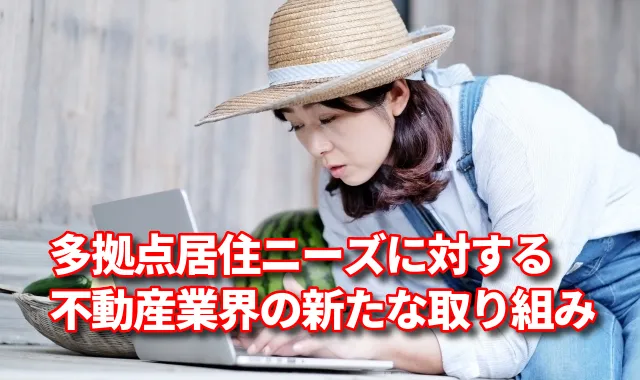
- 多拠点居住で家を貸す?メリット・デメリットと活用方法を解説 公開
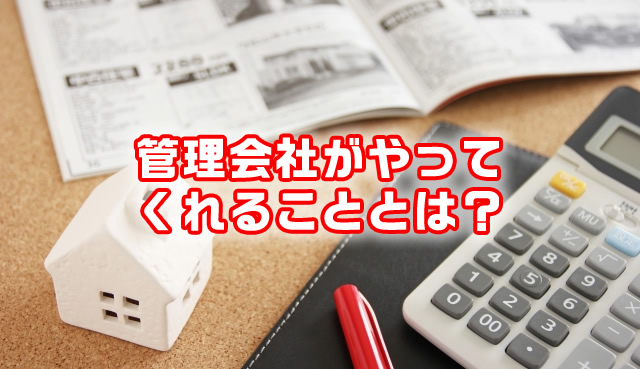
- 家賃収入が変わる!不動産管理会社の選び方と注意点|良い会社の見分け方速読ガイド 公開

- 転勤中でも安心!定期借家契約で持ち家を賃貸活用するメリットと注意点 公開