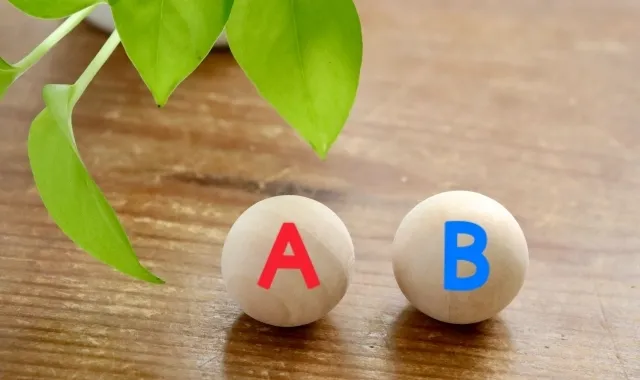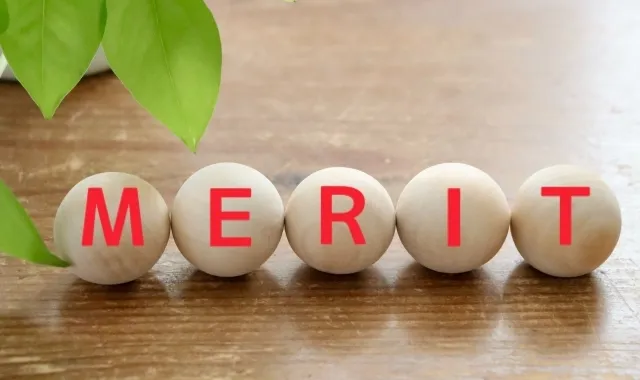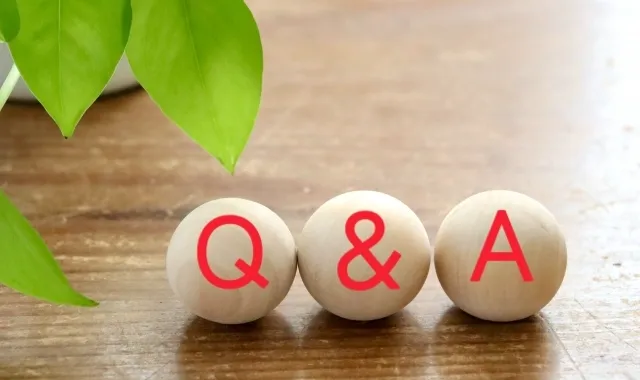- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- リロケーション
- リロケーションのメリット・デメリット
- 【貸主必見】定期借家契約のメリット・デメリットを理解すれば賃貸トラブルの不安は解消できる【イエカレ】
【貸主必見】定期借家契約のメリット・デメリットを理解すれば賃貸トラブルの不安は解消できる【イエカレ】
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.「定期借家契約」とは?貸主の不安を解消する基本概念
定期借家契約は、契約期間の満了をもって賃貸借契約が確実に終了する契約形態です。
この契約は、将来的に自宅を自分で使用する予定がある場合など、期限を決めて物件を貸し出したいと考える貸主にとって非常に有用な手段となります。
契約期間が満了すれば、借主は物件を明け渡さなければならないため、賃貸トラブルの代表格である立ち退きに関する悩みを事前に解消することが可能です。
普通借家契約と比べて、賃貸経営におけるリスクを大幅に軽減できることが最大の強みです。
2.定期借家契約と普通借家契約の最も重要な違い
定期借家契約と普通借家契約の最も重要な違いは、契約の「更新」に関する考え方にあります。
普通借家契約は、借主が希望すれば原則として契約が自動で更新されるため、貸主からの一方的な契約終了は非常に困難です。
契約を終了させるためには、貸主側に「正当事由」が必要とされ、多くの場合、高額な立ち退き料を支払うことが求められます。
一方で、定期借家契約には更新という概念がありません。契約期間が満了すると、契約は確実に終了します。
貸主と借主が双方の合意に基づいて再契約をすることは可能ですが、それはあくまで「新たな契約」であり、貸主は再契約の可否を自由に判断できます。
この法的性質が、将来の利用計画がある物件を安心して貸し出したいと考える貸主のニーズに応えています。
3.定期借家契約の貸主側メリット|「不安」を「安心」に変える3つのポイント
定期借家契約は、貸主が抱える賃貸経営の様々な不安を解消し、安心へと変える3つの大きなメリットがあります。
具体的には、契約期間が満了すれば物件が確実に返還されるという法的優位性、立ち退き費用が不要なこと、そして再契約の可否を自由に判断できることです。
これらのメリットは、貸主が自身のライフプランや資産運用計画に沿って物件を安全に貸し出すことを可能にします。
普通借家契約に比べ、貸主の立場が強く、予期せぬ賃貸トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
3-1.ポイント1:契約期間満了で確実に終了できる|立ち退きトラブルや訴訟リスクを回避
定期借家契約は、契約期間の満了をもって賃貸借契約が確実に終了するという法的優位性を持っています。
この特性により、貸主は将来的に物件を自分で使用する予定がある場合でも、安心して賃貸に出すことができます。
普通借家契約のように契約が自動更新されることはなく、期間満了後の賃貸トラブルを回避できます。
特に、転勤や海外赴任、相続した実家の活用など、予め自宅に戻る時期や物件の売却時期が決まっている貸主にとって、この点は非常に大きなメリットです。
借主が期間満了後も退去を拒む場合でも、法的に賃貸借契約は終了しています。そのため、立ち退きを求めるための交渉や、高額な立ち退き料の支払いを迫られるリスクを回避できます。
万が一訴訟になった場合でも、定期借家契約の法的根拠が貸主の主張を強く支持します。これにより、貸主は心理的・経済的な負担から解放され、安心して賃貸経営を継続できます。
3-2.ポイント2:立ち退き料の支払い不要|費用負担の心配がない
定期借家契約では、立ち退き料を支払う必要がありません。
普通借家契約では、貸主の都合で契約を終了させる場合、借主が新しい住居を探すための費用や引っ越し費用として、立ち退き料を支払わなければならないケースが多くあります。
これは、法律が借主の居住権を強く保護しているためです。この立ち退き料は物件や地域によって異なりますが、数十万円から数百万円に及ぶこともあり、貸主にとって大きな費用負担となることがあります。
しかし、定期借家契約では、契約期間の満了をもって契約が終了することが法律で定められています。したがって、貸主は借主に対して立ち退き料を支払う必要がありません。
この費用負担がゼロになることは、賃貸経営における予期せぬ出費をなくし、収益性を向上させる重要な要素です。
また、賃料設定においても、普通借家契約のように立ち退きリスクを考慮する必要がないため、より柔軟に設定できる可能性があります。貸主は、安心して物件の賃貸経営を行えるのです。
3-3.ポイント3:再契約の可否を貸主が自由に判断できる
定期借家契約は、契約期間の満了をもって契約が終了しますが、貸主と借主が双方の合意に基づいて再契約をすることは可能です。この再契約の可否を、貸主が自由に判断できることが大きなメリットです。
普通借家契約のように、借主が希望すれば契約が原則として更新されてしまうことはありません。
再契約を検討する際、貸主は借主の賃料の支払い状況や物件の使用状況、コミュニケーションの取りやすさなどを総合的に評価し、再契約の意思を決定できます。
たとえば、賃料の滞納が頻繁にあった場合や、賃貸トラブルを多く起こした借主とは再契約しないという選択が可能です。
逆に、良好な関係を築けている借主に対しては、再契約を提案することで、空室期間を設けることなく安定した賃料収入を確保できます。再契約の主導権を貸主が持つことで、より理想的な賃貸経営を実現できるでしょう。
4.定期借家契約の貸主側デメリット|契約前に知っておくべき注意点
定期借家契約は、貸主にとって多くのメリットをもたらしますが、その一方で、契約前に正確に理解し、対策を講じるべきデメリットも存在します。
具体的には、入居者が見つかりにくい可能性や、法律で厳格に定められた手続きがあることです。
これらのデメリットを軽視すると、空室リスクや契約自体の無効という深刻なトラブルに繋がりかねません。
貸主は、これらの注意点を事前に把握し、適切な対策を講じることで、安心して賃貸経営を始められます。
4-1.普通借家契約よりも入居者が見つかりにくい可能性がある
定期借家契約の最大のデメリットは、普通借家契約と比べて入居希望者が限られる可能性があることです。
借主の視点から見ると、契約期間が決まっており、更新が保証されていないため、長く住みたいと考える人にとっては魅力的ではありません。
特に、2年程度の短期契約では、2年後にまた引っ越しをしなければならないという点が、借主にとって心理的な負担となります。
このため、普通借家契約の物件と比較して、入居者が見つかるまでに時間がかかる場合があります。
この空室リスクを回避するためには、賃料設定を普通借家契約の相場よりも低めに設定するなど、入居者にメリットを感じてもらえるような工夫が必要です。
また、物件の魅力を最大限に引き出すためのリフォームや、家具付き物件として貸し出すなどの付加価値をつけることも有効な対策となります。
4-2.賃貸借契約の要件が法律で厳格に定められている
定期借家契約を有効に成立させるためには、法律で厳格に定められた手続きを遵守する必要があります。特に重要なのが「書面による事前説明義務」と「書面による契約締結」です。
まず、賃貸借契約を締結する前に、貸主は借主に対して「契約の更新がなく、期間満了によって契約が終了する」旨を記載した書面を交付し、その内容を口頭で説明しなければなりません。この事前説明を怠ると、契約は無効となり、普通借家契約と見なされる可能性があります。
また、契約自体も、契約期間、再契約の可否、建物の滅失に関する特約などを記載した書面によって行わなければなりません。
これらの手続きに不備があった場合、定期借家契約の最大のメリットである「期間満了による確実な終了」が認められず、普通借家契約と同様に、貸主都合の退去には正当事由や立ち退き料が必要となるリスクが生じます。
法的なトラブルを避けるためにも、賃貸管理会社や弁護士など、専門家への相談が不可欠です。
5.【重要】「リロケーションサービス」で安心して貸し出し
定期借家契約を正しく行うには、煩雑な手続きを正確に進める必要があります。しかし、個人で全てを管理するのは非常に手間がかかり、法律の専門知識も必要です。そんな時、心強い味方となるのがリロケーションサービスです。
リロケーションとは、主に転勤などで一時的に自宅を空ける際に、その期間だけ専門会社に賃貸管理を委託するサービスのこと。定期借家契約に特化したサービスが多く、貸主の不安を解消し、スムーズな賃貸経営を実現してくれます。
定期借家契約に精通した専門家が、法律で定められた厳格な手続きを全てサポートしてくれるため、貸主は安心して物件を貸し出すことができます。
| 代行してくれる主な手続き | メリット |
|---|---|
| 入居者募集 | リロケーションを希望する法人や個人のネットワークがあるため、一般的な賃貸募集よりも、迅速かつスムーズに借り手が見つかりやすいというメリットがあります。 また、質の高い入居者を選定してくれるため、トラブルのリスクを減らせます。 |
| 賃貸借契約書の作成 | 借地借家法に基づいた正確な契約書を専門家が作成します。これにより、契約内容の不備による無効リスクや、将来のトラブルにつながる法的リスクを未然に回避できます。 個人では見落としがちな条項や特約も適切に盛り込めます。 |
| 契約前の書面による事前説明 | 定期借家契約の有効要件である、借主への「契約更新がない」旨の書面説明を、専門家が確実に行います。 この手続きを怠ると契約が無効になり、普通借家契約と見なされるため、最も重要なプロセスのひとつです。 |
| 期間満了時の終了通知 | 法律で定められた「期間満了の1年前から6ヶ月前まで」という厳格な通知期間を正確に管理し、内容証明郵便など法的効力のある方法で通知を代行します。 これにより、「通知を受け取っていない」という借主からのトラブルを回避できます。 |
| 賃料の集金と送金 | 毎月の賃料集金や滞納時の督促を全て任せられます。貸主は安定した賃料収入を確実に受け取ることができ、滞納リスクや精神的な負担から解放されます。 |
| 物件の管理とトラブル対応 | 入居中の設備故障、近隣トラブル、騒音問題など、予期せぬ事態への対応を24時間体制で代行します。 これにより、遠方にいても安心して物件を任せることができ、入居者との直接的なやり取りによるストレスを軽減できます。 |
5-1.サービスを選ぶ際のポイント
多くのリロケーションサービスがありますが、あなたのニーズに合ったものを選ぶことが重要です。以下の点を参考に検討してみましょう。
- サポート範囲: どこまでを代行してくれるか(入居者募集のみか、賃貸管理まで一括か)。
- 実績と信頼性: 過去の成約実績や利用者の口コミ、会社の信頼性を確認する。
- 料金体系: 初期費用や管理手数料が明確か。
面倒な手続きや法的な不安を解消し、あなたのライフプランに合わせた最適な賃貸経営を実現するために、まずは専門のリロケーションサービスに相談することをおすすめします。
6.【Q&A】定期借家契約に関するよくある質問
定期借家契約に関して、貸主の方がよく疑問に思う点をQ&A形式で解説します。契約時の不安を解消し、スムーズな賃貸経営に役立ててください。
6-1.Q1: 契約期間の途中でも借主を退去させることはできますか?
定期借家契約は、原則として貸主からの中途解約は認められていません。法律上、契約期間中は借主の居住権が保護されるため、貸主の都合だけで退去させることはできません。
ただし、中途解約に関する特約を事前に契約書に盛り込んでおくことで、特定のやむを得ない事情が発生した場合に、借主との合意の上で解約できる可能性があります。
また、借主が賃料を滞納するなどの契約違反があった場合には、契約解除を求めることも可能です。
6-2.Q2: 期間満了時に借主が退去してくれない場合はどうなりますか?
定期借家契約は期間満了で契約が終了するため、借主には物件を明け渡す義務があります。
しかし、万が一借主が退去を拒否した場合は、まずは書面で退去を再度催促します。それでも退去しない場合は、訴訟など法的な手続きが必要になる可能性があります。
このような事態を避けるためにも、契約書の内容を明確にし、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、内容証明郵便で「終了通知」を送付することが極めて重要です。この事前通知を怠ると、貸主側の主張が認められにくくなるリスクがあります。
6-3.Q3: 再契約しなかった場合、立ち退き料を支払う必要はありますか?
立ち退き料を支払う必要はありません。これは普通借家契約との最も大きな違いであり、定期借家契約の最大のメリットの一つです。
定期借家契約は、期間満了をもって契約が終了することが法律で定められているため、貸主には立ち退き料の支払い義務は生じません。貸主は、立ち退きに関する費用負担の心配なく、安心して賃貸経営を行えます。
6-4.Q4: 契約期間満了後、物件を再度貸し出すことはできますか?
可能です。期間満了後、物件を再度貸し出したい場合は、借主が退去した後に、新たな借主と改めて定期借家契約を締結します。
ただし、借主との間で再契約の合意ができた場合は、同じ借主と再度賃貸借契約を結ぶこともできます。この場合、以前の契約は一度終了し、新たな契約が開始されます。
6-5.Q5: 定期借家契約の手続きが面倒です。代行してくれるサービスはありますか?
賃貸管理会社や専門のサービスに委託することで、面倒な手続きから物件管理まで全て任せることが可能です。
不動産会社の中には、定期借家契約の締結手続きに精通した専門部署を持っているところもあります。このようなサービスを利用すれば、法律で定められた厳格な手続きも漏れなく行ってもらえます。
契約書作成や終了通知、物件の入居者募集、入居後の賃貸管理まで、安心して専門家に任せ、手間をかけずに安定した賃貸経営を実現できるでしょう。
まとめ|定期借家契約で安心して物件を貸し出すという選択
この記事では、定期借家契約が貸主にとってなぜ安心できる契約形態なのかを、そのメリットとデメリット、そして具体的な手続き方法に焦点を当てて解説しました。
普通借家契約とは異なり、定期借家契約は「期間満了で確実に終了する」「立ち退き料が不要」「再契約の主導権を貸主が握れる」という3つの大きなメリットがあります。これにより、将来的にご自身で物件を使用する予定がある方も、安心して賃貸経営を始めることが可能です。
一方で、定期借家契約には「入居者が見つかりにくい可能性」や、「法律で定められた厳格な手続き」という注意点もあります。しかし、賃料設定の工夫や専門家への相談によって、これらのデメリットを十分にカバーできます。
あなたの抱える「物件が戻らない」という不安は、定期借家契約という選択肢を知ることで解消されるでしょう。不動産管理会社に相談すれば、煩雑な手続きを任せて、物件の持つ価値を最大限に引き出し、安全な資産運用を実現できます。まずは、お気軽に専門家への相談から始めてみてはいかがでしょうか。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- リロケーションのメリット・デメリット
リロケーションのメリット・デメリットの関連記事

- 空き家を「普通借家ではなく定期借家」にすべき?メリット・デメリットを徹底比較 公開
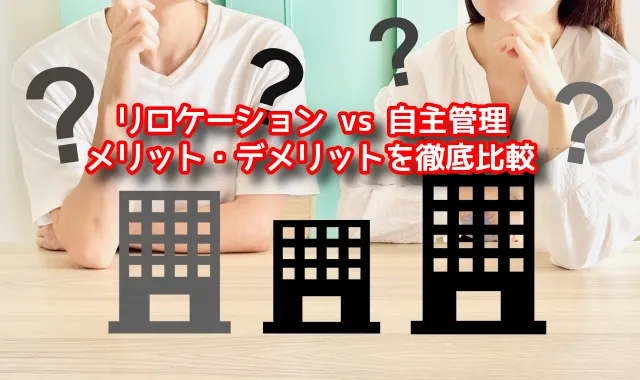
- 転勤時の最適な自宅管理の選び方 リロケーション vs 自主管理のメリット・デメリットを徹底比較 公開
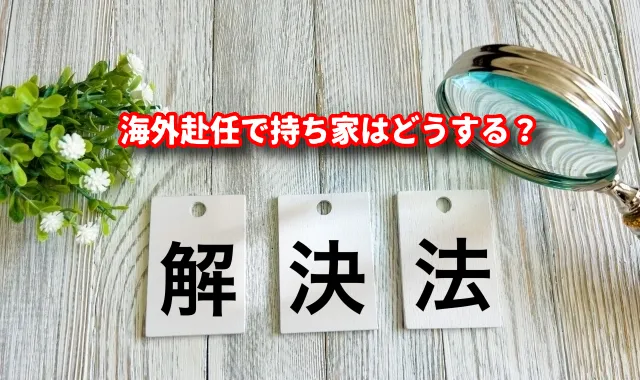
- 海外赴任で持ち家はどうする?売却・賃貸・空き家の最適解とリロケーション活用法 公開
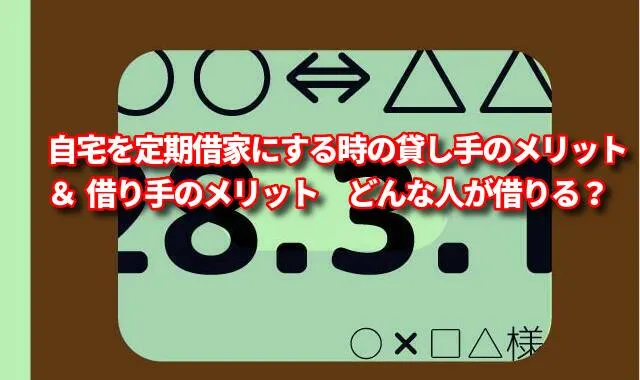
- 自宅を定期借家にする時の貸し手のメリットと借り手のメリット どんな人が借りるの? 公開
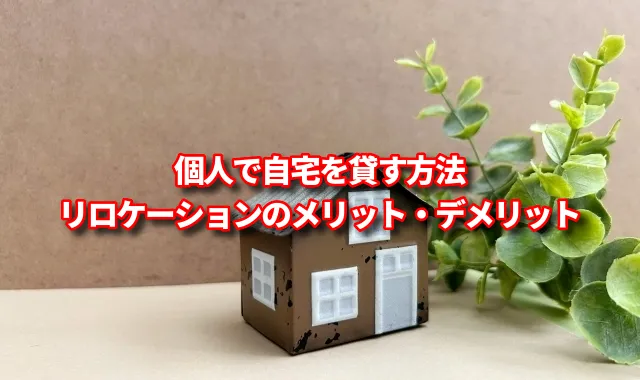
- 個人で自宅を貸す方法 リロケーションのメリット・デメリットとは? 公開
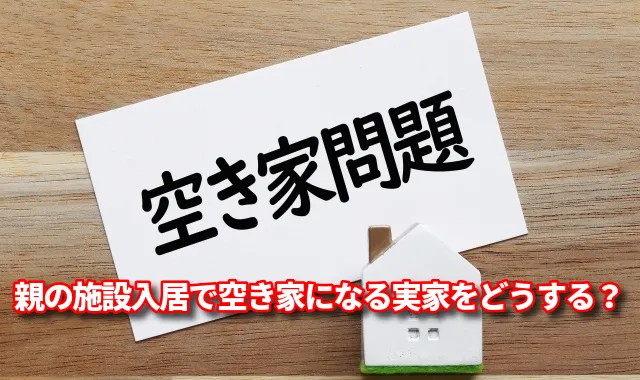
- 親の施設入居で空き家になる実家をどうする?リロケーションサービスで空き家問題と施設費用を同時に解決 公開
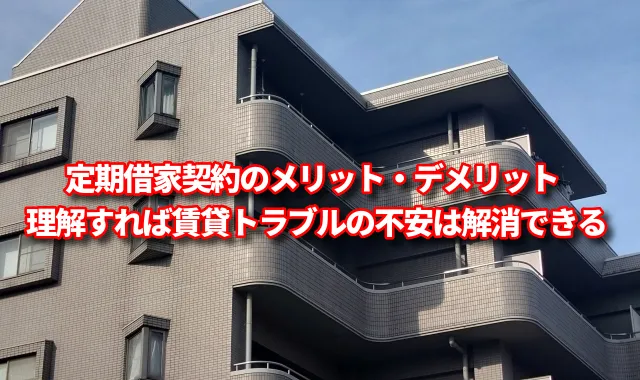
- 【貸主必見】定期借家契約のメリット・デメリットを理解すれば賃貸トラブルの不安は解消できる 公開
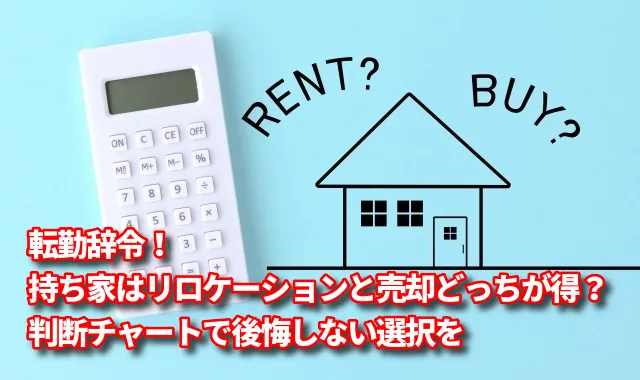
- 転勤辞令!持ち家はリロケーションと売却どっちが得?判断チャートで後悔しない選択を 公開
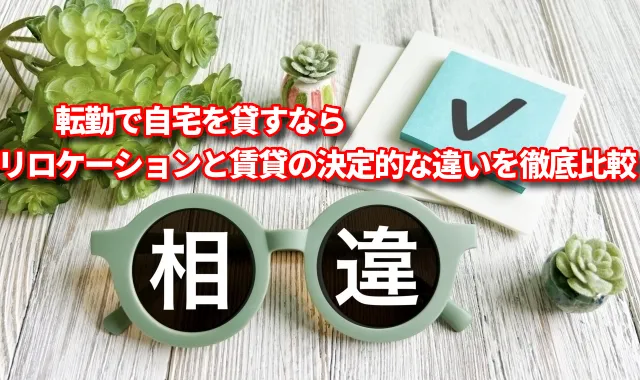
- 転勤で自宅を貸すなら リロケーションと賃貸の決定的な違いを徹底比較 公開

- 【徹底比較】転勤で自宅を貸すならどっち?リロケーションとサブリースの違い 公開
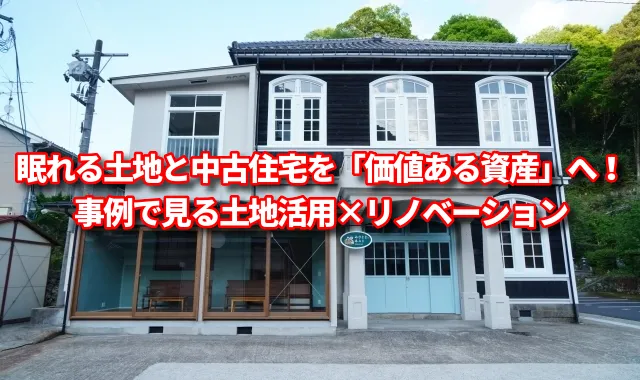
- 眠れる土地と中古住宅を「価値ある資産」へ!事例で見る土地活用×リノベーション 公開

- 自宅を貸すときの管理はどこまで頼める?留守宅の賃貸管理サービス徹底解説 公開

- 海外赴任中の持ち家をどうする?安心・高収益で貸す方法と注意点 公開