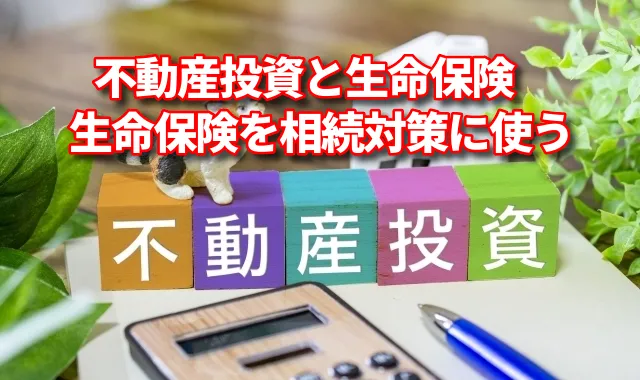- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 土地活用・賃貸経営
- FAQーよくあるご質問ー
- 【イエカレ】不動産投資で使える生命保険|相続対策に効果的な活用法を解説
【イエカレ】不動産投資で使える生命保険|相続対策に効果的な活用法を解説
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.不動産投資には団体信用生命保険の加入が必要
金融機関からの融資を受けて不動産投資をする際、団体信用生命保険に加入できる場合があります。
団体信用生命保険では、金融機関が保険料を支払います。投資家に万が一のことがあったときには、保険金で融資金を回収する仕組みです。死亡保障の保険料は無料、3大疾病などの特約の保険料はローン金利に上乗せとなることが一般的です。
投資家に万が一のことがあった際に、残された物件と債務は遺族に引き継がれます。しかし、遺族が相続放棄する可能性もあるため、金融機関にとっての保険として成り立っているのです。
この記事を読みながら、もし、「うちも何か活用できるかも?」と感じた方は、
一括資料請求でまずは情報を取り寄せてみましょう。思わぬヒントや好条件が見つかるかもしれません。
どなたでもかんたん!資料請求(無料)2.団体信用生命保険でローンを完済できる
団体信用生命保険に加入して融資を受けると、一家の大黒柱にもしものことがあっても、ローンを完済できます。
つまり、生命保険の死亡保障の代わりに、借金のなくなった物件と月々の家賃収入を残せるのです。
家族に資産を残すために不動産投資を考えたとき、融資の完済前に自分にもしものことがあっては、残された家族が心配です。
団体信用生命保険に加入すれば、家族に借金を残すことがなくなるため、投資リスクをおさえられます。
また、多額の融資を受ける不動産投資に対して、家族が反対している場合にも、説得する材料となります。
3.団体信用生命保険と通常の生命保険との違い
通常の生命保険と団体信用生命保険を比べると、現物資産を残すか、現金を残すかの違いがあります。
| 団体信用生命保険 | |
|---|---|
| 契約期間 | 融資完済まで |
| 死亡時の保障内容 | 残債を金融機関へ支払い |
| 家族に遺す資産 | 不動産と家賃収入 |
| 生命保険 | |
|---|---|
| 契約期間 | 終身か定期 |
| 死亡時の保障内容 | 契約した保険金 |
| 家族に遺す資産 | 現金 |
団体信用生命保険に加入すれば、家賃収入と返済金額の差額が、実質的な保険料と考えられます。
返済金額と同等の家賃収入が見込める物件を探せば、保険料をおさえることが可能です。
ただし、家賃収入だけでは毎月の生活費はまかなえない可能性があります。
収支のバランスを考えて、生活費が足りないようであれば、追加で生命保険に加入することをおすすめします。
4.相続対策で不動産投資を行うメリット
不動産投資を生命保険の代わりに利用したときに、相続対策はどうなるのでしょうか。
不動産投資の相続上のメリットをご紹介します。
4-1.相続後、売却益や家賃収入が得られる
不動産投資の相続上のメリットは、相続後に売却益や家賃収入が得られることです。
マンションの価格は上昇傾向にあり、価値の高い資産といえます。額面通りの価値以上に、毎月の家賃収入も得られる不動産経営は家族に残す資産としておすすめです。
4-2.相続税を節税できる
相続対策としての不動産投資には、相続税を通常よりも節税できるメリットがあります。
なぜなら、相続税の計算に使われる相続税評価額は、不動産の時価よりも低くおさえられているからです。
相続税評価額において、建物は時価の約7割程度、土地は時価の約8割程度の価値とされています。
また、小規模宅地等の特例が適用されれば、貸家が建つ土地の相続税評価額は時価の5割まで減額されます。
相続財産が現金のみであれば、相続税評価額は額面通りであり、減額はされません。
相続税の節税対策をするなら、不動産投資は有効な手段です。
5.不動産投資のデメリット(注意点)
投資には、リスクが伴います。不動産ならではの注意点を理解したうえで、不動産投資を検討してください。
5-1.運営コストがかかる
不動産経営には、運営コストがかかります。
賃貸物件を所有すると、入居者募集や入居者との契約、家賃の確認や督促などさまざまな作業が発生します。これらの作業は管理会社への委託が一般的です。そのため、管理会社に支払う管理費用が発生します。
また、物件を所有することで固定資産税もかかります。他にも設備や部屋の修繕費用、退去後の原状回復費用なども必要です。
空室が埋まらなければ、入居者募集の広告費用がかかる可能性もあります。
5-2.運営にはリスクが伴う
不動産投資には、リスクが伴います。
賃貸物件は、入居者がいなければ収益をあげられません。築年数が増すことで、老朽化により入居者が集まらなくなる可能性があります。
他人に貸すことで、物件の破損や、設備故障など入居者クレームに起因するコストのリスクも生まれます。
また不動産は、売却しにくい資産です。価格が高く、売却したいタイミングで買い手が見つからないこともあり得ます。
他にも、不動産自体の価格が下落し、資産価値が下がる可能性もあります。
リスクを理解した上で、不動産投資を検討しましょう。
6.相続における不動産投資のデメリット(注意点)
不動産投資には、相続の観点から見るとトラブルに発展しやすい面があります。ポイントを理解して、家族に負担をかけない方法を事前に検討しましょう。
6-1.不動産の分割でもめやすい
不動産は、分割しにくい資産です。
現金であれば、額面通りの金額を平等に分けられます。しかし、不動産は簡単に分けられないため、相続人同士で争いになる可能性があります。
特に、残された現金が少ない場合には、不動産の権利の取り合いになるでしょう。
争いを避けるには、子どもが2人であれば、同じ条件の不動産を2つ所有するという工夫が必要です。もしくは、不動産と現金を同じ程度残し、分割方法で揉めないように公正証書遺言を作成しておきます。
不動産だけを残すと、相続税の支払いに困る可能性があります。相続税が支払えるだけの現金も平等に残す工夫が必要です。
6-2.手続きが負担になる
不動産の相続手続きは、現金に比べて複雑です。現金とは違って、相続する不動産の価値を確認する必要があります。
不動産会社に物件の査定を依頼し、価格が確定してから遺産分割の協議を行います。この際、分割しやすい状態になっていなければ、遺産分割協議がまとまりません。
不動産管理の手間を避けるため、相続人のすべてが不動産の相続を放棄する可能性もあります。その場合は、不動産を売却する手間がかかります。
不動産の相続人が決まっているときも、手続きは必要です。必要書類を揃えて法務局にて登記変更する必要があります。
7.不動産と生命保険を併せて相続対策を行う方法
不動産相続には、分割しにくさによるデメリットが存在します。そのため、事前に遺産分割しやすい状況にしておくと、相続によるトラブルを防げます。
また、不動産は現金化しにくいため、相続税分の現金を残すことも重要です。このような場合、不動産の相続トラブル防止に生命保険の活用を考えると良いでしょう。
つまり、「不動産と現金資産のバランスを重視した資産運用」を心掛けるべきなのです。
その一例として、以下では「不動産」と「生命保険」を”合わせワザ”にして「相続対策を行う方法」をご紹介します!
7-1.家族の状況
自宅を所有し、賃貸用マンションを経営する夫と、妻、長男、長女、次女の5人家族のケースを想定し、シミュレーションします。
賃貸用マンションのローンは残っていますが、団体信用生命保険に加入しています。賃貸用マンションは、マンション経営を手伝っている長男に任せるつもりです。生活基盤としての自宅は、妻に相続させたいと考えています。
7-2.資産の状況
資産状況をまとめます。
自宅:4,500万円相当
賃貸用マンション:3,500万円相当
預貯金:1,000万円
不動産と預貯金をあわせて、9,000万円相当の資産があります。 通常の遺産分割であれば、妻に4,500万円、長男、長女、次女にそれぞれ1,500万円ずつ配分する内容です。
遺言状を作成し、妻に自宅を、長男にマンションを相続させる場合には、預貯金の1,000万円のみを長女、次女の2人で500万円ずつ分けます。
しかし、長女と次女には遺言に左右されない遺留分を請求する権利があり、その額は各自750万円です。
7-3.相続の結果
遺留分が請求された場合、通常よりも多く相続している長男が支払う必要があります。しかし、相続した資産は不動産のみのため、現金を用意できません。
このようなケースでは、不動産のほかに長男に生命保険金を残すと問題を解決できます。生命保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割する必要はありません。
また、生命保険金には、法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。今回のケースでは、4人の相続人がいるため、2,000万円までが非課税枠です。
長男には2人へ支払う遺留分と、不動産の相続税をまかなえるだけの生命保険金を残すと、金銭的な問題を解決できます。
8.ご注意事項ー相続対策で生命保険を活用するなら、必ず保険の専門家へ相談しましょう!
生命保険は専門性が高いため、取り扱いや説明には資格が必要です。現在では、資格を持つライフプランナーが顧客のライフプランに寄り添いながら、最適な保険内容を提案するのが一般的になっています。
かつてのように一方的に保険加入を迫られる時代ではなく、顧客の家計状況や将来設計に基づき、オーダーメイドでプランを組み立てられるのが大きな特徴です。
特に相続対策として生命保険を活用する場合には、信頼できるファイナンシャルプランナー(FP)や保険代理店をパートナーに選ぶことが重要です。分かりにくい制度や保障内容も丁寧に説明してくれ、家計診断から将来を見据えた資金計画までサポートしてもらえれば、納得のいく保険選びにつながるでしょう。
生命保険は「相続対策」と「ライフプラン」を結びつける有効な手段です。信頼できる専門家と出会い、自分に合った最適なプランを検討してみてください。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- FAQーよくあるご質問ー
FAQーよくあるご質問ーの関連記事
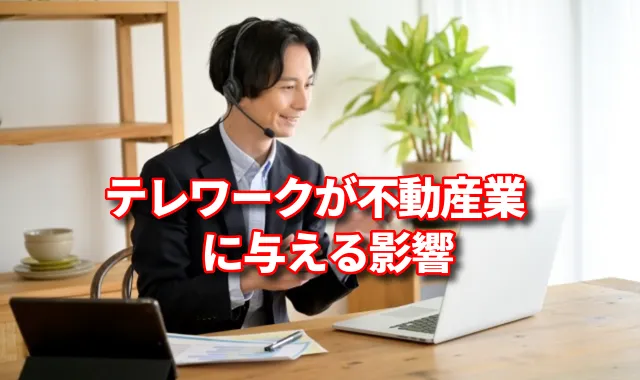
- リモートワークで変わるアパート経営|郊外ニーズが高まる理由と成功のポイント 公開

- 中国不動産バブル崩壊が日本に与える影響とは|投資家が知っておくべきポイント 公開
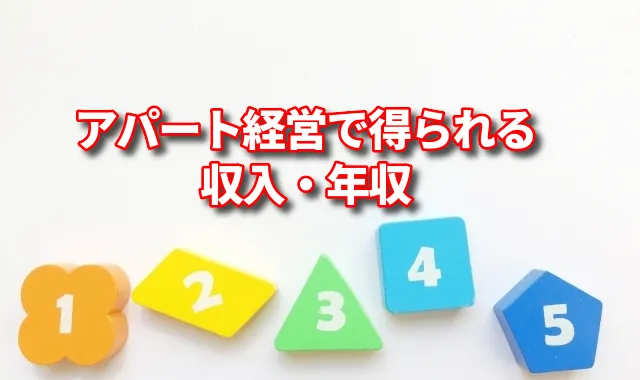
- アパート経営の年収相場と収支内訳|収入の実態と税金まで徹底解説 公開
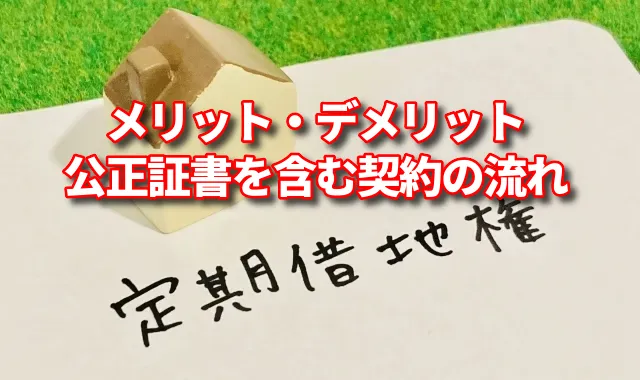
- 土地を貸して有効活用をしたい方へ|事業用定期借地権のメリット・デメリットを解説 公開
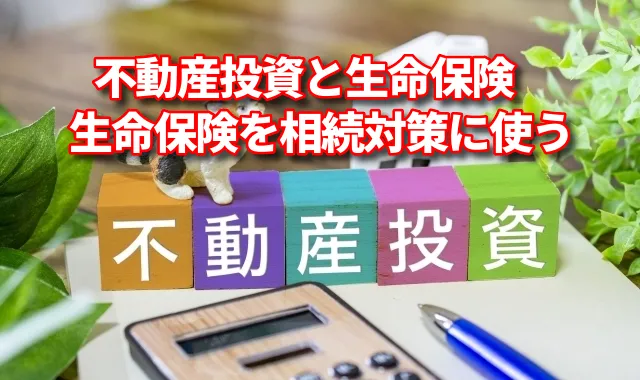
- 不動産投資で使える生命保険|相続対策に効果的な活用法を解説 公開
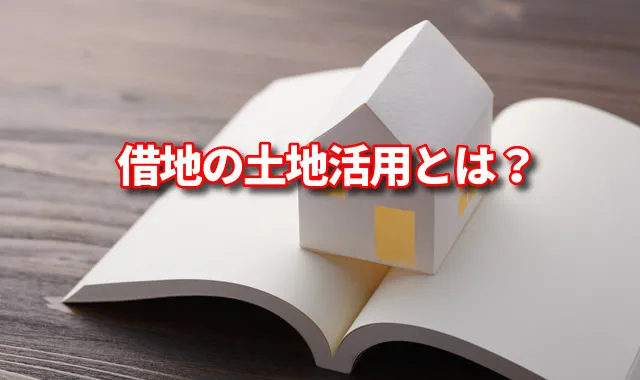
- 借地で賢く土地活用|地代相場と定期借地権メリットを徹底解説 公開
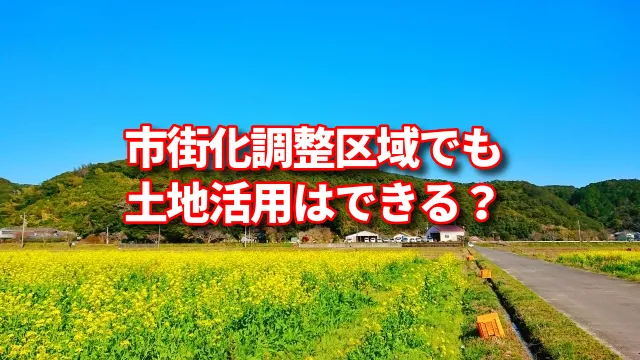
- 市街化調整区域でもあきらめない!土地活用の可否と実現のポイントとは 公開

- アパート建築費用の相場はいくら?|坪単価・自己資金・会社選びをやさしく解説 公開

- 30坪の狭小地はこう活かす!失敗しない土地活用アイデア9選 公開
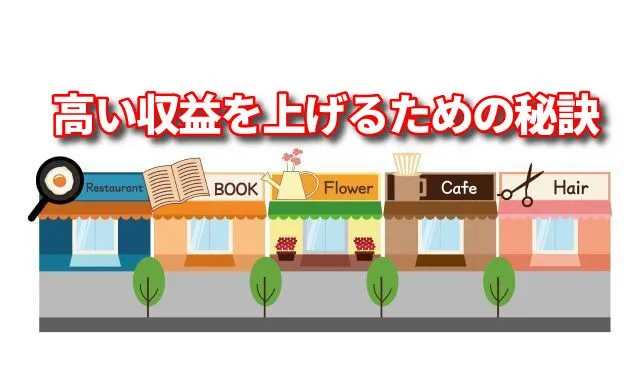
- 商業施設経営をする時の気になる費用を紹介|高収益を上げるコツも解説 公開

- アパート建築会社と管理会社の比較ポイント|選び方を解説 公開