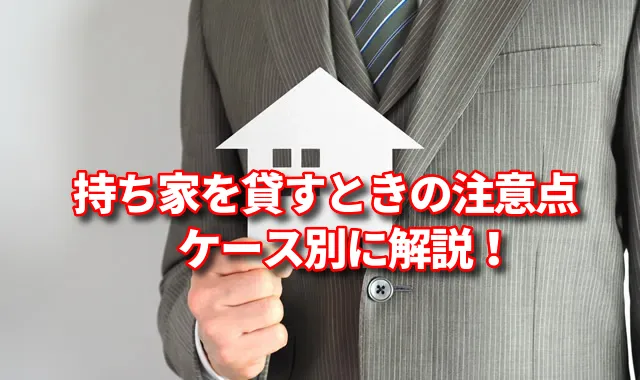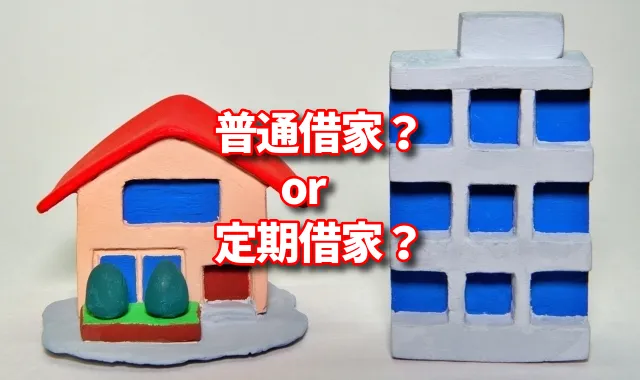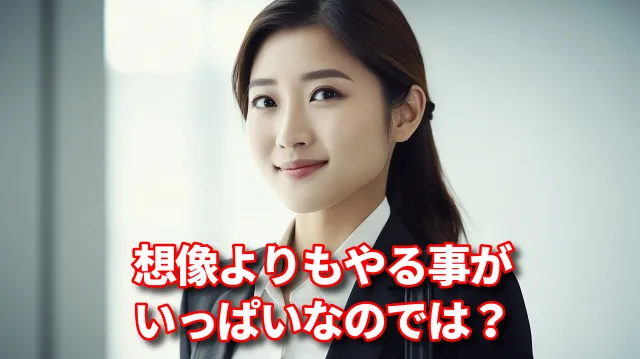- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- リロケーション
- 家を貸す際に注意すべきこと
- 【家を貸す】初心者必見!持ち家を貸し出すときの注意点をケース別に詳細に解説します【イエカレ】
【家を貸す】初心者必見!持ち家を貸し出すときの注意点をケース別に詳細に解説します【イエカレ】
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.家に戻れなくなることも!?契約内容は細かくチェック!
もし、あなたが急な転勤を命じられて、ご所有の自宅を貸して賃料収入を得ることにした場合は、家の貸主(物件オーナー)となるため、その家に住んでくれる借主(入居者)との間で「賃貸借契約」を締結することになります。
賃貸借契約とは、民法第601条に定められている法律で、そこには「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた者を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」と記載されています。
つまり、家を貸すにあたっては、貸主になるあなたは、借主と「敷金」「礼金」「賃料」など金銭面のことについて、しっかりと契約書に基づいてチェックを行い、事前に借主の同意を得る必要があります。
賃貸借契約の中では、それ以外の項目についても様々な重要な注意点がありますので、早速、以下でいっしょに確認をして行きましょう。
1-1.普通借家なのか、定期借家なのか
家を貸す場合、借主と結ぶ契約形態には「定期借家」と「普通借家」の2種類があります。
これらは、借主に対してあなたの家に「住める期間」を取り決めるものになりますから、どちらを選択するか?は、あなたにとっても大変重要なことになります。
まず「定期借家」から解説しましょう。
定期借家は、借主との契約期間満了=契約終了となり、契約更新を必要としない契約形態です。
例えるなら、使用可能期限が設定されている電車やバスの「定期券」の定期と同じ意味合いです。将来、借主との契約期間が満了になると「再契約はできない」と厳格に取り決めする場合もあります。
これに対して「普通借家」はどうでしょうか?
この契約形態は極めて一般的な契約形態で、借主との間で「契約の更新が可能なことを前提」に取り交わす契約形態です。
契約で取り決めた契約期間が満了した場合でも、借主から事前に「契約を更新してそのまま住み続けたい」という意思表示があった場合、貸主は「正当な事由がない限り」貸主側から借主に対して契約更新を拒絶することはできないことになっています。
では、転勤のように決まった期間だけ自宅を空けることになり、一時的にその期間だけ家を賃貸物件として貸したい場合、貸主となるあなたはどちらの契約形態を選択するのが適切でしょうか?
「将来、転勤期間が終了した後は、その家に戻って暮らしたい」と希望しているなら定期借家を選択するのが適切となります。
ではもう一つ。上記と同じく「将来、転勤期間が終了した後は、その家に戻って暮らしたい」と希望している前提で、もし普通借家を選択して借主と契約をしていた場合どうなるでしょうか?
将来、転勤期間が終わり、いざ自分の家に戻りたいと思った時、借主から「契約を更新してまだ住み続けたいのですが…」と言われてしまえば、自分が自分の家に戻ることができないという笑い話にもならないオチが待ち受けることになります。
このように、契約形態を決めるときは、貸主のあなたが「どのくらいの期間自分の家を貸したいのか?」を明確にした上で、普通借家なのか?定期借家なのか?契約形態を選択するようにしましょう。
1-2.原状回復に関する取り決めについても確認
これは契約満了に伴って借主である入居者が、あなたの家から退去する場合の話しです。
借主が退去した際は、あなたの家の「原状回復」をしたいと思うでしょう。
なぜこの件について入居契約の段階でしっかりと詰めておく必要があるのかと言えば、この原状回復をめぐっては「費用面」や「家の状態をどの状態まで戻すのか?」といったことについて、事前に借主と細かく取り決めをしておかないと、将来、借主が退去する時にトラブルになりやすい項目だからです。
また、こうした項目をしっかりと詰めておくことで、借主の頭のなかで「(あなたの)家を大事に取り扱おう」という意識が芽生える効果があります。そのため、賃貸借契約を交わす際は、以下の点についてしっかり確認しておきましょう。
- 原状回復にかかる費用は誰が負担するのか
- 費用の負担割合
- 原状回復を求めるレベル
退去後のトラブル予防のために、貸す前の家全体の状態などを確認しておき、画像などで記録に残したうえで、借主と共有しておくことも有効でしょう。
2.賃貸事業はやることがたくさん!?管理業務を確認
家を貸す上での考え方の点でご注意頂きたいこともあります。転勤などで自宅をしばらく空けざるを得ず、一時的に人に貸す場合、人によっては「まぁ、一時的に人に貸すだけだから!」と賃貸借について簡単に考えてしまう方が少なからずいるものです。
何となく分かる気もするのですが、たとえそれが自宅であっても、他人に賃貸をして家賃収入を得ることになれば、それは立派な賃貸経営という「事業」になります。
敷金や礼金、毎月の賃料を借主から頂いて家を貸す以上は、借主が心地よく定住できるようにしっかりとした家の「管理業務」を行う必要が出てしまいます。
また、そうした意識を大事にすることによって、貸主であるあなたにも安定した賃貸収入が入ってくるようになるわけです。
ここで大切なポイントは、せっかくの家を手放すことなく、賃料収入を得ることが出来る訳ですから、家を貸すときは「どういう管理業務を誰が行うのか?」を計画して準備をすることです。
家を賃貸している方々が行っている賃貸事業の管理業務には以下の内容があります。
項目が、非常に多岐に渡りますが、これらも大変重要ですからしっかり確認しておきましょう。
2-1.入居者管理
まず一つ目が「入居者管理」です。これには主に以下の内容があります。
- 入居者の募集
- 賃貸借契約
- 家賃の回収
- トラブルやクレームへの対応
- 入退去の管理
以上5つになります。
こうした項目の中には、ご自身でできることもあるかもしれませんが、基本的には専門知識や経験、蓄積された業務ノウハウが必要になることが多いため、特に「入居者募集」や「賃貸借契約の締結」については「不動産仲介会社」、その他の項目は「管理会社」に委託管理を依頼している貸主が大多数です。
それぞれをもっと掘り下げて解説します。詳しく見ていきましょう。
2-1-1.入居者の募集
家を貸し出す場合、まずは何と言っても自分の希望に叶う質の良い入居者を募集する必要があります。
貸主となる物件オーナー様は、不動産仲介会社と契約して入居者を斡旋仲介してもらうと、効率的にそうした入居者を早く見つけることができます。
その際に大事なポイントが以下の2点になります。
- 不動産仲介会社に依頼をして、貸し出す物件の詳細を伝える
- 賃貸として出す条件を不動産仲介会社と取り決める
不動産管理会社へ入居者の募集を含めた委託管理を依頼すれば、一気通貫で、物件の広告宣伝や入居希望者の内見対応といった業務をすべて行ってもらえます。
2-1-2.賃貸借契約
冒頭でもお伝えしましたが、入居希望者が見つかり、借主として入居をしてもらえることになったら、その入居希望者と賃貸借契約を締結します。
上述した通り、賃貸借契約には、借主の契約更新方法を定めた「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
「普通借家契約」は、特に契約期間の定めがない契約であることはお伝えしましたが、一般的な契約期間は1~2年(一般的には2年が多い)です。
その契約期間が満了した後は、借主から事前に退去希望が無い限りは自動更新となります。
その際、正当な事由がない限り、貸主から一方的に契約を解除、契約の更新を拒否することはできませんので、あらかじめ理解をしておきましょう。
一方「定期借家契約」は、電車やバスの「定期券」と同じ意味合いで、借主がその賃貸物件に住める一定の契約期間を定めた内容だと上述しました。
普通借家契約と違い、契約満了の期日を迎えれば自動更新はありません。契約期間が終了した時点で、借主は貸主に家を明け渡して退去をする必要があります。
定期借家契約の契約期間については、原則的には物件オーナー様である貸主が任意で定めることが可能です。
ただ、不動産管理会社へ委託管理を依頼する場合、契約期間が短いと、会社によっては委託管理の取り扱いができないと言う会社もありますので、委託管理候補としてピックアップした会社ごとによく確認をした方がよいでしょう。
一般的には定期借家契約を「2年未満」で希望した場合、その取り扱いをしていない企業が多いようです。
2-1-3.家賃の回収
借主からの家賃回収についてです。この業務は、基本的には貸主が行います。
家賃については、毎月支払日にしっかり払ってくれる借主もいれば、理由は様々で予測ができないことですが、借主の経済状況が突然悪化してしまい、支払いが滞ったり、もっと経済的に苦しくなってしまうと家賃を滞納する借主が出てしまうことが考えられます。
借主への支払い督促は、時として感情が絡む難しい問題になるケースもあります。
借主が滞納している家賃の早期支払いに応じてくれるように、上手に督促をするノウハウが必要です。
しかし、貸主自らがこれを行うのは精神的にキツイ面が出てくるものです。
この家賃回収も、管理会社へ委託管理を依頼すれば、貸主自身で行うことはなく管理会社が家賃回収を代行して行い、貸主へ入金をしてくれます。
また、貸主の家賃滞納について補足になりますが、借主が「支払う意思」を見せていれば、1,2ヶ月程度の滞納では退去をしてもらうことは難しいです。
ただ、もっと長期で滞納をする借主に対して取れる法的手段としては「契約解除」「差し押さえ」「明け渡し請求」のいずれかになります。
これを実行する時は、まず前段として「家賃滞納が続いていることを証明する書類」が必要になります。
家賃滞納を行う借主へいきなり退去を伝えるのではなく、まず先に「内容証明」を家賃滞納している借主へ送付をしましょう。
そうした書面で伝えても支払いに応じてもらえない場合は「訴訟」という強い方法で対応することにもなります。
2-1-4.トラブルやクレームへの対応
これも非常に重要な管理業務になります。なぜなら、借主からのトラブルやクレームに対してタイムリーに適切な処理対応ができないと、最悪、退去をされてしまうことがあるからです。
せっかく入居をしてくれた借主の怒りを買ってしまい退去をされてしまうと、家は空室となり、その期間は貸主への家賃収入が途絶えてしまいます。
空室がすぐに別の入居希望者で埋まれば良いですが、空室期間が長引くことになると、あらたな募集広告に費用が掛かったり、当初想定していた収支計画にも悪影響が出てしまいます。
トラブルやクレームには「建物の不具合や設備故障に対する修理要請」、また、貸し出している家が分譲マンションだった場合は、同じ物件内で起こる「入居者同士のトラブル」「近隣の住民からクレーム」など様々なケースが想定されます。
こうしたクレーム対応処理を、貸主本人が対応するのは現実的ではありません。
ケース毎に適切な対応方法がありますから、これも管理業務を取り扱う管理会社へ相談の上で委託管理を依頼すれば、貸主の意向を確認した上で、管理会社がすべて適切に対応をしてくれます。
とはいえ、不測のトラブルならまだしも、借主からのクレームについては、クレームが発生しないように事前対策をしておくが大前提にはなります。
思わぬことが原因でクレームに発展する場合もあるものですが、管理会社に委託管理を依頼する場合は、管理会社にクレームが起こった場合の基本対処法を事前相談しておいた上で、適切な初期対応を行ってもらえるよう打合せておきましょう。
また万が一クレームが発生した場合は、管理会社と一緒に再発防止ができるように対策をしましょう。
2-1-5.入退去の管理
借主(入居者)の入退去時は「修繕」「ハウスクリーニング」が必要になります。とくに退去後に以下のような場合は原状回復する必要があります。
- 床や壁の傷や汚れ
- カビやシミ
- たばこなどによる匂いや汚れ
- トイレやキッチンなどの水回りの汚れ など
次の入居希望者に気持ちよく家を内見してもらい、入居を決めてもらったあとも気持ちよく家に住んでもらえるように、原状回復のための修繕やハウスクリーニングを行うことは重要な管理業務です。
また、これは補足になるのですが、借主が退去した後にリノベーションやリフォームを実施する場合は、その間空室が続くと家賃収入が途絶えることになりますので、家のどこをリノベーションやリフォームをする必要があるのか、収支もあわせて検討したうえで、無理のない範囲で、費用や工事期間を決定するようにしましょう。
2-2.物件管理
物件管理についても、貸主自身で管理することができますが、管理会社に委託管理を依頼するのが一般的ですし、その方が安全です。
主な物件管理の項目は以下の3つです。
- 建物の清掃
- 建物の修繕
- 設備のメンテナンスや修理
以上3つです。
地味に思える項目だと思われた方も多いかもしれませんが、これらは意外と重要な項目ばかりです。
以下でさらに補足解説をします。
2-2-1.建物の清掃
建物の清掃は、管理会社に委託管理を依頼した場合は管理会社で行ってくれるようになります。
管理会社へ委託をしない場合は、貸主自身でそれを行うか、直接、専門の清掃業者へ依頼するのも方法のひとつです。
管理会社や清掃業者に清掃業務を依頼する時は、掃除の頻度、方法、料金について予め打合せて確認をしておきましょう。
建物の清掃が行き届いていないと、借主の入居者満足度に影響が出てしまいます。
また、空室となってしまい新たな入居者を募集していた場合は、入居希望者が内見に来てくれても清掃が行き届いていないと印象が悪くなってしまい、せっかくの入居希望者が別の物件へ流れてしまう可能性が十分考えられます。
そうなってしまいますと本当に勿体ない話しです。ですから、清潔感が漂う物件にしておくことが必要です。
2-2-2.建物の修繕
これも上述しましたが、家を賃貸物件として貸し出す場合、建物の経年劣化による破損等は、貸主や管理会社側に修繕義務があります。
建物の修繕項目としては、「屋根」「柱」「床」「内装」「設備」など入居者に貸している部分全てになります。
ただ、借主がそれらを壊してしまった場合は、当然、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済してもらうことになるか?の取り決めを入居契約時にしておくことは重要です。
2-2-3.設備のメンテナンスや修理
また、建物の修繕に加えて、家の設備のメンテナンス・修理も大家または管理会社が行う対象になります。
これらも管理会社に委託管理を依頼する場合は、設備・メンテナンスの実施範囲やその管理費用について事前に取り決めておく必要があります。
ただ、設備に関しても建物同様、借主が壊してしまった場合は、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、これに関してもまた、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済をしてもらうことになるか?この取り決めも入居契約時に詰めておくことが重要です。
2-3.経営管理
これも上述しました通り、家を賃貸物件として貸して賃料収入を得る行為は、賃貸経営という「事業」にあたることになるため、以下の経営管理も必要となってきます。
- 帳簿をつける
- 確定申告をする
- 税金などの支払いをする
以上3つです。家を貸して「収支が成り立つか?」といった収支計画の確認は最低限必要となります。
ここまでご覧いただいてお分かり頂けた部分も多いかと思いますが、家を貸すと、様々な管理業務が発生します。
そうした管理業務をすべてご自身で行うことは不可能に近いでしょう。
管理業務を不動産会社や管理会社に委託管理を依頼すると当然「管理委託料」が必要になるのですが、貸主の日常生活に支障が出ることなく、家の賃貸経営が問題なく回るのであれば、大多数の方は管理費を支払ってでも家を貸すことを選択していると言えます。
自分自身が家に住んでいたときは気にする機会が少なかった支出も、貸すときは把握する必要が出てきます。
では、家を貸す場合に想定される支出にはどういうものがあるのでしょうか?
家を貸す場合に想定される支出には、以下が挙げられます。
- 固定資産税、都市計画税
- 火災保険料
- 仲介手数料(不動産会社に仲介を委託する場合)
- 管理委託料(管理業務を管理会社に委託する場合)
- 清掃費用
- 原状回復費用
- 修繕費(積み立てておくのが一般的)
2-3-1.固定資産税
「固定資産税」とは、毎年1月1日時点で土地・建物などの固定資産を所有している人に対して課税される税金です。
賃貸オーナーも毎年固定資産税を支払う必要があります。家賃収入がゼロの場合でも支払い義務は発生しますので、固定資産税分は現金を確保しておくことが大切です。
2-3-2.都市計画税
「都市計画税」とは、土地・建物を所有している人に対して、都市計画や区画整理などの費用に充てるために課税される税金です。
固定資産税に含まれていることが多く、税率は市町村によって異なりますが、上限は0.3%となっています。所有している物件がある市町村に確認しておく必要があります。
2-3-3.火災保険料
賃貸経営に際して、物件のオーナー様向けの火災保険に加入することが一般的です。
保険料は保険会社や保険商品、物件の条件などで変動します。借家の大きさや、借家がある地域、借家となる建物の建物評価額などに基づいて保険料が設定されています。保険の設計プランによって異なりますが、火災だけでなく自然災害や落雷、爆発などさまざまな災害への保障が含まれていることが一般的です。
2-3-4.仲介手数料
不動産仲介会社に物件の客付けを依頼する場合は、仲介手数料を支払う必要があります。
賃貸物件の場合、「賃貸借契約」を締結した際に支払います。物件オーナー様が不動産仲介会社に支払う仲介手数料は会社によって異なりますが、原則「賃料の半月分が上限」と宅地建物取引業法で定められています。
ただし、別途広告費の支払いについて取り決めている場合は、広告費の支払が発生します。
2-3-5.管理委託料
管理委託料の上限は法律などで決まっていません。そのため、管理会社によって金額が異なります。
平均的な管理委託料の設定は3%~8%となっています。そのため、管理会社を選ぶ時は「管理委託料がいくらになるか?」を確認して契約しましょう。
2-3-6.清掃費用
物件オーナー様自身が清掃をする場合は、掃除道具や機器、洗剤等の調達費用のみかかります。
ただし、ご自身で清掃ができない範囲については、管理会社や清掃業者に依頼をする必要があります。
物件の規模にもよりますが、数万~数十万円の費用がかかるケースがあります。
2-3-7.原状回復費用
入居者(借主)の退去時には、部屋の傷や汚れを入居前の状態まで戻すための「原状回復工事」を行います。
この原状回復の費用については、入居者との間で取り決めておく必要があります。
▶原状回復費用の補てん方法
・賃貸借契約の際、退去時に入居者から支払ってもらう契約を取り決める
・入居時の敷金から原状回復費用を支払い、残った額を入居者に返金する
なお、敷金を超える原状回復費用がかかった場合、「修繕費として入居者に請求する」か、もしくは「オーナー様が自己負担するか」どうかについても取り決めておくと、入居者とのトラブルを回避できます。
2-3-8.修繕費
修繕費は、「物件オーナー様が負担する分」と「入居者が負担する分」の2種類があります。
入居者が故意に破損した場合でなければ、物件オ-ナー様が負担することが基本です。
「ベランダの防水工事」「外壁改修」「クッションフロア張り替え」などが挙げられます。修繕にかかる費用は使う材料や依頼する業者によって異なるため、依頼業者との契約時に必ず確認しましょう。
▶賃貸収入で支出をカバーするのが基本
入居者からは敷金や礼金も支払われますが、これはあくまで1回限りのもので、基本的には毎月の賃料が賃貸収入となります。
そして、家を貸す場合にかかる支出は、この賃貸収入によってカバーするのが基本です。
そのため、家を貸すときは慎重な収支計画を立て、委託する業務と自分で行う業務についても細かく決めていくようにしましょう。
また、賃料については「どれくらいの支出があるのか?」ということを慎重に考えた上で決めましょう。
以上、賃貸事業で必要になる管理業務を網羅してみました。
ご自身のなかで必要となりそうな項目があったら、今一度よく確認してみて頂ければと思います。
【イエカレ運営局より】
【完全無料/最大8社紹介】自宅を高額家賃でお得に貸したいなら!管理プランと管理費を徹底比較。
高い家賃で経費を抑えた賃貸管理、質の高い入居者紹介ができる不動産会社を比較・選択できます!
より高くなら、各社、無料訪問査定もご対応します。お気軽にお問い合わせください。
3.ケース特有の家を貸す注意点をご紹介
ここでは「全然知りませんでした...」では済まない、家を貸すときの注意点をいくつかご紹介します。
これらも重要なものばかりです。
3-1:賃貸で借りている家を貸す「又貸し」はNG
一つ目は「又貸し」です。これは貸主というより借主側の問題ですが、貸主である賃貸オーナー様にも知っておいて欲しい内容になります。
又貸しとは「賃貸物件を契約者自身で借りているにも関わらず、その契約者自身は入居をせずにさらに別の第三者に貸す行為」のことです。
つまり、借主が自分で借りた賃貸物件には住まずに別の第三者に貸して、借主が家賃収入を得る行為です。
住まずに物件を賃貸に出すことができるのは、基本的にその賃貸物件の「所有権を持つ名義人ご自身の場合のみ」です。
「又貸しが禁止の理由」と「発見された場合にどうなるか」も以下でご紹介します。
3-1-1.又貸しがNGの理由
賃貸物件を借りた借主が、第三者に又貸しをした場合、それが原因で何らかのトラブルが発生したときは「貸主である物件オーナー様」と「借主である契約者(本来の入居者)」の間に「又貸しで住んでいる第三者」が加わることになるため、話がこじれてしまい問題解決が難しくなることが非常に多いです。
借主は入居審査を経て入居契約を交わした上で貸主から物件を借りたわけですが、又貸しで住んでいる第三者は貸主と入居契約を交わしたわけではない全くの無関係者です。
これが許されてしまうと何でも有りの世界にもなってしまいます。もちろん、第三者に又貸しを行った借主は、無断でそのような行為を行った責任を問われることになります。
貸主に多大な迷惑が掛かるのはもちろん、借主にとってもいろんな意味でリスクが高くなるため原則禁止されています。
3-1-2.又貸しが万が一発見された場合
もしも又貸しが発見された場合は、その借主は貸主側から「強制退去」や「多額の違約金の支払いが求められる」ケースがあります。
場合によっては訴訟といった裁判沙汰へ発展することもあります。ですから、貸主は、借主と結ばれる賃貸借契約書に「又貸し禁止事項」の記載がしっかりされていることをよく確認しましょう。
「少しくらいいいや」と思ったモラルがなかった借主にこうした違反行為をされてしまうと想像以上に大きな問題に発展しやすいため、借主が安易に又貸しできないように必ず契約で縛っておく必要があります。「又貸し被害」にあわない様に十分注意したいものです。
3-2.自分の持ち家全体(一軒家)を貸す場合
一軒家を所有されている方の場合、急な転勤や相続などが原因で「一時的に転勤期間だけ家を賃貸物件と貸し出したい」ですとか「実家を相続したが、居住する家族はいないのでできれば売らずに長期間貸し出したい」と考えている方は少なくないでしょう。
この章では、一軒家を貸す場合、どのような注意点があるのか以下で詳しく解説しますので気になっている方は、是非、参考にしてください。
3-2-1.外壁や屋根など一軒家特有の修繕費
一軒家を貸している間、外壁や屋根などの建物の修繕が必要になった場合、その修繕費は貸主負担となります。
大事に住んでいたとしても、建物の外壁や屋根は築年数が経てば経つほど、どうしても経年劣化による老朽化は避けられません。
不具合をそのまま放置をしてしまうと物件の資産価値が大きく下がる可能性があります。
修繕は建物の維持費用と割り切ってあらかじめ収支計画に入れておきましょう。
3-2-2.災害のリスク
これは誰にも予測がつかないことですが、災害のリスクも考慮しておくことが必要です。
例えば、地震や台風で家の一部が倒壊、または全壊した場合、修繕費用は貸主が自己負担する必要があります。
また、借主が一時的に別の賃貸物件などへ避難してせざるを得なくなった場合はその間の家賃を借主に請求することはできません。
損害を最小限に留めるためもに、火災保険や地震保険などの各種損害保険に加入しておくのがよいでしょう。
3-2-2.防犯性や管理体制
一軒家を貸す場合は、借主に安心して住んでもらえる様に、民間のセキュリティ・サービスを利用することも考慮に入れましょう。
マンションやアパートの場合でしたら、その管理業務は管理会社に依頼する方が多いのですが、一軒家の場合は、貸主ご自身でその対応をされる方も見受けられます。
マンションやアパートは玄関のオートロックや防犯カメラが設置されている場合がもはや当たり前になっていますが、一軒家では貸主ご自身で防犯対策をする必要があります。
借主の万が一に備え、住む方の「安全性」や「防犯性」に考慮した対応が求められます。
ただ、こうした対応についても家の管理業務そのものを管理会社に依頼する場合は、管理会社の担当者へ相談をすれば対策を考えてくれるはずですので、一度問い合わせてみることをお勧めします。
3-3.自宅の一室を貸す(賃貸併用住宅)の場合
また、所有している自宅の「空き部屋」だけを貸す「賃貸併用住宅」という賃貸方法があります。
賃貸併用住宅として家を貸し出す場合の注意点は、以下となりますのでこちらもあわせて確認してみて下さい。
3-3-1.賃貸併用住宅の間取り
「賃貸併用住宅」は同じ家(建物)の一部のなかに賃貸用として貸し出せる部屋が併設されている賃貸物件となります。
貸主である物件オーナー様は借主と同じ建物内で生活をすることになるため、お互いのプライバシーが保護できる動線や視線に配慮した間取りにすることが大切です。
例えば、自宅・賃貸の玄関を別々することはもちろん、借主とできるだけ顔を合わせないように設計をするとお互いのプライバシーを保護しやすくなり生活がしやすくなります。
また、防音や騒音対策への配慮も重要です。貸主と借主では生活スタイルや活動時間に違いが出る場合も考えられます。
間取りや設備の配置で防音・騒音対策を考えましょう。
3-3-2.入居者との距離感
貸主と借主のお互いのプライバシー尊重と言う点でもう一つ。
賃貸併用住宅では貸主は借主との距離感を常に一定に保つことが必要です。
貸主と借主が同じ建物内で生活をしているなかで、段々とその距離が近づき過ぎるようになると、悪い意味で「馴れ合いの関係」になってしまうことがあり、それが原因でトラブルに発展してしまうことが考えられます。
貸主と借主がフレンドリーな関係でいることはもちろん重要ですし、貸主の運用方針やスタイルにもよりますが、借主とは近すぎず遠すぎず、お互いにとって程よい距離感を保てるように模索することが重要です。
3-4.マンション、アパートを貸す場合
次は、マンションやアパートの一室を不動産投資物件として購入をして、賃貸物件として貸し出すパターンでの注意点について説明します。
この場合は以下の注意点があります。
3-4-1.入居者同士のトラブル
マンションやアパートは集合住宅と言う性質上、入居者同士のトラブルが出てしまうことを忘れずに想定しておかなくてはなりません。
そのため、借主との入居契約時にトラブルが起こりそうな項目について取り決めをしておく必要があります。
また、借主からクレームが出たらすぐに対応・対策をすることが大切です。
これは補足説明ですが「マンションやアパート一棟」の賃貸オーナーとして貸し出す場合は、貸主が全ての借主に対して自主管理で管理業務の対応することは現実的には難しいため、尚更のこと、やはり管理業務を委託できる管理会社を選定する方が望ましいと言えるでしょう。
3-4-2.管理組合の参加
分譲マンションの場合、共用部分の維持管理や各入居者の生活マナーの維持についての取り決めや管理を行うために必ず「管理組合」が設けられています。
管理組合はマンションの住民で構成をされています。例えば、理事長の選任時や、定例会に参加するか・しないかで、組合員である他の住民とトラブルになったり、管理組合の総会で議決された取り決めを実行するときに他の住民から反対にあったりする可能性がつきものです。
分譲マンションを賃貸で家を貸すときには、貸主は管理組合の一員としての役割が発生することを覚えておきましょう。
まとめ
以上、自宅の部屋や持ち家を貸すときの注意点をケース別に解説してきました。
家を賃貸物件として貸し出しす場合の「チェックポイント」をしっかりと抑えておけば、トラブルを回避しやすくなりますし、安心・安全な賃貸経営が可能となるでしょう。
家を貸す場合、以下のような注意点があります。
・賃貸借契約の種類やその内容について、細かくチェックする
・管理業務にはどのようなものがあるのか、あらかじめ把握しておく
・慎重な収支計画を立てる
貸主ご自身ですべての管理を行うことはできませんし現実的ではありません。
不動産会社では、一時的に使わない家を活用する方法について相談に乗ってくれる専門の管理会社があります。
ご自身だけで判断するのが難しい場合は、ご自身の状況を踏まえて「こんな管理業務を委託したいが可能なのか?」といった形で希望を伝えた上で、管理会社の専門家の意見を仰いでみることを強くおすすめします。
また、家を賃貸に出すにあたって、何よりも大切にしてほしいポイントがあります。
それは管理業務に関する委託管理の相談を管理会社へ依頼する場合は、できる限り、すぐに一つの不動産会社と話を進めようとしてはいけないということです。
確かに「急な転勤」などで急ぐ場合や、不動産会社との交渉が複数社に及べば、面倒で時間も手間もかかります。
そうなると「もう早く決めてしまいたい」という心理から、最初に連絡が取った会社と話を進めてしまいがちです。
しかし、よく考えて頂きたいことは「家の委託管理を依頼する」ということは、あなたの大切な不動産の管理を第三者へ依託をして、いわばあなたの賃貸経営をサポートしてもらうということです。
結果的には多くのお金が動く商取引になりますし「あの時、焦らずにもっと慎重に委託管理先を探すべきだった...」と後から悔やまれてしまうのでは本当に残念な話しとなってしまいます。
あなたの家という財産の管理をしっかり任せられる実績と実力がある管理会社を探すべきです。
また、会社探しの上では、担当者と貸主との相性も重要だといわれます。
貸主の信頼にしっかり応えようと、些細なことにも迅速に丁寧な応対をする担当者との出会いが必要です。
トラブルが起きたら逃げ腰になるような担当者は論外です。複数社の会社へ問合せを行い、応対や態度などを観察すればだいたい分かるものです。
担当者の応対で少しでも気になる点があれば条件が良かったとしてもすぐに委託契約を交わさない方が吉ということもあり得ます。そうした担当者の質も含めて「良い条件で賃貸に出す」ことを何よりも優先すべきです。
最後に、比較検討する上では、他の会社の査定内容を探ってきたり、なぜか一社だけ飛びぬけて高い賃料を提示してきた場合も要注意です。
担当者が管理契約を取りたいがために、「高い賃料を提示している」という事情が隠れている場合があるかもしれません。そのような事情を見抜くためにも、やはり比較検討は必要です。
【イエカレより】「ご自宅を貸し出したい」「空き家にしたままよりも有効活用を検討したい」とお考えの方々に、ご自宅資産に合わせて留守宅管理専門の不動産管理会社をご紹介しています。一度のご登録で、最高8社の管理会社へ家賃査定依頼が可能です!ご利用は無料です。
各社、訪問査定も対応しています!大切なご自宅資産を丁寧に査定、直接ご希望もお伺いして高額査定を目指します!入居者仲介方法、管理代行・保証内容など、各社の提案を比較できますので、お留守の間、安心してお頂け頂ける不動産会社をお選びいただけます。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部
【イエカレ】では、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
(コラム・アドバイザー)檜垣 知宏

株式会社ライフアドバンス代表取締役の檜垣知宏です。 2014年8月に設立し、恵比寿不動産という屋号で賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理を行う不動産業者です。 不動産業界歴15年の経験を生かし、 運営しているサービスサイトである「不動産の相談窓口」の運営者も務めております。
【保有資格】宅地建物取引士
【関連URL】
[恵比寿不動産×賃貸]
[恵比寿不動産×売買]
[恵比寿不動産×リフォーム]
[不動産の相談窓口]
[資産運用の相談窓口]
[転勤東京.com]
[LGBT不動産]
[賃貸管理ナビ]
[ライフアドバンス]
Copyright (C) EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 家を貸す際に注意すべきこと
家を貸す際に注意すべきことの関連記事
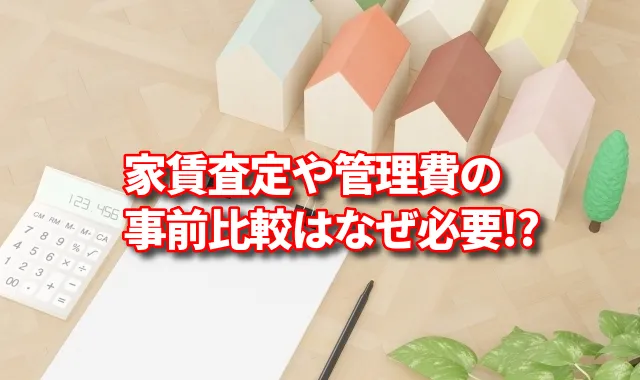
- 【自宅を貸したい場合】家賃査定や管理費の事前比較の必要性について解説します 公開
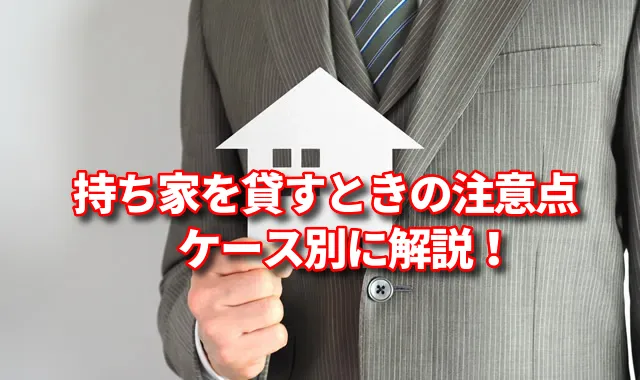
- 【家を貸す】初心者必見!持ち家を貸し出すときの注意点をケース別に詳細に解説します 公開
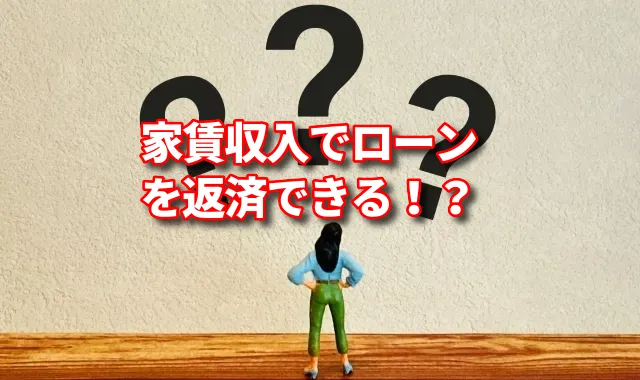
- 【賃貸管理】住宅ローン返済中に持ち家を貸すリロケーションについておしえます 公開

- 【物件の貸し出し】住宅ローン返済中の物件をリロケーションを使って貸す! 公開

- 【家を貸したい】海外赴任時のリロケーション!自家用車はどうすれば!? 公開

- 【家を貸す】定期で貸せるリロケーション!税金に関する注意点を解説します 公開

- 【家を貸したい】空き家バンクの仕組みと一般の賃貸管理会社を利用する場合の違いをお伝えします 公開

- 【空き家の活用事例】空き家ビジネスの最前線!成功事例や失敗事例をご紹介 公開

- 【家を貸したい】貸す前に絶対に確認しておきたい重要事項!! 公開

- 【持ち家を貸す】素朴な疑問!家を貸すとき家具やマイカーは置いておけるの? 公開
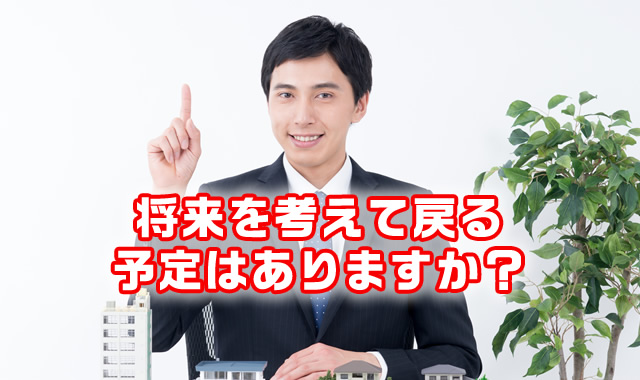
- 【持ち家を貸す】入居者退去後の原状回復の方法・事前確認をしてトラブル防止! 公開

- 【賃貸管理】大失敗しない持ち家・マンションを貸す方法!5つのチェックポイントをおしえます 公開
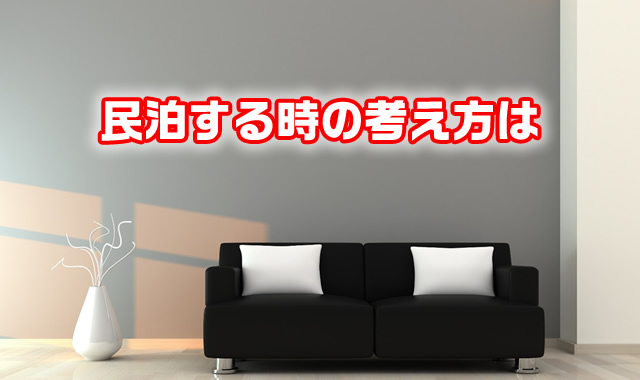
- 【民泊運営】民泊で家を貸す時の重要ポイントをおしえます! 公開
家を貸し出す場合、まずは何と言っても自分の希望に叶う質の良い入居者を募集する必要があります。
貸主となる物件オーナー様は、不動産仲介会社と契約して入居者を斡旋仲介してもらうと、効率的にそうした入居者を早く見つけることができます。
その際に大事なポイントが以下の2点になります。
- 不動産仲介会社に依頼をして、貸し出す物件の詳細を伝える
- 賃貸として出す条件を不動産仲介会社と取り決める
不動産管理会社へ入居者の募集を含めた委託管理を依頼すれば、一気通貫で、物件の広告宣伝や入居希望者の内見対応といった業務をすべて行ってもらえます。
冒頭でもお伝えしましたが、入居希望者が見つかり、借主として入居をしてもらえることになったら、その入居希望者と賃貸借契約を締結します。
上述した通り、賃貸借契約には、借主の契約更新方法を定めた「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
「普通借家契約」は、特に契約期間の定めがない契約であることはお伝えしましたが、一般的な契約期間は1~2年(一般的には2年が多い)です。
その契約期間が満了した後は、借主から事前に退去希望が無い限りは自動更新となります。
その際、正当な事由がない限り、貸主から一方的に契約を解除、契約の更新を拒否することはできませんので、あらかじめ理解をしておきましょう。
一方「定期借家契約」は、電車やバスの「定期券」と同じ意味合いで、借主がその賃貸物件に住める一定の契約期間を定めた内容だと上述しました。
普通借家契約と違い、契約満了の期日を迎えれば自動更新はありません。契約期間が終了した時点で、借主は貸主に家を明け渡して退去をする必要があります。
定期借家契約の契約期間については、原則的には物件オーナー様である貸主が任意で定めることが可能です。
ただ、不動産管理会社へ委託管理を依頼する場合、契約期間が短いと、会社によっては委託管理の取り扱いができないと言う会社もありますので、委託管理候補としてピックアップした会社ごとによく確認をした方がよいでしょう。
一般的には定期借家契約を「2年未満」で希望した場合、その取り扱いをしていない企業が多いようです。
2-1-3.家賃の回収
借主からの家賃回収についてです。この業務は、基本的には貸主が行います。
家賃については、毎月支払日にしっかり払ってくれる借主もいれば、理由は様々で予測ができないことですが、借主の経済状況が突然悪化してしまい、支払いが滞ったり、もっと経済的に苦しくなってしまうと家賃を滞納する借主が出てしまうことが考えられます。
借主への支払い督促は、時として感情が絡む難しい問題になるケースもあります。
借主が滞納している家賃の早期支払いに応じてくれるように、上手に督促をするノウハウが必要です。
しかし、貸主自らがこれを行うのは精神的にキツイ面が出てくるものです。
この家賃回収も、管理会社へ委託管理を依頼すれば、貸主自身で行うことはなく管理会社が家賃回収を代行して行い、貸主へ入金をしてくれます。
また、貸主の家賃滞納について補足になりますが、借主が「支払う意思」を見せていれば、1,2ヶ月程度の滞納では退去をしてもらうことは難しいです。
ただ、もっと長期で滞納をする借主に対して取れる法的手段としては「契約解除」「差し押さえ」「明け渡し請求」のいずれかになります。
これを実行する時は、まず前段として「家賃滞納が続いていることを証明する書類」が必要になります。
家賃滞納を行う借主へいきなり退去を伝えるのではなく、まず先に「内容証明」を家賃滞納している借主へ送付をしましょう。
そうした書面で伝えても支払いに応じてもらえない場合は「訴訟」という強い方法で対応することにもなります。
2-1-4.トラブルやクレームへの対応
これも非常に重要な管理業務になります。なぜなら、借主からのトラブルやクレームに対してタイムリーに適切な処理対応ができないと、最悪、退去をされてしまうことがあるからです。
せっかく入居をしてくれた借主の怒りを買ってしまい退去をされてしまうと、家は空室となり、その期間は貸主への家賃収入が途絶えてしまいます。
空室がすぐに別の入居希望者で埋まれば良いですが、空室期間が長引くことになると、あらたな募集広告に費用が掛かったり、当初想定していた収支計画にも悪影響が出てしまいます。
トラブルやクレームには「建物の不具合や設備故障に対する修理要請」、また、貸し出している家が分譲マンションだった場合は、同じ物件内で起こる「入居者同士のトラブル」「近隣の住民からクレーム」など様々なケースが想定されます。
こうしたクレーム対応処理を、貸主本人が対応するのは現実的ではありません。
ケース毎に適切な対応方法がありますから、これも管理業務を取り扱う管理会社へ相談の上で委託管理を依頼すれば、貸主の意向を確認した上で、管理会社がすべて適切に対応をしてくれます。
とはいえ、不測のトラブルならまだしも、借主からのクレームについては、クレームが発生しないように事前対策をしておくが大前提にはなります。
思わぬことが原因でクレームに発展する場合もあるものですが、管理会社に委託管理を依頼する場合は、管理会社にクレームが起こった場合の基本対処法を事前相談しておいた上で、適切な初期対応を行ってもらえるよう打合せておきましょう。
また万が一クレームが発生した場合は、管理会社と一緒に再発防止ができるように対策をしましょう。
2-1-5.入退去の管理
借主(入居者)の入退去時は「修繕」「ハウスクリーニング」が必要になります。とくに退去後に以下のような場合は原状回復する必要があります。
- 床や壁の傷や汚れ
- カビやシミ
- たばこなどによる匂いや汚れ
- トイレやキッチンなどの水回りの汚れ など
次の入居希望者に気持ちよく家を内見してもらい、入居を決めてもらったあとも気持ちよく家に住んでもらえるように、原状回復のための修繕やハウスクリーニングを行うことは重要な管理業務です。
また、これは補足になるのですが、借主が退去した後にリノベーションやリフォームを実施する場合は、その間空室が続くと家賃収入が途絶えることになりますので、家のどこをリノベーションやリフォームをする必要があるのか、収支もあわせて検討したうえで、無理のない範囲で、費用や工事期間を決定するようにしましょう。
2-2.物件管理
物件管理についても、貸主自身で管理することができますが、管理会社に委託管理を依頼するのが一般的ですし、その方が安全です。
主な物件管理の項目は以下の3つです。
- 建物の清掃
- 建物の修繕
- 設備のメンテナンスや修理
以上3つです。
地味に思える項目だと思われた方も多いかもしれませんが、これらは意外と重要な項目ばかりです。
以下でさらに補足解説をします。
2-2-1.建物の清掃
建物の清掃は、管理会社に委託管理を依頼した場合は管理会社で行ってくれるようになります。
管理会社へ委託をしない場合は、貸主自身でそれを行うか、直接、専門の清掃業者へ依頼するのも方法のひとつです。
管理会社や清掃業者に清掃業務を依頼する時は、掃除の頻度、方法、料金について予め打合せて確認をしておきましょう。
建物の清掃が行き届いていないと、借主の入居者満足度に影響が出てしまいます。
また、空室となってしまい新たな入居者を募集していた場合は、入居希望者が内見に来てくれても清掃が行き届いていないと印象が悪くなってしまい、せっかくの入居希望者が別の物件へ流れてしまう可能性が十分考えられます。
そうなってしまいますと本当に勿体ない話しです。ですから、清潔感が漂う物件にしておくことが必要です。
2-2-2.建物の修繕
これも上述しましたが、家を賃貸物件として貸し出す場合、建物の経年劣化による破損等は、貸主や管理会社側に修繕義務があります。
建物の修繕項目としては、「屋根」「柱」「床」「内装」「設備」など入居者に貸している部分全てになります。
ただ、借主がそれらを壊してしまった場合は、当然、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済してもらうことになるか?の取り決めを入居契約時にしておくことは重要です。
2-2-3.設備のメンテナンスや修理
また、建物の修繕に加えて、家の設備のメンテナンス・修理も大家または管理会社が行う対象になります。
これらも管理会社に委託管理を依頼する場合は、設備・メンテナンスの実施範囲やその管理費用について事前に取り決めておく必要があります。
ただ、設備に関しても建物同様、借主が壊してしまった場合は、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、これに関してもまた、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済をしてもらうことになるか?この取り決めも入居契約時に詰めておくことが重要です。
2-3.経営管理
これも上述しました通り、家を賃貸物件として貸して賃料収入を得る行為は、賃貸経営という「事業」にあたることになるため、以下の経営管理も必要となってきます。
- 帳簿をつける
- 確定申告をする
- 税金などの支払いをする
以上3つです。家を貸して「収支が成り立つか?」といった収支計画の確認は最低限必要となります。
ここまでご覧いただいてお分かり頂けた部分も多いかと思いますが、家を貸すと、様々な管理業務が発生します。
そうした管理業務をすべてご自身で行うことは不可能に近いでしょう。
管理業務を不動産会社や管理会社に委託管理を依頼すると当然「管理委託料」が必要になるのですが、貸主の日常生活に支障が出ることなく、家の賃貸経営が問題なく回るのであれば、大多数の方は管理費を支払ってでも家を貸すことを選択していると言えます。
自分自身が家に住んでいたときは気にする機会が少なかった支出も、貸すときは把握する必要が出てきます。
では、家を貸す場合に想定される支出にはどういうものがあるのでしょうか?
家を貸す場合に想定される支出には、以下が挙げられます。
- 固定資産税、都市計画税
- 火災保険料
- 仲介手数料(不動産会社に仲介を委託する場合)
- 管理委託料(管理業務を管理会社に委託する場合)
- 清掃費用
- 原状回復費用
- 修繕費(積み立てておくのが一般的)
2-3-1.固定資産税
「固定資産税」とは、毎年1月1日時点で土地・建物などの固定資産を所有している人に対して課税される税金です。
賃貸オーナーも毎年固定資産税を支払う必要があります。家賃収入がゼロの場合でも支払い義務は発生しますので、固定資産税分は現金を確保しておくことが大切です。
2-3-2.都市計画税
「都市計画税」とは、土地・建物を所有している人に対して、都市計画や区画整理などの費用に充てるために課税される税金です。
固定資産税に含まれていることが多く、税率は市町村によって異なりますが、上限は0.3%となっています。所有している物件がある市町村に確認しておく必要があります。
2-3-3.火災保険料
賃貸経営に際して、物件のオーナー様向けの火災保険に加入することが一般的です。
保険料は保険会社や保険商品、物件の条件などで変動します。借家の大きさや、借家がある地域、借家となる建物の建物評価額などに基づいて保険料が設定されています。保険の設計プランによって異なりますが、火災だけでなく自然災害や落雷、爆発などさまざまな災害への保障が含まれていることが一般的です。
2-3-4.仲介手数料
不動産仲介会社に物件の客付けを依頼する場合は、仲介手数料を支払う必要があります。
賃貸物件の場合、「賃貸借契約」を締結した際に支払います。物件オーナー様が不動産仲介会社に支払う仲介手数料は会社によって異なりますが、原則「賃料の半月分が上限」と宅地建物取引業法で定められています。
ただし、別途広告費の支払いについて取り決めている場合は、広告費の支払が発生します。
2-3-5.管理委託料
管理委託料の上限は法律などで決まっていません。そのため、管理会社によって金額が異なります。
平均的な管理委託料の設定は3%~8%となっています。そのため、管理会社を選ぶ時は「管理委託料がいくらになるか?」を確認して契約しましょう。
2-3-6.清掃費用
物件オーナー様自身が清掃をする場合は、掃除道具や機器、洗剤等の調達費用のみかかります。
ただし、ご自身で清掃ができない範囲については、管理会社や清掃業者に依頼をする必要があります。
物件の規模にもよりますが、数万~数十万円の費用がかかるケースがあります。
2-3-7.原状回復費用
入居者(借主)の退去時には、部屋の傷や汚れを入居前の状態まで戻すための「原状回復工事」を行います。
この原状回復の費用については、入居者との間で取り決めておく必要があります。
▶原状回復費用の補てん方法
・賃貸借契約の際、退去時に入居者から支払ってもらう契約を取り決める
・入居時の敷金から原状回復費用を支払い、残った額を入居者に返金する
なお、敷金を超える原状回復費用がかかった場合、「修繕費として入居者に請求する」か、もしくは「オーナー様が自己負担するか」どうかについても取り決めておくと、入居者とのトラブルを回避できます。
2-3-8.修繕費
修繕費は、「物件オーナー様が負担する分」と「入居者が負担する分」の2種類があります。
入居者が故意に破損した場合でなければ、物件オ-ナー様が負担することが基本です。
「ベランダの防水工事」「外壁改修」「クッションフロア張り替え」などが挙げられます。修繕にかかる費用は使う材料や依頼する業者によって異なるため、依頼業者との契約時に必ず確認しましょう。
▶賃貸収入で支出をカバーするのが基本
入居者からは敷金や礼金も支払われますが、これはあくまで1回限りのもので、基本的には毎月の賃料が賃貸収入となります。
そして、家を貸す場合にかかる支出は、この賃貸収入によってカバーするのが基本です。
そのため、家を貸すときは慎重な収支計画を立て、委託する業務と自分で行う業務についても細かく決めていくようにしましょう。
また、賃料については「どれくらいの支出があるのか?」ということを慎重に考えた上で決めましょう。
以上、賃貸事業で必要になる管理業務を網羅してみました。
ご自身のなかで必要となりそうな項目があったら、今一度よく確認してみて頂ければと思います。
【イエカレ運営局より】
【完全無料/最大8社紹介】自宅を高額家賃でお得に貸したいなら!管理プランと管理費を徹底比較。
高い家賃で経費を抑えた賃貸管理、質の高い入居者紹介ができる不動産会社を比較・選択できます!
より高くなら、各社、無料訪問査定もご対応します。お気軽にお問い合わせください。
3.ケース特有の家を貸す注意点をご紹介
ここでは「全然知りませんでした...」では済まない、家を貸すときの注意点をいくつかご紹介します。
これらも重要なものばかりです。
3-1:賃貸で借りている家を貸す「又貸し」はNG
一つ目は「又貸し」です。これは貸主というより借主側の問題ですが、貸主である賃貸オーナー様にも知っておいて欲しい内容になります。
又貸しとは「賃貸物件を契約者自身で借りているにも関わらず、その契約者自身は入居をせずにさらに別の第三者に貸す行為」のことです。
つまり、借主が自分で借りた賃貸物件には住まずに別の第三者に貸して、借主が家賃収入を得る行為です。
住まずに物件を賃貸に出すことができるのは、基本的にその賃貸物件の「所有権を持つ名義人ご自身の場合のみ」です。
「又貸しが禁止の理由」と「発見された場合にどうなるか」も以下でご紹介します。
3-1-1.又貸しがNGの理由
賃貸物件を借りた借主が、第三者に又貸しをした場合、それが原因で何らかのトラブルが発生したときは「貸主である物件オーナー様」と「借主である契約者(本来の入居者)」の間に「又貸しで住んでいる第三者」が加わることになるため、話がこじれてしまい問題解決が難しくなることが非常に多いです。
借主は入居審査を経て入居契約を交わした上で貸主から物件を借りたわけですが、又貸しで住んでいる第三者は貸主と入居契約を交わしたわけではない全くの無関係者です。
これが許されてしまうと何でも有りの世界にもなってしまいます。もちろん、第三者に又貸しを行った借主は、無断でそのような行為を行った責任を問われることになります。
貸主に多大な迷惑が掛かるのはもちろん、借主にとってもいろんな意味でリスクが高くなるため原則禁止されています。
3-1-2.又貸しが万が一発見された場合
もしも又貸しが発見された場合は、その借主は貸主側から「強制退去」や「多額の違約金の支払いが求められる」ケースがあります。
場合によっては訴訟といった裁判沙汰へ発展することもあります。ですから、貸主は、借主と結ばれる賃貸借契約書に「又貸し禁止事項」の記載がしっかりされていることをよく確認しましょう。
「少しくらいいいや」と思ったモラルがなかった借主にこうした違反行為をされてしまうと想像以上に大きな問題に発展しやすいため、借主が安易に又貸しできないように必ず契約で縛っておく必要があります。「又貸し被害」にあわない様に十分注意したいものです。
3-2.自分の持ち家全体(一軒家)を貸す場合
一軒家を所有されている方の場合、急な転勤や相続などが原因で「一時的に転勤期間だけ家を賃貸物件と貸し出したい」ですとか「実家を相続したが、居住する家族はいないのでできれば売らずに長期間貸し出したい」と考えている方は少なくないでしょう。
この章では、一軒家を貸す場合、どのような注意点があるのか以下で詳しく解説しますので気になっている方は、是非、参考にしてください。
3-2-1.外壁や屋根など一軒家特有の修繕費
一軒家を貸している間、外壁や屋根などの建物の修繕が必要になった場合、その修繕費は貸主負担となります。
大事に住んでいたとしても、建物の外壁や屋根は築年数が経てば経つほど、どうしても経年劣化による老朽化は避けられません。
不具合をそのまま放置をしてしまうと物件の資産価値が大きく下がる可能性があります。
修繕は建物の維持費用と割り切ってあらかじめ収支計画に入れておきましょう。
3-2-2.災害のリスク
これは誰にも予測がつかないことですが、災害のリスクも考慮しておくことが必要です。
例えば、地震や台風で家の一部が倒壊、または全壊した場合、修繕費用は貸主が自己負担する必要があります。
また、借主が一時的に別の賃貸物件などへ避難してせざるを得なくなった場合はその間の家賃を借主に請求することはできません。
損害を最小限に留めるためもに、火災保険や地震保険などの各種損害保険に加入しておくのがよいでしょう。
3-2-2.防犯性や管理体制
一軒家を貸す場合は、借主に安心して住んでもらえる様に、民間のセキュリティ・サービスを利用することも考慮に入れましょう。
マンションやアパートの場合でしたら、その管理業務は管理会社に依頼する方が多いのですが、一軒家の場合は、貸主ご自身でその対応をされる方も見受けられます。
マンションやアパートは玄関のオートロックや防犯カメラが設置されている場合がもはや当たり前になっていますが、一軒家では貸主ご自身で防犯対策をする必要があります。
借主の万が一に備え、住む方の「安全性」や「防犯性」に考慮した対応が求められます。
ただ、こうした対応についても家の管理業務そのものを管理会社に依頼する場合は、管理会社の担当者へ相談をすれば対策を考えてくれるはずですので、一度問い合わせてみることをお勧めします。
3-3.自宅の一室を貸す(賃貸併用住宅)の場合
また、所有している自宅の「空き部屋」だけを貸す「賃貸併用住宅」という賃貸方法があります。
賃貸併用住宅として家を貸し出す場合の注意点は、以下となりますのでこちらもあわせて確認してみて下さい。
3-3-1.賃貸併用住宅の間取り
「賃貸併用住宅」は同じ家(建物)の一部のなかに賃貸用として貸し出せる部屋が併設されている賃貸物件となります。
貸主である物件オーナー様は借主と同じ建物内で生活をすることになるため、お互いのプライバシーが保護できる動線や視線に配慮した間取りにすることが大切です。
例えば、自宅・賃貸の玄関を別々することはもちろん、借主とできるだけ顔を合わせないように設計をするとお互いのプライバシーを保護しやすくなり生活がしやすくなります。
また、防音や騒音対策への配慮も重要です。貸主と借主では生活スタイルや活動時間に違いが出る場合も考えられます。
間取りや設備の配置で防音・騒音対策を考えましょう。
3-3-2.入居者との距離感
貸主と借主のお互いのプライバシー尊重と言う点でもう一つ。
賃貸併用住宅では貸主は借主との距離感を常に一定に保つことが必要です。
貸主と借主が同じ建物内で生活をしているなかで、段々とその距離が近づき過ぎるようになると、悪い意味で「馴れ合いの関係」になってしまうことがあり、それが原因でトラブルに発展してしまうことが考えられます。
貸主と借主がフレンドリーな関係でいることはもちろん重要ですし、貸主の運用方針やスタイルにもよりますが、借主とは近すぎず遠すぎず、お互いにとって程よい距離感を保てるように模索することが重要です。
3-4.マンション、アパートを貸す場合
次は、マンションやアパートの一室を不動産投資物件として購入をして、賃貸物件として貸し出すパターンでの注意点について説明します。
この場合は以下の注意点があります。
3-4-1.入居者同士のトラブル
マンションやアパートは集合住宅と言う性質上、入居者同士のトラブルが出てしまうことを忘れずに想定しておかなくてはなりません。
そのため、借主との入居契約時にトラブルが起こりそうな項目について取り決めをしておく必要があります。
また、借主からクレームが出たらすぐに対応・対策をすることが大切です。
これは補足説明ですが「マンションやアパート一棟」の賃貸オーナーとして貸し出す場合は、貸主が全ての借主に対して自主管理で管理業務の対応することは現実的には難しいため、尚更のこと、やはり管理業務を委託できる管理会社を選定する方が望ましいと言えるでしょう。
3-4-2.管理組合の参加
分譲マンションの場合、共用部分の維持管理や各入居者の生活マナーの維持についての取り決めや管理を行うために必ず「管理組合」が設けられています。
管理組合はマンションの住民で構成をされています。例えば、理事長の選任時や、定例会に参加するか・しないかで、組合員である他の住民とトラブルになったり、管理組合の総会で議決された取り決めを実行するときに他の住民から反対にあったりする可能性がつきものです。
分譲マンションを賃貸で家を貸すときには、貸主は管理組合の一員としての役割が発生することを覚えておきましょう。
まとめ
以上、自宅の部屋や持ち家を貸すときの注意点をケース別に解説してきました。
家を賃貸物件として貸し出しす場合の「チェックポイント」をしっかりと抑えておけば、トラブルを回避しやすくなりますし、安心・安全な賃貸経営が可能となるでしょう。
家を貸す場合、以下のような注意点があります。
・賃貸借契約の種類やその内容について、細かくチェックする
・管理業務にはどのようなものがあるのか、あらかじめ把握しておく
・慎重な収支計画を立てる
貸主ご自身ですべての管理を行うことはできませんし現実的ではありません。
不動産会社では、一時的に使わない家を活用する方法について相談に乗ってくれる専門の管理会社があります。
ご自身だけで判断するのが難しい場合は、ご自身の状況を踏まえて「こんな管理業務を委託したいが可能なのか?」といった形で希望を伝えた上で、管理会社の専門家の意見を仰いでみることを強くおすすめします。
また、家を賃貸に出すにあたって、何よりも大切にしてほしいポイントがあります。
それは管理業務に関する委託管理の相談を管理会社へ依頼する場合は、できる限り、すぐに一つの不動産会社と話を進めようとしてはいけないということです。
確かに「急な転勤」などで急ぐ場合や、不動産会社との交渉が複数社に及べば、面倒で時間も手間もかかります。
そうなると「もう早く決めてしまいたい」という心理から、最初に連絡が取った会社と話を進めてしまいがちです。
しかし、よく考えて頂きたいことは「家の委託管理を依頼する」ということは、あなたの大切な不動産の管理を第三者へ依託をして、いわばあなたの賃貸経営をサポートしてもらうということです。
結果的には多くのお金が動く商取引になりますし「あの時、焦らずにもっと慎重に委託管理先を探すべきだった...」と後から悔やまれてしまうのでは本当に残念な話しとなってしまいます。
あなたの家という財産の管理をしっかり任せられる実績と実力がある管理会社を探すべきです。
また、会社探しの上では、担当者と貸主との相性も重要だといわれます。
貸主の信頼にしっかり応えようと、些細なことにも迅速に丁寧な応対をする担当者との出会いが必要です。
トラブルが起きたら逃げ腰になるような担当者は論外です。複数社の会社へ問合せを行い、応対や態度などを観察すればだいたい分かるものです。
担当者の応対で少しでも気になる点があれば条件が良かったとしてもすぐに委託契約を交わさない方が吉ということもあり得ます。そうした担当者の質も含めて「良い条件で賃貸に出す」ことを何よりも優先すべきです。
最後に、比較検討する上では、他の会社の査定内容を探ってきたり、なぜか一社だけ飛びぬけて高い賃料を提示してきた場合も要注意です。
担当者が管理契約を取りたいがために、「高い賃料を提示している」という事情が隠れている場合があるかもしれません。そのような事情を見抜くためにも、やはり比較検討は必要です。
【イエカレより】「ご自宅を貸し出したい」「空き家にしたままよりも有効活用を検討したい」とお考えの方々に、ご自宅資産に合わせて留守宅管理専門の不動産管理会社をご紹介しています。一度のご登録で、最高8社の管理会社へ家賃査定依頼が可能です!ご利用は無料です。
各社、訪問査定も対応しています!大切なご自宅資産を丁寧に査定、直接ご希望もお伺いして高額査定を目指します!入居者仲介方法、管理代行・保証内容など、各社の提案を比較できますので、お留守の間、安心してお頂け頂ける不動産会社をお選びいただけます。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部
【イエカレ】では、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
(コラム・アドバイザー)檜垣 知宏

株式会社ライフアドバンス代表取締役の檜垣知宏です。 2014年8月に設立し、恵比寿不動産という屋号で賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理を行う不動産業者です。 不動産業界歴15年の経験を生かし、 運営しているサービスサイトである「不動産の相談窓口」の運営者も務めております。
【保有資格】宅地建物取引士
【関連URL】
[恵比寿不動産×賃貸]
[恵比寿不動産×売買]
[恵比寿不動産×リフォーム]
[不動産の相談窓口]
[資産運用の相談窓口]
[転勤東京.com]
[LGBT不動産]
[賃貸管理ナビ]
[ライフアドバンス]
Copyright (C) EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 家を貸す際に注意すべきこと
家を貸す際に注意すべきことの関連記事
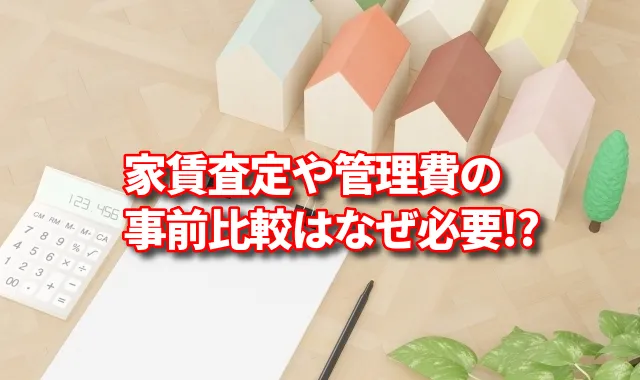
- 【自宅を貸したい場合】家賃査定や管理費の事前比較の必要性について解説します 公開
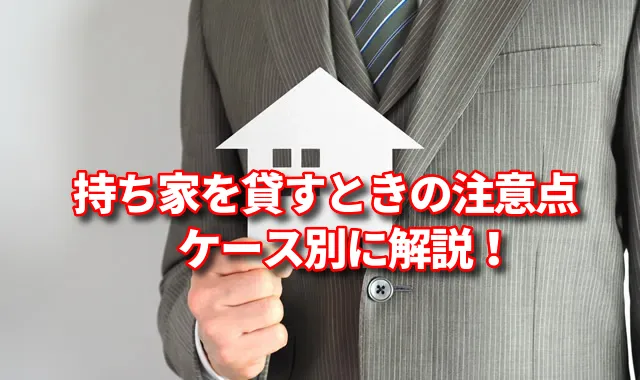
- 【家を貸す】初心者必見!持ち家を貸し出すときの注意点をケース別に詳細に解説します 公開
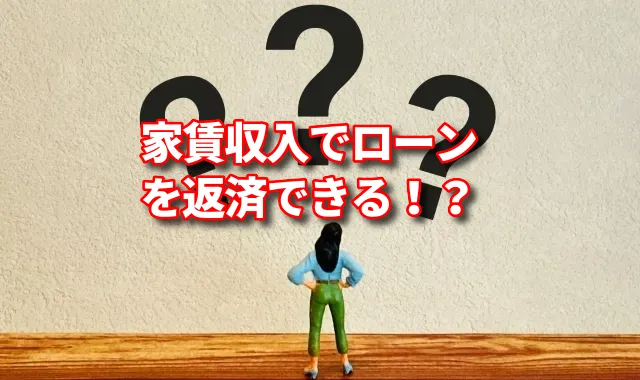
- 【賃貸管理】住宅ローン返済中に持ち家を貸すリロケーションについておしえます 公開

- 【物件の貸し出し】住宅ローン返済中の物件をリロケーションを使って貸す! 公開

- 【家を貸したい】海外赴任時のリロケーション!自家用車はどうすれば!? 公開

- 【家を貸す】定期で貸せるリロケーション!税金に関する注意点を解説します 公開

- 【家を貸したい】空き家バンクの仕組みと一般の賃貸管理会社を利用する場合の違いをお伝えします 公開

- 【空き家の活用事例】空き家ビジネスの最前線!成功事例や失敗事例をご紹介 公開

- 【家を貸したい】貸す前に絶対に確認しておきたい重要事項!! 公開

- 【持ち家を貸す】素朴な疑問!家を貸すとき家具やマイカーは置いておけるの? 公開
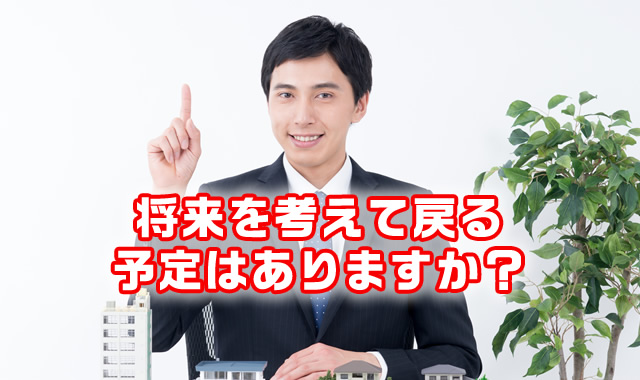
- 【持ち家を貸す】入居者退去後の原状回復の方法・事前確認をしてトラブル防止! 公開

- 【賃貸管理】大失敗しない持ち家・マンションを貸す方法!5つのチェックポイントをおしえます 公開
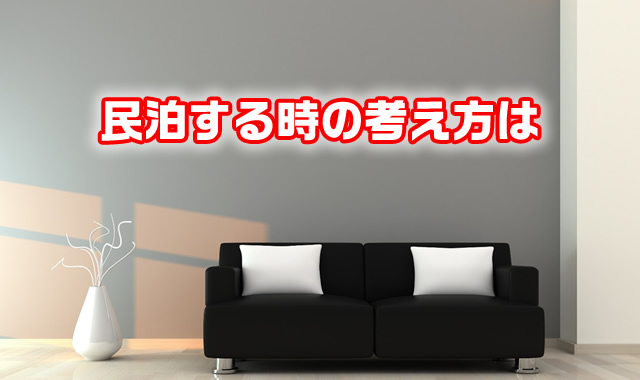
- 【民泊運営】民泊で家を貸す時の重要ポイントをおしえます! 公開
借主からの家賃回収についてです。この業務は、基本的には貸主が行います。
家賃については、毎月支払日にしっかり払ってくれる借主もいれば、理由は様々で予測ができないことですが、借主の経済状況が突然悪化してしまい、支払いが滞ったり、もっと経済的に苦しくなってしまうと家賃を滞納する借主が出てしまうことが考えられます。
借主への支払い督促は、時として感情が絡む難しい問題になるケースもあります。
借主が滞納している家賃の早期支払いに応じてくれるように、上手に督促をするノウハウが必要です。
しかし、貸主自らがこれを行うのは精神的にキツイ面が出てくるものです。
この家賃回収も、管理会社へ委託管理を依頼すれば、貸主自身で行うことはなく管理会社が家賃回収を代行して行い、貸主へ入金をしてくれます。
また、貸主の家賃滞納について補足になりますが、借主が「支払う意思」を見せていれば、1,2ヶ月程度の滞納では退去をしてもらうことは難しいです。
ただ、もっと長期で滞納をする借主に対して取れる法的手段としては「契約解除」「差し押さえ」「明け渡し請求」のいずれかになります。
これを実行する時は、まず前段として「家賃滞納が続いていることを証明する書類」が必要になります。
家賃滞納を行う借主へいきなり退去を伝えるのではなく、まず先に「内容証明」を家賃滞納している借主へ送付をしましょう。
そうした書面で伝えても支払いに応じてもらえない場合は「訴訟」という強い方法で対応することにもなります。
これも非常に重要な管理業務になります。なぜなら、借主からのトラブルやクレームに対してタイムリーに適切な処理対応ができないと、最悪、退去をされてしまうことがあるからです。
せっかく入居をしてくれた借主の怒りを買ってしまい退去をされてしまうと、家は空室となり、その期間は貸主への家賃収入が途絶えてしまいます。
空室がすぐに別の入居希望者で埋まれば良いですが、空室期間が長引くことになると、あらたな募集広告に費用が掛かったり、当初想定していた収支計画にも悪影響が出てしまいます。
トラブルやクレームには「建物の不具合や設備故障に対する修理要請」、また、貸し出している家が分譲マンションだった場合は、同じ物件内で起こる「入居者同士のトラブル」「近隣の住民からクレーム」など様々なケースが想定されます。
こうしたクレーム対応処理を、貸主本人が対応するのは現実的ではありません。
ケース毎に適切な対応方法がありますから、これも管理業務を取り扱う管理会社へ相談の上で委託管理を依頼すれば、貸主の意向を確認した上で、管理会社がすべて適切に対応をしてくれます。
とはいえ、不測のトラブルならまだしも、借主からのクレームについては、クレームが発生しないように事前対策をしておくが大前提にはなります。
思わぬことが原因でクレームに発展する場合もあるものですが、管理会社に委託管理を依頼する場合は、管理会社にクレームが起こった場合の基本対処法を事前相談しておいた上で、適切な初期対応を行ってもらえるよう打合せておきましょう。
また万が一クレームが発生した場合は、管理会社と一緒に再発防止ができるように対策をしましょう。
2-1-5.入退去の管理
借主(入居者)の入退去時は「修繕」「ハウスクリーニング」が必要になります。とくに退去後に以下のような場合は原状回復する必要があります。
- 床や壁の傷や汚れ
- カビやシミ
- たばこなどによる匂いや汚れ
- トイレやキッチンなどの水回りの汚れ など
次の入居希望者に気持ちよく家を内見してもらい、入居を決めてもらったあとも気持ちよく家に住んでもらえるように、原状回復のための修繕やハウスクリーニングを行うことは重要な管理業務です。
また、これは補足になるのですが、借主が退去した後にリノベーションやリフォームを実施する場合は、その間空室が続くと家賃収入が途絶えることになりますので、家のどこをリノベーションやリフォームをする必要があるのか、収支もあわせて検討したうえで、無理のない範囲で、費用や工事期間を決定するようにしましょう。
2-2.物件管理
物件管理についても、貸主自身で管理することができますが、管理会社に委託管理を依頼するのが一般的ですし、その方が安全です。
主な物件管理の項目は以下の3つです。
- 建物の清掃
- 建物の修繕
- 設備のメンテナンスや修理
以上3つです。
地味に思える項目だと思われた方も多いかもしれませんが、これらは意外と重要な項目ばかりです。
以下でさらに補足解説をします。
2-2-1.建物の清掃
建物の清掃は、管理会社に委託管理を依頼した場合は管理会社で行ってくれるようになります。
管理会社へ委託をしない場合は、貸主自身でそれを行うか、直接、専門の清掃業者へ依頼するのも方法のひとつです。
管理会社や清掃業者に清掃業務を依頼する時は、掃除の頻度、方法、料金について予め打合せて確認をしておきましょう。
建物の清掃が行き届いていないと、借主の入居者満足度に影響が出てしまいます。
また、空室となってしまい新たな入居者を募集していた場合は、入居希望者が内見に来てくれても清掃が行き届いていないと印象が悪くなってしまい、せっかくの入居希望者が別の物件へ流れてしまう可能性が十分考えられます。
そうなってしまいますと本当に勿体ない話しです。ですから、清潔感が漂う物件にしておくことが必要です。
2-2-2.建物の修繕
これも上述しましたが、家を賃貸物件として貸し出す場合、建物の経年劣化による破損等は、貸主や管理会社側に修繕義務があります。
建物の修繕項目としては、「屋根」「柱」「床」「内装」「設備」など入居者に貸している部分全てになります。
ただ、借主がそれらを壊してしまった場合は、当然、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済してもらうことになるか?の取り決めを入居契約時にしておくことは重要です。
2-2-3.設備のメンテナンスや修理
また、建物の修繕に加えて、家の設備のメンテナンス・修理も大家または管理会社が行う対象になります。
これらも管理会社に委託管理を依頼する場合は、設備・メンテナンスの実施範囲やその管理費用について事前に取り決めておく必要があります。
ただ、設備に関しても建物同様、借主が壊してしまった場合は、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、これに関してもまた、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済をしてもらうことになるか?この取り決めも入居契約時に詰めておくことが重要です。
2-3.経営管理
これも上述しました通り、家を賃貸物件として貸して賃料収入を得る行為は、賃貸経営という「事業」にあたることになるため、以下の経営管理も必要となってきます。
- 帳簿をつける
- 確定申告をする
- 税金などの支払いをする
以上3つです。家を貸して「収支が成り立つか?」といった収支計画の確認は最低限必要となります。
ここまでご覧いただいてお分かり頂けた部分も多いかと思いますが、家を貸すと、様々な管理業務が発生します。
そうした管理業務をすべてご自身で行うことは不可能に近いでしょう。
管理業務を不動産会社や管理会社に委託管理を依頼すると当然「管理委託料」が必要になるのですが、貸主の日常生活に支障が出ることなく、家の賃貸経営が問題なく回るのであれば、大多数の方は管理費を支払ってでも家を貸すことを選択していると言えます。
自分自身が家に住んでいたときは気にする機会が少なかった支出も、貸すときは把握する必要が出てきます。
では、家を貸す場合に想定される支出にはどういうものがあるのでしょうか?
家を貸す場合に想定される支出には、以下が挙げられます。
- 固定資産税、都市計画税
- 火災保険料
- 仲介手数料(不動産会社に仲介を委託する場合)
- 管理委託料(管理業務を管理会社に委託する場合)
- 清掃費用
- 原状回復費用
- 修繕費(積み立てておくのが一般的)
2-3-1.固定資産税
「固定資産税」とは、毎年1月1日時点で土地・建物などの固定資産を所有している人に対して課税される税金です。
賃貸オーナーも毎年固定資産税を支払う必要があります。家賃収入がゼロの場合でも支払い義務は発生しますので、固定資産税分は現金を確保しておくことが大切です。
2-3-2.都市計画税
「都市計画税」とは、土地・建物を所有している人に対して、都市計画や区画整理などの費用に充てるために課税される税金です。
固定資産税に含まれていることが多く、税率は市町村によって異なりますが、上限は0.3%となっています。所有している物件がある市町村に確認しておく必要があります。
2-3-3.火災保険料
賃貸経営に際して、物件のオーナー様向けの火災保険に加入することが一般的です。
保険料は保険会社や保険商品、物件の条件などで変動します。借家の大きさや、借家がある地域、借家となる建物の建物評価額などに基づいて保険料が設定されています。保険の設計プランによって異なりますが、火災だけでなく自然災害や落雷、爆発などさまざまな災害への保障が含まれていることが一般的です。
2-3-4.仲介手数料
不動産仲介会社に物件の客付けを依頼する場合は、仲介手数料を支払う必要があります。
賃貸物件の場合、「賃貸借契約」を締結した際に支払います。物件オーナー様が不動産仲介会社に支払う仲介手数料は会社によって異なりますが、原則「賃料の半月分が上限」と宅地建物取引業法で定められています。
ただし、別途広告費の支払いについて取り決めている場合は、広告費の支払が発生します。
2-3-5.管理委託料
管理委託料の上限は法律などで決まっていません。そのため、管理会社によって金額が異なります。
平均的な管理委託料の設定は3%~8%となっています。そのため、管理会社を選ぶ時は「管理委託料がいくらになるか?」を確認して契約しましょう。
2-3-6.清掃費用
物件オーナー様自身が清掃をする場合は、掃除道具や機器、洗剤等の調達費用のみかかります。
ただし、ご自身で清掃ができない範囲については、管理会社や清掃業者に依頼をする必要があります。
物件の規模にもよりますが、数万~数十万円の費用がかかるケースがあります。
2-3-7.原状回復費用
入居者(借主)の退去時には、部屋の傷や汚れを入居前の状態まで戻すための「原状回復工事」を行います。
この原状回復の費用については、入居者との間で取り決めておく必要があります。
▶原状回復費用の補てん方法
・賃貸借契約の際、退去時に入居者から支払ってもらう契約を取り決める
・入居時の敷金から原状回復費用を支払い、残った額を入居者に返金する
なお、敷金を超える原状回復費用がかかった場合、「修繕費として入居者に請求する」か、もしくは「オーナー様が自己負担するか」どうかについても取り決めておくと、入居者とのトラブルを回避できます。
2-3-8.修繕費
修繕費は、「物件オーナー様が負担する分」と「入居者が負担する分」の2種類があります。
入居者が故意に破損した場合でなければ、物件オ-ナー様が負担することが基本です。
「ベランダの防水工事」「外壁改修」「クッションフロア張り替え」などが挙げられます。修繕にかかる費用は使う材料や依頼する業者によって異なるため、依頼業者との契約時に必ず確認しましょう。
▶賃貸収入で支出をカバーするのが基本
入居者からは敷金や礼金も支払われますが、これはあくまで1回限りのもので、基本的には毎月の賃料が賃貸収入となります。
そして、家を貸す場合にかかる支出は、この賃貸収入によってカバーするのが基本です。
そのため、家を貸すときは慎重な収支計画を立て、委託する業務と自分で行う業務についても細かく決めていくようにしましょう。
また、賃料については「どれくらいの支出があるのか?」ということを慎重に考えた上で決めましょう。
以上、賃貸事業で必要になる管理業務を網羅してみました。
ご自身のなかで必要となりそうな項目があったら、今一度よく確認してみて頂ければと思います。
【イエカレ運営局より】
【完全無料/最大8社紹介】自宅を高額家賃でお得に貸したいなら!管理プランと管理費を徹底比較。
高い家賃で経費を抑えた賃貸管理、質の高い入居者紹介ができる不動産会社を比較・選択できます!
より高くなら、各社、無料訪問査定もご対応します。お気軽にお問い合わせください。
3.ケース特有の家を貸す注意点をご紹介
ここでは「全然知りませんでした...」では済まない、家を貸すときの注意点をいくつかご紹介します。
これらも重要なものばかりです。
3-1:賃貸で借りている家を貸す「又貸し」はNG
一つ目は「又貸し」です。これは貸主というより借主側の問題ですが、貸主である賃貸オーナー様にも知っておいて欲しい内容になります。
又貸しとは「賃貸物件を契約者自身で借りているにも関わらず、その契約者自身は入居をせずにさらに別の第三者に貸す行為」のことです。
つまり、借主が自分で借りた賃貸物件には住まずに別の第三者に貸して、借主が家賃収入を得る行為です。
住まずに物件を賃貸に出すことができるのは、基本的にその賃貸物件の「所有権を持つ名義人ご自身の場合のみ」です。
「又貸しが禁止の理由」と「発見された場合にどうなるか」も以下でご紹介します。
3-1-1.又貸しがNGの理由
賃貸物件を借りた借主が、第三者に又貸しをした場合、それが原因で何らかのトラブルが発生したときは「貸主である物件オーナー様」と「借主である契約者(本来の入居者)」の間に「又貸しで住んでいる第三者」が加わることになるため、話がこじれてしまい問題解決が難しくなることが非常に多いです。
借主は入居審査を経て入居契約を交わした上で貸主から物件を借りたわけですが、又貸しで住んでいる第三者は貸主と入居契約を交わしたわけではない全くの無関係者です。
これが許されてしまうと何でも有りの世界にもなってしまいます。もちろん、第三者に又貸しを行った借主は、無断でそのような行為を行った責任を問われることになります。
貸主に多大な迷惑が掛かるのはもちろん、借主にとってもいろんな意味でリスクが高くなるため原則禁止されています。
3-1-2.又貸しが万が一発見された場合
もしも又貸しが発見された場合は、その借主は貸主側から「強制退去」や「多額の違約金の支払いが求められる」ケースがあります。
場合によっては訴訟といった裁判沙汰へ発展することもあります。ですから、貸主は、借主と結ばれる賃貸借契約書に「又貸し禁止事項」の記載がしっかりされていることをよく確認しましょう。
「少しくらいいいや」と思ったモラルがなかった借主にこうした違反行為をされてしまうと想像以上に大きな問題に発展しやすいため、借主が安易に又貸しできないように必ず契約で縛っておく必要があります。「又貸し被害」にあわない様に十分注意したいものです。
3-2.自分の持ち家全体(一軒家)を貸す場合
一軒家を所有されている方の場合、急な転勤や相続などが原因で「一時的に転勤期間だけ家を賃貸物件と貸し出したい」ですとか「実家を相続したが、居住する家族はいないのでできれば売らずに長期間貸し出したい」と考えている方は少なくないでしょう。
この章では、一軒家を貸す場合、どのような注意点があるのか以下で詳しく解説しますので気になっている方は、是非、参考にしてください。
3-2-1.外壁や屋根など一軒家特有の修繕費
一軒家を貸している間、外壁や屋根などの建物の修繕が必要になった場合、その修繕費は貸主負担となります。
大事に住んでいたとしても、建物の外壁や屋根は築年数が経てば経つほど、どうしても経年劣化による老朽化は避けられません。
不具合をそのまま放置をしてしまうと物件の資産価値が大きく下がる可能性があります。
修繕は建物の維持費用と割り切ってあらかじめ収支計画に入れておきましょう。
3-2-2.災害のリスク
これは誰にも予測がつかないことですが、災害のリスクも考慮しておくことが必要です。
例えば、地震や台風で家の一部が倒壊、または全壊した場合、修繕費用は貸主が自己負担する必要があります。
また、借主が一時的に別の賃貸物件などへ避難してせざるを得なくなった場合はその間の家賃を借主に請求することはできません。
損害を最小限に留めるためもに、火災保険や地震保険などの各種損害保険に加入しておくのがよいでしょう。
3-2-2.防犯性や管理体制
一軒家を貸す場合は、借主に安心して住んでもらえる様に、民間のセキュリティ・サービスを利用することも考慮に入れましょう。
マンションやアパートの場合でしたら、その管理業務は管理会社に依頼する方が多いのですが、一軒家の場合は、貸主ご自身でその対応をされる方も見受けられます。
マンションやアパートは玄関のオートロックや防犯カメラが設置されている場合がもはや当たり前になっていますが、一軒家では貸主ご自身で防犯対策をする必要があります。
借主の万が一に備え、住む方の「安全性」や「防犯性」に考慮した対応が求められます。
ただ、こうした対応についても家の管理業務そのものを管理会社に依頼する場合は、管理会社の担当者へ相談をすれば対策を考えてくれるはずですので、一度問い合わせてみることをお勧めします。
3-3.自宅の一室を貸す(賃貸併用住宅)の場合
また、所有している自宅の「空き部屋」だけを貸す「賃貸併用住宅」という賃貸方法があります。
賃貸併用住宅として家を貸し出す場合の注意点は、以下となりますのでこちらもあわせて確認してみて下さい。
3-3-1.賃貸併用住宅の間取り
「賃貸併用住宅」は同じ家(建物)の一部のなかに賃貸用として貸し出せる部屋が併設されている賃貸物件となります。
貸主である物件オーナー様は借主と同じ建物内で生活をすることになるため、お互いのプライバシーが保護できる動線や視線に配慮した間取りにすることが大切です。
例えば、自宅・賃貸の玄関を別々することはもちろん、借主とできるだけ顔を合わせないように設計をするとお互いのプライバシーを保護しやすくなり生活がしやすくなります。
また、防音や騒音対策への配慮も重要です。貸主と借主では生活スタイルや活動時間に違いが出る場合も考えられます。
間取りや設備の配置で防音・騒音対策を考えましょう。
3-3-2.入居者との距離感
貸主と借主のお互いのプライバシー尊重と言う点でもう一つ。
賃貸併用住宅では貸主は借主との距離感を常に一定に保つことが必要です。
貸主と借主が同じ建物内で生活をしているなかで、段々とその距離が近づき過ぎるようになると、悪い意味で「馴れ合いの関係」になってしまうことがあり、それが原因でトラブルに発展してしまうことが考えられます。
貸主と借主がフレンドリーな関係でいることはもちろん重要ですし、貸主の運用方針やスタイルにもよりますが、借主とは近すぎず遠すぎず、お互いにとって程よい距離感を保てるように模索することが重要です。
3-4.マンション、アパートを貸す場合
次は、マンションやアパートの一室を不動産投資物件として購入をして、賃貸物件として貸し出すパターンでの注意点について説明します。
この場合は以下の注意点があります。
3-4-1.入居者同士のトラブル
マンションやアパートは集合住宅と言う性質上、入居者同士のトラブルが出てしまうことを忘れずに想定しておかなくてはなりません。
そのため、借主との入居契約時にトラブルが起こりそうな項目について取り決めをしておく必要があります。
また、借主からクレームが出たらすぐに対応・対策をすることが大切です。
これは補足説明ですが「マンションやアパート一棟」の賃貸オーナーとして貸し出す場合は、貸主が全ての借主に対して自主管理で管理業務の対応することは現実的には難しいため、尚更のこと、やはり管理業務を委託できる管理会社を選定する方が望ましいと言えるでしょう。
3-4-2.管理組合の参加
分譲マンションの場合、共用部分の維持管理や各入居者の生活マナーの維持についての取り決めや管理を行うために必ず「管理組合」が設けられています。
管理組合はマンションの住民で構成をされています。例えば、理事長の選任時や、定例会に参加するか・しないかで、組合員である他の住民とトラブルになったり、管理組合の総会で議決された取り決めを実行するときに他の住民から反対にあったりする可能性がつきものです。
分譲マンションを賃貸で家を貸すときには、貸主は管理組合の一員としての役割が発生することを覚えておきましょう。
まとめ
以上、自宅の部屋や持ち家を貸すときの注意点をケース別に解説してきました。
家を賃貸物件として貸し出しす場合の「チェックポイント」をしっかりと抑えておけば、トラブルを回避しやすくなりますし、安心・安全な賃貸経営が可能となるでしょう。
家を貸す場合、以下のような注意点があります。
・賃貸借契約の種類やその内容について、細かくチェックする
・管理業務にはどのようなものがあるのか、あらかじめ把握しておく
・慎重な収支計画を立てる
貸主ご自身ですべての管理を行うことはできませんし現実的ではありません。
不動産会社では、一時的に使わない家を活用する方法について相談に乗ってくれる専門の管理会社があります。
ご自身だけで判断するのが難しい場合は、ご自身の状況を踏まえて「こんな管理業務を委託したいが可能なのか?」といった形で希望を伝えた上で、管理会社の専門家の意見を仰いでみることを強くおすすめします。
また、家を賃貸に出すにあたって、何よりも大切にしてほしいポイントがあります。
それは管理業務に関する委託管理の相談を管理会社へ依頼する場合は、できる限り、すぐに一つの不動産会社と話を進めようとしてはいけないということです。
確かに「急な転勤」などで急ぐ場合や、不動産会社との交渉が複数社に及べば、面倒で時間も手間もかかります。
そうなると「もう早く決めてしまいたい」という心理から、最初に連絡が取った会社と話を進めてしまいがちです。
しかし、よく考えて頂きたいことは「家の委託管理を依頼する」ということは、あなたの大切な不動産の管理を第三者へ依託をして、いわばあなたの賃貸経営をサポートしてもらうということです。
結果的には多くのお金が動く商取引になりますし「あの時、焦らずにもっと慎重に委託管理先を探すべきだった...」と後から悔やまれてしまうのでは本当に残念な話しとなってしまいます。
あなたの家という財産の管理をしっかり任せられる実績と実力がある管理会社を探すべきです。
また、会社探しの上では、担当者と貸主との相性も重要だといわれます。
貸主の信頼にしっかり応えようと、些細なことにも迅速に丁寧な応対をする担当者との出会いが必要です。
トラブルが起きたら逃げ腰になるような担当者は論外です。複数社の会社へ問合せを行い、応対や態度などを観察すればだいたい分かるものです。
担当者の応対で少しでも気になる点があれば条件が良かったとしてもすぐに委託契約を交わさない方が吉ということもあり得ます。そうした担当者の質も含めて「良い条件で賃貸に出す」ことを何よりも優先すべきです。
最後に、比較検討する上では、他の会社の査定内容を探ってきたり、なぜか一社だけ飛びぬけて高い賃料を提示してきた場合も要注意です。
担当者が管理契約を取りたいがために、「高い賃料を提示している」という事情が隠れている場合があるかもしれません。そのような事情を見抜くためにも、やはり比較検討は必要です。
【イエカレより】「ご自宅を貸し出したい」「空き家にしたままよりも有効活用を検討したい」とお考えの方々に、ご自宅資産に合わせて留守宅管理専門の不動産管理会社をご紹介しています。一度のご登録で、最高8社の管理会社へ家賃査定依頼が可能です!ご利用は無料です。
各社、訪問査定も対応しています!大切なご自宅資産を丁寧に査定、直接ご希望もお伺いして高額査定を目指します!入居者仲介方法、管理代行・保証内容など、各社の提案を比較できますので、お留守の間、安心してお頂け頂ける不動産会社をお選びいただけます。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部
【イエカレ】では、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
(コラム・アドバイザー)檜垣 知宏

株式会社ライフアドバンス代表取締役の檜垣知宏です。 2014年8月に設立し、恵比寿不動産という屋号で賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理を行う不動産業者です。 不動産業界歴15年の経験を生かし、 運営しているサービスサイトである「不動産の相談窓口」の運営者も務めております。
【保有資格】宅地建物取引士
【関連URL】
[恵比寿不動産×賃貸]
[恵比寿不動産×売買]
[恵比寿不動産×リフォーム]
[不動産の相談窓口]
[資産運用の相談窓口]
[転勤東京.com]
[LGBT不動産]
[賃貸管理ナビ]
[ライフアドバンス]
Copyright (C) EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 家を貸す際に注意すべきこと
家を貸す際に注意すべきことの関連記事
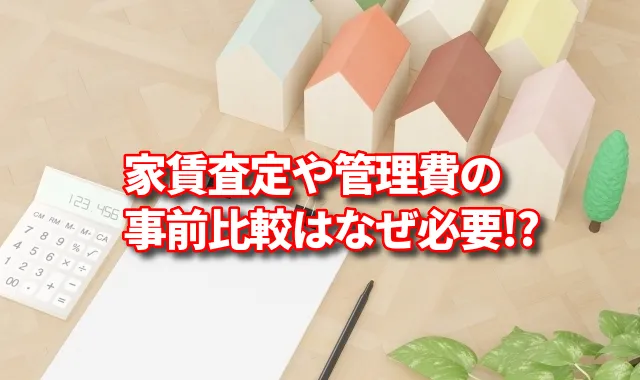
- 【自宅を貸したい場合】家賃査定や管理費の事前比較の必要性について解説します 公開
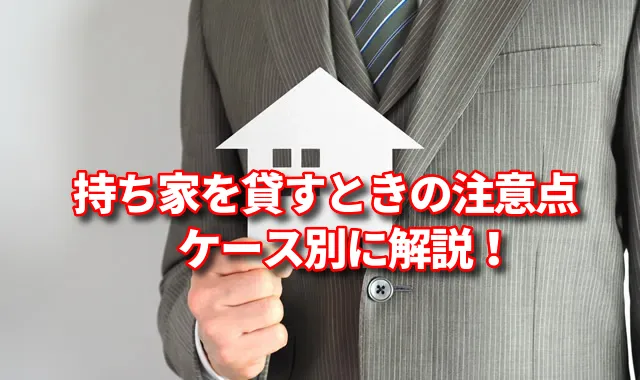
- 【家を貸す】初心者必見!持ち家を貸し出すときの注意点をケース別に詳細に解説します 公開
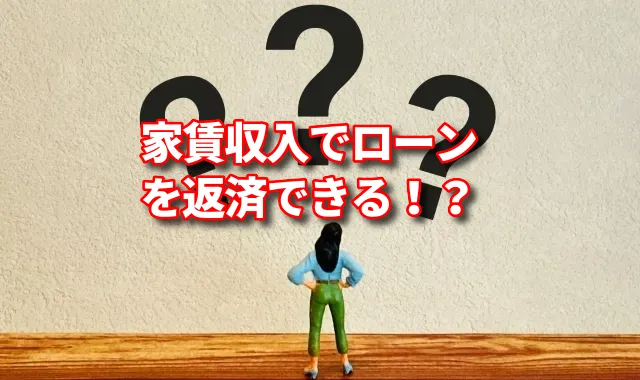
- 【賃貸管理】住宅ローン返済中に持ち家を貸すリロケーションについておしえます 公開

- 【物件の貸し出し】住宅ローン返済中の物件をリロケーションを使って貸す! 公開

- 【家を貸したい】海外赴任時のリロケーション!自家用車はどうすれば!? 公開

- 【家を貸す】定期で貸せるリロケーション!税金に関する注意点を解説します 公開

- 【家を貸したい】空き家バンクの仕組みと一般の賃貸管理会社を利用する場合の違いをお伝えします 公開

- 【空き家の活用事例】空き家ビジネスの最前線!成功事例や失敗事例をご紹介 公開

- 【家を貸したい】貸す前に絶対に確認しておきたい重要事項!! 公開

- 【持ち家を貸す】素朴な疑問!家を貸すとき家具やマイカーは置いておけるの? 公開
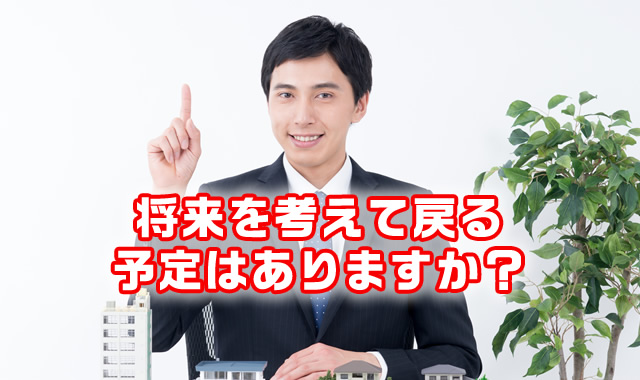
- 【持ち家を貸す】入居者退去後の原状回復の方法・事前確認をしてトラブル防止! 公開

- 【賃貸管理】大失敗しない持ち家・マンションを貸す方法!5つのチェックポイントをおしえます 公開
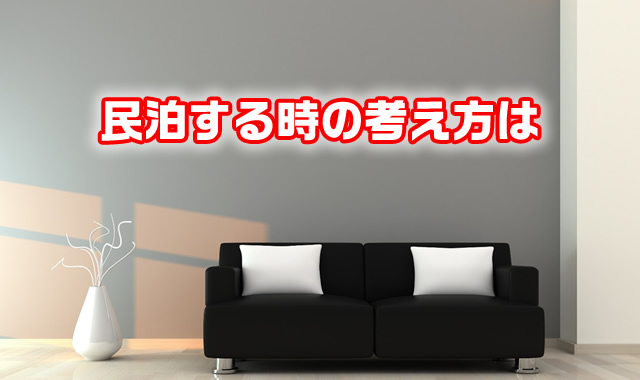
- 【民泊運営】民泊で家を貸す時の重要ポイントをおしえます! 公開
借主(入居者)の入退去時は「修繕」「ハウスクリーニング」が必要になります。とくに退去後に以下のような場合は原状回復する必要があります。
- 床や壁の傷や汚れ
- カビやシミ
- たばこなどによる匂いや汚れ
- トイレやキッチンなどの水回りの汚れ など
次の入居希望者に気持ちよく家を内見してもらい、入居を決めてもらったあとも気持ちよく家に住んでもらえるように、原状回復のための修繕やハウスクリーニングを行うことは重要な管理業務です。
また、これは補足になるのですが、借主が退去した後にリノベーションやリフォームを実施する場合は、その間空室が続くと家賃収入が途絶えることになりますので、家のどこをリノベーションやリフォームをする必要があるのか、収支もあわせて検討したうえで、無理のない範囲で、費用や工事期間を決定するようにしましょう。
物件管理についても、貸主自身で管理することができますが、管理会社に委託管理を依頼するのが一般的ですし、その方が安全です。
主な物件管理の項目は以下の3つです。
- 建物の清掃
- 建物の修繕
- 設備のメンテナンスや修理
以上3つです。
地味に思える項目だと思われた方も多いかもしれませんが、これらは意外と重要な項目ばかりです。
以下でさらに補足解説をします。
建物の清掃は、管理会社に委託管理を依頼した場合は管理会社で行ってくれるようになります。
管理会社へ委託をしない場合は、貸主自身でそれを行うか、直接、専門の清掃業者へ依頼するのも方法のひとつです。
管理会社や清掃業者に清掃業務を依頼する時は、掃除の頻度、方法、料金について予め打合せて確認をしておきましょう。
建物の清掃が行き届いていないと、借主の入居者満足度に影響が出てしまいます。
また、空室となってしまい新たな入居者を募集していた場合は、入居希望者が内見に来てくれても清掃が行き届いていないと印象が悪くなってしまい、せっかくの入居希望者が別の物件へ流れてしまう可能性が十分考えられます。
そうなってしまいますと本当に勿体ない話しです。ですから、清潔感が漂う物件にしておくことが必要です。
2-2-2.建物の修繕
これも上述しましたが、家を賃貸物件として貸し出す場合、建物の経年劣化による破損等は、貸主や管理会社側に修繕義務があります。
建物の修繕項目としては、「屋根」「柱」「床」「内装」「設備」など入居者に貸している部分全てになります。
ただ、借主がそれらを壊してしまった場合は、当然、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済してもらうことになるか?の取り決めを入居契約時にしておくことは重要です。
2-2-3.設備のメンテナンスや修理
また、建物の修繕に加えて、家の設備のメンテナンス・修理も大家または管理会社が行う対象になります。
これらも管理会社に委託管理を依頼する場合は、設備・メンテナンスの実施範囲やその管理費用について事前に取り決めておく必要があります。
ただ、設備に関しても建物同様、借主が壊してしまった場合は、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、これに関してもまた、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済をしてもらうことになるか?この取り決めも入居契約時に詰めておくことが重要です。
2-3.経営管理
これも上述しました通り、家を賃貸物件として貸して賃料収入を得る行為は、賃貸経営という「事業」にあたることになるため、以下の経営管理も必要となってきます。
- 帳簿をつける
- 確定申告をする
- 税金などの支払いをする
以上3つです。家を貸して「収支が成り立つか?」といった収支計画の確認は最低限必要となります。
ここまでご覧いただいてお分かり頂けた部分も多いかと思いますが、家を貸すと、様々な管理業務が発生します。
そうした管理業務をすべてご自身で行うことは不可能に近いでしょう。
管理業務を不動産会社や管理会社に委託管理を依頼すると当然「管理委託料」が必要になるのですが、貸主の日常生活に支障が出ることなく、家の賃貸経営が問題なく回るのであれば、大多数の方は管理費を支払ってでも家を貸すことを選択していると言えます。
自分自身が家に住んでいたときは気にする機会が少なかった支出も、貸すときは把握する必要が出てきます。
では、家を貸す場合に想定される支出にはどういうものがあるのでしょうか?
家を貸す場合に想定される支出には、以下が挙げられます。
- 固定資産税、都市計画税
- 火災保険料
- 仲介手数料(不動産会社に仲介を委託する場合)
- 管理委託料(管理業務を管理会社に委託する場合)
- 清掃費用
- 原状回復費用
- 修繕費(積み立てておくのが一般的)
2-3-1.固定資産税
「固定資産税」とは、毎年1月1日時点で土地・建物などの固定資産を所有している人に対して課税される税金です。
賃貸オーナーも毎年固定資産税を支払う必要があります。家賃収入がゼロの場合でも支払い義務は発生しますので、固定資産税分は現金を確保しておくことが大切です。
2-3-2.都市計画税
「都市計画税」とは、土地・建物を所有している人に対して、都市計画や区画整理などの費用に充てるために課税される税金です。
固定資産税に含まれていることが多く、税率は市町村によって異なりますが、上限は0.3%となっています。所有している物件がある市町村に確認しておく必要があります。
2-3-3.火災保険料
賃貸経営に際して、物件のオーナー様向けの火災保険に加入することが一般的です。
保険料は保険会社や保険商品、物件の条件などで変動します。借家の大きさや、借家がある地域、借家となる建物の建物評価額などに基づいて保険料が設定されています。保険の設計プランによって異なりますが、火災だけでなく自然災害や落雷、爆発などさまざまな災害への保障が含まれていることが一般的です。
2-3-4.仲介手数料
不動産仲介会社に物件の客付けを依頼する場合は、仲介手数料を支払う必要があります。
賃貸物件の場合、「賃貸借契約」を締結した際に支払います。物件オーナー様が不動産仲介会社に支払う仲介手数料は会社によって異なりますが、原則「賃料の半月分が上限」と宅地建物取引業法で定められています。
ただし、別途広告費の支払いについて取り決めている場合は、広告費の支払が発生します。
2-3-5.管理委託料
管理委託料の上限は法律などで決まっていません。そのため、管理会社によって金額が異なります。
平均的な管理委託料の設定は3%~8%となっています。そのため、管理会社を選ぶ時は「管理委託料がいくらになるか?」を確認して契約しましょう。
2-3-6.清掃費用
物件オーナー様自身が清掃をする場合は、掃除道具や機器、洗剤等の調達費用のみかかります。
ただし、ご自身で清掃ができない範囲については、管理会社や清掃業者に依頼をする必要があります。
物件の規模にもよりますが、数万~数十万円の費用がかかるケースがあります。
2-3-7.原状回復費用
入居者(借主)の退去時には、部屋の傷や汚れを入居前の状態まで戻すための「原状回復工事」を行います。
この原状回復の費用については、入居者との間で取り決めておく必要があります。
▶原状回復費用の補てん方法
・賃貸借契約の際、退去時に入居者から支払ってもらう契約を取り決める
・入居時の敷金から原状回復費用を支払い、残った額を入居者に返金する
なお、敷金を超える原状回復費用がかかった場合、「修繕費として入居者に請求する」か、もしくは「オーナー様が自己負担するか」どうかについても取り決めておくと、入居者とのトラブルを回避できます。
2-3-8.修繕費
修繕費は、「物件オーナー様が負担する分」と「入居者が負担する分」の2種類があります。
入居者が故意に破損した場合でなければ、物件オ-ナー様が負担することが基本です。
「ベランダの防水工事」「外壁改修」「クッションフロア張り替え」などが挙げられます。修繕にかかる費用は使う材料や依頼する業者によって異なるため、依頼業者との契約時に必ず確認しましょう。
▶賃貸収入で支出をカバーするのが基本
入居者からは敷金や礼金も支払われますが、これはあくまで1回限りのもので、基本的には毎月の賃料が賃貸収入となります。
そして、家を貸す場合にかかる支出は、この賃貸収入によってカバーするのが基本です。
そのため、家を貸すときは慎重な収支計画を立て、委託する業務と自分で行う業務についても細かく決めていくようにしましょう。
また、賃料については「どれくらいの支出があるのか?」ということを慎重に考えた上で決めましょう。
以上、賃貸事業で必要になる管理業務を網羅してみました。
ご自身のなかで必要となりそうな項目があったら、今一度よく確認してみて頂ければと思います。
【イエカレ運営局より】
【完全無料/最大8社紹介】自宅を高額家賃でお得に貸したいなら!管理プランと管理費を徹底比較。
高い家賃で経費を抑えた賃貸管理、質の高い入居者紹介ができる不動産会社を比較・選択できます!
より高くなら、各社、無料訪問査定もご対応します。お気軽にお問い合わせください。
3.ケース特有の家を貸す注意点をご紹介
ここでは「全然知りませんでした...」では済まない、家を貸すときの注意点をいくつかご紹介します。
これらも重要なものばかりです。
3-1:賃貸で借りている家を貸す「又貸し」はNG
一つ目は「又貸し」です。これは貸主というより借主側の問題ですが、貸主である賃貸オーナー様にも知っておいて欲しい内容になります。
又貸しとは「賃貸物件を契約者自身で借りているにも関わらず、その契約者自身は入居をせずにさらに別の第三者に貸す行為」のことです。
つまり、借主が自分で借りた賃貸物件には住まずに別の第三者に貸して、借主が家賃収入を得る行為です。
住まずに物件を賃貸に出すことができるのは、基本的にその賃貸物件の「所有権を持つ名義人ご自身の場合のみ」です。
「又貸しが禁止の理由」と「発見された場合にどうなるか」も以下でご紹介します。
3-1-1.又貸しがNGの理由
賃貸物件を借りた借主が、第三者に又貸しをした場合、それが原因で何らかのトラブルが発生したときは「貸主である物件オーナー様」と「借主である契約者(本来の入居者)」の間に「又貸しで住んでいる第三者」が加わることになるため、話がこじれてしまい問題解決が難しくなることが非常に多いです。
借主は入居審査を経て入居契約を交わした上で貸主から物件を借りたわけですが、又貸しで住んでいる第三者は貸主と入居契約を交わしたわけではない全くの無関係者です。
これが許されてしまうと何でも有りの世界にもなってしまいます。もちろん、第三者に又貸しを行った借主は、無断でそのような行為を行った責任を問われることになります。
貸主に多大な迷惑が掛かるのはもちろん、借主にとってもいろんな意味でリスクが高くなるため原則禁止されています。
3-1-2.又貸しが万が一発見された場合
もしも又貸しが発見された場合は、その借主は貸主側から「強制退去」や「多額の違約金の支払いが求められる」ケースがあります。
場合によっては訴訟といった裁判沙汰へ発展することもあります。ですから、貸主は、借主と結ばれる賃貸借契約書に「又貸し禁止事項」の記載がしっかりされていることをよく確認しましょう。
「少しくらいいいや」と思ったモラルがなかった借主にこうした違反行為をされてしまうと想像以上に大きな問題に発展しやすいため、借主が安易に又貸しできないように必ず契約で縛っておく必要があります。「又貸し被害」にあわない様に十分注意したいものです。
3-2.自分の持ち家全体(一軒家)を貸す場合
一軒家を所有されている方の場合、急な転勤や相続などが原因で「一時的に転勤期間だけ家を賃貸物件と貸し出したい」ですとか「実家を相続したが、居住する家族はいないのでできれば売らずに長期間貸し出したい」と考えている方は少なくないでしょう。
この章では、一軒家を貸す場合、どのような注意点があるのか以下で詳しく解説しますので気になっている方は、是非、参考にしてください。
3-2-1.外壁や屋根など一軒家特有の修繕費
一軒家を貸している間、外壁や屋根などの建物の修繕が必要になった場合、その修繕費は貸主負担となります。
大事に住んでいたとしても、建物の外壁や屋根は築年数が経てば経つほど、どうしても経年劣化による老朽化は避けられません。
不具合をそのまま放置をしてしまうと物件の資産価値が大きく下がる可能性があります。
修繕は建物の維持費用と割り切ってあらかじめ収支計画に入れておきましょう。
3-2-2.災害のリスク
これは誰にも予測がつかないことですが、災害のリスクも考慮しておくことが必要です。
例えば、地震や台風で家の一部が倒壊、または全壊した場合、修繕費用は貸主が自己負担する必要があります。
また、借主が一時的に別の賃貸物件などへ避難してせざるを得なくなった場合はその間の家賃を借主に請求することはできません。
損害を最小限に留めるためもに、火災保険や地震保険などの各種損害保険に加入しておくのがよいでしょう。
3-2-2.防犯性や管理体制
一軒家を貸す場合は、借主に安心して住んでもらえる様に、民間のセキュリティ・サービスを利用することも考慮に入れましょう。
マンションやアパートの場合でしたら、その管理業務は管理会社に依頼する方が多いのですが、一軒家の場合は、貸主ご自身でその対応をされる方も見受けられます。
マンションやアパートは玄関のオートロックや防犯カメラが設置されている場合がもはや当たり前になっていますが、一軒家では貸主ご自身で防犯対策をする必要があります。
借主の万が一に備え、住む方の「安全性」や「防犯性」に考慮した対応が求められます。
ただ、こうした対応についても家の管理業務そのものを管理会社に依頼する場合は、管理会社の担当者へ相談をすれば対策を考えてくれるはずですので、一度問い合わせてみることをお勧めします。
3-3.自宅の一室を貸す(賃貸併用住宅)の場合
また、所有している自宅の「空き部屋」だけを貸す「賃貸併用住宅」という賃貸方法があります。
賃貸併用住宅として家を貸し出す場合の注意点は、以下となりますのでこちらもあわせて確認してみて下さい。
3-3-1.賃貸併用住宅の間取り
「賃貸併用住宅」は同じ家(建物)の一部のなかに賃貸用として貸し出せる部屋が併設されている賃貸物件となります。
貸主である物件オーナー様は借主と同じ建物内で生活をすることになるため、お互いのプライバシーが保護できる動線や視線に配慮した間取りにすることが大切です。
例えば、自宅・賃貸の玄関を別々することはもちろん、借主とできるだけ顔を合わせないように設計をするとお互いのプライバシーを保護しやすくなり生活がしやすくなります。
また、防音や騒音対策への配慮も重要です。貸主と借主では生活スタイルや活動時間に違いが出る場合も考えられます。
間取りや設備の配置で防音・騒音対策を考えましょう。
3-3-2.入居者との距離感
貸主と借主のお互いのプライバシー尊重と言う点でもう一つ。
賃貸併用住宅では貸主は借主との距離感を常に一定に保つことが必要です。
貸主と借主が同じ建物内で生活をしているなかで、段々とその距離が近づき過ぎるようになると、悪い意味で「馴れ合いの関係」になってしまうことがあり、それが原因でトラブルに発展してしまうことが考えられます。
貸主と借主がフレンドリーな関係でいることはもちろん重要ですし、貸主の運用方針やスタイルにもよりますが、借主とは近すぎず遠すぎず、お互いにとって程よい距離感を保てるように模索することが重要です。
3-4.マンション、アパートを貸す場合
次は、マンションやアパートの一室を不動産投資物件として購入をして、賃貸物件として貸し出すパターンでの注意点について説明します。
この場合は以下の注意点があります。
3-4-1.入居者同士のトラブル
マンションやアパートは集合住宅と言う性質上、入居者同士のトラブルが出てしまうことを忘れずに想定しておかなくてはなりません。
そのため、借主との入居契約時にトラブルが起こりそうな項目について取り決めをしておく必要があります。
また、借主からクレームが出たらすぐに対応・対策をすることが大切です。
これは補足説明ですが「マンションやアパート一棟」の賃貸オーナーとして貸し出す場合は、貸主が全ての借主に対して自主管理で管理業務の対応することは現実的には難しいため、尚更のこと、やはり管理業務を委託できる管理会社を選定する方が望ましいと言えるでしょう。
3-4-2.管理組合の参加
分譲マンションの場合、共用部分の維持管理や各入居者の生活マナーの維持についての取り決めや管理を行うために必ず「管理組合」が設けられています。
管理組合はマンションの住民で構成をされています。例えば、理事長の選任時や、定例会に参加するか・しないかで、組合員である他の住民とトラブルになったり、管理組合の総会で議決された取り決めを実行するときに他の住民から反対にあったりする可能性がつきものです。
分譲マンションを賃貸で家を貸すときには、貸主は管理組合の一員としての役割が発生することを覚えておきましょう。
まとめ
以上、自宅の部屋や持ち家を貸すときの注意点をケース別に解説してきました。
家を賃貸物件として貸し出しす場合の「チェックポイント」をしっかりと抑えておけば、トラブルを回避しやすくなりますし、安心・安全な賃貸経営が可能となるでしょう。
家を貸す場合、以下のような注意点があります。
・賃貸借契約の種類やその内容について、細かくチェックする
・管理業務にはどのようなものがあるのか、あらかじめ把握しておく
・慎重な収支計画を立てる
貸主ご自身ですべての管理を行うことはできませんし現実的ではありません。
不動産会社では、一時的に使わない家を活用する方法について相談に乗ってくれる専門の管理会社があります。
ご自身だけで判断するのが難しい場合は、ご自身の状況を踏まえて「こんな管理業務を委託したいが可能なのか?」といった形で希望を伝えた上で、管理会社の専門家の意見を仰いでみることを強くおすすめします。
また、家を賃貸に出すにあたって、何よりも大切にしてほしいポイントがあります。
それは管理業務に関する委託管理の相談を管理会社へ依頼する場合は、できる限り、すぐに一つの不動産会社と話を進めようとしてはいけないということです。
確かに「急な転勤」などで急ぐ場合や、不動産会社との交渉が複数社に及べば、面倒で時間も手間もかかります。
そうなると「もう早く決めてしまいたい」という心理から、最初に連絡が取った会社と話を進めてしまいがちです。
しかし、よく考えて頂きたいことは「家の委託管理を依頼する」ということは、あなたの大切な不動産の管理を第三者へ依託をして、いわばあなたの賃貸経営をサポートしてもらうということです。
結果的には多くのお金が動く商取引になりますし「あの時、焦らずにもっと慎重に委託管理先を探すべきだった...」と後から悔やまれてしまうのでは本当に残念な話しとなってしまいます。
あなたの家という財産の管理をしっかり任せられる実績と実力がある管理会社を探すべきです。
また、会社探しの上では、担当者と貸主との相性も重要だといわれます。
貸主の信頼にしっかり応えようと、些細なことにも迅速に丁寧な応対をする担当者との出会いが必要です。
トラブルが起きたら逃げ腰になるような担当者は論外です。複数社の会社へ問合せを行い、応対や態度などを観察すればだいたい分かるものです。
担当者の応対で少しでも気になる点があれば条件が良かったとしてもすぐに委託契約を交わさない方が吉ということもあり得ます。そうした担当者の質も含めて「良い条件で賃貸に出す」ことを何よりも優先すべきです。
最後に、比較検討する上では、他の会社の査定内容を探ってきたり、なぜか一社だけ飛びぬけて高い賃料を提示してきた場合も要注意です。
担当者が管理契約を取りたいがために、「高い賃料を提示している」という事情が隠れている場合があるかもしれません。そのような事情を見抜くためにも、やはり比較検討は必要です。
【イエカレより】「ご自宅を貸し出したい」「空き家にしたままよりも有効活用を検討したい」とお考えの方々に、ご自宅資産に合わせて留守宅管理専門の不動産管理会社をご紹介しています。一度のご登録で、最高8社の管理会社へ家賃査定依頼が可能です!ご利用は無料です。
各社、訪問査定も対応しています!大切なご自宅資産を丁寧に査定、直接ご希望もお伺いして高額査定を目指します!入居者仲介方法、管理代行・保証内容など、各社の提案を比較できますので、お留守の間、安心してお頂け頂ける不動産会社をお選びいただけます。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部
【イエカレ】では、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
(コラム・アドバイザー)檜垣 知宏

株式会社ライフアドバンス代表取締役の檜垣知宏です。 2014年8月に設立し、恵比寿不動産という屋号で賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理を行う不動産業者です。 不動産業界歴15年の経験を生かし、 運営しているサービスサイトである「不動産の相談窓口」の運営者も務めております。
【保有資格】宅地建物取引士
【関連URL】
[恵比寿不動産×賃貸]
[恵比寿不動産×売買]
[恵比寿不動産×リフォーム]
[不動産の相談窓口]
[資産運用の相談窓口]
[転勤東京.com]
[LGBT不動産]
[賃貸管理ナビ]
[ライフアドバンス]
Copyright (C) EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 家を貸す際に注意すべきこと
家を貸す際に注意すべきことの関連記事
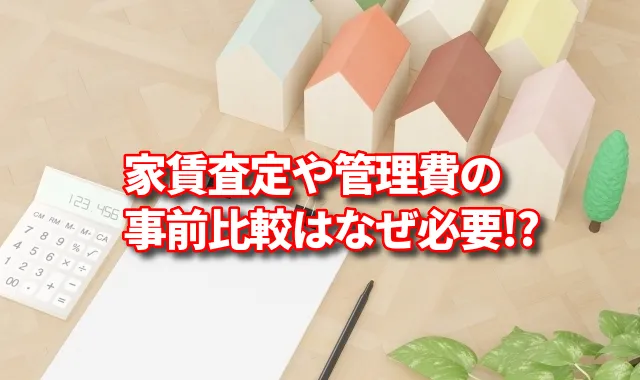
- 【自宅を貸したい場合】家賃査定や管理費の事前比較の必要性について解説します 公開
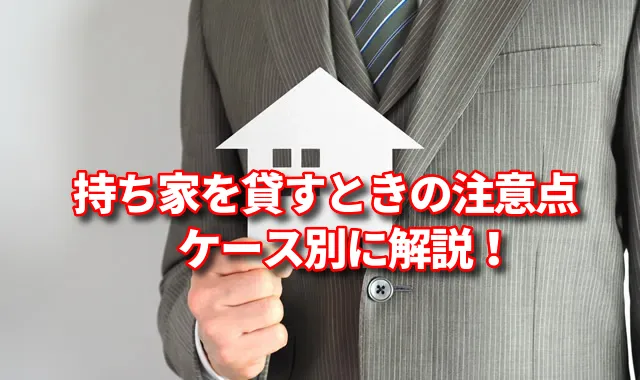
- 【家を貸す】初心者必見!持ち家を貸し出すときの注意点をケース別に詳細に解説します 公開
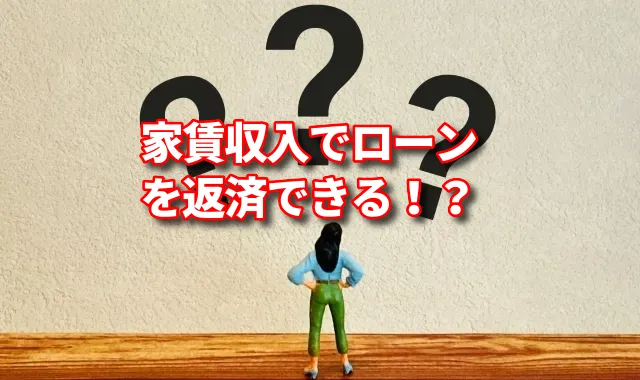
- 【賃貸管理】住宅ローン返済中に持ち家を貸すリロケーションについておしえます 公開

- 【物件の貸し出し】住宅ローン返済中の物件をリロケーションを使って貸す! 公開

- 【家を貸したい】海外赴任時のリロケーション!自家用車はどうすれば!? 公開

- 【家を貸す】定期で貸せるリロケーション!税金に関する注意点を解説します 公開

- 【家を貸したい】空き家バンクの仕組みと一般の賃貸管理会社を利用する場合の違いをお伝えします 公開

- 【空き家の活用事例】空き家ビジネスの最前線!成功事例や失敗事例をご紹介 公開

- 【家を貸したい】貸す前に絶対に確認しておきたい重要事項!! 公開

- 【持ち家を貸す】素朴な疑問!家を貸すとき家具やマイカーは置いておけるの? 公開
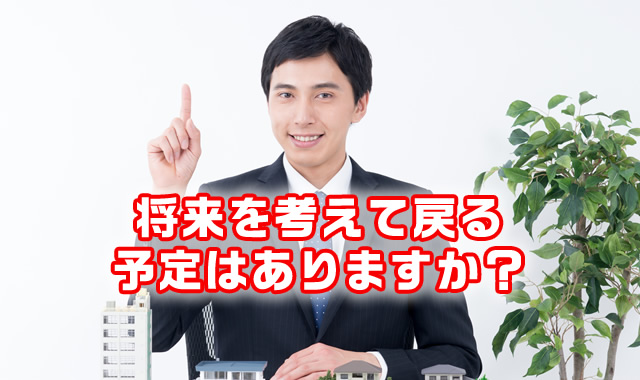
- 【持ち家を貸す】入居者退去後の原状回復の方法・事前確認をしてトラブル防止! 公開

- 【賃貸管理】大失敗しない持ち家・マンションを貸す方法!5つのチェックポイントをおしえます 公開
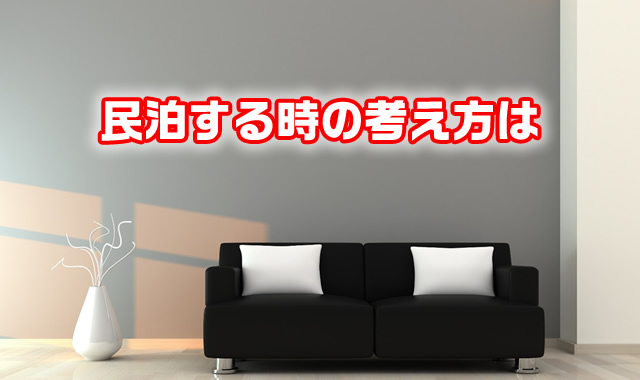
- 【民泊運営】民泊で家を貸す時の重要ポイントをおしえます! 公開
これも上述しましたが、家を賃貸物件として貸し出す場合、建物の経年劣化による破損等は、貸主や管理会社側に修繕義務があります。
建物の修繕項目としては、「屋根」「柱」「床」「内装」「設備」など入居者に貸している部分全てになります。
ただ、借主がそれらを壊してしまった場合は、当然、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済してもらうことになるか?の取り決めを入居契約時にしておくことは重要です。
また、建物の修繕に加えて、家の設備のメンテナンス・修理も大家または管理会社が行う対象になります。
これらも管理会社に委託管理を依頼する場合は、設備・メンテナンスの実施範囲やその管理費用について事前に取り決めておく必要があります。
ただ、設備に関しても建物同様、借主が壊してしまった場合は、借主が弁償をして修繕をしなければならないケースもありますから、これに関してもまた、どういう壊され方をした場合に借主側に弁済をしてもらうことになるか?この取り決めも入居契約時に詰めておくことが重要です。
2-3.経営管理
これも上述しました通り、家を賃貸物件として貸して賃料収入を得る行為は、賃貸経営という「事業」にあたることになるため、以下の経営管理も必要となってきます。
- 帳簿をつける
- 確定申告をする
- 税金などの支払いをする
以上3つです。家を貸して「収支が成り立つか?」といった収支計画の確認は最低限必要となります。
ここまでご覧いただいてお分かり頂けた部分も多いかと思いますが、家を貸すと、様々な管理業務が発生します。
そうした管理業務をすべてご自身で行うことは不可能に近いでしょう。
管理業務を不動産会社や管理会社に委託管理を依頼すると当然「管理委託料」が必要になるのですが、貸主の日常生活に支障が出ることなく、家の賃貸経営が問題なく回るのであれば、大多数の方は管理費を支払ってでも家を貸すことを選択していると言えます。
自分自身が家に住んでいたときは気にする機会が少なかった支出も、貸すときは把握する必要が出てきます。
では、家を貸す場合に想定される支出にはどういうものがあるのでしょうか?
家を貸す場合に想定される支出には、以下が挙げられます。
- 固定資産税、都市計画税
- 火災保険料
- 仲介手数料(不動産会社に仲介を委託する場合)
- 管理委託料(管理業務を管理会社に委託する場合)
- 清掃費用
- 原状回復費用
- 修繕費(積み立てておくのが一般的)
2-3-1.固定資産税
「固定資産税」とは、毎年1月1日時点で土地・建物などの固定資産を所有している人に対して課税される税金です。
賃貸オーナーも毎年固定資産税を支払う必要があります。家賃収入がゼロの場合でも支払い義務は発生しますので、固定資産税分は現金を確保しておくことが大切です。
2-3-2.都市計画税
「都市計画税」とは、土地・建物を所有している人に対して、都市計画や区画整理などの費用に充てるために課税される税金です。
固定資産税に含まれていることが多く、税率は市町村によって異なりますが、上限は0.3%となっています。所有している物件がある市町村に確認しておく必要があります。
2-3-3.火災保険料
賃貸経営に際して、物件のオーナー様向けの火災保険に加入することが一般的です。
保険料は保険会社や保険商品、物件の条件などで変動します。借家の大きさや、借家がある地域、借家となる建物の建物評価額などに基づいて保険料が設定されています。保険の設計プランによって異なりますが、火災だけでなく自然災害や落雷、爆発などさまざまな災害への保障が含まれていることが一般的です。
2-3-4.仲介手数料
不動産仲介会社に物件の客付けを依頼する場合は、仲介手数料を支払う必要があります。
賃貸物件の場合、「賃貸借契約」を締結した際に支払います。物件オーナー様が不動産仲介会社に支払う仲介手数料は会社によって異なりますが、原則「賃料の半月分が上限」と宅地建物取引業法で定められています。
ただし、別途広告費の支払いについて取り決めている場合は、広告費の支払が発生します。
2-3-5.管理委託料
管理委託料の上限は法律などで決まっていません。そのため、管理会社によって金額が異なります。
平均的な管理委託料の設定は3%~8%となっています。そのため、管理会社を選ぶ時は「管理委託料がいくらになるか?」を確認して契約しましょう。
2-3-6.清掃費用
物件オーナー様自身が清掃をする場合は、掃除道具や機器、洗剤等の調達費用のみかかります。
ただし、ご自身で清掃ができない範囲については、管理会社や清掃業者に依頼をする必要があります。
物件の規模にもよりますが、数万~数十万円の費用がかかるケースがあります。
2-3-7.原状回復費用
入居者(借主)の退去時には、部屋の傷や汚れを入居前の状態まで戻すための「原状回復工事」を行います。
この原状回復の費用については、入居者との間で取り決めておく必要があります。
▶原状回復費用の補てん方法
・賃貸借契約の際、退去時に入居者から支払ってもらう契約を取り決める
・入居時の敷金から原状回復費用を支払い、残った額を入居者に返金する
なお、敷金を超える原状回復費用がかかった場合、「修繕費として入居者に請求する」か、もしくは「オーナー様が自己負担するか」どうかについても取り決めておくと、入居者とのトラブルを回避できます。
2-3-8.修繕費
修繕費は、「物件オーナー様が負担する分」と「入居者が負担する分」の2種類があります。
入居者が故意に破損した場合でなければ、物件オ-ナー様が負担することが基本です。
「ベランダの防水工事」「外壁改修」「クッションフロア張り替え」などが挙げられます。修繕にかかる費用は使う材料や依頼する業者によって異なるため、依頼業者との契約時に必ず確認しましょう。
▶賃貸収入で支出をカバーするのが基本
入居者からは敷金や礼金も支払われますが、これはあくまで1回限りのもので、基本的には毎月の賃料が賃貸収入となります。
そして、家を貸す場合にかかる支出は、この賃貸収入によってカバーするのが基本です。
そのため、家を貸すときは慎重な収支計画を立て、委託する業務と自分で行う業務についても細かく決めていくようにしましょう。
また、賃料については「どれくらいの支出があるのか?」ということを慎重に考えた上で決めましょう。
以上、賃貸事業で必要になる管理業務を網羅してみました。
ご自身のなかで必要となりそうな項目があったら、今一度よく確認してみて頂ければと思います。
【イエカレ運営局より】
【完全無料/最大8社紹介】自宅を高額家賃でお得に貸したいなら!管理プランと管理費を徹底比較。
高い家賃で経費を抑えた賃貸管理、質の高い入居者紹介ができる不動産会社を比較・選択できます!
より高くなら、各社、無料訪問査定もご対応します。お気軽にお問い合わせください。
3.ケース特有の家を貸す注意点をご紹介
ここでは「全然知りませんでした...」では済まない、家を貸すときの注意点をいくつかご紹介します。
これらも重要なものばかりです。
3-1:賃貸で借りている家を貸す「又貸し」はNG
一つ目は「又貸し」です。これは貸主というより借主側の問題ですが、貸主である賃貸オーナー様にも知っておいて欲しい内容になります。
又貸しとは「賃貸物件を契約者自身で借りているにも関わらず、その契約者自身は入居をせずにさらに別の第三者に貸す行為」のことです。
つまり、借主が自分で借りた賃貸物件には住まずに別の第三者に貸して、借主が家賃収入を得る行為です。
住まずに物件を賃貸に出すことができるのは、基本的にその賃貸物件の「所有権を持つ名義人ご自身の場合のみ」です。
「又貸しが禁止の理由」と「発見された場合にどうなるか」も以下でご紹介します。
3-1-1.又貸しがNGの理由
賃貸物件を借りた借主が、第三者に又貸しをした場合、それが原因で何らかのトラブルが発生したときは「貸主である物件オーナー様」と「借主である契約者(本来の入居者)」の間に「又貸しで住んでいる第三者」が加わることになるため、話がこじれてしまい問題解決が難しくなることが非常に多いです。
借主は入居審査を経て入居契約を交わした上で貸主から物件を借りたわけですが、又貸しで住んでいる第三者は貸主と入居契約を交わしたわけではない全くの無関係者です。
これが許されてしまうと何でも有りの世界にもなってしまいます。もちろん、第三者に又貸しを行った借主は、無断でそのような行為を行った責任を問われることになります。
貸主に多大な迷惑が掛かるのはもちろん、借主にとってもいろんな意味でリスクが高くなるため原則禁止されています。
3-1-2.又貸しが万が一発見された場合
もしも又貸しが発見された場合は、その借主は貸主側から「強制退去」や「多額の違約金の支払いが求められる」ケースがあります。
場合によっては訴訟といった裁判沙汰へ発展することもあります。ですから、貸主は、借主と結ばれる賃貸借契約書に「又貸し禁止事項」の記載がしっかりされていることをよく確認しましょう。
「少しくらいいいや」と思ったモラルがなかった借主にこうした違反行為をされてしまうと想像以上に大きな問題に発展しやすいため、借主が安易に又貸しできないように必ず契約で縛っておく必要があります。「又貸し被害」にあわない様に十分注意したいものです。
3-2.自分の持ち家全体(一軒家)を貸す場合
一軒家を所有されている方の場合、急な転勤や相続などが原因で「一時的に転勤期間だけ家を賃貸物件と貸し出したい」ですとか「実家を相続したが、居住する家族はいないのでできれば売らずに長期間貸し出したい」と考えている方は少なくないでしょう。
この章では、一軒家を貸す場合、どのような注意点があるのか以下で詳しく解説しますので気になっている方は、是非、参考にしてください。
3-2-1.外壁や屋根など一軒家特有の修繕費
一軒家を貸している間、外壁や屋根などの建物の修繕が必要になった場合、その修繕費は貸主負担となります。
大事に住んでいたとしても、建物の外壁や屋根は築年数が経てば経つほど、どうしても経年劣化による老朽化は避けられません。
不具合をそのまま放置をしてしまうと物件の資産価値が大きく下がる可能性があります。
修繕は建物の維持費用と割り切ってあらかじめ収支計画に入れておきましょう。
3-2-2.災害のリスク
これは誰にも予測がつかないことですが、災害のリスクも考慮しておくことが必要です。
例えば、地震や台風で家の一部が倒壊、または全壊した場合、修繕費用は貸主が自己負担する必要があります。
また、借主が一時的に別の賃貸物件などへ避難してせざるを得なくなった場合はその間の家賃を借主に請求することはできません。
損害を最小限に留めるためもに、火災保険や地震保険などの各種損害保険に加入しておくのがよいでしょう。
3-2-2.防犯性や管理体制
一軒家を貸す場合は、借主に安心して住んでもらえる様に、民間のセキュリティ・サービスを利用することも考慮に入れましょう。
マンションやアパートの場合でしたら、その管理業務は管理会社に依頼する方が多いのですが、一軒家の場合は、貸主ご自身でその対応をされる方も見受けられます。
マンションやアパートは玄関のオートロックや防犯カメラが設置されている場合がもはや当たり前になっていますが、一軒家では貸主ご自身で防犯対策をする必要があります。
借主の万が一に備え、住む方の「安全性」や「防犯性」に考慮した対応が求められます。
ただ、こうした対応についても家の管理業務そのものを管理会社に依頼する場合は、管理会社の担当者へ相談をすれば対策を考えてくれるはずですので、一度問い合わせてみることをお勧めします。
3-3.自宅の一室を貸す(賃貸併用住宅)の場合
また、所有している自宅の「空き部屋」だけを貸す「賃貸併用住宅」という賃貸方法があります。
賃貸併用住宅として家を貸し出す場合の注意点は、以下となりますのでこちらもあわせて確認してみて下さい。
3-3-1.賃貸併用住宅の間取り
「賃貸併用住宅」は同じ家(建物)の一部のなかに賃貸用として貸し出せる部屋が併設されている賃貸物件となります。
貸主である物件オーナー様は借主と同じ建物内で生活をすることになるため、お互いのプライバシーが保護できる動線や視線に配慮した間取りにすることが大切です。
例えば、自宅・賃貸の玄関を別々することはもちろん、借主とできるだけ顔を合わせないように設計をするとお互いのプライバシーを保護しやすくなり生活がしやすくなります。
また、防音や騒音対策への配慮も重要です。貸主と借主では生活スタイルや活動時間に違いが出る場合も考えられます。
間取りや設備の配置で防音・騒音対策を考えましょう。
3-3-2.入居者との距離感
貸主と借主のお互いのプライバシー尊重と言う点でもう一つ。
賃貸併用住宅では貸主は借主との距離感を常に一定に保つことが必要です。
貸主と借主が同じ建物内で生活をしているなかで、段々とその距離が近づき過ぎるようになると、悪い意味で「馴れ合いの関係」になってしまうことがあり、それが原因でトラブルに発展してしまうことが考えられます。
貸主と借主がフレンドリーな関係でいることはもちろん重要ですし、貸主の運用方針やスタイルにもよりますが、借主とは近すぎず遠すぎず、お互いにとって程よい距離感を保てるように模索することが重要です。
3-4.マンション、アパートを貸す場合
次は、マンションやアパートの一室を不動産投資物件として購入をして、賃貸物件として貸し出すパターンでの注意点について説明します。
この場合は以下の注意点があります。
3-4-1.入居者同士のトラブル
マンションやアパートは集合住宅と言う性質上、入居者同士のトラブルが出てしまうことを忘れずに想定しておかなくてはなりません。
そのため、借主との入居契約時にトラブルが起こりそうな項目について取り決めをしておく必要があります。
また、借主からクレームが出たらすぐに対応・対策をすることが大切です。
これは補足説明ですが「マンションやアパート一棟」の賃貸オーナーとして貸し出す場合は、貸主が全ての借主に対して自主管理で管理業務の対応することは現実的には難しいため、尚更のこと、やはり管理業務を委託できる管理会社を選定する方が望ましいと言えるでしょう。
3-4-2.管理組合の参加
分譲マンションの場合、共用部分の維持管理や各入居者の生活マナーの維持についての取り決めや管理を行うために必ず「管理組合」が設けられています。
管理組合はマンションの住民で構成をされています。例えば、理事長の選任時や、定例会に参加するか・しないかで、組合員である他の住民とトラブルになったり、管理組合の総会で議決された取り決めを実行するときに他の住民から反対にあったりする可能性がつきものです。
分譲マンションを賃貸で家を貸すときには、貸主は管理組合の一員としての役割が発生することを覚えておきましょう。
まとめ
以上、自宅の部屋や持ち家を貸すときの注意点をケース別に解説してきました。
家を賃貸物件として貸し出しす場合の「チェックポイント」をしっかりと抑えておけば、トラブルを回避しやすくなりますし、安心・安全な賃貸経営が可能となるでしょう。
家を貸す場合、以下のような注意点があります。
・賃貸借契約の種類やその内容について、細かくチェックする
・管理業務にはどのようなものがあるのか、あらかじめ把握しておく
・慎重な収支計画を立てる
貸主ご自身ですべての管理を行うことはできませんし現実的ではありません。
不動産会社では、一時的に使わない家を活用する方法について相談に乗ってくれる専門の管理会社があります。
ご自身だけで判断するのが難しい場合は、ご自身の状況を踏まえて「こんな管理業務を委託したいが可能なのか?」といった形で希望を伝えた上で、管理会社の専門家の意見を仰いでみることを強くおすすめします。
また、家を賃貸に出すにあたって、何よりも大切にしてほしいポイントがあります。
それは管理業務に関する委託管理の相談を管理会社へ依頼する場合は、できる限り、すぐに一つの不動産会社と話を進めようとしてはいけないということです。
確かに「急な転勤」などで急ぐ場合や、不動産会社との交渉が複数社に及べば、面倒で時間も手間もかかります。
そうなると「もう早く決めてしまいたい」という心理から、最初に連絡が取った会社と話を進めてしまいがちです。
しかし、よく考えて頂きたいことは「家の委託管理を依頼する」ということは、あなたの大切な不動産の管理を第三者へ依託をして、いわばあなたの賃貸経営をサポートしてもらうということです。
結果的には多くのお金が動く商取引になりますし「あの時、焦らずにもっと慎重に委託管理先を探すべきだった...」と後から悔やまれてしまうのでは本当に残念な話しとなってしまいます。
あなたの家という財産の管理をしっかり任せられる実績と実力がある管理会社を探すべきです。
また、会社探しの上では、担当者と貸主との相性も重要だといわれます。
貸主の信頼にしっかり応えようと、些細なことにも迅速に丁寧な応対をする担当者との出会いが必要です。
トラブルが起きたら逃げ腰になるような担当者は論外です。複数社の会社へ問合せを行い、応対や態度などを観察すればだいたい分かるものです。
担当者の応対で少しでも気になる点があれば条件が良かったとしてもすぐに委託契約を交わさない方が吉ということもあり得ます。そうした担当者の質も含めて「良い条件で賃貸に出す」ことを何よりも優先すべきです。
最後に、比較検討する上では、他の会社の査定内容を探ってきたり、なぜか一社だけ飛びぬけて高い賃料を提示してきた場合も要注意です。
担当者が管理契約を取りたいがために、「高い賃料を提示している」という事情が隠れている場合があるかもしれません。そのような事情を見抜くためにも、やはり比較検討は必要です。
【イエカレより】「ご自宅を貸し出したい」「空き家にしたままよりも有効活用を検討したい」とお考えの方々に、ご自宅資産に合わせて留守宅管理専門の不動産管理会社をご紹介しています。一度のご登録で、最高8社の管理会社へ家賃査定依頼が可能です!ご利用は無料です。
各社、訪問査定も対応しています!大切なご自宅資産を丁寧に査定、直接ご希望もお伺いして高額査定を目指します!入居者仲介方法、管理代行・保証内容など、各社の提案を比較できますので、お留守の間、安心してお頂け頂ける不動産会社をお選びいただけます。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部
【イエカレ】では、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
(コラム・アドバイザー)檜垣 知宏

株式会社ライフアドバンス代表取締役の檜垣知宏です。 2014年8月に設立し、恵比寿不動産という屋号で賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理を行う不動産業者です。 不動産業界歴15年の経験を生かし、 運営しているサービスサイトである「不動産の相談窓口」の運営者も務めております。
【保有資格】宅地建物取引士
【関連URL】
[恵比寿不動産×賃貸]
[恵比寿不動産×売買]
[恵比寿不動産×リフォーム]
[不動産の相談窓口]
[資産運用の相談窓口]
[転勤東京.com]
[LGBT不動産]
[賃貸管理ナビ]
[ライフアドバンス]
Copyright (C) EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 家を貸す際に注意すべきこと
家を貸す際に注意すべきことの関連記事
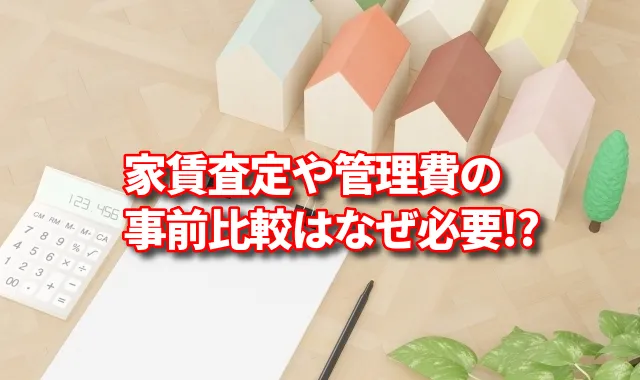
- 【自宅を貸したい場合】家賃査定や管理費の事前比較の必要性について解説します 公開
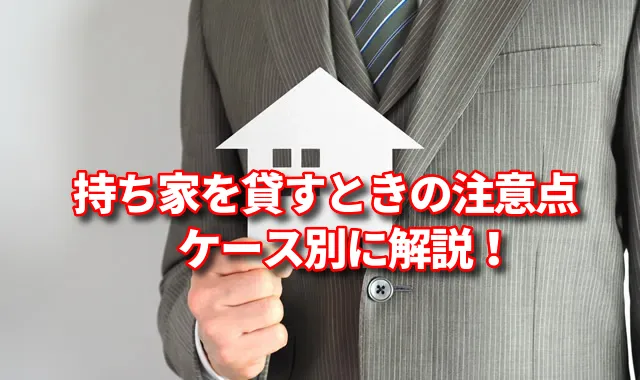
- 【家を貸す】初心者必見!持ち家を貸し出すときの注意点をケース別に詳細に解説します 公開
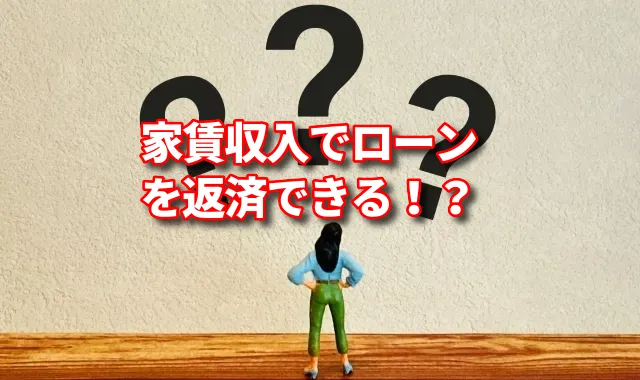
- 【賃貸管理】住宅ローン返済中に持ち家を貸すリロケーションについておしえます 公開

- 【物件の貸し出し】住宅ローン返済中の物件をリロケーションを使って貸す! 公開

- 【家を貸したい】海外赴任時のリロケーション!自家用車はどうすれば!? 公開

- 【家を貸す】定期で貸せるリロケーション!税金に関する注意点を解説します 公開

- 【家を貸したい】空き家バンクの仕組みと一般の賃貸管理会社を利用する場合の違いをお伝えします 公開

- 【空き家の活用事例】空き家ビジネスの最前線!成功事例や失敗事例をご紹介 公開

- 【家を貸したい】貸す前に絶対に確認しておきたい重要事項!! 公開

- 【持ち家を貸す】素朴な疑問!家を貸すとき家具やマイカーは置いておけるの? 公開
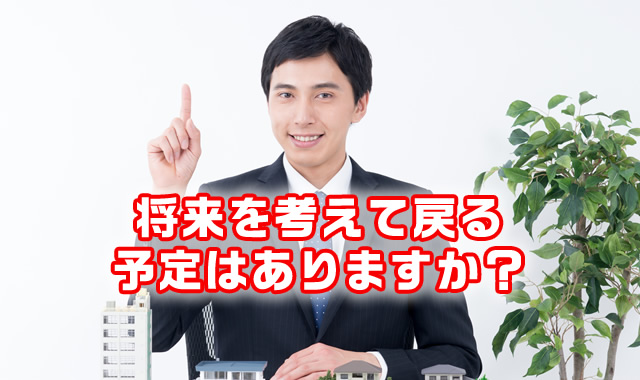
- 【持ち家を貸す】入居者退去後の原状回復の方法・事前確認をしてトラブル防止! 公開

- 【賃貸管理】大失敗しない持ち家・マンションを貸す方法!5つのチェックポイントをおしえます 公開
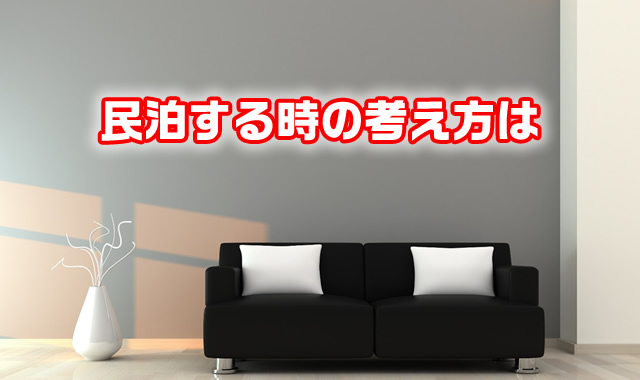
- 【民泊運営】民泊で家を貸す時の重要ポイントをおしえます! 公開
管理委託料の上限は法律などで決まっていません。そのため、管理会社によって金額が異なります。 平均的な管理委託料の設定は3%~8%となっています。そのため、管理会社を選ぶ時は「管理委託料がいくらになるか?」を確認して契約しましょう。
物件オーナー様自身が清掃をする場合は、掃除道具や機器、洗剤等の調達費用のみかかります。
ただし、ご自身で清掃ができない範囲については、管理会社や清掃業者に依頼をする必要があります。
物件の規模にもよりますが、数万~数十万円の費用がかかるケースがあります。
2-3-7.原状回復費用
入居者(借主)の退去時には、部屋の傷や汚れを入居前の状態まで戻すための「原状回復工事」を行います。
この原状回復の費用については、入居者との間で取り決めておく必要があります。
▶原状回復費用の補てん方法
・賃貸借契約の際、退去時に入居者から支払ってもらう契約を取り決める
・入居時の敷金から原状回復費用を支払い、残った額を入居者に返金する
なお、敷金を超える原状回復費用がかかった場合、「修繕費として入居者に請求する」か、もしくは「オーナー様が自己負担するか」どうかについても取り決めておくと、入居者とのトラブルを回避できます。
2-3-8.修繕費
修繕費は、「物件オーナー様が負担する分」と「入居者が負担する分」の2種類があります。
入居者が故意に破損した場合でなければ、物件オ-ナー様が負担することが基本です。
「ベランダの防水工事」「外壁改修」「クッションフロア張り替え」などが挙げられます。修繕にかかる費用は使う材料や依頼する業者によって異なるため、依頼業者との契約時に必ず確認しましょう。
▶賃貸収入で支出をカバーするのが基本
入居者からは敷金や礼金も支払われますが、これはあくまで1回限りのもので、基本的には毎月の賃料が賃貸収入となります。
そして、家を貸す場合にかかる支出は、この賃貸収入によってカバーするのが基本です。
そのため、家を貸すときは慎重な収支計画を立て、委託する業務と自分で行う業務についても細かく決めていくようにしましょう。
また、賃料については「どれくらいの支出があるのか?」ということを慎重に考えた上で決めましょう。
以上、賃貸事業で必要になる管理業務を網羅してみました。
ご自身のなかで必要となりそうな項目があったら、今一度よく確認してみて頂ければと思います。
【イエカレ運営局より】
【完全無料/最大8社紹介】自宅を高額家賃でお得に貸したいなら!管理プランと管理費を徹底比較。
高い家賃で経費を抑えた賃貸管理、質の高い入居者紹介ができる不動産会社を比較・選択できます!
より高くなら、各社、無料訪問査定もご対応します。お気軽にお問い合わせください。
3.ケース特有の家を貸す注意点をご紹介
ここでは「全然知りませんでした...」では済まない、家を貸すときの注意点をいくつかご紹介します。
これらも重要なものばかりです。
3-1:賃貸で借りている家を貸す「又貸し」はNG
一つ目は「又貸し」です。これは貸主というより借主側の問題ですが、貸主である賃貸オーナー様にも知っておいて欲しい内容になります。
又貸しとは「賃貸物件を契約者自身で借りているにも関わらず、その契約者自身は入居をせずにさらに別の第三者に貸す行為」のことです。
つまり、借主が自分で借りた賃貸物件には住まずに別の第三者に貸して、借主が家賃収入を得る行為です。
住まずに物件を賃貸に出すことができるのは、基本的にその賃貸物件の「所有権を持つ名義人ご自身の場合のみ」です。
「又貸しが禁止の理由」と「発見された場合にどうなるか」も以下でご紹介します。
3-1-1.又貸しがNGの理由
賃貸物件を借りた借主が、第三者に又貸しをした場合、それが原因で何らかのトラブルが発生したときは「貸主である物件オーナー様」と「借主である契約者(本来の入居者)」の間に「又貸しで住んでいる第三者」が加わることになるため、話がこじれてしまい問題解決が難しくなることが非常に多いです。
借主は入居審査を経て入居契約を交わした上で貸主から物件を借りたわけですが、又貸しで住んでいる第三者は貸主と入居契約を交わしたわけではない全くの無関係者です。
これが許されてしまうと何でも有りの世界にもなってしまいます。もちろん、第三者に又貸しを行った借主は、無断でそのような行為を行った責任を問われることになります。
貸主に多大な迷惑が掛かるのはもちろん、借主にとってもいろんな意味でリスクが高くなるため原則禁止されています。
3-1-2.又貸しが万が一発見された場合
もしも又貸しが発見された場合は、その借主は貸主側から「強制退去」や「多額の違約金の支払いが求められる」ケースがあります。
場合によっては訴訟といった裁判沙汰へ発展することもあります。ですから、貸主は、借主と結ばれる賃貸借契約書に「又貸し禁止事項」の記載がしっかりされていることをよく確認しましょう。
「少しくらいいいや」と思ったモラルがなかった借主にこうした違反行為をされてしまうと想像以上に大きな問題に発展しやすいため、借主が安易に又貸しできないように必ず契約で縛っておく必要があります。「又貸し被害」にあわない様に十分注意したいものです。
3-2.自分の持ち家全体(一軒家)を貸す場合
一軒家を所有されている方の場合、急な転勤や相続などが原因で「一時的に転勤期間だけ家を賃貸物件と貸し出したい」ですとか「実家を相続したが、居住する家族はいないのでできれば売らずに長期間貸し出したい」と考えている方は少なくないでしょう。
この章では、一軒家を貸す場合、どのような注意点があるのか以下で詳しく解説しますので気になっている方は、是非、参考にしてください。
3-2-1.外壁や屋根など一軒家特有の修繕費
一軒家を貸している間、外壁や屋根などの建物の修繕が必要になった場合、その修繕費は貸主負担となります。
大事に住んでいたとしても、建物の外壁や屋根は築年数が経てば経つほど、どうしても経年劣化による老朽化は避けられません。
不具合をそのまま放置をしてしまうと物件の資産価値が大きく下がる可能性があります。
修繕は建物の維持費用と割り切ってあらかじめ収支計画に入れておきましょう。
3-2-2.災害のリスク
これは誰にも予測がつかないことですが、災害のリスクも考慮しておくことが必要です。
例えば、地震や台風で家の一部が倒壊、または全壊した場合、修繕費用は貸主が自己負担する必要があります。
また、借主が一時的に別の賃貸物件などへ避難してせざるを得なくなった場合はその間の家賃を借主に請求することはできません。
損害を最小限に留めるためもに、火災保険や地震保険などの各種損害保険に加入しておくのがよいでしょう。
3-2-2.防犯性や管理体制
一軒家を貸す場合は、借主に安心して住んでもらえる様に、民間のセキュリティ・サービスを利用することも考慮に入れましょう。
マンションやアパートの場合でしたら、その管理業務は管理会社に依頼する方が多いのですが、一軒家の場合は、貸主ご自身でその対応をされる方も見受けられます。
マンションやアパートは玄関のオートロックや防犯カメラが設置されている場合がもはや当たり前になっていますが、一軒家では貸主ご自身で防犯対策をする必要があります。
借主の万が一に備え、住む方の「安全性」や「防犯性」に考慮した対応が求められます。
ただ、こうした対応についても家の管理業務そのものを管理会社に依頼する場合は、管理会社の担当者へ相談をすれば対策を考えてくれるはずですので、一度問い合わせてみることをお勧めします。
3-3.自宅の一室を貸す(賃貸併用住宅)の場合
また、所有している自宅の「空き部屋」だけを貸す「賃貸併用住宅」という賃貸方法があります。
賃貸併用住宅として家を貸し出す場合の注意点は、以下となりますのでこちらもあわせて確認してみて下さい。
3-3-1.賃貸併用住宅の間取り
「賃貸併用住宅」は同じ家(建物)の一部のなかに賃貸用として貸し出せる部屋が併設されている賃貸物件となります。
貸主である物件オーナー様は借主と同じ建物内で生活をすることになるため、お互いのプライバシーが保護できる動線や視線に配慮した間取りにすることが大切です。
例えば、自宅・賃貸の玄関を別々することはもちろん、借主とできるだけ顔を合わせないように設計をするとお互いのプライバシーを保護しやすくなり生活がしやすくなります。
また、防音や騒音対策への配慮も重要です。貸主と借主では生活スタイルや活動時間に違いが出る場合も考えられます。
間取りや設備の配置で防音・騒音対策を考えましょう。
3-3-2.入居者との距離感
貸主と借主のお互いのプライバシー尊重と言う点でもう一つ。
賃貸併用住宅では貸主は借主との距離感を常に一定に保つことが必要です。
貸主と借主が同じ建物内で生活をしているなかで、段々とその距離が近づき過ぎるようになると、悪い意味で「馴れ合いの関係」になってしまうことがあり、それが原因でトラブルに発展してしまうことが考えられます。
貸主と借主がフレンドリーな関係でいることはもちろん重要ですし、貸主の運用方針やスタイルにもよりますが、借主とは近すぎず遠すぎず、お互いにとって程よい距離感を保てるように模索することが重要です。
3-4.マンション、アパートを貸す場合
次は、マンションやアパートの一室を不動産投資物件として購入をして、賃貸物件として貸し出すパターンでの注意点について説明します。
この場合は以下の注意点があります。
3-4-1.入居者同士のトラブル
マンションやアパートは集合住宅と言う性質上、入居者同士のトラブルが出てしまうことを忘れずに想定しておかなくてはなりません。
そのため、借主との入居契約時にトラブルが起こりそうな項目について取り決めをしておく必要があります。
また、借主からクレームが出たらすぐに対応・対策をすることが大切です。
これは補足説明ですが「マンションやアパート一棟」の賃貸オーナーとして貸し出す場合は、貸主が全ての借主に対して自主管理で管理業務の対応することは現実的には難しいため、尚更のこと、やはり管理業務を委託できる管理会社を選定する方が望ましいと言えるでしょう。
3-4-2.管理組合の参加
分譲マンションの場合、共用部分の維持管理や各入居者の生活マナーの維持についての取り決めや管理を行うために必ず「管理組合」が設けられています。
管理組合はマンションの住民で構成をされています。例えば、理事長の選任時や、定例会に参加するか・しないかで、組合員である他の住民とトラブルになったり、管理組合の総会で議決された取り決めを実行するときに他の住民から反対にあったりする可能性がつきものです。
分譲マンションを賃貸で家を貸すときには、貸主は管理組合の一員としての役割が発生することを覚えておきましょう。
まとめ
以上、自宅の部屋や持ち家を貸すときの注意点をケース別に解説してきました。
家を賃貸物件として貸し出しす場合の「チェックポイント」をしっかりと抑えておけば、トラブルを回避しやすくなりますし、安心・安全な賃貸経営が可能となるでしょう。
家を貸す場合、以下のような注意点があります。
・賃貸借契約の種類やその内容について、細かくチェックする
・管理業務にはどのようなものがあるのか、あらかじめ把握しておく
・慎重な収支計画を立てる
貸主ご自身ですべての管理を行うことはできませんし現実的ではありません。
不動産会社では、一時的に使わない家を活用する方法について相談に乗ってくれる専門の管理会社があります。
ご自身だけで判断するのが難しい場合は、ご自身の状況を踏まえて「こんな管理業務を委託したいが可能なのか?」といった形で希望を伝えた上で、管理会社の専門家の意見を仰いでみることを強くおすすめします。
また、家を賃貸に出すにあたって、何よりも大切にしてほしいポイントがあります。
それは管理業務に関する委託管理の相談を管理会社へ依頼する場合は、できる限り、すぐに一つの不動産会社と話を進めようとしてはいけないということです。
確かに「急な転勤」などで急ぐ場合や、不動産会社との交渉が複数社に及べば、面倒で時間も手間もかかります。
そうなると「もう早く決めてしまいたい」という心理から、最初に連絡が取った会社と話を進めてしまいがちです。
しかし、よく考えて頂きたいことは「家の委託管理を依頼する」ということは、あなたの大切な不動産の管理を第三者へ依託をして、いわばあなたの賃貸経営をサポートしてもらうということです。
結果的には多くのお金が動く商取引になりますし「あの時、焦らずにもっと慎重に委託管理先を探すべきだった...」と後から悔やまれてしまうのでは本当に残念な話しとなってしまいます。
あなたの家という財産の管理をしっかり任せられる実績と実力がある管理会社を探すべきです。
また、会社探しの上では、担当者と貸主との相性も重要だといわれます。
貸主の信頼にしっかり応えようと、些細なことにも迅速に丁寧な応対をする担当者との出会いが必要です。
トラブルが起きたら逃げ腰になるような担当者は論外です。複数社の会社へ問合せを行い、応対や態度などを観察すればだいたい分かるものです。
担当者の応対で少しでも気になる点があれば条件が良かったとしてもすぐに委託契約を交わさない方が吉ということもあり得ます。そうした担当者の質も含めて「良い条件で賃貸に出す」ことを何よりも優先すべきです。
最後に、比較検討する上では、他の会社の査定内容を探ってきたり、なぜか一社だけ飛びぬけて高い賃料を提示してきた場合も要注意です。
担当者が管理契約を取りたいがために、「高い賃料を提示している」という事情が隠れている場合があるかもしれません。そのような事情を見抜くためにも、やはり比較検討は必要です。
【イエカレより】「ご自宅を貸し出したい」「空き家にしたままよりも有効活用を検討したい」とお考えの方々に、ご自宅資産に合わせて留守宅管理専門の不動産管理会社をご紹介しています。一度のご登録で、最高8社の管理会社へ家賃査定依頼が可能です!ご利用は無料です。
各社、訪問査定も対応しています!大切なご自宅資産を丁寧に査定、直接ご希望もお伺いして高額査定を目指します!入居者仲介方法、管理代行・保証内容など、各社の提案を比較できますので、お留守の間、安心してお頂け頂ける不動産会社をお選びいただけます。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部
【イエカレ】では、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
(コラム・アドバイザー)檜垣 知宏

株式会社ライフアドバンス代表取締役の檜垣知宏です。 2014年8月に設立し、恵比寿不動産という屋号で賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理を行う不動産業者です。 不動産業界歴15年の経験を生かし、 運営しているサービスサイトである「不動産の相談窓口」の運営者も務めております。
【保有資格】宅地建物取引士
【関連URL】
[恵比寿不動産×賃貸]
[恵比寿不動産×売買]
[恵比寿不動産×リフォーム]
[不動産の相談窓口]
[資産運用の相談窓口]
[転勤東京.com]
[LGBT不動産]
[賃貸管理ナビ]
[ライフアドバンス]
Copyright (C) EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 家を貸す際に注意すべきこと
家を貸す際に注意すべきことの関連記事
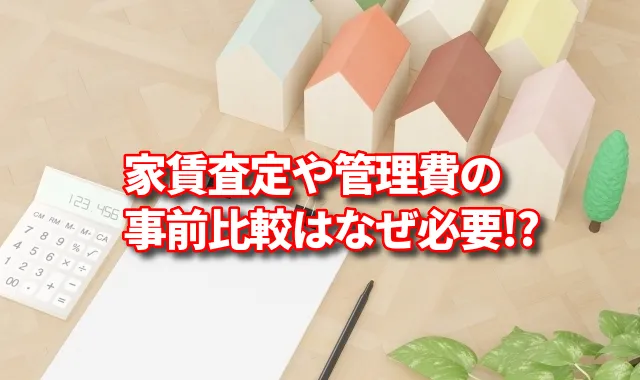
- 【自宅を貸したい場合】家賃査定や管理費の事前比較の必要性について解説します 公開
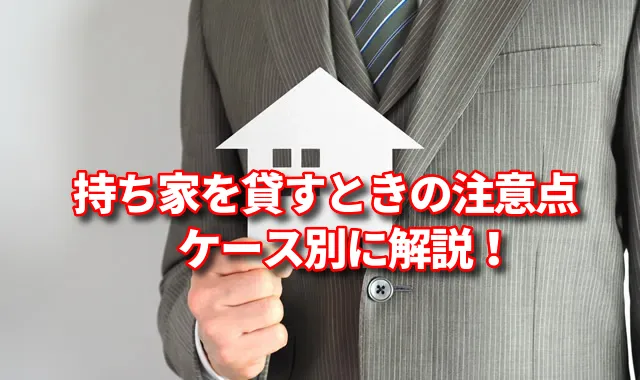
- 【家を貸す】初心者必見!持ち家を貸し出すときの注意点をケース別に詳細に解説します 公開
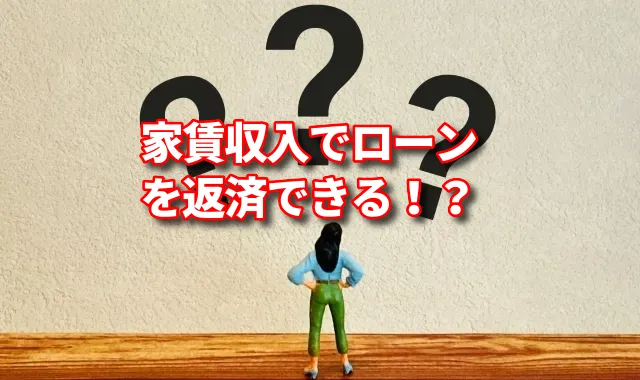
- 【賃貸管理】住宅ローン返済中に持ち家を貸すリロケーションについておしえます 公開

- 【物件の貸し出し】住宅ローン返済中の物件をリロケーションを使って貸す! 公開

- 【家を貸したい】海外赴任時のリロケーション!自家用車はどうすれば!? 公開

- 【家を貸す】定期で貸せるリロケーション!税金に関する注意点を解説します 公開

- 【家を貸したい】空き家バンクの仕組みと一般の賃貸管理会社を利用する場合の違いをお伝えします 公開

- 【空き家の活用事例】空き家ビジネスの最前線!成功事例や失敗事例をご紹介 公開

- 【家を貸したい】貸す前に絶対に確認しておきたい重要事項!! 公開

- 【持ち家を貸す】素朴な疑問!家を貸すとき家具やマイカーは置いておけるの? 公開
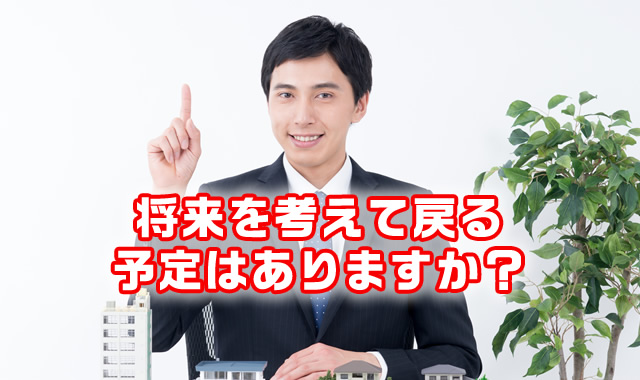
- 【持ち家を貸す】入居者退去後の原状回復の方法・事前確認をしてトラブル防止! 公開

- 【賃貸管理】大失敗しない持ち家・マンションを貸す方法!5つのチェックポイントをおしえます 公開
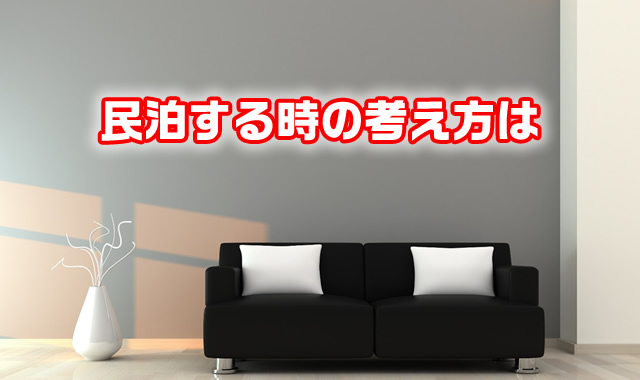
- 【民泊運営】民泊で家を貸す時の重要ポイントをおしえます! 公開
入居者(借主)の退去時には、部屋の傷や汚れを入居前の状態まで戻すための「原状回復工事」を行います。
この原状回復の費用については、入居者との間で取り決めておく必要があります。
▶原状回復費用の補てん方法
・賃貸借契約の際、退去時に入居者から支払ってもらう契約を取り決める
・入居時の敷金から原状回復費用を支払い、残った額を入居者に返金する
なお、敷金を超える原状回復費用がかかった場合、「修繕費として入居者に請求する」か、もしくは「オーナー様が自己負担するか」どうかについても取り決めておくと、入居者とのトラブルを回避できます。
修繕費は、「物件オーナー様が負担する分」と「入居者が負担する分」の2種類があります。
入居者が故意に破損した場合でなければ、物件オ-ナー様が負担することが基本です。
「ベランダの防水工事」「外壁改修」「クッションフロア張り替え」などが挙げられます。修繕にかかる費用は使う材料や依頼する業者によって異なるため、依頼業者との契約時に必ず確認しましょう。
▶賃貸収入で支出をカバーするのが基本
入居者からは敷金や礼金も支払われますが、これはあくまで1回限りのもので、基本的には毎月の賃料が賃貸収入となります。
そして、家を貸す場合にかかる支出は、この賃貸収入によってカバーするのが基本です。
そのため、家を貸すときは慎重な収支計画を立て、委託する業務と自分で行う業務についても細かく決めていくようにしましょう。
また、賃料については「どれくらいの支出があるのか?」ということを慎重に考えた上で決めましょう。
以上、賃貸事業で必要になる管理業務を網羅してみました。
ご自身のなかで必要となりそうな項目があったら、今一度よく確認してみて頂ければと思います。
【イエカレ運営局より】
【完全無料/最大8社紹介】自宅を高額家賃でお得に貸したいなら!管理プランと管理費を徹底比較。
高い家賃で経費を抑えた賃貸管理、質の高い入居者紹介ができる不動産会社を比較・選択できます!
より高くなら、各社、無料訪問査定もご対応します。お気軽にお問い合わせください。
3.ケース特有の家を貸す注意点をご紹介
ここでは「全然知りませんでした...」では済まない、家を貸すときの注意点をいくつかご紹介します。 これらも重要なものばかりです。
3-1:賃貸で借りている家を貸す「又貸し」はNG
一つ目は「又貸し」です。これは貸主というより借主側の問題ですが、貸主である賃貸オーナー様にも知っておいて欲しい内容になります。
又貸しとは「賃貸物件を契約者自身で借りているにも関わらず、その契約者自身は入居をせずにさらに別の第三者に貸す行為」のことです。
つまり、借主が自分で借りた賃貸物件には住まずに別の第三者に貸して、借主が家賃収入を得る行為です。
住まずに物件を賃貸に出すことができるのは、基本的にその賃貸物件の「所有権を持つ名義人ご自身の場合のみ」です。
「又貸しが禁止の理由」と「発見された場合にどうなるか」も以下でご紹介します。
3-1-1.又貸しがNGの理由
賃貸物件を借りた借主が、第三者に又貸しをした場合、それが原因で何らかのトラブルが発生したときは「貸主である物件オーナー様」と「借主である契約者(本来の入居者)」の間に「又貸しで住んでいる第三者」が加わることになるため、話がこじれてしまい問題解決が難しくなることが非常に多いです。
借主は入居審査を経て入居契約を交わした上で貸主から物件を借りたわけですが、又貸しで住んでいる第三者は貸主と入居契約を交わしたわけではない全くの無関係者です。
これが許されてしまうと何でも有りの世界にもなってしまいます。もちろん、第三者に又貸しを行った借主は、無断でそのような行為を行った責任を問われることになります。
貸主に多大な迷惑が掛かるのはもちろん、借主にとってもいろんな意味でリスクが高くなるため原則禁止されています。
3-1-2.又貸しが万が一発見された場合
もしも又貸しが発見された場合は、その借主は貸主側から「強制退去」や「多額の違約金の支払いが求められる」ケースがあります。
場合によっては訴訟といった裁判沙汰へ発展することもあります。ですから、貸主は、借主と結ばれる賃貸借契約書に「又貸し禁止事項」の記載がしっかりされていることをよく確認しましょう。
「少しくらいいいや」と思ったモラルがなかった借主にこうした違反行為をされてしまうと想像以上に大きな問題に発展しやすいため、借主が安易に又貸しできないように必ず契約で縛っておく必要があります。「又貸し被害」にあわない様に十分注意したいものです。
3-2.自分の持ち家全体(一軒家)を貸す場合
一軒家を所有されている方の場合、急な転勤や相続などが原因で「一時的に転勤期間だけ家を賃貸物件と貸し出したい」ですとか「実家を相続したが、居住する家族はいないのでできれば売らずに長期間貸し出したい」と考えている方は少なくないでしょう。
この章では、一軒家を貸す場合、どのような注意点があるのか以下で詳しく解説しますので気になっている方は、是非、参考にしてください。
一軒家を貸している間、外壁や屋根などの建物の修繕が必要になった場合、その修繕費は貸主負担となります。
大事に住んでいたとしても、建物の外壁や屋根は築年数が経てば経つほど、どうしても経年劣化による老朽化は避けられません。
不具合をそのまま放置をしてしまうと物件の資産価値が大きく下がる可能性があります。
修繕は建物の維持費用と割り切ってあらかじめ収支計画に入れておきましょう。
これは誰にも予測がつかないことですが、災害のリスクも考慮しておくことが必要です。
例えば、地震や台風で家の一部が倒壊、または全壊した場合、修繕費用は貸主が自己負担する必要があります。
また、借主が一時的に別の賃貸物件などへ避難してせざるを得なくなった場合はその間の家賃を借主に請求することはできません。
損害を最小限に留めるためもに、火災保険や地震保険などの各種損害保険に加入しておくのがよいでしょう。
一軒家を貸す場合は、借主に安心して住んでもらえる様に、民間のセキュリティ・サービスを利用することも考慮に入れましょう。
マンションやアパートの場合でしたら、その管理業務は管理会社に依頼する方が多いのですが、一軒家の場合は、貸主ご自身でその対応をされる方も見受けられます。
マンションやアパートは玄関のオートロックや防犯カメラが設置されている場合がもはや当たり前になっていますが、一軒家では貸主ご自身で防犯対策をする必要があります。
借主の万が一に備え、住む方の「安全性」や「防犯性」に考慮した対応が求められます。
ただ、こうした対応についても家の管理業務そのものを管理会社に依頼する場合は、管理会社の担当者へ相談をすれば対策を考えてくれるはずですので、一度問い合わせてみることをお勧めします。
また、所有している自宅の「空き部屋」だけを貸す「賃貸併用住宅」という賃貸方法があります。 賃貸併用住宅として家を貸し出す場合の注意点は、以下となりますのでこちらもあわせて確認してみて下さい。
「賃貸併用住宅」は同じ家(建物)の一部のなかに賃貸用として貸し出せる部屋が併設されている賃貸物件となります。
貸主である物件オーナー様は借主と同じ建物内で生活をすることになるため、お互いのプライバシーが保護できる動線や視線に配慮した間取りにすることが大切です。
例えば、自宅・賃貸の玄関を別々することはもちろん、借主とできるだけ顔を合わせないように設計をするとお互いのプライバシーを保護しやすくなり生活がしやすくなります。
また、防音や騒音対策への配慮も重要です。貸主と借主では生活スタイルや活動時間に違いが出る場合も考えられます。
間取りや設備の配置で防音・騒音対策を考えましょう。
貸主と借主のお互いのプライバシー尊重と言う点でもう一つ。
賃貸併用住宅では貸主は借主との距離感を常に一定に保つことが必要です。
貸主と借主が同じ建物内で生活をしているなかで、段々とその距離が近づき過ぎるようになると、悪い意味で「馴れ合いの関係」になってしまうことがあり、それが原因でトラブルに発展してしまうことが考えられます。
貸主と借主がフレンドリーな関係でいることはもちろん重要ですし、貸主の運用方針やスタイルにもよりますが、借主とは近すぎず遠すぎず、お互いにとって程よい距離感を保てるように模索することが重要です。
次は、マンションやアパートの一室を不動産投資物件として購入をして、賃貸物件として貸し出すパターンでの注意点について説明します。
この場合は以下の注意点があります。
マンションやアパートは集合住宅と言う性質上、入居者同士のトラブルが出てしまうことを忘れずに想定しておかなくてはなりません。
そのため、借主との入居契約時にトラブルが起こりそうな項目について取り決めをしておく必要があります。
また、借主からクレームが出たらすぐに対応・対策をすることが大切です。
これは補足説明ですが「マンションやアパート一棟」の賃貸オーナーとして貸し出す場合は、貸主が全ての借主に対して自主管理で管理業務の対応することは現実的には難しいため、尚更のこと、やはり管理業務を委託できる管理会社を選定する方が望ましいと言えるでしょう。
分譲マンションの場合、共用部分の維持管理や各入居者の生活マナーの維持についての取り決めや管理を行うために必ず「管理組合」が設けられています。
管理組合はマンションの住民で構成をされています。例えば、理事長の選任時や、定例会に参加するか・しないかで、組合員である他の住民とトラブルになったり、管理組合の総会で議決された取り決めを実行するときに他の住民から反対にあったりする可能性がつきものです。
分譲マンションを賃貸で家を貸すときには、貸主は管理組合の一員としての役割が発生することを覚えておきましょう。
以上、自宅の部屋や持ち家を貸すときの注意点をケース別に解説してきました。
家を賃貸物件として貸し出しす場合の「チェックポイント」をしっかりと抑えておけば、トラブルを回避しやすくなりますし、安心・安全な賃貸経営が可能となるでしょう。
家を貸す場合、以下のような注意点があります。
・賃貸借契約の種類やその内容について、細かくチェックする
・管理業務にはどのようなものがあるのか、あらかじめ把握しておく
・慎重な収支計画を立てる
貸主ご自身ですべての管理を行うことはできませんし現実的ではありません。
不動産会社では、一時的に使わない家を活用する方法について相談に乗ってくれる専門の管理会社があります。
ご自身だけで判断するのが難しい場合は、ご自身の状況を踏まえて「こんな管理業務を委託したいが可能なのか?」といった形で希望を伝えた上で、管理会社の専門家の意見を仰いでみることを強くおすすめします。
また、家を賃貸に出すにあたって、何よりも大切にしてほしいポイントがあります。
それは管理業務に関する委託管理の相談を管理会社へ依頼する場合は、できる限り、すぐに一つの不動産会社と話を進めようとしてはいけないということです。
確かに「急な転勤」などで急ぐ場合や、不動産会社との交渉が複数社に及べば、面倒で時間も手間もかかります。
そうなると「もう早く決めてしまいたい」という心理から、最初に連絡が取った会社と話を進めてしまいがちです。
しかし、よく考えて頂きたいことは「家の委託管理を依頼する」ということは、あなたの大切な不動産の管理を第三者へ依託をして、いわばあなたの賃貸経営をサポートしてもらうということです。
結果的には多くのお金が動く商取引になりますし「あの時、焦らずにもっと慎重に委託管理先を探すべきだった...」と後から悔やまれてしまうのでは本当に残念な話しとなってしまいます。
あなたの家という財産の管理をしっかり任せられる実績と実力がある管理会社を探すべきです。
また、会社探しの上では、担当者と貸主との相性も重要だといわれます。
貸主の信頼にしっかり応えようと、些細なことにも迅速に丁寧な応対をする担当者との出会いが必要です。
トラブルが起きたら逃げ腰になるような担当者は論外です。複数社の会社へ問合せを行い、応対や態度などを観察すればだいたい分かるものです。
担当者の応対で少しでも気になる点があれば条件が良かったとしてもすぐに委託契約を交わさない方が吉ということもあり得ます。そうした担当者の質も含めて「良い条件で賃貸に出す」ことを何よりも優先すべきです。
最後に、比較検討する上では、他の会社の査定内容を探ってきたり、なぜか一社だけ飛びぬけて高い賃料を提示してきた場合も要注意です。
担当者が管理契約を取りたいがために、「高い賃料を提示している」という事情が隠れている場合があるかもしれません。そのような事情を見抜くためにも、やはり比較検討は必要です。
【イエカレより】「ご自宅を貸し出したい」「空き家にしたままよりも有効活用を検討したい」とお考えの方々に、ご自宅資産に合わせて留守宅管理専門の不動産管理会社をご紹介しています。一度のご登録で、最高8社の管理会社へ家賃査定依頼が可能です!ご利用は無料です。
各社、訪問査定も対応しています!大切なご自宅資産を丁寧に査定、直接ご希望もお伺いして高額査定を目指します!入居者仲介方法、管理代行・保証内容など、各社の提案を比較できますので、お留守の間、安心してお頂け頂ける不動産会社をお選びいただけます。
この記事について
(記事企画)イエカレ編集部
(コラム・アドバイザー)檜垣 知宏

株式会社ライフアドバンス代表取締役の檜垣知宏です。 2014年8月に設立し、恵比寿不動産という屋号で賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理を行う不動産業者です。 不動産業界歴15年の経験を生かし、 運営しているサービスサイトである「不動産の相談窓口」の運営者も務めております。
【保有資格】宅地建物取引士
【関連URL】
[恵比寿不動産×賃貸]
[恵比寿不動産×売買]
[恵比寿不動産×リフォーム]
[不動産の相談窓口]
[資産運用の相談窓口]
[転勤東京.com]
[LGBT不動産]
[賃貸管理ナビ]
[ライフアドバンス]
- カテゴリ:
- 家を貸す際に注意すべきこと
家を貸す際に注意すべきことの関連記事
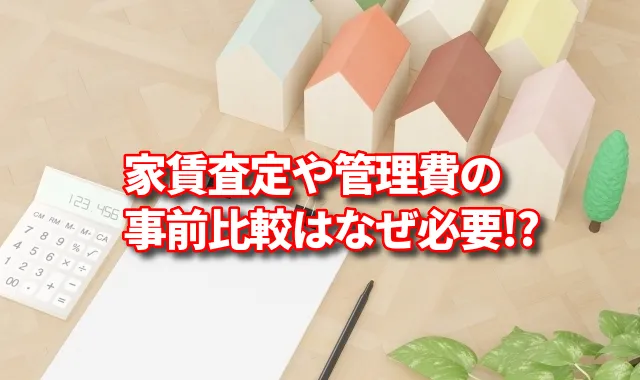
- 【自宅を貸したい場合】家賃査定や管理費の事前比較の必要性について解説します 公開
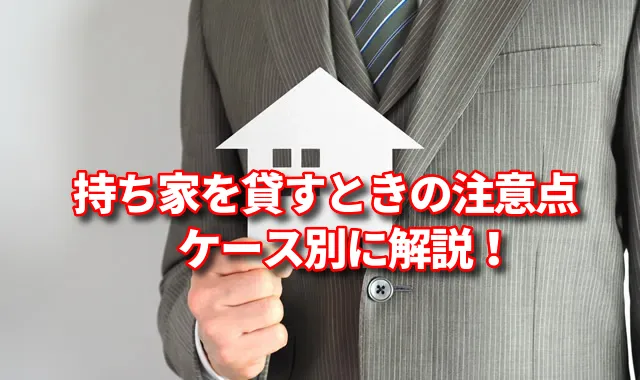
- 【家を貸す】初心者必見!持ち家を貸し出すときの注意点をケース別に詳細に解説します 公開
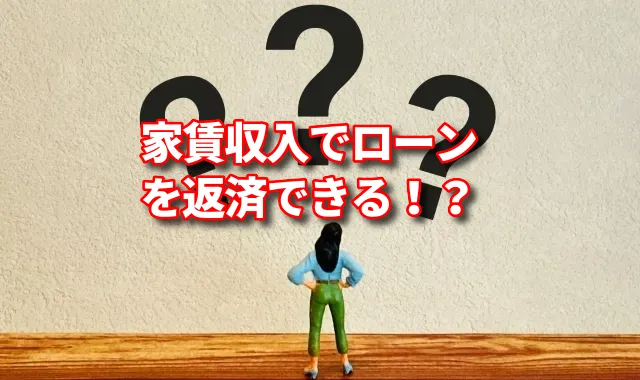
- 【賃貸管理】住宅ローン返済中に持ち家を貸すリロケーションについておしえます 公開

- 【物件の貸し出し】住宅ローン返済中の物件をリロケーションを使って貸す! 公開

- 【家を貸したい】海外赴任時のリロケーション!自家用車はどうすれば!? 公開

- 【家を貸す】定期で貸せるリロケーション!税金に関する注意点を解説します 公開

- 【家を貸したい】空き家バンクの仕組みと一般の賃貸管理会社を利用する場合の違いをお伝えします 公開

- 【空き家の活用事例】空き家ビジネスの最前線!成功事例や失敗事例をご紹介 公開

- 【家を貸したい】貸す前に絶対に確認しておきたい重要事項!! 公開

- 【持ち家を貸す】素朴な疑問!家を貸すとき家具やマイカーは置いておけるの? 公開
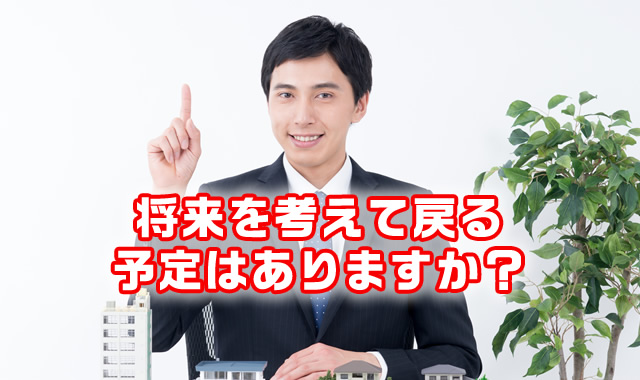
- 【持ち家を貸す】入居者退去後の原状回復の方法・事前確認をしてトラブル防止! 公開

- 【賃貸管理】大失敗しない持ち家・マンションを貸す方法!5つのチェックポイントをおしえます 公開
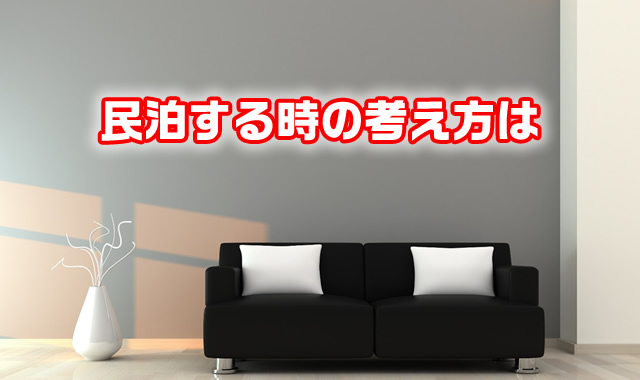
- 【民泊運営】民泊で家を貸す時の重要ポイントをおしえます! 公開