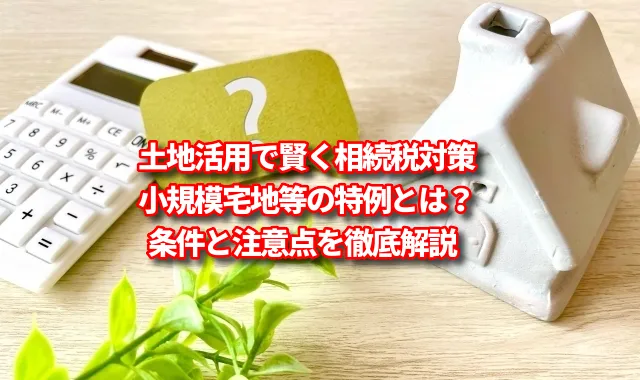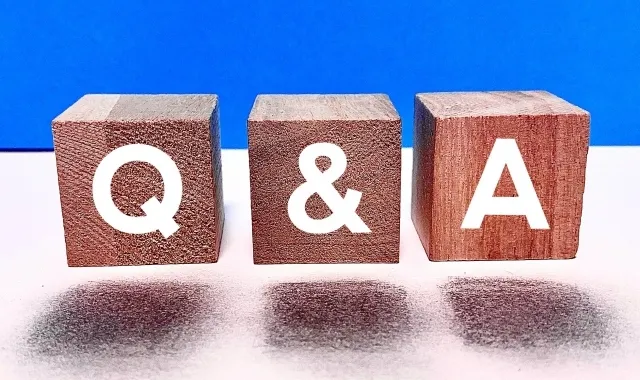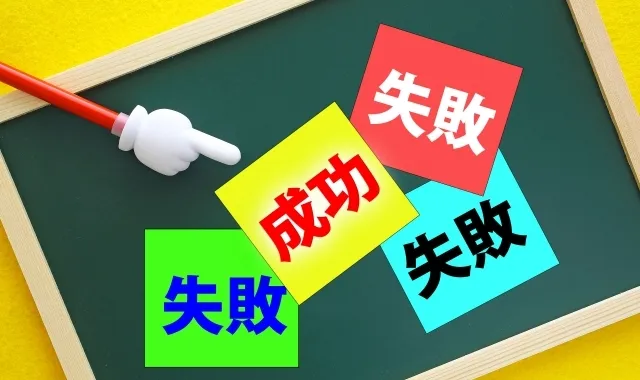- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- リロケーション
- 家を貸す際に注意すべきこと
- 【イエカレ】実家を相続した空き家の活用方法5選|失敗しない選択肢と費用相場を解説
【イエカレ】実家を相続した空き家の活用方法5選|失敗しない選択肢と費用相場を解説
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
空き家放置は非常に心配なこと。実際に貸すことを考えるなら、信頼できる会社と契約を結ぶことが何より大切です。
複数の管理会社に提案をもらい、内容を見比べながら自分に合った方法を選びましょう。管理の対応や条件の違いを知ることで、思いもよらない好条件に出会えることもあります。
どなたでもかんたん!資料請求(無料)1.空き家放置が招く3つのリスク
相続した空き家を適切な管理なしに放置すると、法的な責任や経済的な負担増につながる、主に3つのリスクが生じます。
これらを理解することが、有効活用への第一歩です。
1-1.固定資産税の最大6倍課税
空き家対策特別措置法により、「特定空家」に指定されると、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。
「特定空家」とは、倒壊の危険がある、衛生上有害、景観を損なう、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家を指します。
例えば、屋根が破損して雨漏りしている、庭木が繁茂し越境して近隣に迷惑をかけている、といったケースが該当しうるでしょう。適切な管理を怠ると、本来より高額な固定資産税を支払い続けることになりかねません。
1-2.倒壊時の賠償責任事例
空き家が倒壊し、第三者に損害を与えた場合、所有者は損害賠償責任を負うリスクがあります。これは、民法717条に定められた土地工作物責任に基づくものです。
例として、老朽化した塀が倒れて通行人が怪我をした、強風で屋根瓦が飛散し隣家の車を破損させた、などが考えられます。
過去には、放置された空き家の倒壊が原因で人身事故に至り、多額の賠償請求がなされた事例も存在。空き家の管理を怠ることは、経済的負担だけでなく、法的な責任問題にも発展する可能性もあります。
1-3.行政代執行による強制撤去
特定空家に指定された後、所有者が自治体からの勧告等に従わず適切な改善措置を講じない場合、行政代執行によって強制的に空き家が解体・撤去されることがあります。その際にかかる費用は、最終的に所有者へ請求されます。
例えば、自治体から複数回の改善指導や勧告を受けても危険な状態を放置し続けた結果、最終的に自治体の判断で解体工事が実施され、その費用全額を負担する、といった事態です。
自らの意思に関わらず高額な費用負担が発生するため、特定空家に指定される前に対策を講じることが極めて重要になります。
2.5つの活用方法と費用対効果比較
相続した空き家を有効活用するための主な方法は5つ紹介します。
それぞれの方法には、初期費用、収益性、維持管理の手間といった点で特徴が異なります。
ご自身の状況や目的に合わせ、最適な活用方法を選択しましょう。
2-1.賃貸アパート経営|初期費用500万円〜(目安)
空き家をリフォーム・リノベーションし、賃貸物件として経営する方法です。
比較的安定した家賃収入が期待できる点が魅力といえるでしょう。
例えば、築30年の木造2階建て住宅(延床面積100平方メートル)を2戸の賃貸向け住戸に改修する場合、水回り設備の交換や内装工事などを含め、初期費用としてあくまで目安ですが500万円から1000万円程度が見込まれることがあります。
家賃収入は地域や物件状態によりますが、仮に1戸あたり月額8万円なら年間192万円の収入です。ただし、入居者募集や契約、日々の管理業務、退去時の原状回復費用などが別途発生。空室リスクも考慮に入れる必要があります。
2-2.民泊運営|高収益も期待できるが変動要因多し
空き家を宿泊施設として活用する民泊運営は、近年注目を集める方法です。
特に観光地に近いエリアでは高い収益も期待できます。
例えば、一棟貸しの民泊として運営する場合、簡易的なリフォームや家具・家電の設置費用として、こちらも目安として100万円から300万円程度かかるケースがあります。
宿泊料金は時期や需要で大きく変動しますが、週末を中心に高い稼働率を維持できれば、年間で相応の収入を得ることも可能でしょう。
しかし、地域の条例遵守や近隣住民との良好な関係構築への配慮、清掃や鍵の受け渡しといった運営業務は必須です。年間を通して安定した集客が見込めるかが収益性を大きく左右します。
2-3.売却|地域差が大きい
空き家を売却することは、管理の手間から解放され、まとまった現金を早期に得られるメリットがあります。売却価格は、築年数、立地、建物の状態、周辺の取引事例などによって大きく変動するのが実情です。
例えば、地方の築古戸建てでは数百万円程度での売却となる一方、都市部の好立地であれば数千万円で取引されるケースも。
売却には、仲介手数料や登記費用などの諸経費がかかります。売却のタイミングも重要で、一般的に不動産需要が高まる時期(春先の転勤・入学シーズン前など)や、地域の再開発計画発表後などを狙うのが有効とされています。
2-4.リノベーション|補助金活用術
老朽化した空き家をリノベーションし、新たな価値を付加する手法です。
単に住宅として再生するだけでなく、カフェやシェアオフィス、アトリエなど、多様な用途への転用が考えられます。
例えば、古民家を改修してカフェを開業する場合、デザイン性の高い内装工事や厨房設備の導入に数百万円から、場合によっては数千万円規模の費用がかかることも。
しかし、魅力的な空間を創出できれば、周辺物件との差別化を図り、高い収益性を実現できる可能性も秘めています。
また、多くの自治体では空き家のリノベーションに対する補助金制度を設けています。耐震改修や省エネ化工事などが対象となることが多いので、これらを活用すれば初期費用を抑えることが可能です。
2-5.福祉施設への転用|自治体連携のコツ
空き家を高齢者向けデイサービス施設や障がい者グループホームといった福祉施設へ転用する方法は、地域貢献にもつながる有意義な選択肢です。
この場合、バリアフリー化や消防設備の設置など、専門的な改修が必須となるため、初期費用は比較的高額になる傾向にあります。
しかし、自治体によっては、地域福祉推進の観点から空き家の福祉施設への転用を支援する制度(改修費用の一部補助や運営事業者とのマッチング支援など)を設けている場合があります。成功の鍵は、自治体の担当部署へ積極的に相談し、密接に連携を図ることです。
「貸すのもありかも」と思った方は、いくつかの会社の提案を比べてみるとイメージしやすくなります。
無理に決める必要はありませんが、まずは情報収集から始めてみませんか?
どなたでもかんたん!資料請求(無料)土地活用×空き家リノベーション|デザイン力で資産価値を最大化する方法
3.空き家の活用成功のポイント
空き家の活用を成功に導くには、不動産と税務、両方の専門家の視点を取り入れることが欠かせません。
ここでは、資産価値向上、税負担軽減、契約時の注意点を解説します。
3-1.資産価値を上げる3つの改修ポイント
空き家の資産価値を高めるためには、以下の3点に着目した改修が有効と考えられます。
● 建物の基本性能向上: 耐震補強工事や断熱性能向上工事など。建物の安全性と快適性を高め、入居者や購入希望者への訴求力を上げます。
● 水回り設備の刷新: キッチン、浴室、トイレなどの設備を最新のものへ交換。生活の質が向上し、物件の印象を大きく改善します。
● 内装・外装のリフレッシュ: 壁紙の張り替え、床材の交換、外壁の塗り替えなど。物件全体が明るく清潔な印象となり、資産価値の維持・向上に貢献します。
3-2.相続税評価額の抑え方
相続した空き家は、一定の要件を満たすことで相続税評価額を軽減できる場合があります。
代表的なものが「小規模宅地等の特例」です。これは、被相続人の居住用または事業用の宅地等について、一定面積まで評価額を最大80%減額できる制度。
空き家であっても、被相続人が生前居住していた家屋であれば、適用を受けられる可能性があります。ただし、適用要件は細かく複雑なため、税理士などの専門家へ相談し、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。
また、空き家を賃貸物件として活用する場合、「貸家建付地」として評価され、更地評価よりも相続税評価額を抑えられるケースもあります。
3-3.失敗事例から学ぶ契約の注意点
空き家活用において、契約時の不備がトラブルの原因となるケースは少なくありません。
例えば、賃貸契約では、家賃滞納時の対応や原状回復に関する取り決めが曖昧だったために紛争が生じることがあります。
売買契約では、物件の瑕疵(欠陥)に関する告知義務違反により、契約解除や損害賠償請求に発展することも。リフォームや解体工事の契約でも、見積もり内容の不明確さや工期遅延といったトラブルが発生しがちです。
これらの失敗事例に学び、契約締結前には契約内容を十分に確認し、不明点は必ず専門家へ相談するようにしましょう。契約書に権利義務が明確に記載されているか、特約事項は自身の意向に沿っているかなどを慎重に確認することが肝要です。
土地活用で賢く相続税対策|小規模宅地等の特例とは?条件と注意点を徹底解説
4.Q&A|よくある疑問を解決
空き家の活用に関して、よく寄せられる疑問とその回答をまとめました。
4-1.「空き家管理サービス」の選び方
遠方に住んでいるなどの理由で自身での管理が難しい場合、空き家管理サービスの利用が有効です。選ぶ際には、以下の3点を確認しましょう。
● サービス内容の充実度: 定期的な巡回、清掃、通風換気、郵便物管理、庭木の手入れなど、自身が必要とするサービスが含まれているか。
● 料金体系の明確さ: 基本料金に加え、オプション料金や追加費用が発生する場合の条件などを事前に確認し、総費用を把握することが大切です。
● 実績と評判: 運営会社のウェブサイトや口コミサイトなどで、過去の利用者の評価や実績を確認し、信頼できる業者を選びましょう。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
4-2.相続から活用開始までの流れ
相続発生から空き家の活用を開始するまでの一般的な流れは以下の通りです。
1. 相続登記: まず、法務局で相続登記を行い、空き家の名義を自身(または相続人)に変更します。
2. 現状把握: 空き家の状態を正確に把握するため、必要に応じて専門家(不動産業者、建築士など)による建物診断(インスペクション)を依頼します。
3. 活用方針決定: 診断結果や自身の意向、市場調査などを踏まえ、賃貸、売却、リノベーション、解体など、具体的な活用方法を決定します。
4. 準備・実行: 決定した方針に基づき、リフォームや解体工事、あるいは売却活動や賃貸募集の準備を進めます。
5. 契約・活用開始: 売買契約や賃貸借契約などを締結し、活用を開始します。
各段階で必要に応じて専門家のサポートを得ながら進めることで、手続きをスムーズに進めやすくなります。
4-3.地域別補助金検索ガイド
空き家の活用に関する補助金制度は、国だけでなく、多くの自治体が独自に設けており、内容や条件は様々です。
● 検索方法: まずは、空き家のある自治体のホームページで「空き家 補助金」「空き家 利活用 支援」といったキーワードで検索してみましょう。
● 補助対象の例: 空き家の解体費用、リフォーム・リノベーション費用、家財道具の撤去費用などが対象となることが多いです。耐震化や省エネ化改修に対する補助が手厚い場合もあります。
● 情報収集: 「全国版空き家・空き地バンク」のようなポータルサイトでも、地域ごとの補助金情報を検索できる場合があります。自治体によっては、空き家活用希望者向けのセミナーや相談会、「大家育成支援制度」のようなユニークな取り組みを実施していることもあります。
補助金は申請期間や予算枠が限られている場合が多いので、早めに情報を収集し、要件を確認の上、積極的に活用を検討しましょう。
もし、実際に貸すことを考えるなら、信頼できる会社と契約を結ぶことが何より大切です。
複数の管理会社に提案をもらい、内容を見比べながら自分に合った方法を選びましょう。管理の対応や条件の違いを知ることで、自宅を安心して任せられる会社が見つかります。
どなたでもかんたん!資料請求(無料)まとめ:空き家活用方法で失敗しないために
本記事では、空き家になった実家の活用方法について、5つの活用法から費用相場や失敗しないためのポイントについて解説しました。
空き家活用は、条件によって選択肢が変わるため唯一の正解はありません。
ご自身の状況(資金力、時間的余裕、実家の立地条件など)に合わせて、最適な活用方法を選ぶことが重要です。
もし、迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。専門家からアドバイスを受けることで、最適な活用方法を見つけることができるでしょう。
空き家を放置するのではなく、新たな価値を生み出すためにも、本記事を参考に空き家活用にチャレンジしてみてください。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.
- カテゴリ:
- 家を貸す際に注意すべきこと
家を貸す際に注意すべきことの関連記事

- 転勤で自宅を貸す手順と会社選びのポイント|失敗しないリロケーション活用法 公開

- 原状回復の負担割合|オーナーが入居者へ適切に請求するためのガイドライン徹底解説 公開
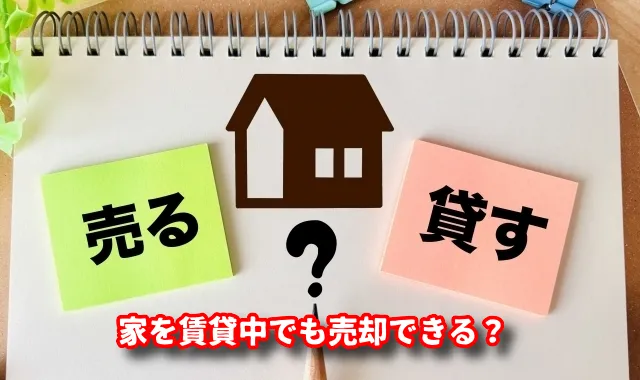
- 海外赴任で持ち家を賃貸中でも売却できる?リロケーション契約中の選択肢と注意点を解説 公開

- 耐震性で空き家の資産価値が上がる!耐震補強の費用や補助金も解説 公開

- 実家を相続した空き家の活用方法5選|失敗しない選択肢と費用相場を解説 公開
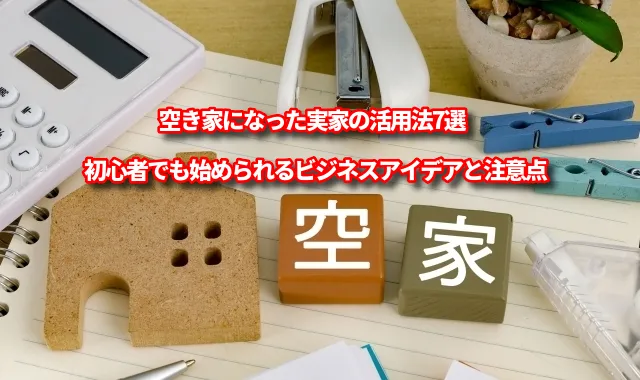
- 空き家になった実家の活用法7選!初心者でも始められるビジネスアイデアと注意点 公開
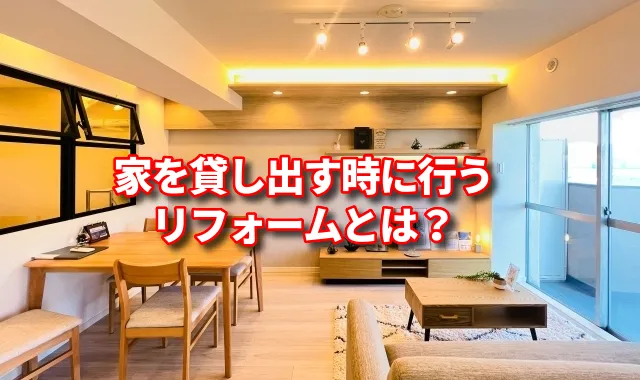
- 家を貸す前に必要なリフォームとは?|費用相場と失敗しないコツを解説 公開
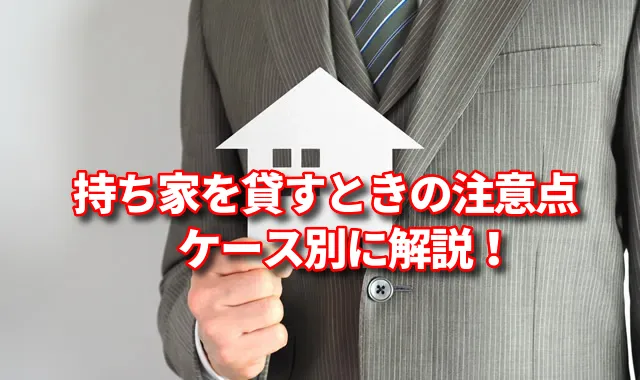
- 家を貸すときに起こりがちな失敗例と対策|初心者が注意すべきポイントを解説 公開

- 住宅ローン返済中でもOK!自宅を貸すための金融機関交渉と収支計画の速読ガイド 公開

- 海外赴任中の家と車の管理方法|自宅を貸すリロケーションも紹介 公開

- 契約書と原状回復で失敗しない!家を貸す貸主が押さえるべき5つの重要ポイント 公開

- 家を貸すときに家具や車はどうしたらいいの? 公開
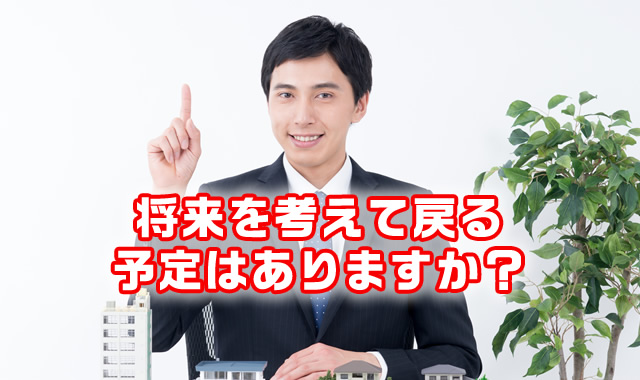
- 家を貸す時、退去後の原状回復トラブルを防ぐ方法を考える|費用負担と契約で押さえるチェックポイント 公開
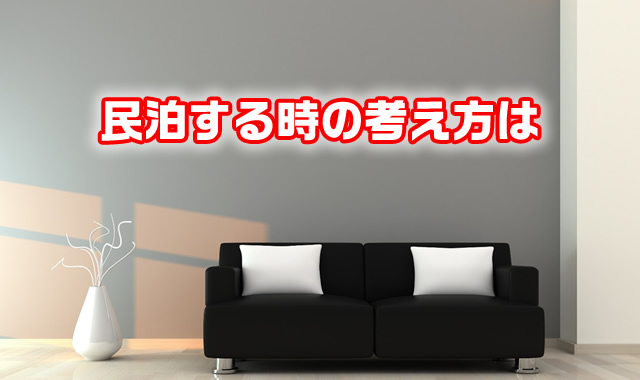
- 民泊を始めるには?家を貸す手続き・保険・注意点を解説 公開