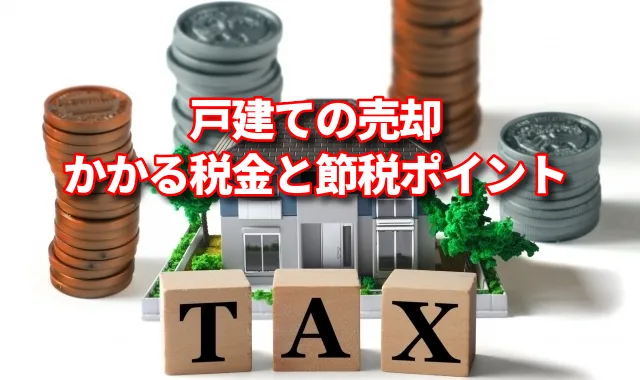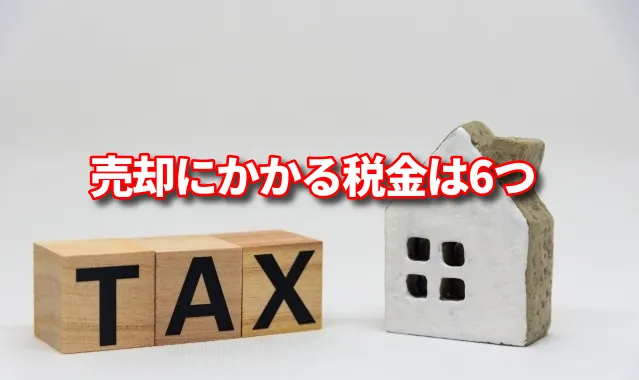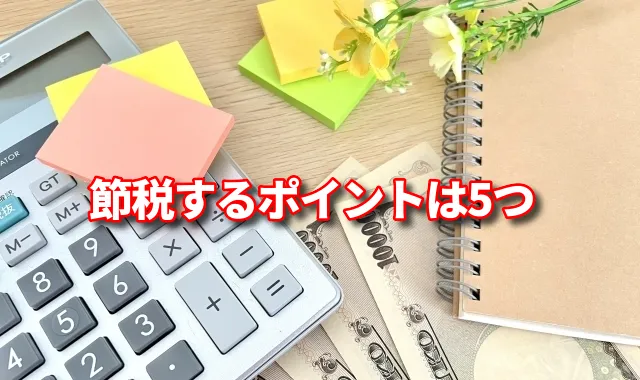- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- 不動産売却
- 不動産売却の基礎知識
- 【イエカレ】戸建ての売却にかかる税金と節税ポイント|どのような税金が課されるのかを事前に把握
【イエカレ】戸建ての売却にかかる税金と節税ポイント|どのような税金が課されるのかを事前に把握
この記事を読むのにかかる時間:10分
目次
1.戸建ての売却にかかる6つの税金
日常生活には、様々な場面で税金が課されます。
例えば、会社から受け取る給料は所得税と住民税、買い物で購入する商品には消費税などです。
戸建てを売却する際も、多くの税金が課されます。
所得税や住民税は源泉徴収で会社が直接徴収してくれる、消費税などはすぐ課されるため、納め忘れるということはありません。
しかし、戸建てを売却する際の税金はしばらく時間が経ってから課されるものもあり、納税時期が到来しても資金がなくて納税できないという事態に陥らないように注意が必要です。
そのような事態に陥らないようにするには、戸建ての売却でどのような税金が課されるか事前に把握しておくことが重要です。
戸建ての売却で課される税金は全部で以下の6つが挙げられます。
- ● 譲渡所得税
- ● 住民税
- ● 復興所得税
- ● 登録免許税
- ● 印紙税
- ● 消費税
それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。
1-1.戸建ての売却にかかる税金①:譲渡所得税
戸建てを売却した人の中には、売却価格が購入価格を上回って、利益が生じる人もいます。
このように戸建ての売却で利益を生じた人は、売却益に対して譲渡所得税が課されるので注意が必要です。
「売却価格が購入価格を下回っている場合は、譲渡所得税を納める必要はない?」と疑問を抱いた人もいるのではないでしょうか?売却価格が購入価格を下回っている状況は利益が生じているとは言えませんが、譲渡所得税が課される可能性があります。
その理由は、譲渡所得税が課されるかどうかは、利益が生じているかではなく、譲渡所得を基準としているためです。譲渡所得は「売却代金-取得費-手数料」という計算式によって算出されます。
取得費とは、土地や建物といった不動産を購入する際にかかった費用です。
例えば、土地の購入費用や建物の建築費用、不動産取得税や印紙税といった各種税金、売買契約を仲介した不動産会社に支払う仲介手数料などが取得費に該当します。
手数料とは、土地や建物といった不動産を売却する際にかかった費用です。
例えば、土地の測定量や建物の解体費用、仲介手数料、印紙税などが手数料に該当します。
また、取得費からは減価償却を引かなくてはなりません。減価償却費とは、築年数の経過で生じる資産価値の減少です。減価償却費は実際に支出を伴いませんが、資産価値の下落分を取得費から引くので取得費が小さくなります。
例えば、売却代金が3,500万円、取得費(減価償却費を含まない)が3,800万円、手数料が200万円の場合、譲渡所得は200万円のマイナスです。
しかし、一見取得費がマイナスでも減価償却費が800万円だった場合には、取得費が3,000万円に減少するため、譲渡所得がプラスになって譲渡所得税が課されるので注意が必要です。
譲渡所得税の税率は物件の所有期間によって以下のように異なります。
| 所有期間 | 所得税 |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 30% |
| 5年超(長期譲渡所得) | 15% |
短期譲渡所得と長期譲渡所得では、所得税の税率に2倍の差があります。
そのため、5年を超えてから戸建てを売却した方が良いと言えます。戸建ての売却で利益が生じている場合、5年を超えているかどうかによる影響が大きいので5年という基準を覚えておきましょう。
1-2.戸建ての売却にかかる税金②:住民税
譲渡所得税について既に説明しましたが、譲渡所得がプラスになった場合は、譲渡所得税に加えて住民税も課されます。
住民税の税率も、譲渡所得税の税率と同様、物件の所有期間で以下のように異なります。
| 所有期間 | 所得税 |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 9% |
| 5年超(長期譲渡所得) | 5% |
住民税も所有期間が5年を超えるか超えないかで、税率が2倍近く異なります。
そのため、譲渡所得がプラスになっている場合には、5年を超えてから売却した方が良いと言えます。
建物の所有期間は、売却した日ではなく、売却した日の属する1月1日時点です。
例えば、令和2年4月1日に取得した戸建てを令和2年5月1日に売却した場合は、暦上は5年を超えていても、所有期間の算出方法では令和2年1月1日が基準なので4年です。
令和2年4月1日に取得した戸建ては、令和8年1月1日を過ぎてから売却してようやく長期譲渡所得の条件を満たします。
長期譲渡所得の条件を満たしているか不安な場合には、不動産会社に確認することをおすすめします。
1-3.戸建ての売却にかかる税金③:復興所得税
戸建ての売却によって生じた利益に課される譲渡所得税には、令和19年まで復興所得税が上乗せされます。
復興所得税とは、東日本大震災の復興に必要な資金を確保するための税金です。
基準所得税額に2.1%の上乗せが行われます。
戸建ての売却で利益が生じた場合に課される税金を全て合算すると以下の通りです。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計(復興特別所得税) |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% | 39.63%(0.63%) |
| 5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% | 20.315%(0.315%) |
所有期間4年の戸建てを売却した際の譲渡所得が1,000万円だった場合、396万3,000円も税金が課されることになります。
所有期間が5年を超えていた場合でも200万3,150円の税金が課されるため、不動産取得税・住民税・復興所得税の与える影響は大きいと言えるでしょう。
1-4.戸建ての売却にかかる税金④:登録免許税
登録免許税とは、戸建ての売却で何らかの登記を行った場合に課される税金です。
戸建てを売却する際は売り手から買い手に所有権が移転するため、それを証明するために所有権の移転登記、抵当権が設定されている場合はそれを抹消するための手続きが行われます。
「抵当権」とは一体何でしょうか?戸建ての購入時には、自己資金だけでは不足するため、住宅ローンを契約するのが一般的です。住宅ローンを提供した金融機関は、契約者が返済に滞った場合、残債を回収できないというリスクを負います。
しかし、抵当権を設定していれば、契約者が滞納しても抵当権を設定した不動産を売却して現金化することで残債を回収することが可能です。
この抵当権が設定されたまま買い手が購入すると、買い手に何の落ち度がなくても、売り手が滞納すると購入した不動産が勝手に売却されるリスクがあるため、売却までに抵当権を抹消しなければなりません。
これらの登記や手続きには登録免許税が課されますが、買い手もしくは売り手のどちらが登録免許税を負担するかは決まっていません。
しかし、不動産売買の慣習上では、買い手が所有権の移転登記にかかる登録免許税、売り手が抵当権の抹消登記にかかる登録免許税を負担するのが一般的です。
抵当権の抹消登記にかかる登録免許税は1つの不動産につき1,000円です。
戸建ての場合、土地と建物の2つの不動産があるため、2,000円の登録免許税が課されます。
抵当権の抹消登記は、手続きに手間と時間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
しかし、司法書士に依頼する際は報酬を支払わなくてはならないため、報酬に登録免許税を加算すると1万円以上になってしまいます。
抵当権抹消の手続きに不備があると、再提出の手間と時間がさらにかかります。それらを踏まえると、司法書士に依頼した方がスムーズに手続きを終えられるでしょう。
1-5.戸建ての売却にかかる税金⑤:印紙税
戸建てを売却する場合は、買い手と売り手との間で売買契約書を交わします。
売買契約書を交わす際は、売買契約書に記載されている戸建ての売却代金に応じて、印紙税という税金を納めなくてはなりません。
印紙税は売買契約書1通に対していくらかかるという設定ではなく、売却代金に合わせて税率が変化します。
売買契約書に適用される売却代金ごとの税率は以下の通りです。
| 売却代金 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
100万円以下、5億円超にも税率が設定されていますが、戸建ての売却で用いられることはほぼないので省略しています。
国税庁の公式ホームページを確認すると、軽減税率に関する記載がありますが、平成26年4月1日~令和2年3月31日までに作成した売買契約書が軽減税率の適用対象です。
その後、期間の更新が行われていないため、軽減税率が適用されていない可能性があります。
現在は適用期間外なので、気になる人は不動産会社や戸建ての住所地を管轄する税務署に確認してみましょう。
1-6.戸建ての売却にかかる税金⑥:消費税
商品の売買は消費税が課されるため、戸建ての売買も消費税が課されると思っている人も多いのではないでしょうか?戸建ての売買では消費税が課されるものと課されないものに分類されるため、何に対して消費税が課されるのか知っておくことが重要です。
消費税が課されないものは以下の通りです。
- ● 土地の売買
- ● 個人による物件の売買
- ● 登録免許税や印紙税
土地は消費という概念に合っていないため、土地の売買には消費税が課されません。
一方、建物の売買は消費という概念に合うため、原則建物の売買には消費税が課されます。
しかし、サラリーマンといった個人が行った戸建ての売買は、消費税の課税事業者が行う売買とは異なるので消費税が課されません。
また、登録免許税や印紙税といった手数料は、手数料そのものが税金であるため、消費税が課されないので覚えておきましょう。
消費税が課されるものは以下の通りです。
- ● 仲介手数料
- ● 司法書士に支払う報酬
- ● 一括返済の手数料
不動産会社に支払う仲介手数料、司法書士に支払う報酬などは、課税事業者が提供しているサービスを利用する場合には消費税がかかります。
また、戸建てを売却して得た売却代金で住宅ローンの残債を一括返済する際にかかる手数料も課税対象です。
令和元年10月より消費税が8%から10%に引き上げられました。高額である戸建ての売却代金には消費税が課されないため、増税の影響はそこまで大きくありませんが、次に高額な仲介手数料は増税の影響を受けます。
たった2%の増税でも、消費税が課される金額が大きくなると税額も大きくなります。宅地建物取引業法には仲介手数料に関する規定がありますが、記載されているのはあくまでも上限なので値下げの交渉をすることは可能です。
応じてもらえない可能性もありますが、応じてもらえた場合、消費税の節税につながるので交渉してみる価値はあると言えるでしょう。
2.戸建ての売却にかかる税金を節税する5つのポイント
戸建ての売却には、譲渡所得税、住民税、復興所得税、登録免許税、印紙税、消費税などの数多くの税金が課されることが分かりました。
かなり多額の税金を納めることになるため、少しでも節税したいと考えている人も多いのではないでしょうか?
戸建ての売却にかかる税金を抑えることは可能です。しかし、選ぶ方法で効果が異なるため、節税に取り組む前にそれぞれの節税ポイントの特徴を把握することが重要です。
戸建ての売却にかかる税金を節税するポイントには以下の5つが挙げられます。
- ● 3,000万円の特別控除の特例
- ● 軽減税率の特例
- ● 買換えの特例
- ● 譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
- ● 売買契約書の作成を工夫する
それぞれの節税ポイントについて詳しく見ていきましょう。
2-1.戸建て売却の節税ポイント①:3,000万円の特別控除の特例
3,000万円の特別控除の特例とは、戸建てを売却した際の譲渡所得がプラスになった場合に、そこから3,000万円の特別控除を受けられる特例です。
譲渡所得がプラスになった場合には、譲渡所得に対して譲渡所得税、住民税、復興所得税が課されますが、特例を受けることができれば譲渡所得が3,000万円までであれば非課税になります。
譲渡所得が1,000万円だった場合には、短期譲渡所得で396万3,000円、長期譲渡所得で200万3,150円の税金が課されるのが通常ですが、これらが非課税になることを考えると、大きな節税効果が期待できると言えるでしょう。
2-2.戸建て売却の節税ポイント②:軽減税率の特例
軽減税率の特例とは、戸建ての所有期間が10年を超えてから売却した場合に、適用される税率を軽減する特例です。特例が適用された場合の税率は以下のように軽減されます。
| 譲渡所得 | 所得税 | 住民税 | 合計(復興特別所得税を含む) |
| 6,000万円までの部分 | 10% | 4% | 14.21% |
| 6,000万円を超える部分 | 15% | 5% | 20.315% |
6,000万円を超える部分については、従来通りの税率が適用されますが、6,000万円までの部分の税率が軽減されます。3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、適用条件が厳しくないため、ほぼ全ての戸建ての売却で適用できるでしょう。
2-3.戸建て売却の節税ポイント③:買換えの特例
買換え特例とは、戸建てを売却する理由が買換えの場合、譲渡所得に対して課される税金を繰り延べることができる特例です。
売却代金よりも高い物件に買換える場合、売却時点では譲渡所得に対する課税が行われず、新しく取得した物件を売却する時にまとめて課税が行われます。
安い物件に買換える場合、売却代金から購入代金を引いた差額分が利益と見なされるため、差額分のみが課税対象となります。しかし、購入代金分の課税については、新しく取得した物件を売却する時に繰り延べることが可能です。
買換え特例は、3,000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例のような直接的な節税効果は期待できません。 課税のタイミングをずらすことで、金銭的な負担を一時的に軽減するのが買換え特例の目的です。
また、買換え特例の適用を受けるためには、過去2年間に3,000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例などを受けていない、居住期間が10年以上で所有期間が10年超である、売却するのが親子や夫婦などに該当しないことなどの条件が設けられています。
3,000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例よりも適用条件が厳しいので、特例の利用を検討している場合は、適用条件を事前に確認しておくことが重要と言えるでしょう。
2-4.戸建て売却の節税ポイント④:譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例とは、所有期間が5年超えの戸建てを売却する際に、住宅ローンが残っていて売却しても損失が生じる場合、他の所得から差し引ける制度です。
また、その年で差し引くことができない損失は、翌年以降3年間繰り越して控除することが可能です。
所得税には所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が適用されているため、譲渡損失の損益通算を活用すれば、所得を抑える、税率を下げることによる節税効果が期待できます。
譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例の適用を受けるには、過去3年間で同じ特例の適用、売却した年の前年または前々年に3,000万円の特別控除の特例といった他の特例の適用を受けていないなどの条件を満たしていなければなりません。
買換えの特例と同様、適用条件が複雑であるため、譲渡損失の損益通算・繰越控除の適用を検討している場合は、適用条件を事前に確認しておくことが重要と言えるでしょう。
2-5.戸建て売却の節税ポイント⑤:売買契約書の作成を工夫する
買い手と売り手が交わす売買契約書に課される印紙税は、1通ごとに課されるため、双方に配布することから通常は2通分の印紙税が課されます。
しかし、1通をコピーで対応した場合、1通分の印紙税を減らすことが可能です。
例えば、戸建ての売却価格が3,000万円の場合、売買契約書1通に課される印紙税は1万円です。双方に配布した場合は2通分で2万円ですが、コピーで対応することで1通分の1万円に抑えることができます。
節税という点では、大きな効果はありませんが、抑えられる部分をしっかりと抑えることが重要と言えるでしょう。
まとめ
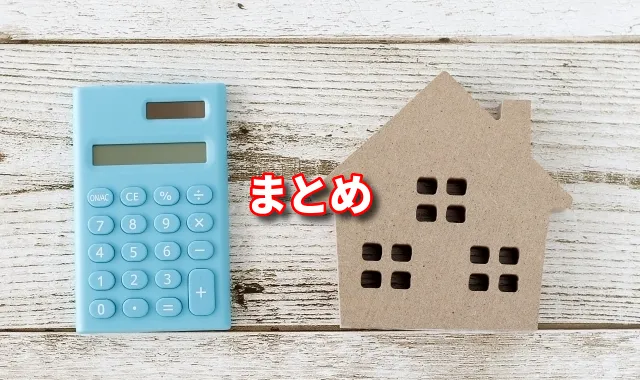
給与所得に所得税や住民税、日常の買い物に消費税が課されるのと同様、戸建ての売却にも様々な税金が課されます。
戸建ての売却にかかる税金の中には、すぐにかかるものもあれば、しばらく時間が経ってからかかるものもあります。
しばらく時間が経ってからかかる税金については、手元に資金がなく、納税できないという事態に陥る可能性もあるので注意が必要です。
そのような事態を未然に防ぐには、どのような税金が課されるのか事前に把握することが重要です。
この記事は、戸建ての売却にかかる税金と節税ポイントについて記載しています。この記事を参考にしながら戸建てを売却すれば、税金を滞納して延滞税が課される事態を未然に防ぐことが期待できるでしょう。【初回公開日2020年5月7日】
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
- カテゴリ:
- 不動産売却の基礎知識
不動産売却の基礎知識の関連記事
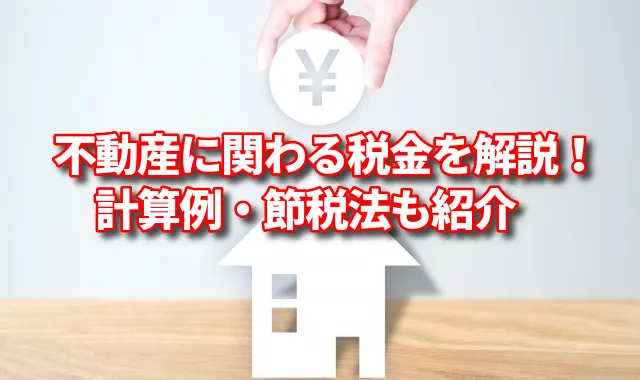
- 不動産に関わる税金を解説|計算例や節税方法を紹介 公開
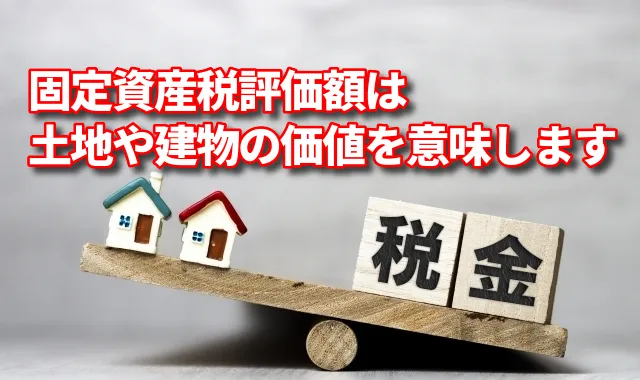
- 固定資産税評価額とは?|調べ方や計算方法も解説 公開
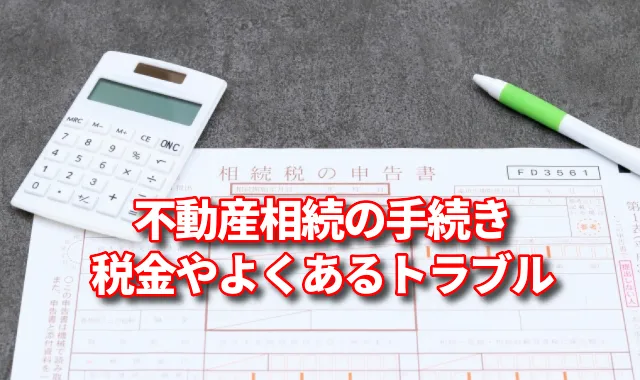
- 不動産相続の手続きを5ステップで解説|かかる費用や税金、トラブル事例、注意点も解説 公開

- 不動産売却時の仲介手数料を抑えるコツとは?計算方法と信頼できる会社の選び方を解説 公開
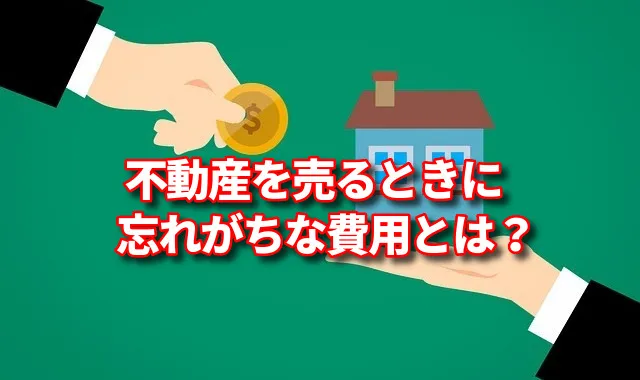
- 不動産売却で忘れがちな税金について|3種類の税金を紹介 公開
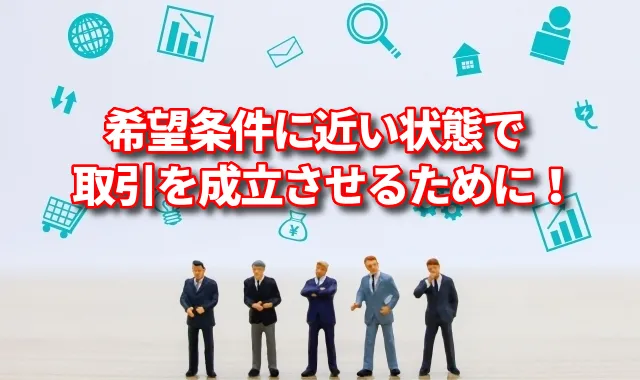
- 不動産売却の流れとそれに必要な期間|売却後の確定申告についても解説 公開

- スムーズに不動産売却するポイント|その手順と税金から確定申告までを解説 公開
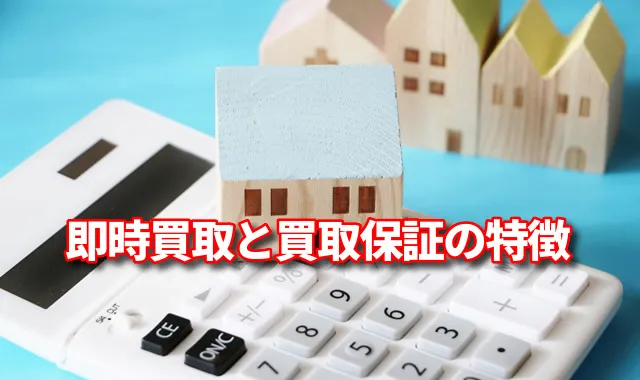
- 不動産買取の即時買取と買取保証とは?|その特徴とメリット・デメリットを解説 公開

- 思ったより高い?マンション売却でかかる仲介手数料とその他の費用とは 公開
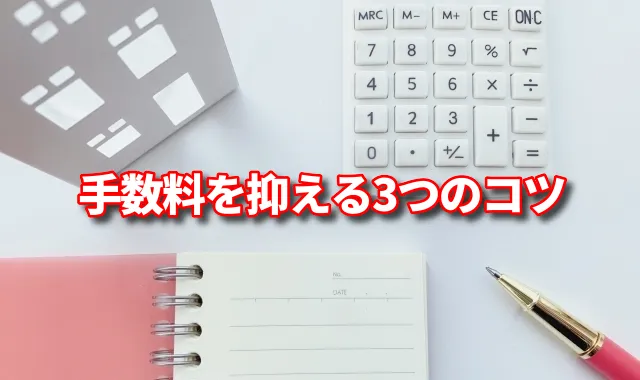
- 知らないと損する!一戸建て売却手数料の抑え方 公開

- 不動産売却に深く関係する公示価格とは|所有物件を損失無く売却したい方へ 公開
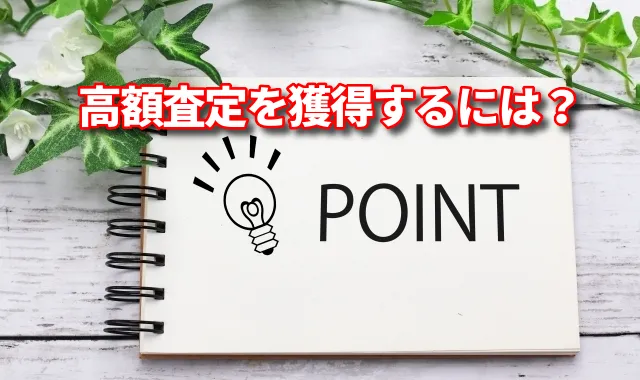
- 土地査定で高く売るための5つのポイント|不動産売却で損しないコツ 公開
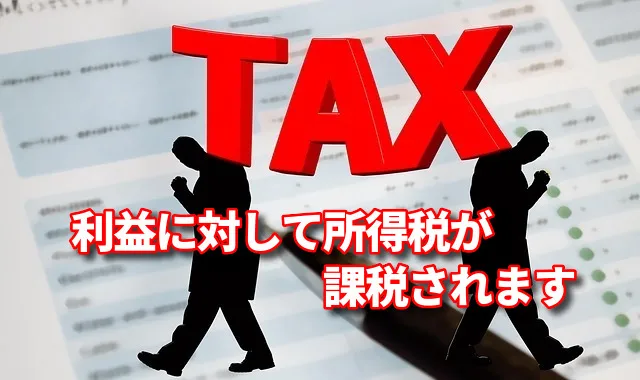
- 不動産売却で得た利益の税金について|所得税申告から税負担が特例で軽減される居住用の話まで| 公開
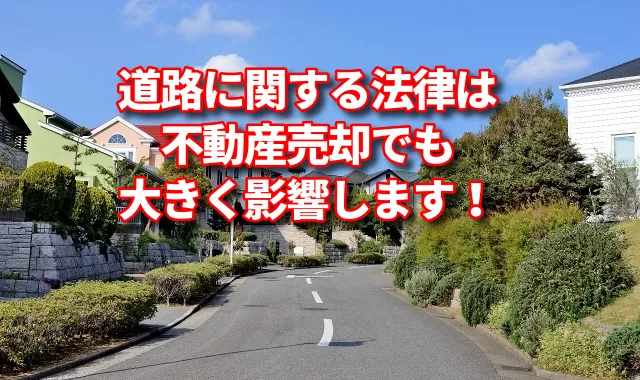
- 不動産で重要視される接道義務とは|不動産売却時の影響について解説 公開
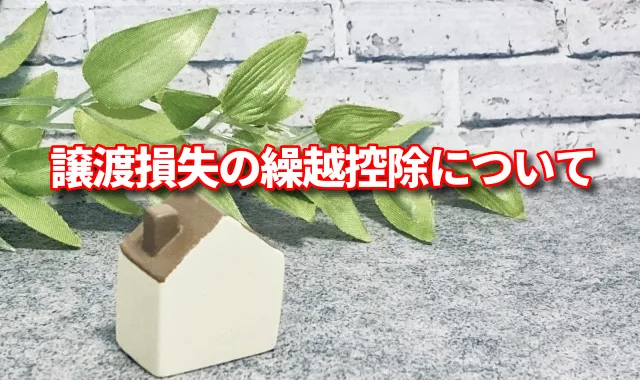
- 居住用財産の譲渡損失の繰越控除とは?|売却によって損失が発生した場合 公開

- 売却査定の前に知っておきたい5つの秘訣|経験がなくても知識で補おう 公開
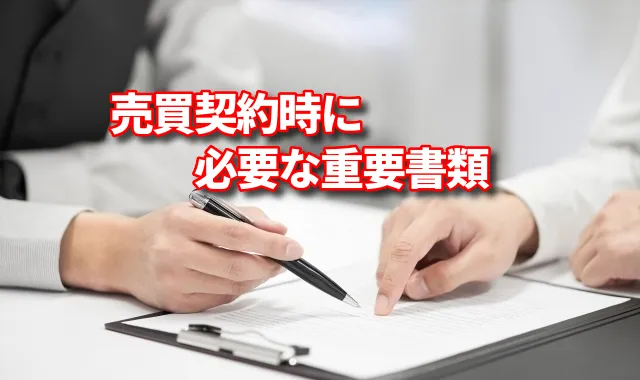
- 不動産売買契約で必要な重要書類とは|押さえておきべき3つのポイントを紹介 公開

- 物件の引き渡しまでに準備しておくこと|不動産売却の流れを解説 公開

- 信頼できる仲介会社選びが重要な理由|不動産売却の流れと一緒に確認 公開

- 不動産の相場がわかる土地総合情報システムとは?|そのシステムの活用方法を紹介 公開